5.経済安全保障(エネルギー・鉱物、食料、海洋、漁業)
(1)エネルギー・鉱物資源
2008年に1バレル当たり147.27米ドルの過去最高値を記録した原油価格は、その後の世界的な景気低迷を受け、2009年2月には1バレル当たり30米ドル台半ばまで下落した(いずれもWTI(注22)原油価格)。油価の大幅な変動は、世界経済の大きなリスク要因であり、その動向はエネルギー産出国及び消費国の双方にとって大きな関心事項となっている。また、エネルギー需要が増大する中国、インドなどとの関係や、気候変動問題への対応において鍵を握るエネルギー効率の改善、再生可能エネルギーの推進等について、日本は、IEAや国際エネルギー・フォーラム(IEF)など関連の国際的取組に積極的かつ主導的に参加し、関係各国と連携・協調しつつ、日本及び世界のエネルギー安全保障の強化に取り組んでいる。また、鉱物資源については、日本への安定供給のための取組に加え、採取産業透明性イニシアティブ(EITI)への貢献など、有限な資源の適切な開発・利用を目指す多国間取組に積極的に参加している。
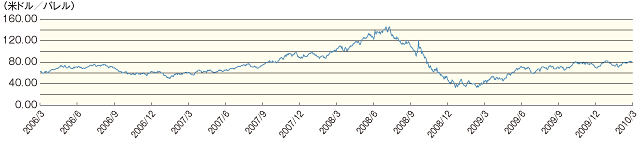
イ 国際機関との連携の強化、国際協調・協力の推進


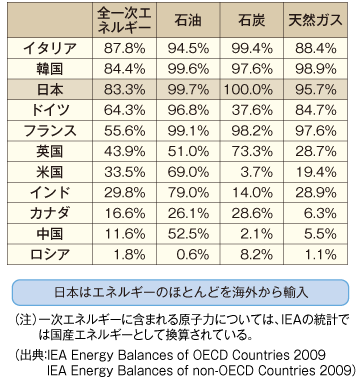
ロ 安定供給の確保
エネルギー市場の安定化を実現し、日本へのエネルギー安定供給を確保するため、日本は資源産出国との二国間関係の強化、中東地域の安定等の環境整備に努めている(第2章第6節「中東と北アフリカ」を参照)。同時に、サハリン島沖合や東シベリア地域の石油・天然ガス開発生産に関する官民一体の取組等を通じ、エネルギー供給源の多様化の推進も図っている。さらに、原油総輸入量の9割が通過する中東から日本までの海上輸送路及び、昨今海賊事案が多発・急増しているソマリア沖・アデン湾等の重要な海上輸送路における航行の安全確保が重要な課題となっている。日本は、沿岸各国に対し、海賊の取締り能力の向上や関係国間での情報共有を通じた協力や航行施設の整備を行っているほか、ソマリア沖・アデン湾では自衛隊を派遣して商船の護衛活動を実施するなど、様々な取組を行っている。また、日本の総発電量の約3割を占める基幹電源である原子力発電の安定供給を確保するため、原料となるウランの確保に資する二国間関係(カザフスタンなど)の強化や放射性物質の円滑な海外輸送確保のための関係国対話に取り組んでいる(原子力の平和的利用については、第3章第1節4.「軍縮・不拡散・原子力」を参照)。
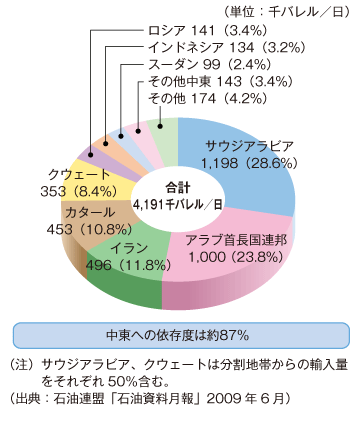
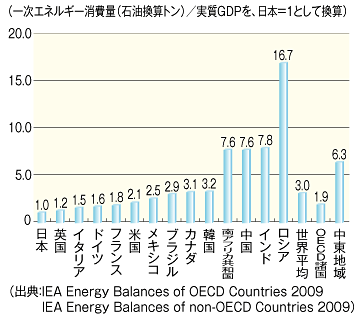
(2)食料安全保障
2008年に歴史的な高騰を記録した食料価格は同年夏には下落基調に転じたが、多くの開発途上国では高水準で推移している。国連食糧農業機関(FAO)によれば、食料価格高騰及びその後の金融危機の影響等により、世界の栄養不足人口は更に増加し、10億人を超えたと見込まれている。食料不安に苦しむ開発途上国の人々の窮状を緩和し、MDGsの達成に貢献することは日本の責務である。同時に、日本は食料供給の約6割(カロリーベース)を海外に依存する世界最大の食料純輸入国であり、日本及び世界の食料安全保障の強化は外交政策の基本目標の一つである。こうした中、日本は9月に「責任ある国際農業投資の促進に関する高級実務者会合」(於:ニューヨーク(米国))を主催するなど、国際社会の取組を主導するため、積極的な外交を展開している。
イ 食料安全保障に関する国際的枠組みの構築
7月のG8ラクイラ・サミット(於:イタリア)では、27か国及び11の国際機関が参加し、食料安全保障に関する拡大会合が開催され、「世界の食料安全保障に関するラクイラ共同声明」が発出された。ここでは、開発途上国主導の農業開発を実現するための原則に合意し、これを具体化するための資金的コミットメントがなされたほか、G8北海道洞爺湖サミットで提唱された農業・食料安全保障に関するグローバル・パートナーシップの推進等が確約された。日本は、前年の議長国として議論の取りまとめに主導的な役割を果たすとともに、今後3年間で少なくとも30億米ドルの農業関連援助を発表し、高い評価を受けた。
11月にはFAO主催の、世界食料安全保障サミットが開催され、G8ラクイラ・サミットの成果を踏まえ、「持続可能な世界の食料安全保障のためのローマ5原則」が合意された。日本は、同サミットに向け、9月のFAO世界食糧安全保障委員会(CFS)改革や、10月のナバロ国連調整官の訪日等を通じて、国際的な議論の方向付けに努めた。
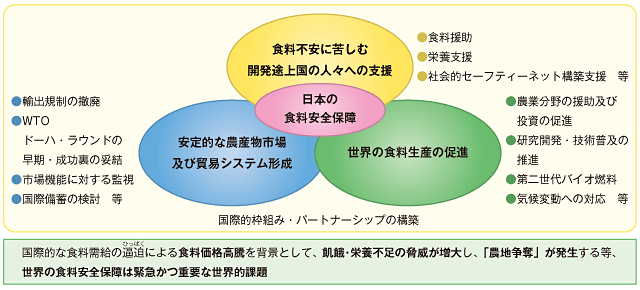
ロ 責任ある国際農業投資の促進に向けた日本の取組
食料価格高騰を背景として、近年、開発途上国への大規模な国際農業投資が増加し、これが「新植民地主義」あるいは「農地争奪」として国際社会の注目を集めている。日本は、この問題が将来の世界の農業及び食料安全保障に重大な影響を与えうるとの考えの下、当初からこれに注目し、3月に東京で国際シンポジウムを開催し、アフリカ等から閣僚級を招へいして議論を行った。その上で、7月のG8ラクイラ・サミットの際に、責任ある国際農業投資を促進するための行動原則及び国際的枠組みの策定を提案し、支持を得た。このイニシアティブを具体化するため、9月の国連総会の際に、世界銀行、FAOなど4つの国際機関との共催により「責任ある国際農業投資の促進に関する高級実務者会合」を主催し、参加した31か国の代表等より支持を得た。
これと並行し、日本への食料安定供給と世界全体の農業生産の増大を見据え、日本から海外への農業投資を促進するため、4月に関係省庁・機関による会議を設置した。検討の結果、8月には、責任ある投資を実現するための日本自身の行動原則を含む、「食料安全保障のための海外投資促進に関する指針」を発表した。これを踏まえ、対象地域における現地調査を含めた情報収集等を進めている。
(3)海洋(大陸棚)
国土面積が小さく天然資源の乏しい島国日本にとって、海洋の生物資源や周辺海域の大陸棚・深海底に埋蔵される海底資源は、経済的な観点から重要である。
日本は、海洋における権益を確保するため、国連海洋法条約(注23)に基づき200海里を超える大陸棚の限界を設定するため、周辺海域の海底地形・地質調査を進めてきた。これら検討・調査の結果、総理大臣を本部長とする総合海洋政策本部会合の決定に基づき、2008年11月、大陸棚限界委員会(CLCS)に対し200海里を超える大陸棚の延長申請を行い、2009年3月に、日本政府代表団は、CLCSにおいて日本の申請に関する口頭説明を行った。9月には、日本の申請を審査する小委員会がCLCSに設置され、審査が開始された。
(4)漁業(マグロ・捕鯨問題等)
世界の漁業資源の約半分は満限(過剰漁獲の一歩手前)に利用されており、約4分の1は過剰漁獲若しくは枯渇状態にある中(注24)、日本は世界有数の漁業国、水産物の消費国として、国際的な海洋生物資源の適切な保存管理及びその持続可能な利用のための協力に積極的な役割を果たしている。
マグロ類は、広い海域を回遊するため、地域漁業管理機関を通じて資源の保存管理が行われているが、一部のマグロ類は資源の減少が深刻になっている。特に大西洋クロマグロについては、10月、ワシントン条約附属書Ⅰに掲載し、国際取引を禁じるとの提案がモナコから提出された。日本は、マグロ類の漁業国であると同時に輸入国として、マグロ類資源の保存管理措置の強化に向けてリーダーシップを発揮し、大西洋まぐろ類保存国際委員会(ICCAT)においては、大西洋クロマグロ総漁獲量の対前年比4割減、中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)においては、初めての太平洋クロマグロの漁獲規制が決定された。
捕鯨については、これまで国際捕鯨委員会(IWC)は資源管理機関として有効に機能してこなかったが、2008年6月の第60回IWC年次会合(於:サンティアゴ(チリ))において、「IWCの将来」について集中的に議論され、調査捕鯨や沿岸小型捕鯨等についてパッケージ合意を目指すために、小作業グループが設立された。2009年6月の第61回IWC年次会合(於:マデイラ(ポルトガル))では、2010年のIWC年次会合での合意に向け、更に1年間「IWCの将来」プロセスを継続することが決定された(注25)。日本は、科学的根拠に基づき鯨類の持続可能な利用を図るべきとの立場であり、今後も関係国に対し、日本の立場への一層の理解と支持を積極的に求め、IWCの正常化に向けて取り組んでいく方針である。
(注22)WTI:ニューヨーク商業取引市場の石油指標銘柄であるウエスト・テキサス・インターミディエートの略。北海ブレント、ドバイとともに世界的な指標原油の一つ。
(注23)海洋法に関する国際連合条約(国連海洋法条約)では、沿岸国の領海を越えて200海里までの区域の海底等をその大陸棚と定めるとともに、大陸棚縁辺部が200海里を超えて延びている場合には、海底の地形・地質等が一定の条件を満たせば、沿岸国は200海里を越える大陸棚を設定できるとしている(1海里は1,852m)。
(注24)FAO, “The State of World Fisheries and Aquaculture 2008,”30ページ。
(注25)これまでIWCでは、持続可能な利用支持国と反捕鯨国が対立したままで、両者の間に建設的な話合いが行われず、したがって、IWCとして実質的な議論や決定が何もなされてこなかった。IWCの目的は、鯨類資源の適当な保存と利用(鯨類産業の秩序ある発展)であり、本来の目的を果たせるよう両者が歩み寄りを示すべきというのが日本の考え方である。