4.国際経済分野の法秩序
(1)多角的自由貿易体制の強化
イ 多角的自由貿易体制と日本
戦後日本の経済発展は、関税及び貿易に関する一般協定(GATT)/WTOを中心とする多角的自由貿易体制の存在抜きには語れない。GATT体制の下で自由貿易制度が整備されて各国の関税が引き下げられたことは、日本製品の輸出促進につながり、日本は貿易を通じた経済的繁栄を実現した。WTOはモノの貿易に加え、サービスの貿易、知的財産権に関するルールづくりや各国の貿易政策の監視、より強化された紛争処理の機能を備えている。世界経済の回復を後押しする上でも、WTO体制の下で、保護主義を抑止するとともに、ドーハ・ラウンド交渉を早期に妥結に導くことが一層重要になっている。
ロ 2009年のWTOドーハ・ラウンド交渉
WTOドーハ・ラウンド(正式名称は「ドーハ開発アジェンダ(DDA:Doha Development Agenda)」)交渉は、2001年の交渉開始後丸8年が経過した。2008年12月の閣僚会合の開催が見送られたことを受け、2009年に入ってからの交渉は、米国新政権の立ち上がりやインドの総選挙の結果を見つつ、実務レベルで続けられた。その一方で、4月のG20ロンドン・サミットでは、改めて妥結に向けた首脳の意思が確認され、7月のG8ラクイラ・サミットにおけるG8+5(中国・インド・ブラジル・メキシコ・南アフリカ共和国)共同宣言では、2010年の交渉妥結を追求するとともに、貿易担当大臣に対しG20ピッツバーグ・サミットの前に閣僚会合を実施することが指示された。こうした議論を経て、9月、インドが閣僚会合をデリーで開催し、引き続いて同月中旬にはジュネーブで高級実務レベル会合が実施され、10月以降毎月高級実務レベル会合が開催され、交渉の進展が図られた。
11月30日から12月2日まで、ジュネーブにおいて第7回WTO定例閣僚会議が開催された。これは2005年の香港閣僚会議以来4年ぶりのものとなった。同会議は、WTOの活動全体をレビューするもので、ドーハについてのラウンド交渉についての多国間の交渉を目的とするものではなかったが、会議場の内外で二国間・少数国間の活発な協議が行われた。閣僚会議の結果としてとりまとめられた議長総括では、2010年の第1四半期に交渉の状況評価(ストックテーキング)を行うことが確認された。
2009年の交渉は、米国新政権の交渉体制の整備や通商政策に対する取組の遅れのために進展が見られなかったとの指摘があるが、総じて言えば、今次ラウンド交渉の成果を大きく享受することになる新興国(中国、ブラジル、インドなど)に対して一層の貢献を求める米国と、これら新興国との間のこう着状態に打開はみられなかったと言えよう。
[1]農業
農業分野では、これまで、[1]一般的な関税削減率及び例外的に関税削減が緩和される品目(重要品目)の数や扱い(市場アクセス(MA))、[2]貿易をゆがめる国内農業助成のための補助金等の削減(国内支持)、[3]貿易をゆがめる輸出補助金等の撤廃(輸出競争)といった論点について議論を行ってきている。
2008年7月の閣僚会合において、開発途上国にのみ認められる特別セーフガード措置(SSM)等をめぐり交渉が決裂した後、実務レベルで協議が継続された結果、同年12月に農業交渉議長から改訂テキストが発出され、2009年の交渉会合では同テキストをベースに引き続き協議が進められた。
2009年は農業交渉議長が交代した後、引き続き実務レベルで、譲許(じょうきょ)表作成に関する技術的な論点や、主にMA分野の残された論点を中心に協議が行われた。また、12月には、長年の懸案であったEUと南米諸国との間でのバナナの輸入税をめぐる通商紛争が決着した。これにより、EUによる輸入バナナの関税削減率を定めたバナナ合意が成立し、ラウンド交渉全体を前進させる契機になるものとして歓迎された。こうした中、日本は、食料純輸入国である日本の農業の特性を踏まえ、引き続きバランスのとれた最終合意を目指して取り組んできている。
[2]非農産品市場アクセス(NAMA)
NAMA分野では、鉱工業品及び林水産品の関税や非関税障壁(NTB)の削減に関する議論を行ってきている。関税の削減に関しては、高関税ほど大きい削減とする関税削減方式(スイス・フォーミュラ)等の論点とともに、開発途上国配慮、分野別関税撤廃(特定分野の関税撤廃・調和を目指すもので、参加は非義務的であるものの、先進国側は主要開発途上国を含む十分な参加を重視)等の交渉を行ってきた。
2009年においては、前年12月に発出されたNAMA交渉議長テキストに沿って実務レベルで協議が続けられたが、特に、NTBに関する協議が集中的に行われ、各国が提案している様々なNTB削減のためのテキストに基づいて、各国の主張の収れんが試みられた。
工業分野で強い競争力を持つ日本は、農業交渉と歩調を合わせた進展を図りつつ、関税削減、NTB削減の双方における高い成果を伴ったモダリティ合意を目指して積極的な交渉への取組を続けているところである。
[3]サービス
2008年7月にジュネーブ(スイス)で行われた閣僚会合において、自国の自由化が可能なサービスの個別分野を示唆し合う「シグナリング閣僚会合」が開催され、先進国、開発途上国の双方から前向きな示唆がなされた。その成果を基に更なる自由化につなげることが課題となっており、2009年には、サービス関連各種会合が4回開催され、分野別の議論が行われた。日本は、これまで中国、インド、ASEAN各国、ブラジルなどとほぼ毎回二国間交渉を行い、コンピュータ関連、電気通信、建設、金融、流通、海運等の関心分野の自由化を求めた。また、サービス関連の免許や資格等の要件・手続等に関する国内規制についての規律の策定に関する作業部会では、日本としての交渉の進展に貢献した。
サービス交渉推進派の一員として、日本は交渉の進め方に関する提案を行うなど積極的にサービス交渉を行っている。今後とも日本のサービス業界の関心等を踏まえつつ交渉を進めていく方針である。
[4]ルール
ルール分野では、2001年のドーハ閣僚宣言、更に、2005年の香港閣僚宣言に基づき、ダンピング防止及び補助金についての規律の強化及び明確化を目的とした交渉が行われてきた。現在の交渉では、ダンピング防止におけるゼロイング(注1)や、WTOで初めて規律が定められることになる漁業補助金(注2)などの扱いが主な課題となっている。日本としては、引き続き日本の主張が反映されるよう積極的に交渉を行っていく考えである。
[5]貿易円滑化
貿易円滑化の分野では、GATT第5条(通過の自由)、第8条(輸入及び輸出に関する手数料及び手続)及び第10条(貿易規則の公表及び施行)に関連する事項の明確化及び改善等を目的として交渉が行われてきた。
2009年には、5回の交渉会合が開催され、日本からの提案である「貿易関連法令等の公表」、「法令等の制定・改正を行う際の事前協議・事前公表」、「不服申立制度」、「予備審査手続」等について、将来の協定化を念頭に置いた検討が進められ、統合交渉テキストが作成された。今後の交渉により、貿易関連事業者が直面する様々な障害が減少し、手続が迅速化されることが期待される。
[6]開発
今次ラウンド交渉が「ドーハ開発アジェンダ」と称されることに示されるように、開発問題は、今次ラウンド交渉の中核的なテーマとなっており、開発途上国に対する「特別かつ異なる待遇(S&D)」、綿花問題(注3)及び「貿易のための援助」(AFT:Aid for Trade)(注4)を主要テーマとして議論が続けられている。
日本は、「貿易のための援助」への貢献として、2005年に発表した「開発イニシアティブ」に引き続いて、2009年7月、第2回「貿易のための援助」グローバル・レビュー会合の機会に、新たに「開発イニシアティブ2009」(注5)を発表し、各種取組を行ってきている。
また、日本はアジア・太平洋地域における効果的な「貿易のための援助」の在り方や、地域格差の分析などを議論している専門家レベルでの会合において共同議長を務めており、日本が過去に実施した援助における成功体験から学んだノウハウを提供する等の取組を通じて、地域レベルでの取組に積極的に貢献している。
[7]知的財産権
地理的表示(GI)(注6)に関して、ドーハ・ラウンド交渉の中で議論されている多国間通報登録制度については、日本は、米国等とともに各国の商標当局等が登録に拘束されない、負担の軽い制度とすることを提案している。これに対しEU等は、登録により強い法的効果を持たせる制度を主張している。また、TRIPS協定(知的所有権の貿易関連の側面に関する協定)第23条の規定による追加的保護(注7)の対象となる産品については、ドーハ・ラウンドの交渉項目には含まれないが、ワインとスピリッツからその他の産品にも拡大するべきかどうかが議論されている。
また、TRIPS協定と生物多様性条約(CBD)との関係についても、交渉項目とはなっていないが、ドーハ・ラウンドに関連して議論がなされており、ブラジル、インドなどの開発途上国は、特許出願における遺伝資源の出所等の開示(例えば、植物の抽出物を使用した薬品における当該植物の原産国・供給国等の開示)を義務化するTRIPS協定改正を提案している。
2009年には、TRIPS理事会特別会合議長から多国間通報登録制度に関する論点を整理した報告書が出され、また、GIの追加的保護拡大、TRIPS協定とCBDとの関係については、ラミー事務局長主催の協議において議論が継続されている。
ハ 紛争解決
WTO体制に信頼性・安定性をもたらす柱として、紛争解決制度(注8)がある。WTO加盟国は、この制度を加盟国間の貿易紛争を解決するために積極的に利用しており、1995年のWTO発足時から2009年末までの15年間の紛争案件数は402件(年平均約26.8件)に上り、400件を突破した(注9)。
2009年も、日本はこの制度の下で紛争案件に関与した。日本企業に対する米国のダンピング防止措置に関連する「ゼロイング」手続がダンピング防止協定等に違反すると認定された案件(注10)については、米国がWTO協定に適合させる是正措置を十分にとらなかったことを争った履行確認手続(注11)において、4月に発出されたパネル報告書が日本の主張を全面的に認めた。さらに、8月に発出された上級委員会報告書もこのパネル報告書の認定を支持したため、米国が本件においてWTOの是正勧告を履行しておらず、また、米国が履行のためとしてとった措置がWTO協定に違反していることが認定された(同月、これら報告書はWTO紛争解決機関によって採択)。この認定は、不当なダンピング防止税賦課による貿易の制限は容認されないことを明確にするものであり、ルールに基づく自由貿易体制の維持・発展に寄与するものとして高く評価できる。今後、米国による誠実かつ速やかな措置の是正が望まれる。
また、デジタル複合機やパソコン用液晶モニタなど、本来無税であるべき情報技術(IT)製品に対する欧州委員会(EC)による関税賦課について、日本が米国、台湾と共同でECを申し立てている案件(注12)では、パネルの手続が進行し、5月及び7月に行われたパネル口頭聴聞等の際に、米国、台湾と連携して主張を展開した。
韓国の半導体製造企業に対する金融支援措置に関し、日本の賦課した相殺関税の補助金協定違反が認定され、その後韓国が履行確認手続に訴えていた案件(注13)については、韓国の要請により3月以降履行確認パネルによる検討は停止されている(注14)。なお、日本は、別の手続に基づき4月に本件相殺関税を廃止した。
(2)経済連携協定(EPA)/自由貿易協定(FTA)交渉の推進
日本は、アジア太平洋諸国を始めとして、世界の国々との間でEPA交渉を積極的に推進してきており、2009年には、ベトナム及びスイスとのEPAが発効した。これにより、日本が締結したEPAの数は11件となり、EPA相手国との貿易額の割合も15.9%となっている。また、オーストラリア、インド及びGCCとの交渉も精力的に続けており、5月にはペルーとの交渉も開始した。さらに、2004年11月以降中断している韓国との交渉については、首脳・閣僚間の合意を受けて、交渉再開に向けた環境醸成のための実務協議を続けている。これら交渉段階にあるものを含めれば、日本とEPA相手国との貿易額の割合は38.2%となる。貿易・投資の自由化による経済成長をより確実なものとするため、EPAを一層積極的に推進していく。
また、日本のEPAは、合同委員会や分野ごとの各種小委員会に関する規定や、発効の一定期間後に協定の一部若しくは全体について見直しをする規定を有しており、既に締結済みのEPAについても、活用をより促進するため、様々な場を通じて協議を続けている。
二国間EPAに加えて、日本は、東アジア及びアジア太平洋地域における広域の経済連携構想の検討や研究にも積極的に参加している。
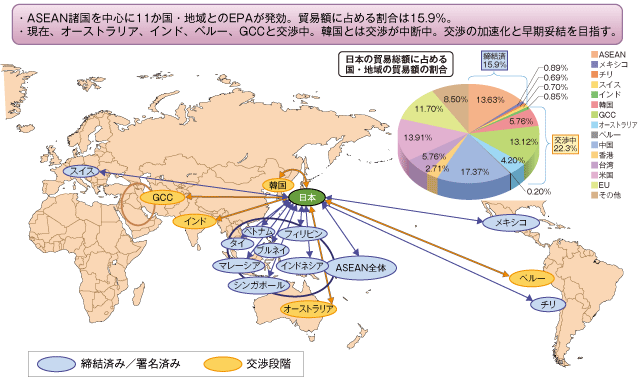
イ 2009年に発効したもの
[1]スイス
9月発効。日本にとって初めての欧州の国とのEPAであり、経済分野における両国の一層の関係強化に寄与するとともに、これまでアジアを中心に進めてきたEPAの網を欧州に広げるという観点からも、日本の経済外交を推進する上で戦略的に重要なEPAと言える。
[2]ベトナム
10月発効。この協定は、物品及びサービスの貿易の自由化並びに関連分野の連携強化を図ることにより、近年目覚ましい経済発展を遂げているベトナムとの貿易及び投資を始めとする経済関係全般の強化に貢献する。ベトナムにとって初めての二国間EPAである。
ロ 交渉中の協定(韓国、GCC、インド、オーストラリア、ペルー)
[1]韓国
日本の隣国であり、貿易・投資を含む経済の相互依存関係が強い韓国とのEPAは、両国に安定的な経済的枠組みを提供し、将来にわたり両国に利益をもたらすものと考えられる。こうした認識の下、2003年12月に交渉を開始したものの、双方の立場の違いから2004年11月以降交渉が中断している。しかし、2008年4月の日韓首脳会談で日韓EPAの重要性について一致したことを受け、交渉の再開に向けた検討及び環境醸成のための実務協議を2008年6月及び12月に開催することとなり、2009年に入っても、7月及び12月に審議官級に格上げした形で実務協議を開催し、早期の交渉再開を目指して協議を続けている。
[2]GCC(湾岸協力理事会)
日本への原油供給国として極めて重要な位置を占めるGCCとの間では、より一層の経済関係強化を図る観点から、2006年9月からFTAの交渉が開始され、これまで2回の交渉会合及び4回の中間会合が開催されている。
[3]インド
10億人を超える人口を有する潜在的な大市場であるインドとの経済関係強化は、両国にとって利益をもたらすとの観点を踏まえ、2007年1月からEPA交渉を開始し、2009年10月には第12回交渉会合が行われた。また、12月の鳩山総理大臣のインド訪問の際にも、交渉の加速化が確認されている。
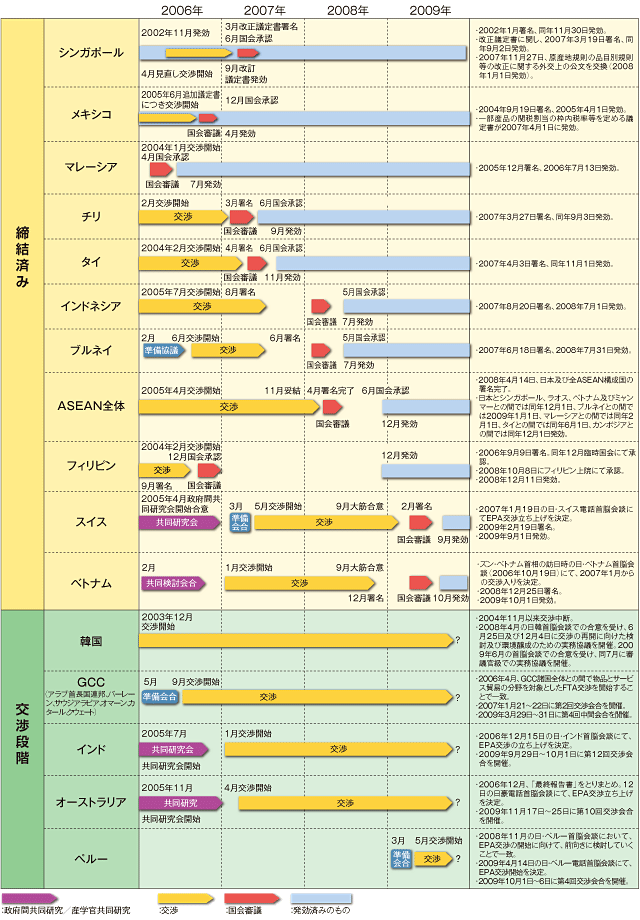
[4]オーストラリア
エネルギーや食料の主要な供給国という経済面のみならず、政治・安全保障の面でも緊密な関係にあるオーストラリアとは、オーストラリアの強い要望を踏まえ2007年4月からEPA交渉を行っている。2009年に開催した3回の会合を含め、11月末までに10回の交渉会合を行っている。
[5]ペルー
歴史的にも日本と関係の深い中南米の主要国であるペルーとは、ペルーの強い要望を踏まえ、2009年4月の日・ペルー電話首脳会談で交渉開始を決定し、5月から10月までに4回の交渉会合を行っている。
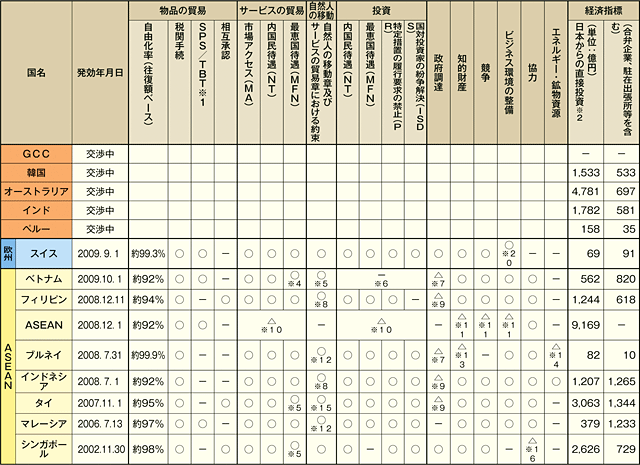
※2 日本からの直接投資の出典:日本銀行「国際収支統計」2007年中 対外・対内直接投資
※3 進出日系企業数の出典:外務省領事局政策課「海外在留邦人数調査統計」2008年速報(2007年10月1日現在)
※4 第三国に付与した待遇よりも不利でない待遇を付与することを考慮又は協議する旨の規定。
※5 現行入管法令の範囲内で、看護師資格をもつ看護業務従事者の受け入れを約束。ベトナム人看護師・介護福祉士候補者の受け入れ可能性については交渉継続。
※6 日・ベトナム投資協定が必要な変更を加えた上で協定の一部となる旨規定(第9条4)。
※7 ビジネス環境整備章に言及がある。
※8 看護師・介護福祉士候補者等の受け入れを約束。
※9 NT又は無差別待遇に関する義務規定はない。
※10 発効後1年以内に設置される小委員会で実体的な規定に関する交渉を継続する旨規定。
※11 経済的協力章内の第53条に協力の分野として挙げられている。
※12 短期商用訪問者等の一時滞在についてサービス貿易章の下で約束。
※13 知的財産章はないが、ビジネス環境整備章に知的財産の保護に関する制度の整備に係る努力義務規定等がある(第97条)。
※14 エネルギーのみを対象としている。
※15 介護福祉士候補者、タイ・スパ・セラピストの受け入れの可能性については交渉継続。
※16 経済関係強化のための協力枠組みについて規定あり(第13~20章)。
※17 現地における拠点設置(LP)の規律により、MAの一部を約束。
※18 税関手続章、TBT章及び競争章において、それぞれの分野における協力に関する規定あり。
※19 知的財産章はないが、知的財産分野における協力に関する規定(第144条)等がある。
※20 「経済関係の緊密化章」を設けている。
ハ 広域経済連携に向けた取組
日本は、東アジア及びアジア太平洋地域における経済連携の枠組みの研究や検討において、WTO体制を含め世界経済・貿易に与える影響、関係各国の考え方等を踏まえ、これら各国と協議しつつ、積極的な参加及び貢献を行っていく考えである。2009年には、ASEANと日中韓の13か国によるFTA(EAFTA)構想や、これら13か国にオーストラリア、ニュージーランド、インドを加えた16か国によるEPA(CEPEA)構想についての民間研究の最終報告がとりまとめられ、ASEAN関連経済大臣会合を経てASEAN+3首脳会合及びEASに報告された。その結果、原産地規則、税関手続、関税分類、協力の分野について、政府間の作業部会で検討を続けることとなった。また、FTAAP構想については、11月のAPEC閣僚・首脳会議において、これまでの検討作業を踏まえ、FTAAPへのあり得べき道筋を探求することに合意し、日本が議長を務める2010年のAPECにおいて検討結果を報告することになった。また、アジア太平洋地域においては、シンガポール、ニュージーランド、チリ、ブルネイによる環太平洋連携協定(TPP)に、米国、オーストラリア、ペルー、ベトナムが参加するという動きがあり、日本としてもその動向に注目している。
さらに、2003年以降続けられてきた日中韓FTAに関する民間研究については、2009年10月の日中韓サミットを経て、日中韓貿易経済大臣会合の結果、政府関係者の参加を含む産官学共同研究に移行することとなった。
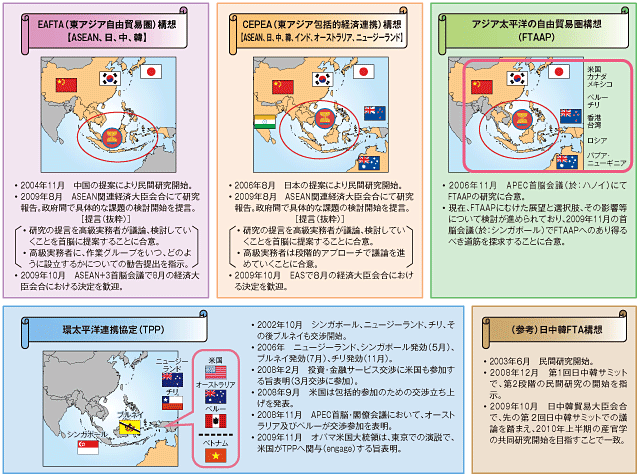
(3)租税条約/投資協定/社会保障協定
イ 租税条約
租税条約は、国境を越える経済活動に対する国家間の課税権を調整することにより、国際的な二重課税を回避するとともに、投資所得(配当、利子、使用料)に対する源泉地国課税の減免等を通じて国際的な投資交流を促進するための重要な法的基盤となっている。また、租税条約は脱税及び租税回避行為等を防止することも目的としており、情報交換や相互協議といった税務当局間の国際協力を推進するための規定も整備している。
1月にはクウェートとの間の条約、6月にはサウジアラビアとの間の条約及びスイスとの間の条約改正、12月にはオランダとの間の条約改正について基本合意に達したほか、租税に関する情報交換ネットワークの整備・拡充を目的として、6月にはバミューダ(英国の海外領土)との間の協定、11月にはベルギー、シンガポールとの間の条約改正、12月にはマレーシア、ルクセンブルクとの間の条約改正について基本合意に達した。また、12月にはブルネイ、カザフスタンとの間の条約が発効した。以上のほか、2009年末時点でアラブ首長国連邦との間の条約締結に向けた交渉を行っている。
ロ 投資協定
貿易の自由化及び円滑化に関しては、WTOにおいて多国間の包括的なルールが定められているが、投資に関してはこのようなルールが存在しないため、各国は、二国間又は複数国間で投資協定を締結することにより、投資を促進するための環境整備に努めている。
日本としてもこのような取組を積極的に進めてきており、ウズベキスタン(9月)及びペルー(12月)との間で、投資の保護、促進及び自由化について規定する二国間投資協定(BIT)が発効したほか、スイス(9月)との間では、同様の投資に関する規定を含むEPAが発効した。また、カザフスタン、カタール、コロンビア、サウジアラビア及び中国・韓国との間で、それぞれ二国間又は三国間投資協定について交渉中であり、さらに、インド、オーストラリア及びGCCとの間でも、投資に関する規定を含むEPAについて交渉中である。投資協定の締結は、投資を促進するための環境を整備・改善するものであり、日本企業の活躍の場が世界的に広がるとともに、投資協定締結の相手国・地域においても、日本からの技術移転、雇用促進等の効果によって経済が活性化し、日本とそれらの国・地域との経済関係の発展にもつながることが期待される。
このほか、日本は、OECDやAPECなどの国際的な枠組みにおいても、投資の自由化及び円滑化を促進するために、多国間のルールを形成する必要性を主張するなど、建設的な役割を果たしてきている。
ハ 社会保障協定
社会保障協定は、社会保険料の二重負担や掛け捨ての問題を解消することなどを目的としており、海外に進出する日本企業や国民の負担を軽減し、ひいては相手国との人的交流や経済交流を一層促進する効果が期待される。
1月にはオーストラリア、3月にはオランダ、6月にはチェコとの協定が発効し、7月にスペイン及びイタリアとの協定がそれぞれ国会で承認された。また、10月にはアイルランドとの協定の署名が行われた。現在、スイス、ハンガリー、ブラジル、スウェーデン及びルクセンブルクとの間で、それぞれ交渉中ないし交渉開始に向けた意見交換中である。
(4)知的財産権保護の強化
知的財産権保護の強化は、技術革新を促進し経済の発展にとって極めて重要である。そのため、日本は、知的財産権保護の強化のため、様々な取組を行っている。
まず、日本が提唱した新しい国際的な法的枠組みである「模倣品・海賊版拡散防止条約(Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA)(仮称)」(注15)については、その早期実現に向けて関係国との交渉を積極的にリードしている。2008年6月から、条文案に関する交渉を行い、2009年11月までに6回の会合を開催した。今後も交渉を継続し、2010年中の可能な限り早期の交渉妥結を目指している。その他、G8サミット、APEC(注16)、OECD、WTO(TRIPS理事会(注17)))や世界知的所有権機関(WIPO)等での多国間の議論に積極的に参画している。
また、二国間では、中国(注18)、韓国、米国(注19)、EU(注20)との間で個別の知的財産権保護の強化・協力に関する対話を続けている。また、EPA(注21)においても、可能な限り知的財産権に関する規定を設けることとしている。
(注1)米国商務省は、ダンピング・マージン(輸出国の国内正常価格より輸出価格が低い場合の価格差)を計算する際に、[1]まず、その産品の個々のモデル又は取引ごとに輸出国の国内正常化価格と対米輸出価格を比較し、[2]その結果を総計して、この産品全体のダンピング・マージンを算定している。総計をする[2]の段階において、[1]の比較で輸出国の国内正常価格より対米輸出価格が高いものについてはその価格差はマイナスとなるが、ゼロイングとは、それらをマイナスとして差し引かず、一律「ゼロ」とみなして計算する方式で、これにより、ダンピング・マージンが不当に高く計算される。2007年11月に発出された議長テキスト案では、日本を含めた多くの国々が強く禁止を主張してきたこのゼロイングが容認されていたが、2008年12月に発出された改訂議長テキストでは、ゼロイングを容認する規定が取り下げられるなど、日本や、ほかの立場に一定の配慮が見られる規定となっている。
(注2)漁業補助金については、韓国、台湾と共同で提案を提出し、欧州委員会(EC)とともに、過剰漁獲につながる補助金に限定して禁止すべきという主張を行ってきた。2007年の議長テキストでは、日本が主張してきた禁止補助金を限定する構造となってはいるが、その対象範囲については日本の主張よりも広範囲にわたるものとなっている。
(注3)西アフリカの後発開発途上国(LDC)4か国(ブルキナファソ、ベナン、マリ、チャド)によって提起されている問題。本来、綿花はこれら諸国にとって十分競争力のある産業であるにもかかわらず、一部先進国が自国の綿花産業に与えている補助金のために、綿花輸出が阻害され大きな打撃を受けているとして、先進国に対して補助金の段階的撤廃及び撤廃完了までの補償措置を要求している。
(注4)開発途上国が貿易から十分な利益を得るためには、貿易自由化だけでは不十分であり、貿易関連の技術支援、生産能力の向上や流通インフラ整備などを含めた供給面での支援、また、これらのモニタリングや評価が必要との観点から、WTO、OECD、国連貿易開発会議(UNCTAD)などで「貿易のための援助」に関する議論が行われている。
(注5)「開発イニシアティブ」は、貿易促進を通じて開発途上国の発展に資することを目的に、2006年から2008年の3年間に100億米ドルのODAや1万人の技術支援及びLDC無税無枠等様々な措置を組み合わせて包括的な支援を行うもの。「開発イニシアティブ」の目標達成に続き、2009年には新たに「開発イニシアティブ2009」を発表し、2009年から2011年の3年間に、120億米ドルのODAや4万人の技術支援、開発途上国との貿易の最新の実情を踏まえた一般特恵関税制度(GSP)の改正への着手等を通じて、開発途上国の発展に貢献する。
(注6)ワインのボルドー、ブランデーのコニャックのように、その商品について確立した品質、評判等が主として地理的原産地に帰せられると考えられる場合において、その商品が当該地理的原産地の産品であることを特定する表示を言う。日本においては、国税庁長官が国内で保護する焼酎乙類や清酒の産地について地理的表示として指定している。
(注7)TRIPS協定は、全産品について当該産品の地理的原産地について、公衆を誤認させる方法等での地理的表示の使用を防止することを原則としつつ(第22条)、ワイン及びスピリッツについては、公衆の誤認等の有無にかかわらず、当該地理的表示によって表示されている場所を原産地としないものへの使用を防止するという追加的保護を定めている(第23条)。
(注8)WTO紛争解決手続(DSU)においては、パネル(小委員会)は個別の紛争案件ごとに構成される。紛争当事国はパネルの法的判断に不服がある場合には、上級委員会に申し立てることができる。上級委員会は7名の委員で構成されており、委員の任期は4年(再任可能)。日本は1995年のWTO発足以降上級委員を輩出しており、松下満雄・元委員(成蹊大学法科大学院教授)、谷口安平・前委員(京都大学名誉教授)に続き、2008年6月以降、大島正太郎氏(前駐韓国特命全権大使)が上級委員の任にある。
(注9)GATTの下での紛争案件数は、1948年から1994年までの間に314件(年平均6.7件)。WTOでの紛争案件数402件のうち、2009年末までに日本が当事国(申立て国又は被申立て国)としてかかわった案件は、28件(なお、件数については、WTOホームページに掲載されているDS番号が付されたすべての案件をそれぞれ1件として計算している)。
(注10)日本は、2005年2月に、米国のゼロイング方式自体とその実際の適用がWTO協定(アンチダンピング協定等)に違反するとして、WTOに申し立てた。2006年1月にWTO協定違反が確定し、米国に対して是正勧告が行われた。米国は、勧告履行期限(2006年12月24日)が到来しても、一部の措置を除いて履行しなかったので、日本は2007年4月に履行確認パネルの設置を求めた。
(注11)パネル・上級委員会での検討の結果採択されるWTO紛争解決機関の勧告の実施状況について、当事国間で見解の相違がある場合に、紛争解決手続(DSU)21条5に基づき勧告が実施されているか否か等について判断を行うための手続。
(注12)ECが、「情報技術製品の貿易に関する閣僚宣言(ITA)」において無税扱いにすべきとされている製品について、製品の多機能化・高機能化を契機に、譲許表上の分類を変更しWTO協定に整合しないと考えられる課税を行っている案件。日本が米国、台湾とともに問題視しているのは、デジタル複合機(税率6%)、パソコン用液晶モニタ(税率14%)、セット・トップ・ボックス(税率13.9%)の3品目である。
(注13)韓国政府による韓国ハイニックス・セミコンダクター社への支援措置に関し、韓国から日本に輸入される同社製DRAM(ダイナミック・ランダム・アクセス・メモリ。半導体の一種)に対する27.2%の相殺関税の賦課について、WTO協定違反が認定されたことを受け、日本は賦課していた相殺関税27.2%のうち、18.1%についてはその対象から除外することとし、2008年9月に関税率を9.1%としたが、韓国がこれを不十分だとして履行確認手続に訴えていた案件。
(注14)DSU第12条12により、パネルの検討の停止から12か月が経過すると、パネルはその設立の根拠を失うとされている。
(注15)日本は、2005年のG8グレンイーグルズ・サミット(於:英国)において、模倣品・海賊版の拡散防止に向けた法的枠組み策定の必要性を提唱して以来、先進国及び知的財産権の保護に高い志を有する開発途上国とともに、本構想の実現に向けて積極的に議論を行ってきた。2007年10月、日本は、米国、EU等とともに、ACTAの実現に向けて、知的財産権の保護に関心の高い国々と緊密に連携を図り、ACTAにおいて実現していくべき内容についての集中的な協議を開始することを発表した。現在、交渉には日本を始め、米国、EU、スイス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、メキシコ、韓国、モロッコ、シンガポールが参加している(模倣品・海賊版対策の取組については、第4章第2節2.(2)「知的財産権保護の強化」を参照)。
(注16)APECでは、11月の首脳宣言において、APEC模倣品・海賊版イニシアティブ及び地域の特許制度を改善する取組の実施についてのエコノミーの進展を歓迎、更なる進展を期待する旨言及された。
(注17)TRIPS理事会とは、TRIPS協定の実施、特に加盟国による義務の遵守を監視し、同協定に関する事項の協議を行う場である。
(注18)日中間では、6月の第2回 日中ハイレベル経済対話において、中国における知的財産権執行強化について要請した。
(注19)日米間では、日米次官級経済対話及び「日米規制改革及び競争政策イニシアティブ」の対話等において、模倣品対策を始めとする知的財産権保護強化のための両国間の緊密な協力関係を維持していくことを確認し、同イニシアティブについての日米両首脳への第8回報告書では上記協力関係を維持する旨記載された。
(注20)日・EU間では、4月の知的財産権に関する日・EU対話で模倣品・海賊版対策協力等について協議した。
(注21)シンガポール、メキシコ、マレーシア、チリ、タイ、フィリピン、ブルネイ、インドネシア、ASEAN、ベトナム、スイスとの間で知的財産権に関する規定を含む協定が発効済み。