6.平和構築
(1)現場における取組
イ 国連PKO(注1)等への貢献
冷戦終結後、内戦の増加等国際環境の変化に伴い、停戦監視等の伝統的な任務に加えて、元兵士の武装解除、動員解除、社会復帰(DDR:Disarmament, Demobilization and Reintegration)や治安部門改革、選挙、人権、法の支配等の分野における支援、政治プロセスの促進、紛争下の文民の保護など、多くの任務を与えられた国連PKOが設立されており、その要員数は最大のミッションで約20,000人、展開中の19の国連ミッション全体で98,000人を超えている(2009年12月末現在)。こうしたミッションの複雑化・大規模化と、必要な資源の不足という事態を受けて、国連を始めとする多くの場でPKOの改革をめぐる議論が行われている。
2008年7月のG8北海道洞爺湖サミット首脳宣言や2009年7月のG8ラクイラ・サミット首脳宣言において平和維持・平和構築に関する軍、警察、文民の能力強化について言及されたように、世界的な平和維持能力の強化が重要な課題となっている。こうした観点から、日本は、アフリカ等のPKO訓練センターの支援を行っているほか、10月、国連PKOの幹部要員候補を対象とする訓練コースを米国と共催した。
日本は、1992年に制定された国際平和協力法(PKO法)に基づき、これまで11の国連PKOなどに延べ5,100人以上の要員を派遣してきた。12月末現在、国連兵力引き離し監視隊(UNDOF)に46名、UNMISに2名、UNMINに6名の計54名の自衛官を派遣している。これらに加え、2010年2月からMINUSTAHに自衛隊の部隊等(約350名)の派遣を開始した。また、同法に基づき、2009年1月には、ガザ地区のパレスチナ被災民を支援するため、UNRWAに毛布29,000枚等、同5月にもスリランカの被災民を支援している国際移住機関(IOM)に対して、給水容器30,000個等の支援物資を提供した。
| 順位 | 国名 | 派遣人数 |
|---|---|---|
| 1位 | パキスタン | 10,764名 |
| 2位 | バングラデシュ | 10,427名 |
| 3位 | インド | 8,757名 |
| 4位 | ナイジェリア | 5,807名 |
| 5位 | エジプト | 5,155名 |
| 11位 | イタリア | 2,451名 |
| 15位 | 中国 | 2,136名 |
| 17位 | フランス | 1,610名 |
| 38位 | 韓国 | 397名 |
| 41位 | ロシア | 365名 |
| 44位 | ドイツ | 288名 |
| 46位 | 英国 | 282名 |
| 56位 | カナダ | 170名 |
| 72位 | 米国 | 75名 |
| 85位 | 日本 | 39名 |
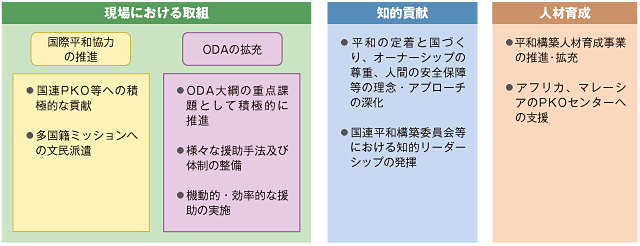
ロ 平和構築に向けたODA等による協力
ODA大綱や、「国際協力企画立案本部」(注2)が策定した「2009年度国際協力重点方針」(注3)は、「平和の構築」を重点課題の一つとして位置づけている。日本は、人間の安全保障の視点に立ち、紛争の予防や緊急人道支援とともに、紛争の終結を促進する支援から平和の定着や国づくり支援に至るまで、継ぎ目のない平和構築支援に積極的に取り組んでいる。
[1]アフガニスタン
アフガニスタンの安定と復興は、国際社会の平和と安定に関わる最重要課題の一つである。このため、日本はアフガニスタンの平和構築のために、警察支援、麻薬対策支援、地雷除去支援などを積極的に実施してきたほか、DDRや非合法武装集団の解体(DIAG)において主導的な役割を果たしてきた。加えて、5月から、アフガニスタンで活動するPRTに開発援助調整のための文民支援チーム(4名)を派遣している(詳細は第2章第4節2.(1)「北大西洋条約機構(NATO)との協力」を参照)。
11月には、日本はアフガニスタン・パキスタンに対する新たな支援策として「テロの脅威に対処するための新戦略」を発表した。この中で、アフガニスタンに対しては、警察支援等の治安能力向上支援、元タリバーン末端兵士の職業訓練や雇用創出のための支援といった社会への再統合支援、アフガニスタンの持続的・自立的発展のための基礎生活分野への支援を柱として支援を実施することとしており(アフガニスタン支援の詳細については、第2章第6節「中東と北アフリカ」を参照)、日本は今後もアフガニスタンの平和構築のために積極的に貢献していく。
[2]アフリカ
日本は「平和の定着」を対アフリカ支援の柱の一つとして位置付け、支援を強化してきている。2008年5月、TICAD Ⅳにおいて、人間の安全保障の確立の一環として「平和の定着・良い統治の促進」を重点事項の一つとして取り上げ、継ぎ目のない支援やアフリカにおける平和維持能力の強化等の重要性を強調した。
例えばスーダンでは、2008年5月に開催された第3回スーダン・コンソーシアム会合において、当面約2億米ドルの支援を表明し、20年以上続いた南北内戦により発生した、計18万人の元兵士に対して、DDRの支援を行っている。また、国際機関や日本のNGOと積極的に連携しながら、難民の帰還・再統合支援、地雷・不発弾の除去活動や回避教育、水供給関連施設整備、医療、食糧支援などを行っている。さらに、日本は、スーダンの平和構築のため人的貢献を行っており、現在、国連機関職員として約30人、NGO職員として約25人の日本人がスーダンで活躍している。
[3]イラク
イラクの復興と安定化は、日本が取り組む平和構築の最重要課題の一つである。相次ぐ戦争と経済制裁により疲弊したイラクが、自力復興の軌道に乗り、安定した民主国家となるまでの橋渡しとして、イラク国民の生活基盤の再建等に重点を置いた無償資金協力や、中長期的な大規模復興需要を手当てするための円借款供与といった資金協力、技術協力による人材育成を通じて、日本はイラクにおける貢献を一貫して実施してきている。
具体的取組としては、イラク国民の生活基盤の再建(電力、水・衛生、医療・保健等)を実施したほか、治安改善支援(警察車両供与、警察訓練等)や、政治プロセス促進のための支援(選挙支援、憲法制定支援、国民融和促進等)を実施してきた。2009年には、政治プロセス支援の一貫として、1月の地方議会選挙、7月のクルディスタン地域選挙にそれぞれ日本選挙監視団の派遣を行った。
(2)知的貢献の強化-平和構築委員会
宗教や民族間の対立など様々な要因による地域紛争や内戦は、一度終結しても紛争予防、社会開発等の点において適切なフォローアップがなされないと、紛争状態に逆戻りするケースも少なくない。このような問題意識の下、2005年12月、国連安保理及び総会に対して紛争後の平和維持から復興・開発まで継ぎ目ない支援に関する助言を行うことを目的として、国連平和構築委員会が設立された。
日本は、創立メンバーとして同委員会の活動に貢献してきており、2007年6月から約1年半にわたり議長職を務めた。同委員会は、国連安保理及び総会と緊密に連携しつつ、関係諸機関や市民社会の知見も活用しながら、対象国における平和構築上の優先課題を特定し、国際支援を呼び込む役割を担っている。
現在対象国となっているブルンジ、シエラレオネ、ギニアビサウ及び中央アフリカ共和国について、日本は、これまでの平和構築支援の経験と知見を最大限活用し、人間の安全保障の理念の共有を含め、これらの国における平和構築戦略の策定と実施にイニシアティブをとってきている。また、同委員会は、策定された平和構築戦略枠組みを具体的に実現していくために、各国、国際機関を始めとする様々な拠出主体に対して、対象国への支援の実施を呼び掛けており、日本は、例えばシエラレオネでは電力供給、ブルンジでは元戦闘員の社会復帰支援やインフラ整備、ギニアビサウでは選挙支援、中央アフリカ共和国では教育を通じた基礎生活改善等、平和構築に不可欠な分野で支援を行っている。さらに、同委員会の活動を確固たるものにするため、新規検討対象国の拡大や国連安保理を始め関係機関との協力強化といった点についても、議論を主導している。
(3)平和構築人材育成事業
平和構築において、人道支援、法の支配の確立、人権の擁護、選挙支援、社会・経済の復興・開発の促進などの活動を担う文民は重要な役割を果たしており、こうした分野で高い専門性を持つ文民の育成は世界的な課題となっている。このような状況を踏まえ、日本は、2007年度に、平和構築の現場で活躍できる日本及びそのほかのアジアの文民専門家を育成することを目的とする、「平和構築人材育成事業」を開始した。2009年度からは、新たなコースの設置による研修員の数と対象の拡大、海外実務研修期間の延長等により、事業を拡充した。過去2年間で約60名に上る本事業の修了生の多くは、既にスーダン、東ティモールなど、世界各地の平和構築の現場で活動しており、その活躍は国際機関等の関係者から高い評価を得ている。

(注1)United Nations peacekeeping operations(国連平和維持活動):UNPKO又は単にPKOという。PKOとは本来、国連安保理決議に基づき、停戦合意の成立後に国連が紛争当事者の間に立って停戦や軍の撤退等を監視することにより、事態の沈静化や紛争の再発防止を図り、紛争当事者による対話を通じた紛争解決を支援することを目的とした活動である。しかし、現在はこれらの伝統的な任務に加え、選挙、難民帰還等の支援から行政・警察能力強化までも任務とする複合的なPKOが増加しており、任務の多様化、複雑化の傾向が進んでいる。
(注2)海外経済協力会議で審議された基本戦略の下、ODAの具体的な企画・立案・調整の中核を担う、外務省が設置した会議。本部長は外務大臣。2009年に開催した同本部では、「2009年度国際協力重点方針」「平和の構築」について議論した。
(注3)海外経済協力会議の結果やODA大綱・ODA中期政策と国ごとの援助指針である国別援助計画を踏まえつつ、外交政策を踏まえた国際協力を推進するため、2007年度から外務省において年度別に策定。