第7節 アフリカ(サブサハラ)
【総論:世界が取り組むべき課題としてのアフリカ問題と国際社会の取組】
<2004年のアフリカ~紛争から平和・安定へ~>
2004年は、アフリカが平和と安定に向けて大きく前進した年であった。長期にわたり紛争が続いたソマリアとスーダンにおいて、それぞれ暫定政権と和平合意が成立し、和平に向けて大きな進展があった。また、停戦後も不安定な情勢が続く大湖地域についても、11月にタンザニアで開催された「第1回大湖地域首脳会議」において、関係国の首脳が一堂に会し、平和と安定に向けた力強いメッセージが発出された。このような各国における平和の進展に加え、アフリカ連合(AU)においても3月には全アフリカ議会が設立され、5月に平和・安全保障理事会が発足するなど、政治的統合に向けた動きが本格化した。
さらに2004年には約10か国において大統領選挙が実施されたが、いずれも平和裡に行われ、アフリカにおける民主化の定着を示した。象徴的な例として、アパルトヘイト後、民主化達成10周年を迎えた南アフリカ共和国では、4月に総選挙が実施され、選挙後に開催された新大統領就任式典及び民主化10周年記念式典には25か国を超えるアフリカの首脳や日本の森喜朗特派大使(前総理大臣)をはじめとする世界各国の要人が参加して、アフリカの新しい時代の始まりの瞬間を共有した。
また、5月には国際サッカー連盟(FIFA)理事会において、2010年FIFAワールドカップを南アフリカで開催することが決定された。このことは、アフリカ大陸初の大会となるだけに、国際的な注目を集めた。さらに、ワンガリ・マータイ女史(ケニア環境・天然資源副大臣)が、持続可能な開発、民主化及び平和への貢献を評価され2004年ノーベル平和賞を受賞した。このように、アフリカ全体の平和と安定化へ向けた動きを象徴するような動きが随所に見られた。
<アフリカの現状>
アフリカにはHIV/AIDS、マラリア等の感染症、紛争、難民、貧困といった、その影響がアフリカのみには留まらない地球的規模の課題が集中して存在している。また、アフリカの一部の地域はテロの脅威に直面するなど、アフリカの問題は、国際社会全体が一体となって取り組むべき問題である。アフリカは、2001年にアフリカ自身による初の包括的開発イニシアティブである「アフリカ開発のための新パートナーシップ(NEPAD)」(注1)を採択し、2002年にはアフリカ統一機構(OAU)をアフリカ連合(AU)(注2)に改組するなど、アフリカ域内の協力の強化を図っている。このような動きは、アフリカ開発に向けたアフリカの自助努力(オーナーシップ)を具体化する新たな動きとして注目を集めている。
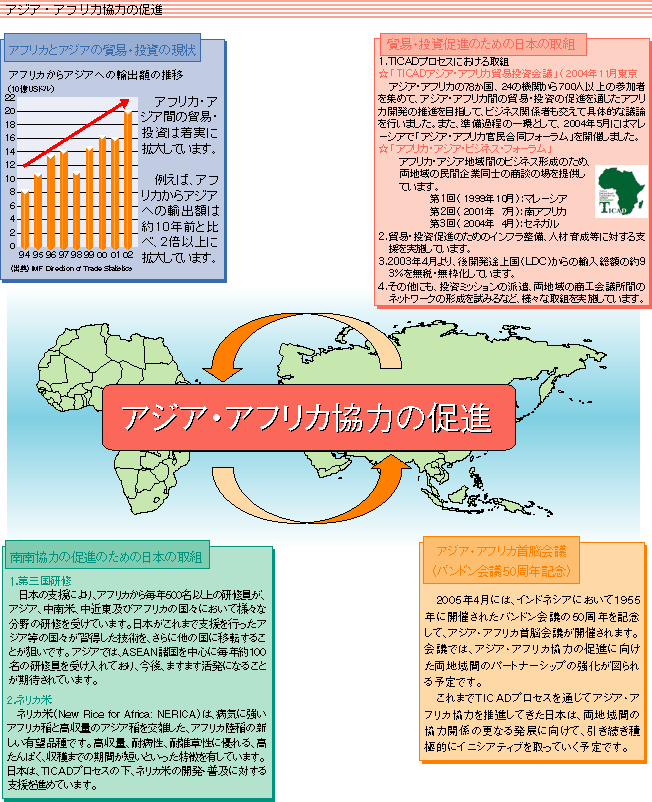
Power Pointファイルはこちら
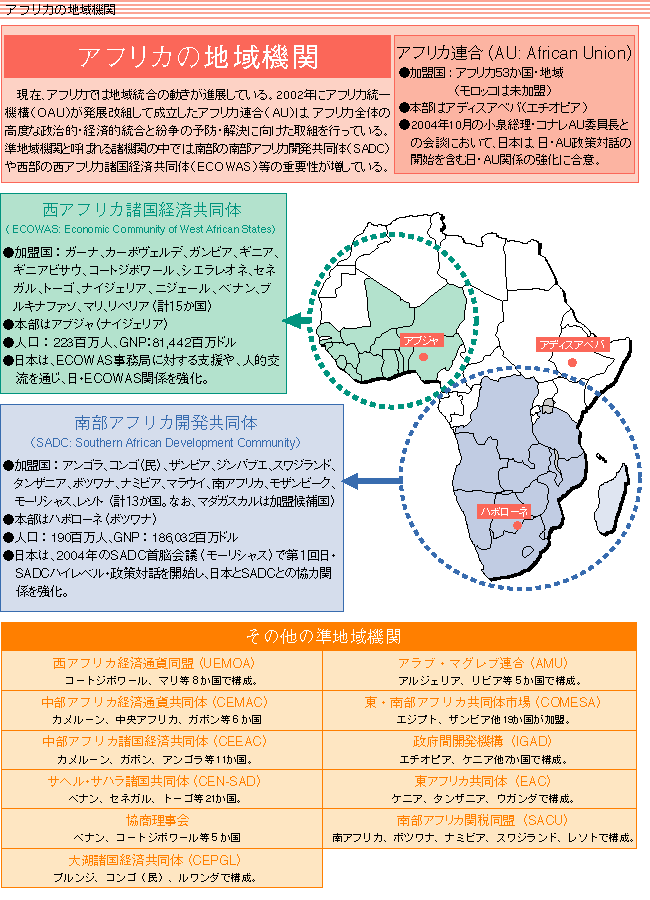
Power Pointファイルはこちら
<国際社会の取組>
このようなアフリカの状況を背景に、近年、国際社会はアフリカ問題への関心を高めてきた。特に先進国首脳会議(G8サミット)では、議長国であった日本の提案によって2000年のG8九州・沖縄サミットの際にアフリカ諸国を含む途上国が招待されたことを契機に、アフリカ問題が主要な議題の一つとなっている。また、2002年のカナナスキス・サミットではG8によるNEPAD支援のための包括的な計画である「G8アフリカ行動計画(AAP)」(注3)が策定された。G8とアフリカ諸国首脳との対話はその後も続いており、2004年6月のシーアイランド・サミットでは6か国のアフリカ首脳が招待された。
日本は様々な国際的な取組(注4)に対し、国際社会の責任ある一員として積極的に参加・貢献し、さらに「アフリカ問題の解決なくして、世界の安定と繁栄はない」との考えの下、日本の独自のイニシアティブであるアフリカ開発会議(TICAD)プロセス(下記参照)を通じて、アフリカ開発への支援を積極的に実施している。また、米国、英国、フランス、欧州連合(EU)といった主要国や国際機関とも協調を行いつつ、対アフリカ支援を実施している。2005年は、英国が議長を務めるG8グレンイーグルズ・サミット、国連ミレニアム宣言に関する首脳会議等を通じてアフリカ問題に一層の焦点が当たるいわば「アフリカの年」であり、日本は対アフリカ協力を強化している。
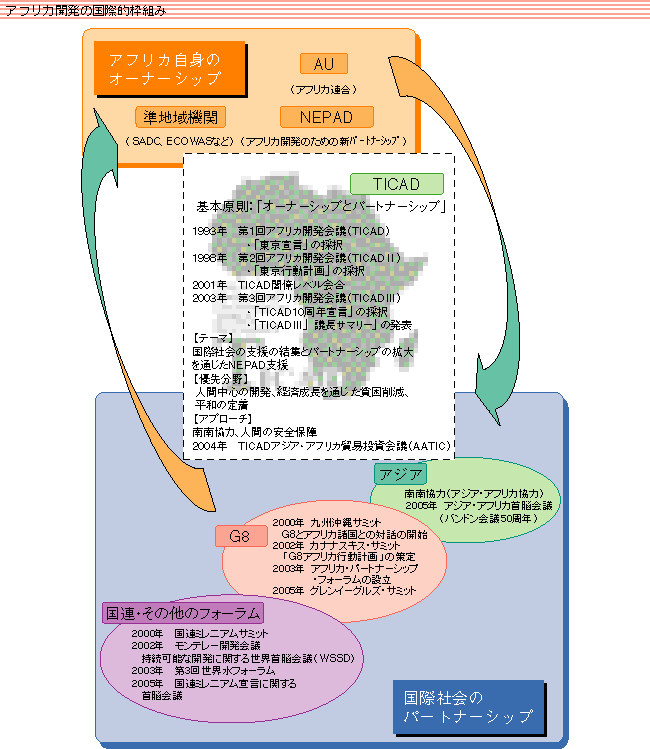
Power Pointファイルはこちら