【拡大中東・北アフリカ構想】
2004年のG8議長国を務めた米国のイニシアティブにより、またアラブ諸国側からも改革の必要性が謳われたことを背景に(注15)、6月のG8シーアイランド・サミットにおいて、政治的、経済的および社会的分野における拡大中東・北アフリカ(注16)地域諸国の自発的な改革努力をG8が支援するものとして「拡大中東・北アフリカ構想」(注17)が合意された。また、同構想を具体化する場として、G8及び地域諸国の閣僚(外相等)による「未来のためのフォーラム」の設立が合意された。日本は、外部からの押し付けではなく、地域の自主性と多様性の尊重が重要であるとの考えを一貫して主張してきており、これは同構想の原則的立場となった。同サミットに出席した小泉総理大臣は、地域の安定と発展のためには急増する若年層への雇用機会の創出が喫緊の課題であるとの認識に基づき、日本が向こう3年間で教育・識字分野で10万人、職業訓練分野で1万人が裨益する支援を行うとともに同地域の中小企業支援のために国際金融公社(IFC)(注18)に設置される基金に最大1,000万ドルの拠出を行う旨を表明した。
9月、ニューヨークにおいて、G8、地域諸国、国際機関の参加を得て「未来のためのフォーラム」外相級準備会合が開催され、第1回会合を年内にモロッコで開催することが合意された。また、G8及びアラブ連盟諸国の外相級会合を開催するとのエジプトの提案が受け入れられた。川口外務大臣(当時)は、「未来のためのフォーラム」がすべての拡大中東・北アフリカ諸国に開かれたものであるべきこと、イスラエル・パレスチナ紛争の解決およびイラクの平和と安定が重要との考えを説明するとともに、「未来のためのフォーラム」の運営においてはAPECの例が参考になるとの考えから、ビジネス界との連携の重要性等を指摘した。
12月、モロッコのラバトにおいて、「未来のためのフォーラム」第1回会合が開催された。会合では、サミットで発表された改革イニシアティブの現状報告及び今後の取組が議論された。また、2005年にバーレーンにおいて第2回会合、2006年にヨルダンにおいて第3回会合を開催することが合意された。日本を代表して第1回会合に参加した逢沢外務副大臣は、新たな取組として、日本が2005年にヨルダンと共同で「職業訓練に関するワークショップ」(注19)を開催することを表明した。
日本は、これまでイスラム諸国との間で、ODA等を通じた協力とともに、「イスラム世界との文明間対話セミナー」、「日本・アラブ対話フォーラム」等を通じた対話を進めてきている。「拡大中東・北アフリカ構想」についても、この地域の国々自身が行う改革努力をG8として後押しすることを支持し、「未来のためのフォーラム」において職業訓練を中心にした取組を進める方針である。また、G8と地域諸国の要人が一堂に会する新たな多国間協議の場として、同フォーラムを日本の対中東外交に活用していく考えである。
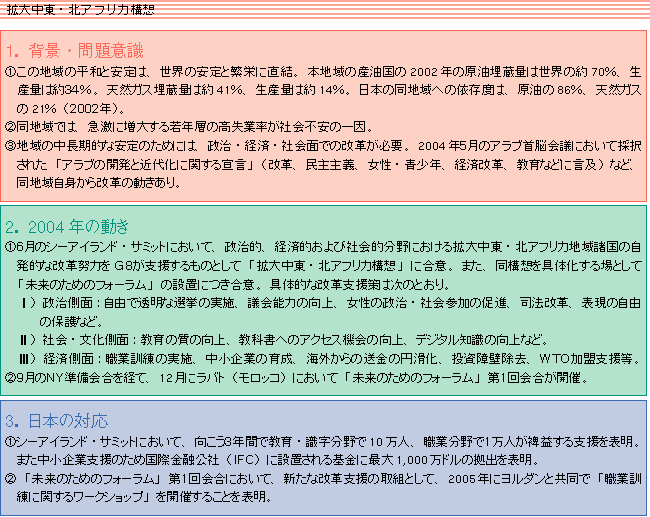
Power Pointファイルはこちら