第3章 > 第1節 > 4 国 連
【総論】
近年、グローバル化が進展する中、紛争防止、テロ、国際組織犯罪、貧困と成長、地球環境、難民、不拡散といった課題が以前にも増して相互に関係するようになっている。こうした問題の解決に向けては、一国ごとあるいは地域ごとの対応では難しい面も多く、国際社会がより一層団結して取り組む必要がある。国連は、平和と安全の問題から経済・社会分野における協力の促進まで広範な分野を扱っており、加盟国数も2002年9月にスイスと東ティモールが加わり191か国となった。国際社会における独立国のほとんどが国連に加盟していることや、扱う問題の広範さからも、国連は最も普遍的かつ包括的な組織であると言える。このような特徴から、国連は、秩序の維持や、新たな秩序の創設のための国際的な努力に対して、法的・政治的な正統性を付与できる国際組織と位置づけられており、国連の果たすべき役割は一層高まっている。
そのような中、日本は、国益の確保に不可欠である国際社会の平和・安定と繁栄を実現していくため、核軍縮、平和維持活動(PKO)への貢献、開発途上国の持続可能な開発に向けての努力への協力、人間の安全保障概念の普及・促進等、幅広い分野において、大きな貢献を行っている。日本としては、例えば、国連が、 国際の平和と安全の維持、
国際の平和と安全の維持、 グローバル化に対応した普遍的で公正なルール作り、
グローバル化に対応した普遍的で公正なルール作り、 開発途上国の開発問題についての持続可能な解決策の提供、といった役割を担っていくことを期待しており、国連での活動に自ら積極的に参加するとともに、国連及び加盟各国へも働きかけていく考えである。
開発途上国の開発問題についての持続可能な解決策の提供、といった役割を担っていくことを期待しており、国連での活動に自ら積極的に参加するとともに、国連及び加盟各国へも働きかけていく考えである。
9月に行われた国連総会の一般討論演説には、日本から小泉総理大臣が出席し、その演説の中で、イラクによる大量破壊兵器等の開発・保有問題について、イラクがすべての安全保障理事会(安保理)決議を遵守するよう求めるとともに、国連が直面する大きな課題として、テロとの闘い、平和の定着と国造り、環境と開発、核軍縮を取り上げ、日本の貢献策を表明した。さらに、これらの諸問題に取り組むにあたっては、国連の機能強化が不可欠であり、そのために安保理改革を始めとする国連の組織・機能を常に見直していくことの重要性を訴えた。
国連の活動の規模の推移
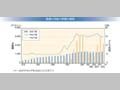
国連通常分担率の推移
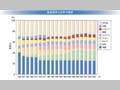
【国連改革】
9月、アナン事務総長は、国連改革に関する事務総長報告書(「国連の強化:更なる変革のためのアジェンダ」)を発表し、国連の機能強化のための改革案を提示した。本報告書は、主として、内部の管理、事務局の機能、総会の作業計画の改善等に焦点をあてている。これを受けて、12月、総会は報告書が示す大きな方向性を支持する内容の決議を採択した。
改革の中でも特に重要なのが、次期2か年予算(2004/05年予算)の編成である。国連予算の増大傾向が続く一方、活用できる資源が限られている中で、国連が21世紀の新たな優先課題に対して適切に対応していくためには、予算面でも優先順位を反映した資源配分が必要である。日本は、優先度の低い課題や時代後れの活動から、優先度の高い活動への資源配分の重要性を訴えており、今後本格化する予算編成作業においても、より効率的・効果的な国連とするよう努めていく考えである。
国連通常予算の規模は、累次効率化を進めることなどにより、1996年以降ほぼ横這〔ば〕いを維持してきたが、2002/03年予算は、国連職員の安全対策、アフガニスタンなどにおける特別政治ミッションといった重点活動に必要な経費等を追加するため、当初の見積もりの26.3億米ドルから12月の改定で28.9億米ドルへと一挙に約10%増額された。日本は、国内の厳しい経済・財政事情を抱えているにもかかわらず、加盟国中第2位の分担率19.669%(2002年)の財政負担を行っており、より適正な予算規模の実現を含めた国連改革の推進に一層積極的な役割を果たしていくことが求められている。
国連加盟国と安保理常任・非常任理事国の地域別構成

【安全保障理事会改革】
安保理改革なくして、いかなる国連の改革も完結しないことは、前述のアナン事務総長の報告書にも明記されている。安保理が国連憲章に基づき平和と安全の問題について大きな責務を果たしていることは、2002年11月のイラク問題に関する安保理決議1441の採択をめぐる動き等を通じて改めて強く認識されたが、安保理が期待される役割を果たすためには、その機能を高める形で改革を行うことが不可欠である。
安保理改革については、2000年9月のミレニアム・サミットを始めとする様々な機会における議論を通じて、これまでに、 安保理改革の早期実現が国連加盟国の総意であること、
安保理改革の早期実現が国連加盟国の総意であること、 常任・非常任議席双方の拡大については多くの加盟国が支持していること、が明らかになっている。一方で、1994年1月に作業を開始した安保理改革作業部会の議論は、2003年で10年目に入ったにもかかわらず、拡大後の安保理議席数、新常任理事国の選出方式、拒否権の扱いといった論点について加盟国の意見は収斂〔しゅうれん〕していない。特に近年、テロとの闘い、アフガニスタン情勢、イラク情勢といった国際社会の緊急の課題に各国の関心が集中していることもあり、安保理改革をめぐる議論は必ずしも活発には行われてこなかった。
常任・非常任議席双方の拡大については多くの加盟国が支持していること、が明らかになっている。一方で、1994年1月に作業を開始した安保理改革作業部会の議論は、2003年で10年目に入ったにもかかわらず、拡大後の安保理議席数、新常任理事国の選出方式、拒否権の扱いといった論点について加盟国の意見は収斂〔しゅうれん〕していない。特に近年、テロとの闘い、アフガニスタン情勢、イラク情勢といった国際社会の緊急の課題に各国の関心が集中していることもあり、安保理改革をめぐる議論は必ずしも活発には行われてこなかった。
このような状況を踏まえ、日本は、拡大後の安保理議席数に関する議論を絞り込むため、米国を始めとする関係国に働きかけを行うとともに、日本の常任理事国入りを含む安保理改革の問題について国内での議論を活性化させることなどを通じて、安保理改革の早期実現のために引き続き積極的に取り組んでいく考えである。
国連加盟国数と安保理議席数の推移

(トピック:安全保障理事会改革 ~なぜ改革が求められているのか~)
【日本人職員】
日本の国連に対する大きな財政貢献に比べて、国連に勤務する日本人職員数は望ましい水準に達していない。現状では、国連事務局が示している望ましい日本人職員数の3分の1程度にとどまっている。このような状況を改善するため、日本は、優秀な人材の発掘や日本人職員の採用・昇進に向けて、国連事務局及び関係国際機関に対して働きかけを行っている。また、若手職員のためのアソシエート・エキスパート等派遣制度の活用、国連事務局などの採用ミッションの受け入れを通じ、日本人職員の増強に努めている。
その結果、国際機関の日本人幹部職員については、2002年には、国連開発計画(UNDP)開発政策局長に西本昌二氏、国連東ティモール支援団(UNMISET)事務総長副特別代表に長谷川祐弘氏、国連工業開発機関(UNIDO)事務局次長兼計画調整・地域事業局長に広瀬晴子氏が就任した。また、若手職員についても一定の成果が得られているが、全体としてはいまだ十分な水準には至っていない。
今後、さらに日本人職員を増強していくためには、資格要件を有する人材の育成・発掘を一層幅広く進める必要がある。このため、外務省国際機関人事センターでは、2002年度より情報提供を含む新たな人材登録システムのためのホームページ(http://www.mofa-irc.go.jp)を開設し、海外在住の日本人を含むより多くの日本人の応募を支援する体制を強化した。
主要国際機関における日本人幹部職員

(コラム:国際機関で活躍する日本人職員 ●バーゼル条約事務局長)
(コラム:国際機関で活躍する日本人職員 ●国連イラク査察団報道官)

 次頁
次頁 国際の平和と安全の維持、
国際の平和と安全の維持、 グローバル化に対応した普遍的で公正なルール作り、
グローバル化に対応した普遍的で公正なルール作り、 開発途上国の開発問題についての持続可能な解決策の提供、といった役割を担っていくことを期待しており、国連での活動に自ら積極的に参加するとともに、国連及び加盟各国へも働きかけていく考えである。
開発途上国の開発問題についての持続可能な解決策の提供、といった役割を担っていくことを期待しており、国連での活動に自ら積極的に参加するとともに、国連及び加盟各国へも働きかけていく考えである。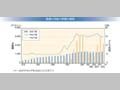
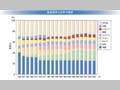

 安保理改革の早期実現が国連加盟国の総意であること、
安保理改革の早期実現が国連加盟国の総意であること、 常任・非常任議席双方の拡大については多くの加盟国が支持していること、が明らかになっている。一方で、1994年1月に作業を開始した安保理改革作業部会の議論は、2003年で10年目に入ったにもかかわらず、拡大後の安保理議席数、新常任理事国の選出方式、拒否権の扱いといった論点について加盟国の意見は収斂〔しゅうれん〕していない。特に近年、テロとの闘い、アフガニスタン情勢、イラク情勢といった国際社会の緊急の課題に各国の関心が集中していることもあり、安保理改革をめぐる議論は必ずしも活発には行われてこなかった。
常任・非常任議席双方の拡大については多くの加盟国が支持していること、が明らかになっている。一方で、1994年1月に作業を開始した安保理改革作業部会の議論は、2003年で10年目に入ったにもかかわらず、拡大後の安保理議席数、新常任理事国の選出方式、拒否権の扱いといった論点について加盟国の意見は収斂〔しゅうれん〕していない。特に近年、テロとの闘い、アフガニスタン情勢、イラク情勢といった国際社会の緊急の課題に各国の関心が集中していることもあり、安保理改革をめぐる議論は必ずしも活発には行われてこなかった。
