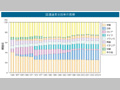第1章 > 6 > (1) 国連の役割
【総論】
冷戦中、国連安全保障理事会(以下「安保理」)は、国連の第一の目的である国際の平和及び安全の維持の分野において必ずしも十分な役割を果たすことができなかったが、冷戦の終焉に伴い、その本来の機能をより有効に果たすことが期待されている。また、近年のグローバル化の進展が人類の一層の繁栄を可能にする一方で、国際社会は、人権侵害、貧困、感染症、犯罪、環境、人口、難民といった問題への対応に迫られている。このような状況において、唯一の普遍的かつ包括的な機関である国連が、2000年9月のミレニアム宣言(注1)も踏まえ、21世紀の国際社会の諸課題への取組において積極的な役割を果たしていくことへの期待はますます高まっている。
このような期待の中にあって、国連は、9月11日に発生した米国同時多発テロに迅速に対応し、テロ活動の国際的な取締り及びアフガニスタンの安定と復興のために大きな役割を果たした。総会においては、10月初め、国際テロ撲滅措置に関する総会審議が大多数の加盟国の参加を得て開催され、その後も第6委員会においてテロ防止のための関連多数国間条約の採択に向けて議論が活発に行われている。また、安保理においては、テロの防止と根絶に向けて、金融面を含む包括的な措置の実施を各国に求める決議が採択されたほか、アフガニスタンの治安確保のため、国際治安支援部隊の設立を認める決議が採択された。
なお、例年9月に行われていた総会一般討論演説は、同時多発テロの影響を被り、11月10日から16日の間に延期された。日本からは宮澤元総理大臣が政府代表として出席し、テロ問題とアフガニスタン問題にテーマを絞った演説を行った。
国連加盟国と安保理常任・非常任理事国の地域別構成

【国連改革】
21世紀の平和と繁栄のために国際社会が取り組むべき課題はますます多様化し、複雑化している。このような状況の中で国連が一層有効に対応するためには、その機能を強化することが不可欠である。特に、国際の平和及び安全の維持に主要な責任を担う安保理は、米国同時多発テロ発生後の対応に見られたように、狭い意味での平和と安全の分野のみならず、国際金融や国内刑事法制といった幅広い分野で活動を行うようになっている。このような新しい国際協力のあり方を踏まえ、安保理がより有効に対処できるようにするためにも、国際社会の現状を反映すべく安保理改革を実現することが急務となっている。
改革の具体的な議論は、1994年1月から約8年にわたり、国連総会の安保理改革に関する作業部会等の場で行われている。2000年のミレニアム・サミットやミレニアム総会における議論を通じて、常任議席と非常任議席の双方を拡大することについては大多数の国からの支持が得られている。10月30日から11月1日まで開催された安保理改革に関する総会審議や、11月10日から16日まで開催された総会一般討論においても、多くの国から、安保理改革の必要性及び常任・非常任議席双方の拡大への支持が表明された。このことは、同時多発テロの影響で各国の関心がテロ問題やアフガニスタン問題に注がれていたにもかかわらず、依然として安保理改革に対する関心が高いことを示すものであった。
一方で、拡大後の安保理の規模(いわゆる「数」の問題)、拒否権の扱い、新常任理事国の選出方法などの論点については、各国の意見が依然として収れんしておらず、改革は実現していない。日本は、米国同時多発テロを契機に生まれた国際協調の機運を安保理改革に向けた原動力に転換していくことができるよう、今後とも積極的に改革に取り組んでいきたいと考えている。
国連の財政改革も引き続き重要な課題である。ますます拡大する国連の活動を支えるためには、健全な財政基盤の確立が不可欠である。日本は、加盟国中第2位(2001年の分担率は19.629%)の財政負担を負っており、 滞納金の支払い促進と資金状況の改善、
滞納金の支払い促進と資金状況の改善、 予算の効率化、
予算の効率化、 分担率の衡平化を中心とする財政改革の重要性を一貫して主張してきている。ただし、2002/03年度(注2)の国連通常予算の交渉においては、日本は予算の効率化による予算規模の抑制に取り組みつつも、国連平和活動の強化に関するブラヒミ報告の履行、国連職員の安全対策といった国連予算の重点分野の重要性を認める立場で臨んだ結果、予算規模は2000/01年度予算と比較して若干増となった。なお、2001年の国連の資金状況は、米国による一部滞納金の支払い等もあり改善が見られた。
分担率の衡平化を中心とする財政改革の重要性を一貫して主張してきている。ただし、2002/03年度(注2)の国連通常予算の交渉においては、日本は予算の効率化による予算規模の抑制に取り組みつつも、国連平和活動の強化に関するブラヒミ報告の履行、国連職員の安全対策といった国連予算の重点分野の重要性を認める立場で臨んだ結果、予算規模は2000/01年度予算と比較して若干増となった。なお、2001年の国連の資金状況は、米国による一部滞納金の支払い等もあり改善が見られた。
国連の活動の規模の推移

国連通常分担率の推移
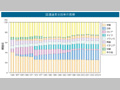
【日本人職員】
日本の国連に対する大きな財政貢献に比べ、国連に勤務する日本人職員数は望ましい水準に達しておらず、国連事務局が示している望ましい日本人職員数の3分の1程度にとどまっている。このような状況を改善するため、日本は、優秀な人材の発掘や日本人職員の採用・昇進に向けた国連事務局及び関係国際機関への働きかけを行うとともに、若手のためのアソシエート・エキスパート等派遣制度の活用、国連事務局などの採用ミッションの受け入れ、国連の人事制度面等を通じ、日本人職員の増強に努めている。
その結果、国際機関の日本人幹部職員については、2001年には、国連人道問題担当事務次長に大島賢三氏、国連アジア太平洋経済社会委員会事務局次長に大海渡桂子氏、国際原子力機関(IAEA)事務次長に谷口富裕氏が就任した。また、若手職員についても一定の成果が得られているが、全体としていまだ十分な水準には至っていないのが現状である。
今後、更に日本人職員を増強するためには、資格要件を備えた人材の育成及び発掘を一層強化する必要がある。このため、外務省国際機関人事センターでは、2002年度より情報提供を含む新たな人材登録システムのためのホームページを開設することにしており、海外在住の日本人を含むより多くの日本人の応募を支援する体制を強化していく。
主要国際機関における日本人幹部職員

(column2参照)
(column3参照)
【国連平和維持活動の強化】
冷戦終了後、紛争解決における国連の役割が見直されるとともに、国際社会が対応を迫られる紛争の多くが国内紛争又は国内紛争と国際紛争の混合型へ変わったことから、軍事部門に加え、選挙、警察、人道、行政など多様な文民部門を含む国連平和維持活動(PKO)が増加しつつある。過去のPKOの教訓を活かしつつ、これらの多様な任務に効果的に対応するため、国連の内外でPKOの強化のための試みが引き続き行われている。
具体的には、2000年8月に公表された「国連の平和活動」に関するブラヒミ報告(注3)を受けて、10月及び2001年6月に国連事務総長からの報告書(実施計画)が提出され、これに基づいた個別の課題に関する議論が国連における関連委員会、総会、安保理等において活発に行われている。勧告の一部、例えば、国連本部事務局要員の補強などは既に実施されている。
日本は、平和活動の改善・強化は国際の平和と安全にとり重要な意義を持つことから、ブラヒミ報告の勧告・提言を真剣に受け止め、議論に積極的に参加するとともに、可能な協力は実施していく考えである。
さらに、ブラヒミ報告において必ずしも取り扱われなかった問題として、PKO要員等の安全の確保に関する問題があるが、日本は、2001年3月に東京でこれをテーマとしたセミナーを実施し、さらに、セミナーの結果を踏まえた提言を国連の関連会合にて行うなど、PKOの強化に向け、積極的に取り組んできている。

 次頁
次頁
 滞納金の支払い促進と資金状況の改善、
滞納金の支払い促進と資金状況の改善、 予算の効率化、
予算の効率化、 分担率の衡平化を中心とする財政改革の重要性を一貫して主張してきている。ただし、2002/03年度(注2)の国連通常予算の交渉においては、日本は予算の効率化による予算規模の抑制に取り組みつつも、国連平和活動の強化に関するブラヒミ報告の履行、国連職員の安全対策といった国連予算の重点分野の重要性を認める立場で臨んだ結果、予算規模は2000/01年度予算と比較して若干増となった。なお、2001年の国連の資金状況は、米国による一部滞納金の支払い等もあり改善が見られた。
分担率の衡平化を中心とする財政改革の重要性を一貫して主張してきている。ただし、2002/03年度(注2)の国連通常予算の交渉においては、日本は予算の効率化による予算規模の抑制に取り組みつつも、国連平和活動の強化に関するブラヒミ報告の履行、国連職員の安全対策といった国連予算の重点分野の重要性を認める立場で臨んだ結果、予算規模は2000/01年度予算と比較して若干増となった。なお、2001年の国連の資金状況は、米国による一部滞納金の支払い等もあり改善が見られた。