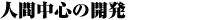
●人材育成、情報通信技術(ICT)
「国づくりは人づくり」。教育分野支援約20億ドルをアフリカ諸国に積極的に活用。教育・保健分野等でICT活用を促進 など
●水
「安全な水を人々のもとへ」。水資源無償を創設、アフリカ支援へも活用。アフリカを含め2003年度より5年間で約1,000人の人材育成を実施 など
●保健・医療
子ども達の未来のため、世界からのポリオ撲滅に向け2005年度までにアフリカ地域を含め約8,000万ドルを目標に支援を実施。沖縄感染症対策イニシアティブの継続的実施 など

|
 |
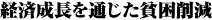
●食糧・農業・農村開発
南部アフリカ食糧危機に3,000万ドルを支援など食糧支援。食糧安全保障に貢献するネリカ米の研究・開発・普及への支援。住民参加型農村開発の推進 など
●インフラ
運輸、通信、エネルギー、水の4分野を中心に、2003年以降約10.6億ドルの支援を実施予定など、インフラ整備を継続的に支援
●貿易・投資促進
日本企業の対途上国投資促進のため、投資金融を通じて今後5年間でアフリカへも約3億ドルを目標に協力を実施 など
●債務救済
アフリカの重債務貧困国等に対し、総額約30億ドルの円借款債権の放棄を実施 など
●国際開発金融機関を通じた支援
世界銀行に設置された貧困削減戦略信託基金等を通じた貧困削減戦略文書(PRSP)の策定・実施支援 |
 |

●紛争で傷ついたコミュニティーの
再生と国内融和のための支援
「紛争予防・平和構築無償」、人間の安全保障基金の活用など、国際機関や市民社会と連携した平和の定着への取り組みを推進 など
●アフリカ自身による紛争解決努力
(平和プロセス)への支援
アフリカ連合(AU)、西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS)等地域機関による紛争予防・解決活動等を支援
 |