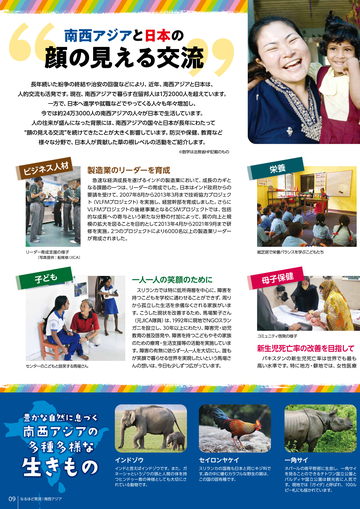日本の対南西アジア外交
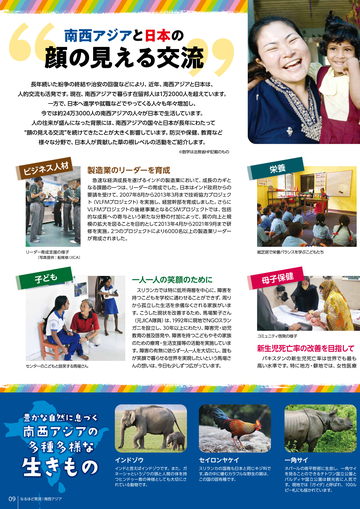
- ページ: 10
- 南西アジアと日本の
顔の見える交流
長年続いた紛争の終結や治安の回復などにより、近年、南西アジアと日本は、
人的交流も活発です。現在、南西アジアで暮らす在留邦人は1万2000人を超えています。
一方で、日本へ進学や就職などでやってくる人々も年々増加し、
今では約24万3000人の南西アジアの人々が日本で生活しています。
人の往来が盛んになった背景には、南西アジアの国々と日本が長年にわたって
“顔の見える交流”を続けてきたことが大きく影響しています。防災や保健、教育など
様々な分野で、日本人が貢献した草の根レベルの活動をご紹介します。
※数字は法務省HP記載のもの
人材
ビジネス
栄養
製造業のリーダーを育成
急速な経済成長を遂げるインドの製造業において、成長のカギと
なる課題の一つは、リーダーの育成でした。日本はインド政府からの
要請を受けて、2007年8月から2013年3月まで技術協力プロジェク
ト(VLFMプロジェクト)を実施し、経営幹部を育成しました。さらに
VLFMプロジェクトの後継事業となるCSMプロジェクトでは、包括
的な成長への寄与という新たな分野の付加によって、質の向上と規
模の拡大を図ることを目的として2013年4月から2021年9月まで研
修を実施。2つのプロジェクトにより6000名以上の製造業リーダー
が育成されました。
リーダー育成支援の様子
紙芝居で栄養バランスを学ぶこどもたち
(写真提供:船尾修/JICA)
子ども
一人一人の笑顔のために
スリランカでは特に低所得層を中心に、障害を
母子 保
健
持つこどもを学校に通わせることができず、周り
から孤立した生活を余儀なくされる家族がいま
す。こうした現状を改善するため、馬場繁子さん
(元JICA隊員)は、1992年に現地でNGOスラン
ガニを設立し、30年以上にわたり、障害児・幼児
教育の普及啓発や、障害を持つこどもやその家族
コミュニティ啓発の様子
す。障害の有無に依らず一人一人を大切にし、誰も
新生児死亡率の改善を目指して
のための療育・生活支援等の活動を実施していま
が笑顔で暮らせる世界を実現したいという馬場さ
センターのこどもと談笑する馬場さん
んの想いは、今日も少しずつ広がっています。
パキスタンの新生児死亡率は世界でも最も
高い水準です。特に地方・僻地では、女性医療
豊かな自然に づく
南西アジアの
多種多様な
生きもの
09
なるほど発見!南西アジア
インドゾウ
セイロンヤケイ
一角サイ
インドと言えばインドゾウです。また、ガ
ネーシャというゾウの頭と人間の体を持
つヒンドゥー教の神様としても大切にさ
れている動物です。
スリランカの国鳥も日本と同じキジ科で
す。森の中に棲むカラフルな野生の鶏は、
この国の固有種です。
ネパールの南平野部に生息し、一角サイ
を見ることのできるチトワン国立公園と
バルディヤ国立公園は観 光 客に人 気で
す。現地では「ガイダ」と呼ばれ、100ル
ピー札にも描かれています。
�
- ▲TOP