第1章 新たなパートナーシップ

モザンビーク「ナカラ回廊農業開発研究能力向上プロジェクト」農業試験場で、試験栽培中のキャッサバを示す研究所職員。ブラジルの農業技術や知識・経験をアフリカ諸国に移転する目的で、モザンビークに対して日本・ブラジルによる農業開発支援を実施している(写真提供:谷本美加/JICA)
第1節 新興国の台頭とODA
近年、「新興ドナー(援助国)」と呼ばれる国々の影響力がますます大きくなってきています。新興ドナーの中には、中国、インド、ブラジルなど急速な経済成長をとげ、インフラ整備等の経済分野を中心とした支援を「南南協力」(開発途上国同士の協力、こちらを参照)として実施している国、チェコ、ポーランド、ハンガリーなど、EU加盟を機にODA供与国に転じ、OECD開発援助委員会(DAC(ダック))(注1)の活動にも積極的に参加している中東欧諸国、サウジアラビア、クウェート、アラブ首長国連邦など、豊かなオイルマネーにより援助を行うアラブ諸国等があり、その援助のあり方は様々です。
新興ドナーの台頭は、開発資金の構成にも大きな変化をもたらしています。DACの推計によると、これら新興ドナーの2008年の援助額は120~140億ドルにのぼります。この額は、同年のDAC加盟国のODA総額の9~10パーセントにも相当します。また、新興ドナーの中には、サウジアラビアのように、多くのDAC加盟国よりも大規模な援助を供与している国もあります。
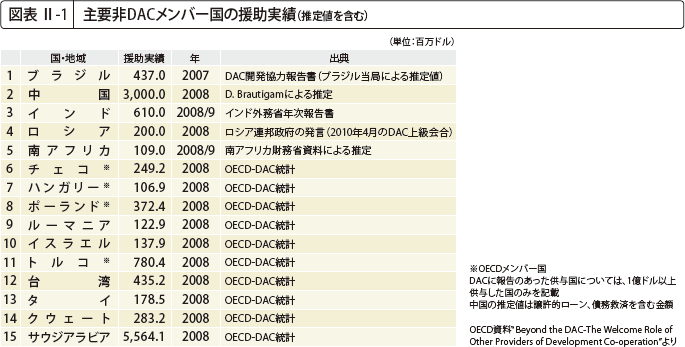
新興ドナーを中心に、開発に携わる国が増えると、被援助国にとっては、開発資金と援助の選択肢の増加や多様化につながります。これは国際社会全体として開発を促進していくためには歓迎すべきことです。日本が被援助国から援助国へ成長した経験を持つように、多くの新興ドナーは、自国の発展の歴史と経験を持っており、それを自ら行う援助に活用していくことに積極的です。
同時に、新興ドナーによる援助がそれぞれ独自のやり方で行われるのではなく、これまで国際社会により、実践されてきた援助実施の手続きやルール等に沿って行われることが、援助を受ける側の途上国に過剰な負担をかけないためにも重要になります。そのため、新興ドナーに対し、協力を働きかけていく必要があります。伝統的ドナーと新興ドナーが自らの知識と経験を共有し、協力して援助を実施していくことが、途上国の開発には不可欠です。今後ミレニアム開発目標(MDGs)をはじめとする国際社会の共通目標の達成に向けて、新興ドナー、市民社会、民間企業等の開発援助における多様な関係者を含んだ幅広い協力関係をつくっていくことが求められています。
現在、様々な国際会議において、新興ドナーとの協力の推進が議論されています。2010年11月に、中国、インド、ブラジル、サウジアラビア等の新興ドナーが参加したG20ソウル・サミット(韓国)で、「共有された成長のためのソウル開発合意」および「開発に関する複数年行動計画」がまとめられました。またDACでは、2011年4月のシニア・レベル会合において「国際開発協力における新たなパートナーシップに関するDACステートメント」が採択されました。2011年11月には、韓国・釜山(プサン)において「第4回援助効果向上に関するハイレベル・フォーラム」が開催されました。このフォーラムにおいて新興ドナーが、国際社会共通の利益や地球規模の課題に取り組むため、新たな協力の枠組みに参加したことは大きな進展です。今後、新興国とも協力して釜山での合意を着実に実施していくことが重要です。(援助効果向上についてはこちらを参照)

韓国・釜山で行われた「第4回援助効果向上に関するハイレベル・フォーラム」にて発言する中野譲外務大臣政務官
注1 : 経済協力開発機構 OECD : Organisation for Economic Co-operation and Development
開発援助委員会 DAC : Development Assistance Committee