本編 > 第III部 > 第2章 > 第5節 > 2. 国民参加の拡大
2. 国民参加の拡大
(1)国民各層の広範な参加
政府開発援助の実施に当たっては、広く国民からの支持と理解を得ながら、国民参加型の国際協力を一層推進することが大切です。国際協力事業への国民各層の広範な参加は、国際協力事業全体の人材の層の拡大にもつながるため重要です。
こうした考えの下、国民参加の拡大のため、様々な段階で国民が国際協力の立案・実施にかかわることができるよう、制度的な整備を進めています。例えば、国別援助計画の策定作業においてNGO・経済界・有識者などとの意見交換会を開催しているほか、外務省のホームページでも幅広く一般国民からの意見を求めています。
青年海外協力隊とシニア海外ボランティア

青年海外協力隊およびシニア海外ボランティア派遣前訓練修了式にて
スピーチを行う伊藤信太郎外務副大臣(福島県二本松市)
国民各層からの政府開発援助事業への参加に関しては、青年海外協力隊事業およびシニア海外ボランティア派遣事業があります。
青年海外協力隊は、20歳から39歳の青年が開発途上国へ2年間滞在し、開発途上国の人々と生活や労働を共にしながら、開発途上国の社会的、経済的発展に協力する国民参加型事業です。青年海外協力隊は40年以上の歴史を持ち、海外でも高く評価されている日本の顔の見える援助の一つです。2007年6月に派遣累計人数が3万人を超え、2007年度末までに、3万1,371名の青年海外協力隊が計82か国に派遣されています。
また、シニア海外ボランティア事業は、幅広い技術、豊かな経験を有する40歳から69歳の年代で、ボランティア精神に基づき開発途上国の発展のために貢献したいという方々が行う活動を日本政府が支援するという国民参加型事業です。1990年度に「シニア海外専門家」として発足しましたが、1996年度に青年海外協力隊のシニア版であるボランティア事業に位置付けられ、「シニア海外ボランティア」に名称変更されました。2007年度までの累計で3,373名のシニア海外ボランティアが計56か国に派遣されています。
青年海外協力隊およびシニア海外ボランティア事業では、現職教員参加制度や1年未満の短期派遣など参加メニューの多様化を図っており、より国民が参加しやすい環境を整えています。
国際協力活動への市民の関心の高まりとNGOの活躍
国際協力活動への市民参加の形として最も身近にあるのが、国際協力に従事するNGOへの支援やその活動への参画です。日本のNGOの数は、1998年に「特定非営利活動促進法(NPO法)」が施行され、法的整備が進んだことから飛躍的に増加しており、その数は3万4,941団体に達しています(注198)。このうち、実際に国際協力活動を行っているのは約400団体といわれており、国際協力の現場で事業に直接携わることを希望する人たちも年々増加しています。日本のNGOがこのような人たちの受け皿となり、さらなる国際協力分野での優秀な人材の育成や政府開発援助の活用の拡大に努め、日本の心を伝える活動主体として活躍していくことが期待されます。
国民参加を促進する事業
国民参加を促進する事業として、以下のようなものがあります。
- 「グローバルフェスタJAPAN」
- 「国際協力の日」(10月6日)を記念して毎年東京の日比谷公園で開催。
- 「国際協力について語ろう」
- 国際協力に関する市民対話。
- 「ODA出前講座」の開催
- 外務省職員が学校・地方自治体・NGOなどを訪問して国際協力について説明。
- 「ODA民間モニター」事業
- 国際協力に関心のある一般国民が実際の援助現場を直接視察。
(2)人材育成と開発研究
(イ)人材育成

国際開発プログラムを英語で実施している政策研究大学院大学(GRIPS)
(写真提供:GRIPS(撮影者:西川公朗))
開発問題の多様化と高度化により、現在、国際協力活動を効果的・効率的に実施していく上では、高度な知識と豊富な経験、外国語コミュニケーション能力などを備えた有能な人材の育成と確保が不可欠です。
1990年に国際開発大学構想を推進する機関として設立された(財)国際開発高等教育機構(FASID(注199))は、援助に携わる人材を対象とした研修や教育、調査・研究事業などを実施しています。FASIDは、開発の理論、政策、実務について能力向上を目的とした各種研修を、政府関係者のほかNGOや民間企業関係者など幅広い層に対して実施していることに加え、開発援助分野の重要テーマに関する調査・研究を行い、その成果を幅広く公表しています(注200)。また、2000年度には、政策研究大学院大学(GRIPS(注201))と連携して、修士課程の国際開発プログラムを開始しています。さらに、FASIDでは、各大学での開発協力関連講座や学科などに対し、講師を派遣しています。
新JICA設立については、囲み4も参照してください。
また、JICAでは、旧JBICとの統合前から、ある程度の専門性を持ちつつも経験の浅い若手の育成のためのジュニア専門員制度や既に一定の専門性や経験を有する国際協力専門員制度のように、幅広い人材の育成と拡充を行っています。こうした取組を通じ、日本の政府開発援助事業以外にもNGOや国際機関などで即戦力として活躍する人材を輩出することが期待されています。
さらに、専門性や意欲を持つ人材を効果的かつ有効に確保・活用するためにJICAでは、「国際協力人材センター」を開設し、JICA、NGOや国際機関といった国際協力関連団体の求人情報の提供、人材登録、各種研修・セミナー情報の提供、およびキャリア相談などを行っています。
このほか、日本貿易振興機構(JETRO(注202))のアジア経済研究所開発スクール(IDEAS(注203))では、開発途上国の経済・社会開発に寄与すべく、高度な能力を持った開発専門家を育成しています。IDEASでは、外国人、日本人の双方に対して研修を実施しており、研修参加者は多方面で活躍しています。
(ロ)開発研究
効果的・効率的な援助を行うためには、開発途上国のニーズや国際社会の動向を適切に把握することが不可欠です。日本では、このための調査研究や知見の活用に向けた積極的な取組が行われています。
JICAでは、旧国際協力総合研修所において、JICA関係者を中心とした研究会を組織してきました。研究会の内容によっては大学や研究機関などの外部有識者の知見を得つつ、国際協力に関する新たな領域での事業戦略策定のための分析や提言、援助潮流や開発理論分析などといった事業戦略研究を行ってきました。これらに加え、これまでの事業経験の体系化や援助マネージメント手法の研究などを中心に調査研究を実施してきました。2007年度には、ほかの援助国、援助相手国、国際機関と共同で「能力開発のために有効な技術協力」の研究を行いました。この研究は、2008年度にガーナのアクラで開催された第3回援助効果向上のためのハイレベルフォーラムで報告されるなど、精力的な活動を行いました。
また、2008年10月まで旧JBICに設置されていた開発金融研究所では、開発途上国の開発政策や事業が効果的かつ効率的に形成・実施され、より高い効果を発現するための協力の一環として、国内外の研究者の知見も活用しながら、開発途上国経済や開発政策・制度・事業などに関する調査・研究を行い、各種出版物や現地セミナー、国際会議などを通じて、政策提言を含む成果物を発信してきました。
2008年10月の新JICAの設立に当たっては、近年の政府開発援助改革や国際社会の動向、開発援助分野における調査・研究業務の重要性が高まっていることを受け、調査・研究事業が独立した号として法律で規定されました。これに伴い、新JICAにも研究所(JICA研究所)が設置されました。この研究所では、さらなる開発援助効果向上のための検討や提言などを行っていくほか、日本の支援を国際的に発信していくための研究や日本による支援の優位性を伸ばすための研究に力を入れていくことが期待されています。新JICAでの開発研究では、研究対象を広く途上国の開発課題や開発政策にまで広げ、国内の関係者だけでなく、途上国政府や国際ドナー・コミュニティーへの発信も念頭に入れながら、理論的な枠組みに依拠した実証的、政策的な研究を推進していきます。当面の研究領域としては、①平和と開発、②成長と貧困削減、③気候変動など世界的な課題、④援助戦略―の4つの領域としていきます。
また、日本貿易振興機構(JETRO(注204))のアジア経済研究所では、研究者を中心に国内外の大学や研究機関などの専門家と共同で開発途上国の政治・経済・社会に関する研究を行っています。例えば、2007年度には、中国やインド、東アジア地域における地域統合、貧困削減と開発戦略という4つの研究分野を重点に研究を実施しました。
(3)情報の公開と発信
政府開発援助は国民の税金などを原資としている以上、事業を継続していくためには、その重要性などについて国民から広く理解と支持を得られるよう努力していかなくてはなりません。このため、外務省や援助実施機関では、広報や開発教育の推進に取り組んでいます。また、これらの活動によって、国際協力に従事する人材層の拡大にもつながっています。
(イ)広報・情報公開
国際協力に関する情報提供および日本の協力案件に関する情報を得る機会を提供するための具体的な施策としては、この白書や外交青書をはじめとする政府刊行物の発行以外にも、以下のような取組があります。
ホームページ・メールマガジン・新聞

毎月発行されている「国際協力新聞」
政府開発援助関連のホームページにおいて情報公開の充実化を図っており、外務省、JICA、国際協力プラザなどのホームページ(注205)では、国際協力に関する多くの情報をタイムリーに掲載するとともに、国際協力について分かりやすく紹介しています。
外務省では、政府開発援助ホームページに加え、メールマガジンも発行しています。この中では、国際協力にかかわる情報を提供しているほか、在外公館職員や青年海外協力隊員、シニア海外ボランティアなどによる実際の援助現場での体験話やエピソードなどを紹介しています。なお、メールマガジンはホームページを通じて随時登録を受け付けており、約1万4,800名(2007年度末現在)の方が登録されています。
また、国際協力に関する最新情報を掲載する「国際協力新聞」を毎月発行し、全国の教育機関、図書館などに配布しています。
市民との対話
「国際協力について語ろう」は、国際協力に関する市民対話の一環として、政府開発援助を巡る動きや日本の取組を広く一般に紹介するため、毎年2回(東京および大阪)開催されています。この中では、国民の生の声を直接聴取することを目的に、有識者や外務省職員と一般市民との間で政府開発援助についての質疑応答の時間を設けています。
また、2005年以降、より機動的な市民対話の一環として、外務省国際協力局の職員が中学校、高校、大学、地方自治体、NGOなどに赴いて、国際協力について説明をする「ODA出前講座」を実施しており、現在までに40回実施されています(2007年度末現在)。
ODA民間モニター事業

現地住民の職業訓練を視察するモニター参加者(ホンジュラス)
(写真提供:APIC)
1999年度に開始されたODA民間モニター事業は、国際協力に関心のある一般国民が実際の援助現場に赴き、日本の政府開発援助案件を直接視察できる事業です。参加者自身が直接視察することにより、日本が実施している国際協力の意義や重要性について正しく理解するとともに、意見や感想などの報告を通じ、一般国民の政府開発援助に対する理解の促進にもつながっています。2007年度までに704名がアジア、アフリカ、中南米など28か国の開発途上国を訪問し、479件のプロジェクトを視察しました。参加者からは、政府開発援助が開発途上国の発展・安定に役立っていることや援助の必要性について理解を深めたなどといった報告がなされています(注206)。また、モニターへの参加をきっかけとして、国際協力に関心を深め、青年海外協力隊やシニア海外ボランティアとして国際協力に参加することとなった方もいます。
国内広報テレビ番組
一般国民の国際協力への関心を高め、理解を促進するため、1997年度以降、シリーズもののテレビ番組を放送しています。開発途上国で頑張っている日本の方々や現地住民の姿などを映像にし、開発途上国の現状や援助の必要性、日本のプロジェクトの実施や効果などを紹介しています。
2007年度は、テレビ東京で毎週1回4分間、「関口知宏の地球サポーター」を放送しました。この番組では、関口知宏さんを番組ナビゲーターとして、パプアニューギニア、マレーシア、ガーナ、中国、ブラジル、スリランカ、モルディブを取り上げ、その平均視聴率は、5.4%にも上りました。また、多くの方々の要望により、この番組の総集編をBSで全国放送しました。
グローバルフェスタJAPAN
1990年以降、日本国内最大の国際協力イベントとして「国際協力フェスティバル」を毎年「国際協力の日」(10月6日)(注207)に合わせて開催してきました。2005年には、若い世代や国際協力になじみの薄い層にも広く参加してもらえるよう、名称を「グローバルフェスタJAPAN」に変更しました。外務省、新JICAおよびJANIC(国際協力NGOセンター)が共催し、東京・日比谷公園で土・日の2日間にわたって行われるこのイベントには、NGOや国際機関、各国大使館などの200団体以上が出展しています。2007年度は、私たちの生活の中心である家族や家庭から、私たちの周りの地域、環境、世界とのきずなを考えてもらい、国際協力や途上国への理解促進を図ることを目指し、「家族と地球」をテーマとしました。また、初めての試みとして民間企業の協賛を得て、企業ブースの展示なども行われ、民間企業も政府、国際機関、NGOと共に日本の国際協力を支えていることを紹介しました。このイベントには、2日間で約8万人の来場者がありました。
(ロ)開発教育

外務省職員が大学・高校に出向く「ODA出前講座」
開発教育は、子どもたちなどに開発問題を含む国際協力についての関心と理解を促し、ひいては国際協力への志を育むことにもつながります。全国の小・中・高等学校で実施されている「総合的な学習の時間」の学習活動の一つとして、開発教育や開発途上国の抱える問題なども取り上げられています。
外務省は、開発教育を推進するために、外務省のホームページ内に「義務教育向け開発教育推進ホームページ(「探検しよう!みんなの地球」)」を立ち上げ、国際協力プラザのホームページにおいて動画なども含めた様々な開発教育教材を随時提供するなど、積極的な取組を行っています。また、2003年度以降は、「開発教育/国際理解教育コンクール」を毎年開催しています。
ODA民間モニター事業では、これまでの「教員枠」に加え、2007年度からは「高校生枠」を設置し、生徒自身の参加も促しています。また、「ODA出前講座」では、外務省国際協力局職員を学校にも派遣しており、政府開発援助政策や国際協力について、援助に携わる人から直接聞く話は、生徒の学習材料として役立っています。
そのほか、JICAにおいても新JICA発足以前から開発教育の普及に努めてきました。例えば、学校教育の現場や地方の国際化を推進する地方自治体などの求めに応じて、青年海外協力隊経験者などを講師として学校などへ派遣する「国際協力出前講座」、全国の中学生・高校生を対象にしたエッセイコンテストなどを実施するとともに、「開発教育指導者セミナー」や「教師海外研修」といった、教育従事者への支援を行ってきました。2006年には、開発教育支援を含む、市民参加協力事業の拠点として、「JICA地球ひろば」を開所しており、2007年度の来所延べ人数は約8万9,000人となっています。
旧JBICでは、修学旅行生のグループ学習の受入や職員による出張講座の実施や「円借款パートナーシップ・セミナー」、大学生・大学院生を対象とした「学生論文コンテスト」を実施してきました。
(ハ)国際社会に対する情報発信の強化
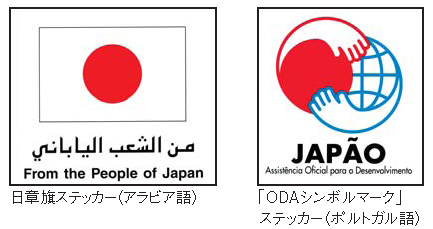
日本国内における広報に限らず、政府開発援助を通じた日本の積極的な国際貢献については海外においても正しく認知され、評価されることが重要です。日本では、従来から海外における日本の支援に対する正しい評価、および個々の案件における日本の貢献の周知を目的として、署名式や引渡式に際してプレスリリースを発出するなど現地プレスの取材に協力したり、日本の援助物資に日章旗ステッカー(英語、アラビア語)や「ODAシンボルマーク」ステッカー(英語、フランス語、スペイン語、アラビア語、ポルトガル語など)を貼付したり、援助により完成した建設物などのそばに看板を設置するなどしています。
また、在外公館では、現地プレスに対して日本の援助現場視察をアレンジし、現地メディアでも日本の協力が取り上げられるような機会づくりに努めています。さらに、在外公館では、各種講演活動や英語・現地語によるホームページの作成、メールマガジンの送信、日本の国際協力に関する様々な広報資料パンフレットの作成も行っています。ほかの援助国・機関を含む国際社会に対しても、日常の外交努力や国際会議における情報発信のほか、各種シンポジウムやセミナーの開催、ホームページなどを通じた情報発信に積極的に取り組んでいます。





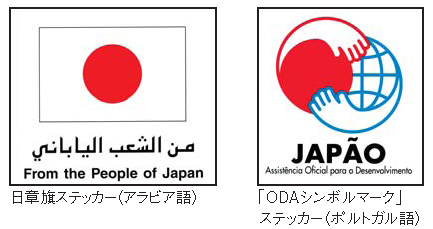
 .
.