囲み 5 二国間援助(バイ)と国際機関(マルチ)を通じた援助の連携事例
| 具体的な事例 | 実施国 | 実施期間 | 案件の内容 | |
| 1 | アジアの持続的成長のための日本の貢献策 (ESDA) |
アジア | 2007年~ | 1.アジアの持続的成長のために必要な、投資の促進、省エネルギー等の促進のため、日本とADBの連携を強化するもの。日本からの支援実績が少ない国の案件分などを中心に、ADBとの連携を深め、その知見を活用し、両機関の手続きの重複を廃することにより、より迅速、かつ広範な円借款支援を可能とする援助形態。 2.投資の促進および省エネルギー等の促進のための制度構築、技術協力、パイロット事業実施のため、ADBに5年で最大1億ドルを目標とした「投資環境整備基金」と「アジアクリーンエネルギー基金」を設置している。 |
| 2 | ジャパン・プラットフォーム (JPF) スーダン南部人道支援 |
スーダン | 2006年 5月~ |
ジャパン・プラットフォームの資金を受け、活動する日本のNGOがUNHCR、WFP、UNICEF等の国連機関、国際NGO等と連携し、水・衛生施設の建設や教育、保健、給水、帰還民の帰還支援・シェルター建設等、様々な事業を展開している(詳しくはコラム16を参照)。 |
| 3 | 「北部ガーナにおけるシアバター産業支援を通じた現地女性のエンパワーメントと貧困削減」プロジェクト | ガーナ | 2006年 2月~ |
JICA開発調査「地場産業活性化計画」の一環として、現金収入の少ない北部地域で、女性の収入向上を目指し、現地で製造されているシアバターのマニュアルを作成している。今後は、日本のWID基金(24万5,927ドル)を活用したUNDPとJICAが共同で、完成したJICAのマニュアルを現地語訳し、更に多くの製造者に使用してもらうことを目指している。このマニュアルはガーナ政府により公認される予定。 |
| 4 | 貧困農民支援によるウガンダのネリカ米普及・生産促進事業について | ウガンダ | 2006年2月 (交換公文(E/N)締結) |
FAO経由で、ウガンダのネリカ米普及・生産促進事業に対し、1億4,700万円の貧困農民支援を行うもの。FAOの農民動員による指導手法を活用しつつ、JICA専門家とFAOが連携し、地元農民に対し幅広くネリカ米の普及と指導を実施。 |
| 5 | アフリカの民間セクター開発のための共同イニシアティブ (Epsa for Africa) |
サブ・サハラ・アフリカ諸国 | 2006年~ | 2005年のG8グレンイーグルズ・サミットにおいて立ち上げた、アフリカ開発銀行(AfDB)の知見をいかして資金供給の迅速化・効率化を図り、民間セクターを支援するための援助形態。 (1)政府および政府機関等に対するAfDB等との協調融資(ソブリン向け融資)、(2)AfDBの民間セクター向けノンソブリン業務に対する融資(ノンソブリン向け融資、ツー・ステップ・ローン)の2つがある。 これまでにソブリン向け融資には、4か国合計146億円の供与を決定している。具体的にはセネガル(首都ダカールとマリの首都バマコを結ぶ国際幹線道路の建設)、タンザニア(ドドマからケニアの首都ナイロビへ続く唯一の国際幹線道路の整備)、モザンビーク(北部にあるタンザニア国境沿いのカーボ・デルガド州とニアッサ州を横断する国道の改良)、ウガンダ(送電網の整備)を決定している。 ノンソブリン向け融資には、115億円の供与を決定しており、具体的には地場銀行を通じた中小企業向け融資、マイクロクレジット、民活インフラ事業等への支援を実施している。 また、中小零細企業育成、金融機関の能力向上、公共部門のガバナンス強化のための技術支援等を実施するために、2億ドルを目標とした信託基金を設置している。 |
| 6 | パレスチナにおける母子健康手帳 | パレスチナ | 2005年 8月~ |
インドネシアを含めアジア各国で広まっている日本の母子手帳を、中東地域では初めてパレスチナで普及を目指すもの。現地NGO、パレスチナ自治政府保健庁、UNICEF、UNRWA、UNFPAがJICAと連携し、母子健康手帳の普及活動を実施。技術協力の一環として、専門家の派遣と研修員の受入、分離壁や検問により移動制限をされている状況で母子手帳を配布するなど、手帳作成から配布に至るきめの細かい援助が行われている。 |
| 7 | スマトラ沖大地震・インド洋津波被災者支援およびパキスタン等大地震被災者支援 | インドネシア、 スリランカ、 パキスタン |
2005~2006年 | スマトラ沖大地震・インド洋津波被災者支援に際し、ジャパン・プラットフォームの資金を受けた(特活)ピースウィンズ・ジャパンは、スマトラ島の村落で、UNICEFと協働で水浄化システムの設置やFAOと協力して農業資機材の配給支援を実施した(インドネシア)。また、(特活)難民を助ける会とIOMが協働で、心のケアや生活再建を通じた地域活性化のための活動を実施し、また、円借款によりインフラ復興や中小企業活動を支援した(スリランカ)。その他にも、パキスタン等大地震の際、IOMは日本政府がパキスタン政府に供与した緊急援助物資を被災地に配布したり、物資輸送を通じて日本のNGOへの協力などを行った。 |
| 8 | 教育の質の改善プログラム (3分間算数テスト) |
バングラデシュ | 2004年~ | 技術協力である理数科プロジェクトの一環として、JOCV隊員により教材開発された算数ドリルを、UNICEFとの協力で全国展開するもの。日本が持つ理数科教育の知見と、UNICEFが持つ草の根レベルでの活動を通じたネットワークを活用することで、より効果的な支援が可能となっている。 |
| 9 | 子どもにやさしい学校事業 | ネパール | 2003年~ | UNICEFネパール事務所とJICAの連携により、子どもにやさしい学校事業の草の根レベルでの展開が可能となった例。UNICEFが実施している教育プロジェクトに、JOCV隊員が参加し、教員の指導力向上を目指している。JOCV隊員から、プロジェクトに対する提言も行われている。現地の受入態勢が整っているUNICEFと連携することで、効率よく技術や知識の移転が可能となっている。 |
| 10 | バック・トゥ・スクール (学校へ戻ろう) |
アフガニスタン | 2002年 | 学校教育再開において、日本政府はUNICEFに対し緊急支援(500万ドル)を通じて、本キャンペーンを実施。日本のNGO6団体から11人のスタッフが派遣され、このキャンペーンのモニタリングをした。推定300万人の子どもたちが学校に戻ることができた。 |
| 11 | 血液供給システム改善事業 | スリランカ | 2001年 1月~ |
WHOとJBICの初の連携案件。本事業の実施機関であるJBICが、WHOから助言を得ながら、円借款事業(15億800万円を限度額)として中央輸血センターの整備および地域血液銀行への機材提供を行い、安全かつ効率的な輸血供給システムを確立し、保健医療水準の向上に寄与するもの。また、JICAを通じて研修員の受入を行うなど、JBICとJICAの連携も見られる事例(詳しくはコラム4を参照)。 |
| 12 | 予防接種拡大計画 (ポリオ根絶への支援) |
セネガル、 ケニア、 ザンビアなど |
1989年~ | JICAの技術協力(専門家派遣、研修員受入等)とUNICEF(調達部を通じた資機材(ワクチンを含む)支援)との連携により、ポリオ撲滅を目指すもの。1989年から開始され、1998年以降は、母子保健分野まで連携が拡大されている。アジア・アフリカの国々を中心にポリオ根絶に成功しており、大きな成果を残している。 |
| 13 | スクールマッピング・マイクロプランニング (SMMP) |
タンザニア | 1999~2002年 | 地域教育の改善、地域格差の是正を目的として、UNICEFがタンザニアの42県を対象に、地域教育情報の収集を目的としたスクールマッピングを作成。JICAがこの結果をもとに、県、区、学校の関係者とも協力し、教育アクセス向上を目指した地域ごとの教育計画を作成した。これまでに33県に対し実施している。 |
 |
(写真提供 : UNDP/Africa 2000 Network Ghana)
 |
(写真提供 : 船尾修/JICA)
 |
(写真提供 : IOM / Jonathan Perugia / OnAsia 2005)
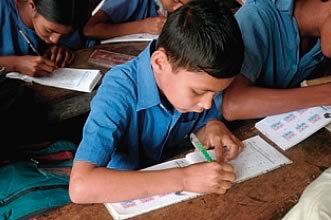 |
(写真提供 : JICA)
 |
(写真提供 : UNICEF / Shehzad Noorani / HQ03-0104)
 |
(写真提供 : 今村健志朗/JICA)