スーダンはアフリカ大陸最大の国土を持つ国で、面積は日本の約6.6倍、人口は日本の約3割の約3,700万人です。1983年以来、20年以上にわたって続いた南北内戦は、2005年1月、南北包括和平合意(CPA:Comprehensive Peace Agreement)の締結により、ようやく終止符が打たれました。しかし長年の紛争が残した傷跡は深く、道路や上下水道などの基礎インフラは破壊され、武器や地雷が拡散、最低限の食糧や医療、教育もままならない国内はまさに壊滅状態にありました。さらに南部では、隣国のエチオピアやケニアに逃れていた55万人の難民、500万人以上ともいわれる国内避難民の帰還が見込まれる中、日本はこのスーダンに対し積極的に平和の定着を支援しています。
具体的には、難民・避難民の帰還支援、食糧支援、地雷・不発弾の除去、医療支援、小児感染症予防支援、給水支援、貧困農民支援、教育支援等をUNHCR、WFP、UNMAS、UNICEF、ICRC、IOMなどの国際機関を通じて無償資金協力によって実施しているほか、都市計画づくりのための開発調査や職業訓練などの技術協力を開始しています。
また、ジャパン・プラットフォーム(JPF)(注)に提供されている政府開発援助資金で日本のNGOによる緊急人道支援活動も行われています。これら日本のNGOは、事前に現地において国連機関(UNHCR、WFP、UNICEF、UNMAS等)や国際NGOと連携して事業形成を行うことで、効率のよい支援を実施しています(下図を参照)。
一方、スーダン西部のダルフール地方では2003年2月から新たな紛争が始まり、250万人以上の難民・国内避難民が発生しています。2006年5月にダルフール和平合意(DPA:Darfur Peace Agreement)が締結されましたが、反政府勢力側は一派だけが合意に参加し、その後、分裂をくり返し、状況はむしろ悪化しました。永続的な和平達成に向け、国連とアフリカ連合を中心とした国際社会の一致した包括的な取組が一層求められています。
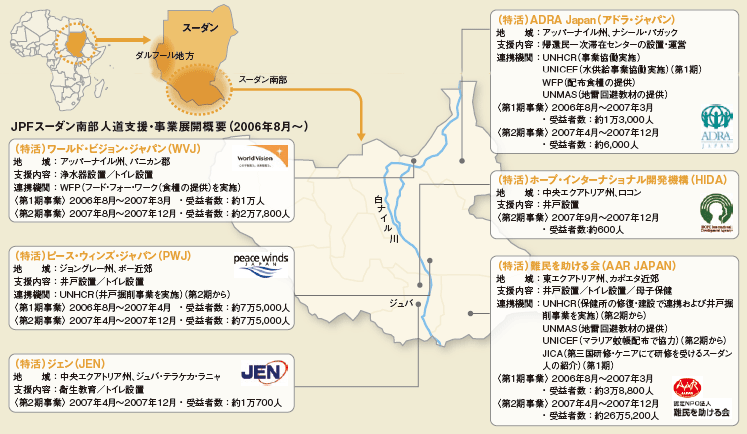 |
食糧支援を通じて平和を築く
WFP 国連世界食糧計画スーダン局長
忍足謙朗さん
私は国連職員としてこれまでおよそ10の国や地域で仕事をしてきましたが、スーダンはその中でも特に過酷な状況にあります。慢性的な貧困に加え、20年以上続いた南北の紛争と、今も続く西部ダルフールの紛争による打撃は大きく、合計で700万人近い難民・避難民が発生し、5歳未満の子どもの6人に1人が栄養不足です。
このような状況下、WFPは、南北包括和平合意(CPA)が成立し少しずつ復興が進む南部と、いまだ紛争が続くダルフールを中心に、スーダン全土で550万人(全人口の6分の1)を対象に食糧支援を行っています。スーダンでの食糧支援はWFPが世界で行っている事業の中で最大で、WFPの年間予定支出の4分の1以上に当たる870億円が充てられ、全職員の4分の1に当たる2,500人が従事しています。日本人職員も8人います。
 |
明日の食べ物を心配しなければならないような状況では、平和は築けません。食べ物の心配がなくなってこそ初めて人々は平和づくりに専念できます。私たちは食糧支援を通じてスーダンの平和構築の一助になりたいと考えています。
最近、力を入れているのは学校給食プログラムです。これは、給食を出すことで子どもたちを学校に呼び寄せ、栄養状態の改善と就学率の向上を図るというものです。実際、2006年度、給食を出した学校では就学率が24%上昇しました。スーダンの平和と未来を担う子どもたちを育成するため、学校給食事業はできる限り拡大していきたいと思っています。
 |
WFPが日本などから支援を受け、南部で行った地雷除去と道路整備事業も、スーダンの平和構築に貢献しています。南部では、内戦中の道路破壊と地雷埋設により陸路が寸断されていましたが、道路整備の結果、以前は飛行機で輸送していた食糧をトラックで輸送できるようになりました。さらに、人々が乗るバスの運賃が半額になったり、近隣諸国との貿易が活性化したりするなど、住民にも多くの利益をもたらしました。人々は「和平の配当」を実感しており、これは日本の支援の大きな成果の一つだと思います。
最大の課題は治安です。ダルフール和平合意(DPA)締結後もダルフールでは戦闘が続き、治安はむしろ悪化の一途をたどっています。人道支援関係者に対する襲撃も増加し、10月には3人のドライバーが射殺されました。治安悪化のため食糧を届けられないこともあり、残念でなりません。WFPの食糧はまさに人々の命を支える生命線です。スタッフの安全を確保しながら、どうやって人々にきちんと食糧を届けるかが重大な課題です。
2006年、WFPスーダン局は日本政府からおよそ25億円の拠出を受けました。日本の皆さんのお金がスーダンの人々を支えています。是非皆さんにはもっとスーダンの現状を知っていただき、平和構築の過程を見守っていただきたいと思います。
人々が安心して故郷に戻れるように
(特活)ADRA Japan スーダン駐在員 了戒紗世さん
ADRA Japanは、2006年8月から、ジャパン・プラットフォームと国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)の資金協力を受けて、スーダン南部、アッパーナイル州のパガックとナシールで、帰還民を支援する「一時滞在センター」の設置・運営事業を開始しました。エチオピアには、約8万人のスーダン難民が登録されています。これらの難民がスーダンの故郷の村まで安全に帰還できるよう、センターでは、帰還民の登録、輸送手配、数日間の宿泊の確保、地雷回避教育、食糧・生活用品の配布などを提供します。
スーダンは長期にわたる紛争のためインフラが未整備で、また一年の半分は雨季で湿地帯と化しています。これらのチャレンジを乗り越え、2007年3月にはセンター開所式を行い、開始以来、約7,000人の帰還民を受け入れ、送り出すことができました。
帰還民輸送の際には、様々な歓喜の再会シーンに出会いました。車で到着した娘を見て、川で水浴びをしていた家族が叫びながら裸のまま駆け寄ってきて抱きしめ大騒ぎになったり、寝込んでいたおじいさんが帰還した孫を見て起き上がったり。 「スーダンには何もないと聞いてきたが、トイレや水、シェルターもあるこのような施設があり助かった。ADRAには本当に感謝だ」、と帰還民から何回も言ってもらうことができました。
 |
人々が安心して生活できるように
(特活)難民を助ける会(AAR JAPAN) スーダン駐在員 南香子さん
「スーダン」と聞いて、何を思い浮かべるだろうか? 乾いた大地、貧困、ダルフール紛争。そして、南北の間で20年以上続いた内戦。
南部スーダンでは、紛争の影響で生活に必要なインフラが絶対的に不足している。周辺国からの帰還民は、口をそろえて「井戸、学校、病院がないため、自分の国であるスーダンに戻ってきても、自分と家族の将来が見えない」と言う。このため、隣国の難民キャンプから遠路はるばる帰還してきても、施設が整い、子どもたちに教育を受けさせることのできる難民キャンプに再び戻ってしまう例が多い。
難民を助ける会は、2006年8月から、南部スーダンの東エクアトリア州にて、井戸掘削、衛生・マラリア予防活動を実施している。これまでに同地域で計30基の井戸を掘削した(2007年10月25日現在)。井戸の掘削といっても、数多く残っている地雷の影響で、掘削自体ができないこともある。さらに、掘れば必ず水が出るわけでもない。しかしながら、このように苦労を重ねながらも、村に井戸が1つできるだけで、住民の生活は一変する。安全で清潔な水の確保、衛生状況の改善、病気の予防、水くみのための時間の短縮など、その効果は計り知れない。日本のNGOそして一人の日本人として何ができるか、自らのこと、自らの問題としてとらえ、事業を継続していきたい。
 |
注 : ジャパン・プラットフォームは、日本のNGOによる迅速で効率的な緊急人道支援を目的として、NGO、経済界、政府、メディア等が協力して2000年に設立したNGO。難民発生時や自然災害時などに、事前に供与された政府開発援助資金や一般企業・市民からの寄付金を活用して援助を実施する。