ヒマラヤの山懐に抱かれたネパールは、標高8,000メートルを超える高地から100メートル以下の平野部までの多様な地形の中に、多様な歴史を経てこの地に定着した各種民族が、カースト制を含む歴史的社会制度の中で伝統的社会を維持してきた国です。しかし、特定階層による権力の集中もあり、民主化・近代化の過程において様々な形での権力闘争が行われてきました。
1996年、ネパール共産党毛沢東主義派を名乗る共産主義勢力(マオイスト)は、当国中西部において反政府武装闘争を開始、その後闘争は全国に飛び火し、11年間にわたりネパールの国土全体が内戦による混乱の渦中に置かれてきました。しかし2006年4月、連日数十万人の市民が参加した「第2次民主化運動」を通じ政権を掌握した主要7政党は、マオイストとの停戦交渉に着手し、同年11月、ついに、主要7政党とマオイストとの間での包括的和平合意への署名が行われ、内戦に終止符が打たれました。ネパールは恒久的和平に向けた長いプロセスを歩み始めました。
まず、マオイストが要求し続けてきた新しい憲法を制定するための議会構成員を選定する制憲議会選挙を、2007年6月までに実施することになりました。そのために、マオイストおよびネパール国軍それぞれが兵舎内にとどまり、その武器の管理状況の監視については国連にゆだねることなどが決定されました。ネパール政府およびマオイスト双方はこの決定に基づき国連に支援を求め、国連は安保理決議1740号に基づき、武器・兵士管理の監視、および同選挙の実施に向けた技術的支援等のために国連ネパール政治ミッション(UNMIN)を設立しました。これにあわせネパール政府側は、兵営地の整備や選挙の実施に必要になる各種物資や資金、紛争の影響で避難生活を余儀なくされた人々の救済計画への支援等を国際社会にアピールしました。
日本は、1969年にネパールへの経済協力を開始してから、教育、保健、農業開発、道路・発電等のインフラ整備、環境保全など様々な形でネパールの開発を支援してきた主要援助国です。また、アジアの最貧国の一つであるネパールの開発に深くかかわってきた経緯がありますが、長引く紛争中にはネパールの経済・社会開発は低迷し、また援助関係者の安全確保のために協力事業の展開に制約を受けるなどの困難にも直面してきました。これから、日本としても、ネパールが安定を取り戻し、平和な環境下で社会的経済的開発を進めるためにも、この和平プロセスの推進のため積極的に、かつ多角的に支援を行っています。
例えば、マオイスト兵関連では、マオイスト兵営地内で管理されている武器および兵士の監視要員として日本の自衛隊員6名を国際平和協力隊員としてUNMINに派遣し、他国の監視員とともにネパールの首都から遠く離れた兵営地での監視業務に従事しています。また、マオイスト軍と行動を共にしてきた児童(児童兵)の社会復帰のために、UNICEFが実施する事業に資金協力を行っています。
一方、制憲議会選挙開催支援のため、今回の選挙に必要となるすべての投票箱6万箱を2007年5月までに供与するとともに、JICAから専門家をUNMINの選挙支援部門に派遣し、国連とも協力し選挙実施に向けたネパール政府の体制整備を支援しています。加えて、2007年2月にはネパールの選挙管理委員会関係者5名を日本に招へいし、愛知県の地方選挙の視察などを通じ、日本の選挙の実態を伝えているほか、選挙広報を行うにあたり、ネパールの山間部では唯一のメディアとなる国営AMラジオ局の老朽化した放送機材の更新を開始することで、制憲議会選挙の後に続く、総選挙や地方選挙を目指した、ネパール側の能力強化を目指しています。
和平プロセスの進展のためには、このような政治プロセスに加え、実際に紛争の被害を受けた人々に対する支援を行い、平和の到来を実感してもらうことも必要です。このため日本は、UNICEFや国連人口基金といった国連専門機関が、紛争の影響を強く受けた地域で実施する医療事業に対し資金協力を行うとともに、日本のNGOである、(社)セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン(SCJ)に日本NGO連携無償資金協力を行い、紛争のために国内で避難生活をしている子どもたちに向けた教育支援事業を実施しています。
日本をはじめとする各国、そして国連からの多様な支援を受けて進んでいるネパールの和平プロセスですが、その中核の一つである制憲議会選挙は、2007年6月に実施される予定でしたが、技術的理由により同年11月に延期され、さらに政治的理由により11月の選挙も再延期され、その後、新たな選挙日程が決定されていない状況となっています。また、本選挙に向けて設立した暫定内閣においても、マオイスト閣僚が辞表を提出するなどの紆余曲折が見られ、当初予定していたとおりの進展が見られているわけではありません。しかし、日本はUNMINの選挙支援業務への協力等を通じ、多くの村の人々から「選挙が実施されればネパールが生まれ変わるのだ」といった期待の表明を受けています。ネパールの人々の心の中で、11年間の内戦が過去のものとなり、よりよい社会への変革の期待が高まる中で、日本はこの和平プロセスが後退することのないよう、また、長期的な経済社会開発が進展するよう、国際社会と協調しつつ支援を継続しています。
 |
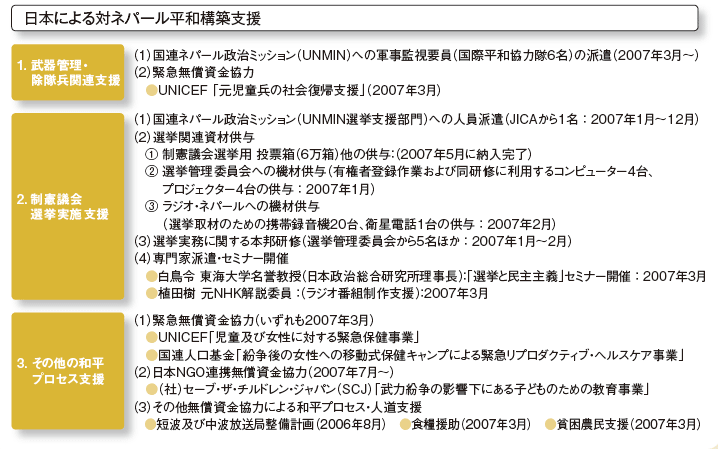 |
ノートと鉛筆を寄付したお母さんたち
SCJネパール事務所代表
定松栄一さん
「それって、ひょっとして、昨日寄付を申し出てくれたノートと鉛筆なの?」
研修4日目の朝、小学生のお母さんとおぼしき女性二人がノートと鉛筆の束を抱えて会場に現れたのを見て、私は思わず声をかけた。
ここはネパール西部平野のダン郡にあるブカリヤ小学校。今年(2007年)7月から、(社)セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン(SCJ)は、日本NGO連携無償資金協力の支援を受けて「武力紛争の影響下にある子どものための教育事業」を開始した。
11年に及ぶネパールの内戦は子どもたちや教育にも大きな影響を与えた。戦闘に巻き込まれて親や兄弟を亡くした子どもたち。学校そのものが兵舎に使われたり少年兵のリクルートの拠点になったこともある。昨年11月に和平合意が成立し、ようやく村の再建のための活動が各地で始まった。学校も例外ではない。
疲へいした校舎の修復も必要だが、それ以上に大切なのが子どもたちが安心して勉強できる環境づくりだ。内戦の被害を受けて生活の苦しい農村ほど、親は子どもを学校に通わせずに農作業や家事を手伝わせようとする。通学が許されても、ノートも鉛筆も持たずに登校する子どもたちが跡を絶たない。これではいくら勉強したくても、できない。
「教育は子どもの大切な権利。それを守るのは村全体の責任。皆が力を合わせなければ学校の再興はおぼつかない」そのことを分かってもらうために5日間の研修を開催した。
研修3日目。村人全員が集まり校庭に村の地図を描いた。村の近くを流れる川にすむ魚や森からとれる材木など身近な物でも有効に活用すれば学校を支える財源になる。それでも学校の維持費をねん出するのが精一杯で、机・椅子や文房具を買うための資金には足りない。村人を前にSCJのネパール人スタッフが言う。
「この学校のために私は個人的に100ルピー寄付します。皆さんも一人ひとりが学校のために何ができるか考えてください」
「お金は出せないが、おれは大工仕事が得意だから、生徒のために机と椅子をつくろう」とお父さん。「私も、たくさんは無理だけど、1ダースなら鉛筆を寄付します」、「私はノートを1ダース」とお母さんたち。
こうしてこの日は終わったが、正直なところ、私は貧しい村の人たち、中でも現金収入のない女性が本当にノートや鉛筆を寄付できるのか半信半疑だった。「皆の前だから、ああは言ったものの・・・」
ところが翌朝、お母さん二人がさっそくノートと鉛筆の束を手に会場に現れた。「本当に寄付してくれるんだね」カメラを向けると、ちょっと照れくさそうにほほえんだ。
 |
(写真提供 : SCJ)