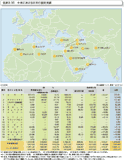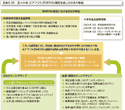日本の中東に対する2006年の二国間政府開発援助は、約10億4,900万ドルで、二国間援助全体に占める割合は14.0%です。
日本の輸入原油の約9割を供給し、世界の主要エネルギー供給地域としての中東地域の平和と安定確保を実現することは、国際社会全体の平和と繁栄に直結する重要な問題です。イラクやアフガニスタンの復興、中東和平プロセスの進展は、中東地域全体の不安定化を回避し、同地域の平和と安定達成に死活的な重要性を有することから、日本は、国際社会と連携しつつ引き続き積極的に支援しています。また、水資源に乏しい中東地域では、その確保や管理が地域的な安定にも影響を及ぼしうる重要な課題です。さらに、技術者育成などの人材育成は域内に共通する大きな課題となっており、開発・社会格差是正のための経済社会インフラ整備や貧困対策も重要です。また、資源を有する国の中では、クウェート、カタール、アラブ首長国連邦など、一定の経済発展を達成し、既に政府開発援助を卒業してきています。
日本は、イラクやアフガニスタンにおける平和構築支援、パレスチナや周辺アラブ諸国への支援等中東和平支援のための協力、水資源管理のための支援、経済社会インフラ整備、人材育成支援、環境保全対策を重視しつつ、中東の社会的安定と経済的発展のための支援を積極的に行ってきています。
● イラク・アフガニスタンへの支援
対イラク支援については、日本は自衛隊による人道復興支援、50億ドルの政府開発援助、60億ドルの債務救済、国民融和促進等、積極的な取組を行ってきています。また、対アフガニスタン支援については、日本は、2006年3月末までに10億ドルの支援を実施することを表明し、また、2006年1月に開催されたアフガニスタン復興支援会議(ロンドン会議)における4.5億ドルの追加支援表明も含め、これまでに計14.5億ドルの支援を表明しており、現在(注31)までに既に総額約12.4億ドルの支援を実施あるいは決定済みです。
→ イラク・アフガニスタンへの支援については、第II部のこちらとこちらも参照してください
● 中東和平支援
中東和平支援については、日本は、現在の和平プロセスが開始された1993年以降、現在までに約9億ドルの対パレスチナ支援を実施、イスラエルとパレスチナが共存共栄する二国家構想の実現を支持し、アッバース・パレスチナ自治政府(PA (注32))大統領による和平努力を一貫して支援してきています。2006年3月、ハマス主導のパレスチナ自治政府内閣が成立後、日本は同内閣に対し、民主的に選出された責任を自覚し、イスラエルとの共存共栄の道を歩むよう呼びかける一方、パレスチナ人に対する人道支援を継続、同年7月、小泉純一郎総理大臣(当時)のパレスチナ自治区訪問の際、人道支援等からなる約3,000万ドルの支援を表明しました。
 |
事務局長の表敬訪問を受ける小野寺五典外務副大臣(写真右)
また、日本独自の中東和平への中長期的な取組として、イスラエル、ヨルダン、パレスチナ、日本の四者の地域協力を通じてヨルダン渓谷の経済開発を図る「平和と繁栄の回廊」構想を提案し、各首脳の賛同を得ました。具体的には、「農産業団地の設置」、「配送センターの設置」、「物流の促進」への支援を通じ、当該地域の開発を図り、その利益を関係国が共有することで信頼醸成を図るものです。2007年3月、東京において閣僚級の四者協議立ち上げ会合、同年6月の事務レベルでの第1回四者協議(ヨルダン)の開催に続き、同年8月には、麻生太郎外務大臣(当時)によるパレスチナ自治区の訪問の際、ジェリコにおいて四者協議閣僚級会合を開催するなど、構想の具体化に向け積極的に取り組んでいます。上記閣僚級会合において、麻生外務大臣から、農産業団地のジェリコ県南部への建設や本構想に引き続き推進することなどを提案し、四者で合意しました。
なお、対パレスチナ支援については、同年3月、医療、雇用創出および食糧からなるパレスチナ人への人道支援1,260万ドルを、また、ハマスによるガザ掌握を受けて同年6月にファイヤード緊急内閣が成立したことも踏まえ、上記麻生外務大臣訪問時に、パレスチナ自治政府に対する直接支援をはじめとする総額約2,000万ドルの支援を表明しました。
中東諸国の改革努力を支援するイニシアティブである「拡大中東・北アフリカ(BMENA)」構想について、日本は、人を育て、人をいかすための取組の重要性を強調し、職業訓練、教育支援に重点的に取り組んでいます。G8とBMENA諸国の外相級の対話の場である「未来のためのフォーラム」は、2006年はヨルダンにおいて第3回会合が開催されました。日本は、教員の養成、技術教育の訓練センター、情報通信技術(IT)による学習システムの開発のほか、パレスチナ自治区における学校建設、教材整備やカリキュラムの提供、サウジアラビアにおけるコンピューターを活用した女性の自宅就労支援などの具体的取組を紹介しました。
図表II-38 拡大中東・北アフリカ(BMENA)構想を通じた日本の取組
資源・エネルギーの乏しい日本にとって、その確保は重要な外交課題の一つです。一定の経済発展を遂げ、政府開発援助を卒業した国との間でも、長期にわたる安定的な二国間関係を構築する必要があります。こうした国については、政府開発援助以外の公的資金(OOF (注34))の活用や民間を主体とし、どのような協力が可能かを検討していくことが課題です。例えば、2007年5月に安倍晋三総理大臣(当時)が訪問したカタールにおいて、教育協力の更なる強化を表明しており、そのフォローアップが進められています。