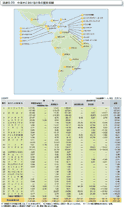日本の中南米に対する2006年の二国間政府開発援助は、約4億3,152万ドルで、二国間援助全体に占める割合は5.8%です。
中南米諸国は、日本にとって、民主主義、自由市場経済などの価値観を共有する重要なパートナーです。また地理的に日本とは離れていますが、日本人移住者とその子孫である日系人を「懸け橋」に、伝統的に友好的な関係を築いている地域です。さらに、この地域は5.5億人(東南アジア諸国連合(ASEAN)とほぼ同じ)に及ぶ人口、2.95兆ドル(ASEANの約2.8倍)に達する域内総生産を持つ大きな市場であり、地域統合(中米統合機構(SICA (注35))、南米南部共同市場(MERCOSUR (注36))、カリブ共同体(CARICOM (注37))、アンデス共同体(CAN (注38)))の動き、諸外国との自由貿易協定の締結によってその存在感を高めています。また近年の資源価格の高騰とも相まって、豊富なエネルギー・鉱物(鉄鉱・銅鉱・銀鉱(注39)・原油・天然ガス・バイオ燃料)、食料資源(食肉・大豆等)の供給地としても注目を浴びているほか、メキシコおよびチリと経済連携協定(EPA (注40))が締結されるなど日本の信頼できる経済パートナーとなりつつあります。平均所得水準は政府開発援助対象国の中では比較的高い国が多いものの、一方で国内の貧富の格差が大きい国が多いことも、この地域の特徴です。
また、2006年には12か国で選挙が行われ、勝利した候補が社会政策の充実を公約の全面に打ち出していた点が注目されます。これは、自由開放経済を維持する一方で、根強く残る貧困や貧富の格差等の歴史的な問題に取り組むことが、中南米における民主化達成後の課題となっていることを示しています。
日本は中南米地域の安定と発展のため、政府開発援助を通じて、歴史的課題である貧困や所得格差等の是正、平和の構築、地球規模問題でもある環境問題への対応、地域の持続的な経済発展、地域統合の促進などを支援しています。
援助の実施にあたっては、効果的・効率的な運用を重視しています。この観点から、地域に共通した開発課題について複数国に利益となる広域案件の形成を進めています。また、他の援助国との連携を強化、南南協力をも活用しています。
● 貧困、所得格差の是正
歴史的課題であるこれらの問題については、保健・医療、教育、水と衛生、農村開発など被援助国による適切な社会開発政策を支援していく考えです。
● 環境問題
中南米では、各地で経済開発に伴う環境汚染が懸案となっており、また、アマゾンなどの熱帯雨林が存在することから、地球環境問題対策という意義も踏まえて、公害対策や自然環境保全を支援しています。
● 平和構築
ハイチやコロンビアなど政情不安や国内武力抗争が継続していることから、平和の構築に向け、選挙支援、国内避難民への職業訓練などの支援を行っています。
● 地域の持続的な経済発展支援
日本は、中南米地域の持続的な経済発展を支援するため、ビジネス環境改善のためのインフラ整備やすそ野産業振興、中小企業育成、職業訓練などの分野で協力を行っています。2006年度においては、ペルー・エクアドル国境の「新マカラ国際橋建設計画」の無償資金協力やエクアドルの「職業訓練改善プロジェクト」の技術協力を行いました。また、同地域は豊富な資源を有し、経済機会が拡大していることから、地域の発展にも資するとともに日本企業の活動に対する支援ともなりうる、政府開発援助以外の公的資金(OOF (注41))も活用しつつ、資源エネルギー開発支援にも取り組んでいます。
さらに、政府開発援助を通じて、2005年4月に発効した日本・メキシコ経済連携協定(EPA)に関連した、中小企業・すそ野産業支援や環境分野における技術協力などを進めています。現在までに、大気汚染、沿岸の水質に関してモニタリング能力強化などを行ってきたほか、今後、農村地域でのバイオガスを利用した小規模クリーン開発メカニズム(CDM (注42))事業モデルの実施を行っていく予定です。また、中小企業の人材養成についても、支援の内容につき、メキシコ政府との間で協議を進めています。
● 地域統合支援と広域協力の推進
中南米地域においては、同地域の地域統合イニシアティブの一つである中米のプエブラ・パナマ計画(PPP (注43))、および南米インフラ統合計画(IIRSA (注44))があり、これらのイニシアティブに対して日本も協力しています。2006年度からは、プエブラ・パナマ計画の一環として、ホンジュラス・エルサルバドルの国境をまたがる道路・橋りょう整備計画である「日本・中米友好橋建設計画」を実施しています。
● 広域協力
中米においては、中米地域で国境を越えて感染が広がる熱帯病であるシャーガス病根絶に積極的に取り組んでおり、2002年にグアテマラで実施した後、2004年以降はエルサルバドル、ホンジュラスと対象を拡大しています。また、地域の子どもの基礎学力向上のために、2003年にホンジュラスで実施し高い評価を得ている「算数指導能力向上プロジェクト(PROMETAM (注45))」も、グアテマラ、ニカラグア等に対象の範囲を広げています。
カリブ共同体に対しては、技術協力プロジェクト(注46)を実施し、2006年度には、カリブ共同体を相手機関として、初めての広域開発調査(注47)を開始しました。メルコスールに対しても開発調査(注48)や技術協力プロジェクト(注49)を実施しました。SICA、カリコム、プエブラ・パナマ計画の事務局に専門家も派遣しています。
さらに、援助体制に関しても広域化に取り組んでいます。中米においては、各在外公館、JICA、JBICなど実施機関現地事務所を主要なメンバーとして構成される現地ODAタスクフォースのほかに、これら現地ODAタスクフォースのメンバーに東京の関係者を加え、中米広域タスクフォースを立ち上げ、2006年3月から、広域での連携、案件形成に向けた議論を行っています。SICAとも協調し、広域での協力の意義を踏まえた、援助の実施を目指しています。
→ 現地ODAタスクフォースについては、こちらも参照してください
● 南南協力
チリ、ブラジル、アルゼンチン、メキシコの4か国とパートナーシップを結び、主に他の中南米諸国を対象として、経済・社会開発の分野を中心に、第三国研修、第三国専門家派遣等を実施しています。また、メキシコとの間では、2003年10月に署名した日墨パートナーシップ・プログラム(JMPP (注50))の枠組みの下、日本はメキシコ政府と共同で中米等をはじめとする対中南米諸国への技術協力を行っています。