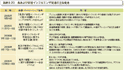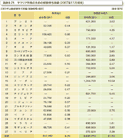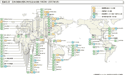実績については、保健医療・福祉分野の実績を参照してください。
HIV/エイズ、結核、マラリアの三大感染症をはじめとする感染症は、開発途上国国民一人ひとりの健康問題にとどまらず、今や開発途上国の経済・社会開発への重要な阻害要因となっています。HIVについては、世界で約4,000万人が感染していると推測されており、2007年7月に公表されたミレニアム開発目標(MDGs)報告では、2006年、エイズによる死亡者数は全世界で約290万人に増加し、エイズ拡大を減速できず、2005年、1,500万人以上の子どもがエイズで片親または両親を失ったと報告しています。結核は、毎年19億人が感染し、約880万人が発症、そのうち160万人が死亡しており、その健康被害は、途上国に95%以上が集中しています。また、世界107か国の約32億人がマラリアの感染リスク地域に居住し、マラリアの発症数は年間3.5~5億人、年間死亡者数は100万人を超えるといわれています(注124)。感染症は、グローバル化の進展に伴い人やモノの移動が容易になったことから、国境を越えて他国にも広まる可能性が高くなり、地球的規模の問題として、国際社会が協力して対処するべき課題となっています。
日本は、「沖縄感染症対策イニシアティブ(IDI (注125))」終了後、2005年6月、保健分野に関連するMDGs達成への貢献を目標にした「『保健と開発』に関するイニシアティブ(HDI (注126))」を発表しました。このイニシアティブでは、感染症対策を含む保健医療分野に対し、2005年度から2009年度の5年間で50億ドルをめどとする包括的な支援を実施する方針です。また、HDIをアフリカで具現化するため、2006年5月に「アフリカ感染症行動計画」を策定し、日本として、アフリカにおける三大感染症対策、寄生虫対策等の分野におけるアジア・アフリカ協力(南南協力)等を推進することを表明しました。
感染症対策への国際社会の取組は、G8九州・沖縄サミットを契機として、2002年1月の世界エイズ・結核・マラリア対策基金(GFATM (注127)、以下、世界基金)の設立につながりました。政府間協力というこれまでの伝統的な枠組みを超えて、広範なパートナーシップを実現した世界基金に対して、日本はこれまでに総額6億6,268万ドルを拠出し、また世界基金の設立当初から理事会の一員として世界基金の効果的、効率的運営のためにも貢献しています。
また、国連の「人間の安全保障基金」、国際NGOである国際家族計画連盟(IPPF (注128))の「HIV/エイズ日本信託基金」、国連教育科学文化機関(UNESCO (注129))の「人的資源開発信託基金」および「エイズ教育信託特別基金」、世界銀行の「日本社会開発基金」など、日本が資金拠出して設置したそれぞれの基金を通じてもHIV/エイズをはじめとする多くの感染症対策を実施しています。
三大感染症に対する具体的な取組状況は以下のとおりです。
→ 感染症以外の保健分野における取組については、こちらを参照してください
世界基金
1. 支援事業(2007年10月12日現在)
これまで136か国、451件以上の感染症対策に、86億ドルを承認。承認された資金供与の58%がHIV/エイズ対策に、24%がマラリア、17%が結核に活用されています。また、国際的な三大感染症対策のための支援資金のうち、HIV/エイズ対策で21%、結核で67%、マラリアで64%を世界基金からの支援額が占めています。
2. 支援の成果(明記のない限り2006年12月現在。( )内は承認事業完了時の予測成果)
(1) HIV/エイズ
◆ 110万人(180万人)に対する抗レトロウイルス薬治療(2007年7月)
◆ 940万人(6,200万人)に対するHIV予防のための自発的カウンセリング・検査(VCT)サービス提供
(2) 結核
◆ 280万人(500万人)へのDOTS治療(2007年5月)
◆ 8,600人に対するMDR-TBの治療
(3) マラリア
◆ 3,000万張り(1億900万張り)の殺虫剤浸漬蚊帳配布(2007年5月)
◆ 2,300万人(2億6,400万人)に対する多剤耐性マラリアのためのアルテミシニン薬をベースとした併用療法
● 新興感染症
近年、地球的規模の問題として関心が高まっている新興感染症の一つである鳥インフルエンザは、特にアジアにおいて深刻な状況にあります。日本は、鳥および新型インフルエンザ対策を積極的に支援してきており、特に早期対応、情報公開、透明性の確保を柱とした国際協力が重要と考えています。2006年12月には、「鳥および新型インフルエンザに関する閣僚級ドナー会合」にて新たに6,700万ドルの支援を表明し、WHO、UNICEF等の国際機関を通じて、住民啓発活動、開発途上国におけるワクチン生産能力向上のための支援、早期警戒システムや迅速な封じ込め体制構築の支援などを行っています。2006年以降の支援の総額は、2.22億ドルになっています。
● HIV/エイズ
日本は、若年者層とハイリスク・グループへのHIV/エイズの予防活動、自発的な検査とカウンセリング活動(VCT(注130))、HIV/エイズ検査・診断体制の整備などに貢献しています。また、国際社会は、2010年までに可能な限り、予防・治療・看護支援を提供することに合意しています。
タンザニアでは、2006年3月から性感染症治療・VCTプログラムを運営する保健社会福祉省国家エイズ対策プログラムの組織強化を行う技術協力プロジェクトを実施し、性感染症治療・VCTサービスの国家指針、研修マニュアルの整備やモニタリング体制の強化などにより、エイズ対策の行政サービスの標準化と質の向上を支援しています。
また、円借款による大規模インフラ整備事業の実施においては、移動労働者の雇用等によるHIV感染リスクの増大を踏まえて、エイズ対策にも取り組んでいます。
→ インフラ整備におけるエイズ対策については、2006年版ODA白書コラムII-6も参照してください
2006年11月には、タイのチェンライにおいて、東南アジア諸国連合(ASEAN)各国からHIV/エイズ対策に携わる保健行政官やHIV/エイズの予防・治療・看護に携わる医療従事者を招へいし、日・ASEAN HIV/エイズワークショップを開催しました。ワークショップでは、医療施設、ケアセンターの現地視察を挟み、地域ぐるみの支援体制(注131)を直接確認したほか、視察や各国のプレゼンテーションなどを踏まえ、国や職種を横断した活発な議論がなされました。
先行国の経験を共有し、よりよいHIV/エイズ対策へ
HIV/エイズを取り巻く状況は各国で異なりますが、近隣国間では共通の課題を抱えている場合もあり、ある国の先行経験を他国へ共有することによって、よりよい対策につなげていくことができます。
例えば、タイにおける「HIV/エイズ地域協力センタープロジェクト」では、カンボジア、ラオス、ベトナム、ミャンマー各々のニーズに合った各国別研修と共通課題の研修を行っています。知識の習得だけでなく、タイのHIV/エイズ対策事業の視察や実務者との意見交換、参加者によるワークショップにより、タイの経験を各国でいかに応用・活用できるかに焦点を当てています。
またタイにおけるエイズの看護と治療に関する共通研修には、ガーナやザンビアのHIV/エイズ対策関係者が参加しました。保健医療制度や、感染経路など背景の相違があるので、アフリカ諸国がすぐにタイの経験を活用するとはいかないものの、エイズ対策に真剣に取り組んできたタイの試行錯誤の過程など学ぶことも多く、アジア―アフリカ間の交流は、大きな刺激となっています。
● マラリア
日本は、マラリアによる死亡者数の約8割を占めるなど状況が最も深刻なアフリカにおいて、2007年までに1,000万張りの長期残効型蚊帳(LLITNs (注132))を供与することを発表しました。国連児童基金(UNICEF(注133))等との連携を通じて、2007年8月末時点で約949万張りを配布しています。UNICEFの試算によると、これによって、年間11万人から16万人に上るアフリカの5歳以下の子どもの死亡が減少し、最大62万人の乳幼児死亡を予防することが期待できるといわれています。
図表II-21 マラリア対策のための蚊帳供与実績(2007年11月現在)
● 結核
かつて結核は日本の感染症対策の中心であったことから、日本は、結核分野での研究・検査・治療技術の水準が高く、長年の蓄積をいかした開発途上国支援を行ってきました。現在の日本の取組としては、DOTS(注134)(直接服薬指導による短期化学療法)普及を中心として、結核分野の国際的な協調に基づき策定された「Global Plan to Stop TB 2006~2015」に沿った協力を目指し、抗結核薬や検査機材の供与をWHOの結核対象重点国(High Burden Countries)など結核被害の深刻な国に対して重点的に実施しています。また、アフガニスタン、パキスタン、ミャンマー、フィリピン、バングラデシュ、ザンビアなどに専門家を派遣し、現地の結核対策プログラムの運営体制の強化、検査能力向上のために研修・指導や指針作成支援などを実施しており、これらの取組を通じてDOTSの拡大・普及に貢献しています。
内戦終結後、世界で最も結核患者の割合が高くなったカンボジアにおいては、無償資金協力による結核センター改修、抗結核薬の供与、技術協力による人材育成を通じたDOTS管理能力の強化のみならず、地域社会において治療が受けられるようにするためにコミュニティDOTSといった対策支援等を一体的に協力してきており、プロジェクト開始前と比較して年間に2万人程度の結核患者をより多く治療できるようになりました。
日本の協力はその他の国においても着実に成果を上げています。世界の80%の結核が集中している22の結核高負担国のうち中国、ベトナム、フィリピンの3か国が国際的な目標を達成していますが、これらは、日本がこれまで技術協力、無償資金協力などを一体的に組み合わせて協力してきた国々です。
最近では、継続的な投薬が完了しない等の理由により、より治療が困難な多剤耐性結核(MDR-TB(注135))や超多剤耐性結核(XDR-TB (注136))が、HIV/エイズ感染者の重複感染拡大と併せて新たな問題として浮上しています。
図表II-22 日本の結核分野に対する主な支援(1963年~2007年5月)
● ポリオ
西太平洋地域で2000年に世界保健機関(WHO(注137))によるポリオ根絶宣言が出され、2006年にはポリオ流行国とされる国は残り4か国(ナイジェリア、インド、アフガニスタン、パキスタン)にまで減少し、全世界のポリオ根絶に向けた取組は最終段階を迎えています。このような状況を受け、2007年2月、WHOは、2007年から2008年の当面2年間は、ポリオ流行4か国を中心に集中的支援を投入するという新戦略を発表しました。
日本は、WHOのポリオ撲滅戦略に従い、UNICEF等と協力しながらポリオ・ワクチン供与の支援を行っています。日本も、対象国を決めて集中的に支援をすることでポリオ撲滅を図るため、2007年は、上記4か国のうち、特に最も状況が深刻でアフリカで唯一の流行国であるナイジェリアへの支援を強化する方針です。
● 寄生虫症
日本は、寄生虫対策として、学校や地域社会を通じた予防、治療、啓発活動への支援、トイレ設置などの衛生対策支援を実施しています。また、タイ、ケニアおよびガーナに設立した国際寄生虫対策センターを拠点として人材育成等に取り組んでおり、合計220名以上に対して研修を行いました。
最近は、シャーガス病、ギニアウォーム症、フィラリア症、住血吸虫症等の「顧みられない感染症(Neglected Tropical Disease)」への対策の必要性について再び注目が集まっています。日本は、世界に先駆けて中米諸国でのシャーガス病対策に本格的に取り組み、媒介虫対策体制確立に向けた支援によって感染リスク減少の大きな成果を上げています。また、人体に寄生虫がとどまり、長期的に健康や社会生活に被害をもたらすフィラリア症についても、WHOとの協力の下、2010年をめどとした大洋州地域、2015年をめどとしたバングラデシュでのフィラリア症撲滅に取り組み、駆虫剤と啓発教材の供与および協力隊員による啓発予防活動により、大幅な新規患者数の減少や非流行状態の維持に成果を上げてきています。