保健医療・福祉分野の2006年度の実績は、無償資金協力約181億円(36か国)、技術協力では、4,841人の研修員受入、675人の専門家派遣、337人の協力隊員を派遣しました。
多くの開発途上国においては、先進国であれば日常的に受けることができる基礎的な保健医療サービスを依然として受けることができずに、多くの人が苦しんでいます。具体的には、予防接種や環境衛生などが整備されていないために、感染症や栄養障害、下痢症などの回避可能な原因によって、毎日3万人以上の子どもが命を落としています。また妊娠中および出産時に、助産師などの専門技能者の立ち会いがなかったり緊急産科医療にかかれないために、毎年50万人以上の女性が命を落としています(注70)。ミレニアム開発目標(MDGs)では、保健医療分野の目標として、乳幼児死亡率の削減、妊産婦の健康の改善、感染症などのまん延防止の3つが掲げられています。
2005年6月、日本は、「保健関連MDGsに関するアジア太平洋ハイレベル・フォーラム」を開催し、この会議の場で、2005年度から2009年度までの5年間で50億ドルをめどとする支援を行う「『保健と開発』に関するイニシアティブ(HDI)(注71)」を発表しました。このイニシアティブに基づき、日本は、感染症対策、母子保健対策、保健医療システムの整備のほか、分野横断的支援、例えば、ジェンダー平等のための支援、教育、水と衛生、病院施設等のインフラ整備などへの取組によって、保健医療の基盤強化などに資する包括的支援を行っています。また、2006年には、外務省、関係省庁、JICA、JBIC等から構成される保健医療分野タスクフォースを立ち上げました。二国間および国際機関を通じた支援を、より一貫性、整合性を持って効果的に遂行することを目的としています。これまでに、鳥・新型インフルエンザへの対策や、アフリカにおける保健・医療の在り方などについて、情報交換、議論を行ってきています。特にポリオ対策に関しては、当面、ナイジェリアなどポリオ撲滅を達成していない4か国を中心とした支援を強化するとの方針を策定し、UNICEF (注72)を通じたポリオ・ワクチン支援を実施中です。
● 保健医療体制の基盤整備に関する支援
開発途上国に対する国際社会の支援は、HIV/エイズ、結核、マラリアなどの直接的な疾病に関する対策に焦点が当てられてきましたが、日本は、同時に保健医療の基盤強化を行うことが、膨大な保健分野の課題へ取り組むために重要だと考えています。日本は、より多くの人々へ平等に基礎的な保健医療サービスを提供し、人々が自らの健康を守り、改善していくための能力強化と環境づくりを進めることを目的とし、開発途上国の実情に即した保健医療制度の構築、地域保健医療の強化、予防活動の強化、保健医療に携わる人材の育成、保健医療インフラの整備などを支援しています。
アフリカの一部の国では、地方分権化と直接財政支援による地方自主財源の増加に伴い、地方の保健行政官の管理能力強化が急務の課題となっています。タンザニアでは、モロゴロ州をモデル地区に選定し、州・県の保健行政官に対して、情報管理などの技術支援、地域の実情に即したデータを活用しながらの地域保健計画の策定・実践・評価に関するシステム構築を行いました(注73)。これは、地方保健行政システムの模範として、タンザニア政府から高い評価を受けています。
● 母子保健に関する支援
母子保健を取り巻く問題は、医療サービス、医療制度、公衆衛生から、母親となる女性を取り巻く社会環境まで多岐にわたっています。開発途上国、特に後発開発途上国(LDC (注74))においては、妊産婦の健康の改善、乳幼児の死亡・疾病の低減、性感染症・HIV/エイズへの対策が急務となっています。
妊産婦の健康の改善については、助産師・看護師など母子保健サービスに従事する人材の育成、緊急産科の体制整備、緊急産科施設への物理的・社会的アクセスの確保(道路の整備や、女性が適切な産科診療を受けることのできる社会環境の構築など)に対する支援を実施しているほか、望まない妊娠の低減のために、家族計画の教育・情報提供、避妊法・避妊具(薬)の普及、思春期人口への教育の推進などへの支援にも取り組んでいます。例えば2006年度には、カンボジア・コンポンチャム県において「地域における母子保健サービス向上プロジェクト」を開始し、地域レベルでの保健医療従事者の育成や伝統的産婆との協働体制の構築、地域住民の啓もう活動などを通じた妊娠・出産にかかわる健康管理の向上に取り組んでいます。
乳幼児の死亡・疾病の低減については、乳幼児の死亡原因となりうるポリオ、はしか、破傷風などの疾病に対する予防接種や、蚊帳の配布等のマラリア対策を支援しています。また、小児下痢症に対し経口補液の普及を図った基礎医療サービス支援も実施しています。
→ マラリア対策のための蚊帳の配布についてはI部のこちら、II部のこちらも参照してください
海を渡った日本の母子手帳
日本の経験をいかした母子健康手帳の普及はインドネシアの乳幼児死亡率の改善をもたらしました。さらにパレスチナ(注75)でも母子保健サービスの改善や母子保健の啓発とともに、アラビア語初の母子手帳の作成、普及を支援し、パレスチナ全域の母子保健の向上を目指しています。また、モロッコ(注76)では「女性健康手帳」の開発を支援し、女性の健康管理の手段として全国に普及しています。母子健康手帳や女性健康手帳は適切なサービスを受けるために必要な情報を本人と医療従事者に提供し、女性自身の健康管理への参画を促し、途上国の母子保健を向上させることに役立っています。
 |
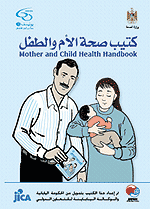 |
HIV/エイズの母子感染対策
HIV/エイズの母子感染対策としては、予防の側面と治療の側面から取り組まなければなりません。保健サービスや情報へのアクセスを考慮し、例えば妊娠・出産にかかわる健康管理のため、性感染症対策や自発的な検査とカウンセリング(VCT (注77))活動を行うなどして、多方面からの配慮と包括的なアプローチで支援を行っています。
日本は、2005年度にマダガスカルで実施した「マジュンガ州母子保健施設整備計画」などのように、母子保健医療の改善および母子保健従事医療者の技術向上・育成を目的とした二国間協力に取り組んでいます。
● 米国・NGO等との連携
日本は、保健分野の援助に関して様々な援助関係機関との連携を進めており、米国国際開発庁(USAID (注78))との間では、2002年以降、「保健分野における日米パートナーシップ」に基づき効率的・効果的な援助実施のために連携を行っています。具体的な内容は、JICAとUSAIDの人事交流や、合同でのプロジェクト形成調査や評価の実施などです。実際のプロジェクト実施における連携としては、2005年から行われているセネガルでの「エイズ・性感染症対策、家族計画」支援において、JICAの技術協力プロジェクトとUSAIDに加え、国連人口基金(UNFPA (注79))、国際NGOとの連携を通じて、青年カウンセリングセンターの設置、啓発活動を全国で展開しました。さらに、JICA、USAID、UNFPAの三者で避妊具の供与を行っており、2007年まで支援を行う予定です。このほかにも、ザンビア、タンザニアでエイズ、性感染症対策支援、ナイジェリアでマラリア対策支援、カンボジアでエイズ・結核対策支援を行うなど、日米の連携は広がっています。
また、地球規模の保健、感染症、人口に関する、外務省とNGOとの懇談会を1994年から行っており、現在までに76回開催(注80)しています。家族計画国際協力財団(JOICFP (注81))が事務局となり、これらの分野におけるプロジェクトの形成調査団へのNGOの参加や、プロジェクトの実施、評価をNGOと共同で行うなど、積極的に連携を行っています。
このほか、2002年に設立された世界エイズ・結核・マラリア対策基金(GFATM (注82)、以下、世界基金)は、政府間協力を超えて広範な官民パートナーシップを実現しており、日本は、世界基金の設立当初から重要な役割を果たしています。
第5回ASEAN・日本社会保障ハイレベル会合
2007年8月末、東南アジア諸国連合(ASEAN)事務局および世界保健機関(WHO)の協力を得て、ASEAN10か国から社会福祉および保健医療政策を担当するハイレベルの行政官を招へいし(次官級1名を含む計41名が参加)、第5回ASEAN・日本社会保障ハイレベル会合を開催しました。会合では、「社会福祉・保健医療サービスの連携と人材育成・地域開発」のテーマの下、地域における高齢者の福祉および保健サービスの提供、福祉と保健の連携、人材育成、地域開発に焦点を当てて、各国の状況、対応策、モデル事例といった情報・経験が共有され、今後のASEAN諸国の取組に向けて建設的な提言が行われました。