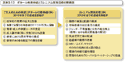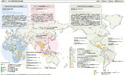開発途上国の貧困削減のためには、持続的成長に向けた経済的な取組に加え、教育や保健などの基礎社会サービスを受けられないことや、性別による社会的格差(ジェンダー格差)、意思決定過程への参加機会がないことに対する社会的、政治的な取組を行っていく必要があります。世界共通の開発目標であるミレニアム開発目標(MDGs)でも、初等教育の普及、保健の改善やジェンダー平等の推進等が8つの目標の中に掲げられ、国際社会は2015年までの達成を目指して努力しています。以下では、日本の社会開発への支援について説明します。
2006年度の教育分野の実績は、無償資金協力が約109億円(15か国)、円借款が約279億円(2か国)、技術協力では、1,871人の研修員受入、535人の専門家派遣、320人の協力隊員を派遣しました。
教育は、それぞれの国の経済社会開発において重要な役割を果たすとともに、人間一人ひとりが自らの才能と能力を伸ばし、尊厳を持って生活することを可能にします。
しかし、世界には、様々な理由から、今なお学校に通うことのできない子どもたちが7,700万人以上もおり、そのうち女子が約6割を占めています。また、最低限の識字能力を持たない成人も7億8,000万人に上り、その3分の2が女性です(注56)。
このような状況の改善に向け、国際社会は、1990年から、すべての人に基礎的な教育の機会を提供する「万人のための教育(注57)」の実現に取り組んでいます。2000年には「万人のための教育ダカール行動枠組」によって具体的な目標が設定され、MDGsにも2015年までの初等教育の完全普及の達成等、ダカール行動枠組の内容が盛り込まれました。
図表II-13 ダカール教育枠組とミレニアム開発目標の関係図
日本は、従来「国づくり」と「人づくり」を重視し、開発途上国における基礎教育、高等教育および職業訓練の拡充に向けた支援に加え、日本の高等教育機関への留学生受入などを通じた幅広い分野における人材育成支援に取り組んでいます。
日本は2002年に「成長のための基礎教育イニシアティブ(BEGIN (注58))」を発表し、開発途上国の「万人のための教育」の達成に向けた努力を支援しています。BEGINでは、学校建設等のハード面の支援と教員養成等のソフト面の支援を組み合わせ、教育の機会の確保、質の向上、そしてマネジメントの改善の3点を重点項目として取組を積極的に支援しています。
また、国際的な教育目標である「2015年までの初等教育の完全普及」等を目指す国際的な支援枠組みとして、2002年に世界銀行の主導で発足した、ファスト・トラック・イニシアティブ(FTI (注59))は、FTIの承認を受けた国を含む多くの開発途上国に対して二国間援助や国際機関を通じた支援を実施しています。これに加え、2007年、日本はFTIの関連基金に対して約2億7,840万円の新規拠出を行うことを表明しました。また、2008年にはFTI運営委員会の共同議長国にG8代表として就任し、FTIの議論に深く関与することとなります。2007年6月のG8ハイリゲンダム・サミットにおいても、FTIへの協力が合意されています。
さらに日本は、技術教育や高等教育を通じて、その国の経済を支える人材育成、社会基盤の底上げに資する支援を行っています。具体的には、現地の雇用状況に合った技術教育の実施や産業界と効果的に連携を進め、また女性の自立を助けるための小規模融資と組み合わせた職業訓練の支援も行っています。高等教育分野でも、その量・質の拡充とともに、近年では国境を越えた高等教育機関のネットワーク化を推進しています。
日本は、2002年8月の持続可能な開発に関する世界首脳会議において、「国連持続可能な開発教育(ESD (注60))の10年」を提唱しました。同年12月の国連総会でこの提案が採択されました。これを受けて、国連教育科学文化機関(UNESCO (注61))がESD主導機関となり「ESD」の10年を国際的に推進するための「国際実施計画」を策定・採択しました。日本はUNESCOおよび加盟国への取組強化を働きかけており、2005年から「ESD信託基金」をUNESCOに拠出しているほか、2007年の第34回UNESCO総会では、「ESDの10年」の更なる推進のための決議を提案し、採択されるなど、関連事業を積極的に支援しています。
理数科教育は、開発途上国が科学技術の進歩や経済・社会の発展を実現するために不可欠です。また、人間の探究心や論理的思考、創意工夫・発明の力をかん養し、創造的で豊かな人間性を育む役割も担っています。日本は、明治以降の教育の近代化とともに、科学技術振興に向けて理数科教育を拡充して、今日の経済発展を支える人材を育成しました。こうした経験に基づき、日本は開発途上国の理数科・理工系教育の質の改善に積極的に取り組んでいます。また日本による理数科・理工系教育支援は、アフリカにおける初等中等理数科教育強化計画および域内連携ネットワーク(SMASSE-WECSA (注62))、中南米における算数大好きプロジェクト(注63)など、各地域で広域協力へと発展しています。
ネパールでは、基礎教育分野の援助に関して、1990年代から、援助協調やネパール政府のプログラムに基づいた取組を進めてきました。現在は、「万人のための教育」に関する2004年から2009年の取組に対して、各援助国・機関が協調して援助を行っています。具体的には、世界銀行、ノルウェー、英国、フィンランド、デンマークが財政支援を行い、日本、ユネスコ、国連児童基金(UNICEF (注64))が財政支援以外の援助を行う形で、援助協調を進めています。日本の支援としては、無償資金協力を通じた小学校の建設や、NGOと連携した地域社会への啓もう普及活動などがあります。特に、小学校の建設に関しては、建設に必要な資材を日本が提供する一方で、資材の運搬や配布、建設の監督を日本からの支援を得ながらネパール国が実施し、建設作業は住民の参加を得て実施するという、効率性と自主性に優れた実施方法を確立しました。この結果、2005年までに8,024教室を建設し(注65)、ネパールおよび他の援助国・機関からも高く評価されています。
紛争終結後の国づくりにおいて、教育は復興の基盤となるばかりでなく、相互理解を促進し平和の礎ともなるものです。また、個人の能力開発を行うことにより、個人が外部の脅威から自らを守る力をつけるという、人間の安全保障を推進する観点からも重要です。例えばアフガニスタンでは、識字教育や除隊兵士の社会復帰のための技能訓練などを支援しています。また、スーダン、エリトリア、ルワンダなどの紛争終結国においても、基礎的な職業訓練などを通じて貧困層の人々の生計向上を支援しています。
アフガニスタン 「識字教育支援」
アフガニスタンでは、内戦やタリバン支配の結果、国の教育システムが破壊され、多くの国民が教育を受ける機会を逸しました。その結果、成人識字率は男性30%、女性5%にとどまり、非識字人口は700万人に上ると推定されています。これら教育の機会を得ることができなかった人々が、自らの課題解決能力を高め、生活を向上させ、開発に参加し、今後の同国の平和の定着、民主的な国家の建設、経済的・社会的発展を図る上で、識字教育の推進は重要かつ緊急な課題となっています。
日本は、2002年1月のアフガニスタン復興支援国際会議を踏まえ、同年9月から、ユネスコに設置した人的資源開発信託基金を通じて、識字教育とノン・フォーマル教育(注66)の推進を目的とする「ランド・アフガン・プロジェクト(LAND AFGHAN)」を支援しました。LAND AFGHANで開発した識字教育カリキュラムが、国家カリキュラムとして採用されたのを受け、ダリ語とパシュトゥ語の識字入門書を作成しました。これらの成果について、アトマル教育相は、「アフガニスタンの教育発展の礎となるもの」と称賛しています。また日本は、2006年3月から、JICAを通じて、アフガニスタンが識字教育を推進するにあたって中核となる教育省識字局のデータ管理、教本・教具等の在庫管理システムの改善、研修の実施と、識字教室の展開に向けてニーズ調査、詳細計画の策定、NGO委託による事業実施等を支援(注67)しています。
 |
(写真提供:JICA)
開発途上国の持続的発展に貢献するため、日本は文部科学省を中心に「国際協力イニシアティブ」を推進しています。具体的には、大学等の知見をいかした国際協力活動を促進することを目的に、(1)日本の教育研究関係者が有する知見をもとに教材やガイドライン等を作成し、それらを活用できるように公開すること、(2)日本の大学が提供できるもの(人材、教育研究機能等)と途上国の大学が必要としているものに関する情報を収集し、マッチング状況を分析すること、(3)専門家で構成する分野別の委員会を核とする人的なネットワークを整備し、分野別の動向分析、助言を行うこと-等に取り組んでいます。
また、日本の教育経験をいかした国際協力を進める上で、現職の教員が途上国において協力活動に従事することは非常に有益です。また、現職教員が開発途上国において、様々な障壁を克服し協力活動に従事することは、問題への対処能力や指導力の向上、視野の拡大など教員の資質能力の向上が期待されるほか、さらに帰国後は自身の貴重な体験を教育現場に還元でき、ひいては日本の教育の質を高めることにもつながります。こうした観点から、現職教員の青年海外協力隊(JOCV (注68))への参加を促進するために、2001年度に「青年海外協力隊現職教員特別参加制度」(注69)を創設しました。2002年度から2007年度派遣分の6年間で累計437名の現職教員が派遣され、多くの国で教育協力活動に携わり、活躍しています。