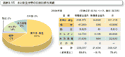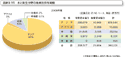2006年度は、水と衛生分野で、無償資金協力約216億円(30か国)、円借款約3,385億円(13か国)を合わせた約3,601億円の協力を行いました。
技術協力については、2006年度は633人の研修員受入、64人の専門家を派遣しました。この結果、日本水協力イニシアティブで発表した目標(2003年度から5年間で約1,000人)に関し、累計で派遣した専門家は541人、受け入れた研修生は4,001人となりました。
世界保健機関(WHO)と国連児童基金(UNICEF (注83))が作成した「水と衛生に関するMDG達成に向けて-都市部・村落部での挑戦の10年-」(2006年)によると、上水道や井戸などの安全な水を利用できない人口は2004年に世界で約11億人おり、そのうち、アジアが約6億人、アフリカが約3億人となっています(注84)。また、世界で約26億人が下水道などの基本的な衛生施設を利用できない状況にあり、うちアジアが約19億人、アフリカが約5億人となっています。
水と衛生の問題は人の生命にかかわる重要な問題であり、同報告書によると年間約160万人の幼い子どもの命が奪われているのが現状です。このような状況を反映し、国連はミレニアム開発目標(MDGs)の中で「安全な飲料水および基本的な衛生施設を継続的に利用できない人の割合を2015年までに半減する」という目標を掲げるとともに、2005~2015年を「『命のための水』国際の10年」として様々な取組を進めています。例えば、国連持続可能な開発委員会(CSD (注85))は、2004~2005年に水、衛生施設および人間居住を特定テーマとしてとりあげ集中的に討議し、2005年4月に政策決定文書を発表しました。また、国連「水と衛生に関する諮問委員会」は、2004年7月の設立以降、2007年6月までに8回開催され、第4回世界水フォーラム(2006年3月)の機会に「橋本行動計画(Hashimoto Action Plan)」(注86)を発表しました。
日本は、水と衛生の分野では従来大きな貢献をしています。1990年代から継続的にDAC諸国の中で最大の支援を政府開発援助を通じて行っています。2001年から2005年までの5年間で二国間援助国の37%に当たる48.8億ドルの政府開発援助を実施しました(注87)。
2003年3月に京都で開催された第3回世界水フォーラムでは「日本水協力イニシアティブ」を発表し、日本の水分野の援助における包括的な取組を表明しました。また、2006年3月にメキシコ・シティで開催された第4回世界水フォーラムでは、水と衛生分野で国際機関、他の援助国、内外のNGO等との連携を強化し、一層質の高い援助を追求するため、「水と衛生に関する拡大パートナーシップ・イニシアティブ(WASABI (注88))」を発表しました。
また、国際的なパートナーシップの強化のため、日本は、日米水協力「きれいな水を人々へ」イニシアティブに基づき米国との連携を進めています。第4回世界水フォーラムの機会には、日米両国がセッションおよび共同会見を共催し、同パートナーシップの進展と成果を発表しました。現在、インドネシア、インド、フィリピン、ジャマイカの4か国において、国際協力銀行(JBIC (注89))、国際協力機構(JICA)を通じ、米国国際開発庁(USAID (注90))との間で試験的な協力が行われています。フィリピンでは、USAIDとの間で、JICAを通じ協調して技術協力を行っており、また、JBICを通じ、円借款により支援を受けたフィリピン開発銀行向けの融資とUSAIDの保証制度を組み合わせた事業を実施し、水・衛生事業への民間投資の促進を図っています。
日本は、WASABIにおいても、水利用の持続可能性の追求のため、治水・利水をはじめ統合的に水を管理していくことを重視しており、このような総合的な取組を推進していきます。具体的な案件例として、インドの「オリッサ州総合衛生改善計画」への円借款の供与を決定しました。これは、オリッサ州のブバネシュワール市およびカタック市において、下水道施設、雨水排水施設の整備等を行い、貧困層を含む住民の衛生・生活環境の改善を図るものです。また、オリッサ州では、上下水道事業の運営・維持管理業務を州政府から地方自治体に移管(権限委譲)する等のセクター改革が進められており、このための行動計画がUSAIDの支援によって策定されているところです。本事業においても、USAIDと連携しつつ、権限委譲の取組等を支援していく予定です。
中国での水利人材養成
洪水、土砂災害や水資源不足、水土流出、水質・生態環境の悪化、老朽化した危険ダムの補修・管理強化等、水に関する様々な問題を抱えている中国において、これらの課題に的確に対処する水利人材の育成は急務です。
日本は、1993年から専門家を派遣し、2000年からはJICAの技術協力プロジェクトに拡大しました。このプロジェクトでは、研修管理、水資源管理、建設管理、砂防の4分野において水利人材の研修を行い、これを通じて全国の初級・中級技術者の能力向上を図り、洪水や、土砂災害や水不足等の問題に対応することを目的としています。2006年度末までに育成された指導者は3,000人を超え、また研修を受けた指導者からさらに2万人近い水利分野の人材に研修が実施されました。