地球温暖化をはじめとする環境問題、感染症、人口、食料、エネルギー、災害、テロ、海賊、麻薬、国際組織犯罪といった問題は、一国だけの問題ではなく、国境を越えた地球的規模の問題であり、人間の生存にかかわる脅威となっています。国際社会の安全と繁栄の確保に資するため、日本は国際協力を通じてこの問題に取り組み、同時に国際的な規範づくりに積極的な役割を果たしていく方針です。
2006年度の日本の環境分野における援助実績は、無償資金協力、円借款、技術協力および国際機関に対する拠出金等の合計で約4,135億円であり、政府開発援助全体に占める割合は約35.4%となっています。内訳としては、無償資金協力が約200億円(31か国)、円借款が3,649億円(12か国)、技術協力では、3,786人の研修員受入、161人の専門家派遣、470人のボランティアを派遣しました。
地球温暖化をはじめとする環境問題については、1970年代から国際的に議論されるようになり、1992年の国連環境開発会議「地球サミット(UNCED (注109))」、2002年の「持続可能な開発に関する世界首脳会議(WSSD (注110))」での議論を経て、その一層の重要性が確認されました。
日本は環境問題を全人類的課題と位置付け、重点的に取り組んできました。日本は、2002年の世界首脳会議にあわせ「持続可能な開発のための環境保全イニシアティブ(EcoISD (注111))」を策定し、環境問題への対応のための支援を行っています。また、2005年2月に策定された政府開発援助に関する中期政策においても、「地球的規模の問題への取組」の中で環境問題への取組をとりあげています。
国際社会でも、気候変動対策は大きな関心事項となっており、2007年6月に行われたG8ハイリゲンダム・サミットでは中心的な議題となりました。2008年に日本で開催されるG8北海道洞爺湖サミットでも、引き続き議論される予定です。
● 地球温暖化対策
日本は1997年に発表した「京都イニシアティブ(注112)」の下で、開発途上国に対して温暖化対策に係る技術の移転・普及を図るとともに、科学的、社会的、制度的側面を含めた温暖化問題への対処能力の向上を進めています。また、2007年5月に安倍晋三総理大臣(当時)が行った提案「美しい星50」において、2013年以降の新しい枠組みについての原則を発表しました。この提案では、日本が深刻な公害や石油危機を乗り越え、国内総生産(GDP)を2倍とする中で石油消費を8%減少させてきた過去30年を振り返り、2050年の「美しい星」の実現を目指した提案をしています。
気候変動枠組条約京都議定書に定められたクリーン開発メカニズム(CDM (注113))は、温室効果ガスを削減して開発途上国の持続可能な開発の推進に寄与するとともに、日本の排出削減目標を達成する上でも重要なメカニズムです。日本は、2005年4月に策定した「京都議定書目標達成計画」において、国際的なルールに従いつつ、被援助国の同意を前提として、政府開発援助を用いたCDM事業の推進・活用に取り組むことを決定しました。2007年6月、日本として初めての政府開発援助を活用したCDMプロジェクトである、エジプトのザファラーナ風力発電計画がCDM事業として国連CDM理事会に登録されました。
● 環境汚染対策
日本は、国内の公害問題に取り組む過程で多くの経験と技術を蓄積しており、それらを活用して開発途上国の公害問題への対応に協力しています。特に、急速な経済成長を遂げつつあるアジア諸国を中心に、都市部での公害対策および生活環境改善(大気汚染、水質汚濁、廃棄物処理等)への支援の重点化を進めています。
2006年度、日本はエジプトの大カイロ首都圏(注114)およびアレキサンドリア地域(注115)における環境汚染対策に対して円借款の供与を決定しました(注116)。この地域はエジプトの中でも人口・産業が集中した地域であり、大気汚染、水質汚染が広がっています。現地で対策はとられているものの、ノウハウに乏しく、資金的にも余裕がないことから、必ずしも汚染軽減につながっていないのが現状です。本事業は、世界銀行等との協調融資案件であり、現地の仲介金融機関を通じて(注117)、企業に対する環境改善設備導入のための資金を供与することによって、工場の汚染物質の排出削減を行います。また、JICA、地球環境ファシリティ(GEF (注118))、フィンランド政府等による技術支援と連携し、導入設備の運用、維持管理を行うための指導を行うことで、実施機関の能力強化を図っています。
政策対話を通じた環境保全
開発途上国において環境調和社会の形成および持続的成長を確保するため、アジア諸国との間でグリーン・エイド・プラン(GAP (注119))政策対話を実施し、環境配慮型の経済システム整備、日本の環境産業の国際展開支援に向けた協力を実施しています。これまでに実施したGAP政策対話の結果、環境管理の重要性は認識されつつあり、インドネシアやタイにおいては、本協力により日本の公害防止管理者制度類似の制度が構築されました。しかし、汚染物質の排出量の測定・分析・予測等の基礎的な事項が実施されておらず、管理者の技術も熟練したものではない状況です。これらの分野について、専門家派遣や、日本への受入研修等人材育成を主体とした環境管理の強化を実施しています。
● 「水」問題への取組
環境保全との関連では、日本は、都市部・農村部の特徴を踏まえた上下水道への支援と、水資源管理および水質保全のための支援を実施しています。
● 自然環境保全
日本は、住民の貧困削減を考慮しつつ開発途上国の自然保護区などの保全管理、持続可能な森林経営の推進、砂漠化対策および自然資源管理に対する支援を実施しています。また、2002年3月に地球環境保全に関する関係閣僚会議において決定された「新・生物多様性国家戦略」において、日本と世界、特にアジア地域は自然環境、社会経済両面から深い関係があることから、アジア地域などの生物多様性保全に積極的に貢献していく必要があることが述べられています。さらに、生物多様性条約の下では、2010年までに生物多様性の損失速度を顕著に減少させるという「2010年目標」が設定されており、この目標達成に向けて更なる努力が求められています。
マレーシアのボルネオ島は地球上で最も生物多様性の高い地域といわれていますが、サバ州は、森林伐採やプランテーション開発により森林が急速に減少したため、人々の生活に影響が出ているだけでなく、多くの生物種が絶滅の危機にひんしています。そのため日本は、2002年から2007年までの6年間、技術協力プロジェクトにより研究・教育、公園管理、野生動物生息地管理、環境啓発の各分野を支援し、包括的に自然環境保全を行っていくための体制や手法の確立を目的とした協力を行いました。この結果、新たな保護区設置の動き等人々の環境への意識の向上が見られ、2007年10月からはサバ州生物多様性センターへの支援を中心として第2期の協力を開始しています。
過放牧や森林破壊等による砂漠化は深刻な問題に発展しています。日本は2004年から西アフリカのブルキナファソにおいて、砂漠化対処のための伝統知識がいきている現地の在来技術や簡易技術(土壌保全技術、畜耕技術、生活改善技術等)の移転を支援しています。
世界的な取組として、国際的な資金メカニズムであるGEF、「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」に基づく多数国間基金(MLF (注120))などが設立・運営されています。日本は、これら国際的な基金の活用や国際熱帯木材機関(ITTO (注121))等の国際機関を通じて積極的な取組を進めています。例えば、ITTOを通じて中南米や東南アジア、アフリカ等の熱帯林の持続可能な森林経営を促進するために、2006年度は27のプロジェクトおよび奨学金基金に対し、約654万ドルの支援を行いました。また、モントリオール議定書に基づく多数国間基金では、中国やインド、モンゴルなどに対して、オゾン層破壊物質の全廃に向けた政策立案支援、代替物質・代替技術への転換や技術者の訓練などを行うためのプロジェクトを承認し、地球規模の環境問題対策に取り組んでいます。また、2001年には東アジア酸性雨モニタリングネットワーク(EANET (注122))が本格稼動を開始し、この地域の酸性雨対策に向けた近隣諸国との協力を進めています。
地球地図(注123)プロジェクト
→ 2003年版ODA白書コラムIII-2も参照してください
日本は、1992年の国連環境開発会議(地球サミット)の「アジェンダ21」を受けて、地球環境の現状と変化を把握するために「地球地図プロジェクト」を提唱しました。1996年、日本を事務局として設立された地球地図国際運営委員会(ISCGM)は、2003年から2005年に行われた地球観測サミットの枠組みに国際機関として参加することが承認され、全球地球観測システム10年実施計画の参照文書にISCGMの取組が盛り込まれました。地球地図(注123)は、各国が公認データとして作成した地図を持ち寄り、一部については人工衛星のデータを活用して整備を進めています。地図の作成を担当するのは、各国の国家地図作成機関であり、日本では国土地理院がその役目を担っています。地球地図のデータはインターネットを通じて公開されており、ISCGMのホームページからダウンロードでき、非営利目的であれば、誰でも無料で利用できます。
2007年6月現在、地球地図は156か国・16地域(全陸域の95%)が参加する一大プロジェクトに発展し、35か国・2地域(全陸域の34%)のデータが公開されています。日本はプロジェクト提唱国として技術移転等の支援を行っており、2007年度中に全陸域の地球地図整備完了を目指しています。
一方、アフリカ地域各国の参加が遅れているため、2002年以降ナイロビ(ケニア)やダカール(セネガル)において地球地図セミナーの実施や、2005年の第12回ISCGM会合をカイロ(エジプト)で開催するなど、普及啓発に積極的に取り組んでいます。
全陸域の地球地図が整備されることにより、環境モニタリングや食糧対策、水資源、土地利用など各種将来予測のための地球地図の利用が本格化し、今後開発途上国を中心とする持続可能な開発の実現に役立つことが期待されます。
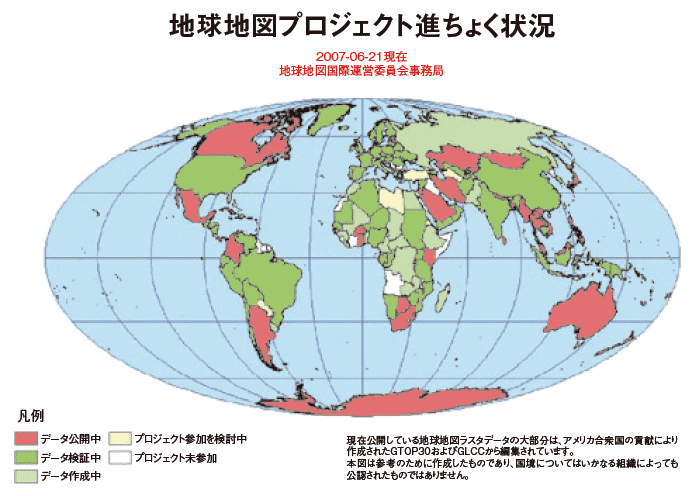 |
図表II-18 持続可能な開発のための環境保全イニシアティブ(EcoISD)の実施状況(事例)
