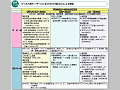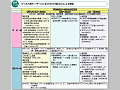本編 > 第I部 > 第2章 > 第3節 > (1)平和の定着と国づくりとは
第3節 平和の定着と国づくりへの協力
Point
1. 2002年5月、小泉総理は「紛争に苦しむ国々に対して平和の定着や国づくりのための協力を強化し、国際協力の柱とする」との決意を表明。
2. わが国は、東ティモールやアフガニスタン、スリランカ、インドネシアのアチェ、フィリピンのミンダナオなどにおいて、和平プロセスの促進、治安への支援、人道・復旧支援といった具体的な取組を実施。
冷戦終了後、宗教的、民族的要因などを主因として紛争が頻発しています。近年の武力紛争は、文民(非戦闘員)が犠牲者の8割にのぼることが大きな特徴です。このように武力紛争は、それ自体が人道危機を引き起こしますが、それのみに留まらず紛争により長年の開発の努力が瞬く間に失われ、膨大な経済的損失を生み出します。特に、近年、東ティモールやアフガニスタンのような騒乱や紛争によって国家の基本的な枠組みが破壊され、現地政府がないか、あるいは統治能力が極めて脆弱化した国や地域(いわゆる破綻国家注))への支援が国際社会の大きな課題となっています。
もとより、こうした状況に対しては第一に政治的・外交的な努力による紛争予防や紛争解決が求められるわけですが、開発援助の果たしうる役割にも大きいものがあります。わが国は、2000年に発表した「『紛争と開発』に関する日本からの行動-アクション・フロム・ジャパン」において、「紛争予防-緊急人道支援-復旧・復興支援-紛争再発防止と本格的な開発支援」という一連の紛争のサイクルのあらゆる段階で貧困対策や基礎生活分野(BHN)支援、基礎インフラの復旧などを通じて被害の緩和に貢献するためODAによる包括的な支援を行っていくことを表明しました。
さらに、2002年5月のシドニーにおける政策演説で小泉総理は、コソボ、東ティモール、アフガニスタンといった地域紛争の経験も踏まえ、わが国は、「紛争に苦しむ国々に対して平和の定着や国づくりのための協力を強化し、国際協力の柱とする」として、特に紛争後の平和構築分野でより積極的な取組を行っていく決意を示しました。
2002年5月の東ティモールの独立は、わが国をはじめとする国際社会の協力が効果的に発揮された一大成果と言えるでしょう(東ティモールへの支援については図表I-20、及び第II部第2章第1節(6)(イ)参照)。
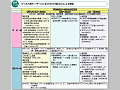
以下では、「平和の定着」と「国づくり」のための支援の具体的内容とわが国のこれまでの取組について解説した後、わが国が包括的な取組を行っているアフガニスタン支援について紹介し、さらに、スリランカ、インドネシアのアチェ、フィリピンのミンダナオなどで相次いで起こっている和平の動きに対し、わが国がODAを積極的に活用しようと努力している現状について説明します。
(1)平和の定着と国づくりとは
和平プロセスの促進
地域紛争の恒久的な解決のためには、紛争が完全に終結する前から支援を行い、平和の萌芽を定着させることが重要です。こうした取組として、和平復興会議の開催や和平プロセスの最終段階における正統政府の樹立に向けた選挙の実施などの「和平プロセス」を促進することが挙げられます。わが国は、96年にカンボジア復旧及び復興に関する閣僚会議や99年に第一回東ティモール支援国会合を主催したほか、2002年1月には東京でアフガニスタン復興支援国際会議を開催しました。
また、わが国は、紛争終結の兆しが見えた段階で、紛争が完全に終結すればODAが供与されるとの可能性を紛争当事者に示すことで、平和を積極的に招き入れ、定着させる努力も行っています。具体的な取組として、2002年12月には、インドネシアのアチェ和平促進のため東京で「アチェにおける和平・復興に関する準備会合」を開催し、また、スリランカについてもわが国は和平・復興プロセスの主導的役割を果たすため明石康元国連事務次長を日本政府代表に任命し、わが国で2003年6月に支援国会議を開催する用意がある旨表明しています。
紛争終結直後の脆弱な内政状況で極めて重要な役割を果たす選挙への支援についても、98年のカンボジア総選挙支援以来、コソボ、東ティモール、モザンビーク、フィジー、ソロモン等に選挙監視・管理要員派遣、選挙関連資金・機材の提供等を行っています。
安定と治安の確保
紛争終結後の多くの国では、国内の治安が極めて悪く、復興・開発への足かせになっているため、紛争当事者間の和平プロセスの進展と併せて速やかに「安定と治安」が確保される必要があります。具体的な措置として、国連平和維持活動(PKO)やいわゆる多国籍軍による国内の安定・治安の確保から、国内治安制度の構築(警察の創設)、対人地雷・不発弾処理、元戦闘員の武装解除、動員解除及び市民社会への復帰(いわゆるDDR)といった様々な活動が含まれます。同分野のODAとしては、地雷除去支援や地雷被害者への支援を行っているほか、国際機関を通じた支援として元戦闘員の武装解除、動員解除及び市民社会への復帰をコソボ、東ティモール、シエラレオネで、わが国が国連に設置した人間の安全保障基金などを通じて行っています。
人道・復旧支援
さらに、長年紛争に苦しんできた人々が実際に「平和の配当」を実感するためには「人道・復旧支援」を通じて人々の生活基盤を回復することが必要です。わが国は、近年、緊急人道支援分野への貢献を積極的に行っており、緊急人道支援に際する国連による人道支援の調整機関である国連人道問題調整事務所(OCHA)担当国連事務次長として大島賢三氏を派遣するなどの人的貢献を行っているほか、二国間や国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)や赤十字国際委員会(ICRC)などの国際機関を通じた緊急人道支援活動を重視し、種々の人道危機に際して人的、資金的貢献を積極的に行っています。また緊急人道支援の際に迅速かつきめ細かい支援が行えるNGOとの協力も重視しており、「NGO緊急活動支援無償」により、人道援助を実施しているわが国NGOへの迅速な資金の供与も行っています。また、初期復旧支援は通常より迅速にODAを実施する必要があるため、99年以来、ニーズ調査と短期的な復興計画の策定に加えて緊急性の高い施設の修復まで行う緊急支援調査団を各地に派遣しています。
なお、こうした人道・復旧支援を行う際には、人道支援から本格的な復興・開発支援へと支援が切れ目なくスムーズに移行していくことが重要です。しかしながら、多くの事態において、大規模な紛争や自然災害に際し、初動の緊急人道支援における国際社会の関心と支援に比して、一定期間を経た後の復興・開発援助への関心と支援が著しく低いのが現状です。また、近年の紛争、自然災害の頻発のため、緊急人道支援すらも活動に必要な資金が恒常的に不足している状況にあります。
これらが「平和の定着」に含まれる三つの要素であると言えるでしょう。しかし、東ティモールやアフガニスタンのように、騒乱や紛争の結果、経済基盤のみならず、政治・社会制度といった国の基本的枠組みそのものが破壊され、現地政府が存在しないか、あるいはその統治能力が極めて脆弱化している場合には、これら三つの要素に加えて、政治・経済、教育、メディア、人権・ジェンダーなど多岐にわたる分野で国の基本的枠組みの構築、すなわち「国づくり」に向けた支援が必要です。
図表I-19 平和の定着の概念図

図表I-20 コソボと東ティモールにおけるわが国ODAによる取組
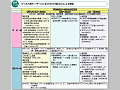
コラムI-8 地雷問題への取組

 次頁
次頁