|
| ||||||||||||||||
| トップページ > 外交政策 > 人権・人道 |
|
| ||||||||||||||||
| トップページ > 外交政策 > 人権・人道 |
第3条男女平等のための国内組織
- (a)「婦人問題企画推進本部」から「男女共同参画推進本部」への組織変更
我が国においては、第3回報告のとおり、女性に関する施策について総合的かつ効果的な対策を推進するため、国内本部機構として、1975年に内閣総理大臣を本部長に、各省庁の事務次官等を構成員とする「婦人問題企画推進本部」を設置し、女性の地位向上のための国内行動計画を策定する等の取組みを行ってきた。
その後、国内本部機構の強化についての国内外各方面の要請を受け、検討した結果、1994年7月12日、閣議決定により「婦人問題企画推進本部」に代え、本部長を内閣総理大臣に、副本部長を内閣官房長官に、本部員をこれまでの事務次官から全大臣とする「男女共同参画推進本部」を内閣に設置し、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の円滑かつ効果的な促進を図っていくことにし、1991年に策定した「西暦2000年に向けての新国内行動計画(第1次改定)」(内容については、前回報告参照)を継承、引き続き推進している。
また、上記検討結果を受けて、1994年6月24日、総理府に男女共同参画審議会が、総理府の大臣官房の中に、男女共同参画室が新規に設置された。同審議会は、同年8月22日、内閣総理大臣から「男女共同参画社会の形成に向けて、21世紀を展望した総合的ビジョン」について諮問を受け、国民各層からの意見・展望や第4回世界女性会議で採択された行動綱領等国際的な動向も踏まえつつ審議を進め、1996年7月30日、内閣総理大臣に「男女共同参画ビジョン」と題する答申を提出した。この答申では、概ね2010年までを念頭に、我が国の経済・社会の変化を踏まえ、男女共同参画社会の実現に向けて、目指すべき方向とそれにいたる道筋が提示されている。右答申に示されている主な取組は、以下のとおり。
- 性別による偏りのない社会システムの構築
- 職場・家庭・地域における男女共同参画の確立
- 政策・方針決定過程への男女共同参画の促進
- 性別にとらわれずに生きる権利を推進・擁護する取組の強化
- 地域社会の「平等・開発・平和」への貢献
- 取組体制の明確化と国内本部機構の組織・機能等の拡充強化
- 国、地方公共団体、NGO間の連携・協力の強化
- (b)女性問題担当大臣の設置
我が国では、1992年12月の宮澤内閣の改造に際し、内閣官房長官が「婦人問題担当」に任命され、次いで、1993年8月には「女性問題担当」に名称を変え、以後歴代内閣官房長官が任命されており、女性問題を総合的に推進するため行政各部の所管する事務の調整を任務とし、これまで様々な活動を行っている。
女性の政策・方針決定参画状況
我が国における国政の分野への女性の参画状況に関し、女性国会議員数については別表1、国会において女性が就いている役職は、別表2のとおり。
我が国では、女性の政策・方針決定への参画を促進するため、上記「西暦2000年に向けての新国内行動計画(第1次改定)」において、ナイロビ将来戦略勧告を踏まえ、国の審議会等における女性委員の割合の飛躍的上昇を目指すこととし、その具体的施策として、1996年3月までに、同割合を総体として15%とすることを目標としてきたが、1996年3月末現在15.5%となり、その目標を達成した(国の審議会等における女性委員の登用状況については、別表5及び6参照)。さらに、目標達成を踏まえ、1996年5月21日、「今後は、国際的な目標である30%をおよそ10年程度の間に達成するよう引き続き努力を傾注するものとし、当面、西暦2000年末までのできるだけ早い時期に20%を達成するよう鋭意努めるものとする」ことを男女共同参画推進本部において決定した。女性雇用対策
- (a)女性の雇用状況
男女雇用機会均等法の施行後10年を経過し、この間企業における雇用管理の改善が進み、法の趣旨は着実に浸透してきている。例えば、女性が配置される職務が増えるとともに、女性の配置の基本的な考え方として能力や適性に応じて男性と同様の職務に配置するという考え方の企業が5割近くとなっている。また、女性の管理職も増加しており、女性が係長相当職以上の管理職となっている企業の割合は約6割となっている(別表3参照)。女性の管理職が少ない企業が、その理由としてあげているのは、「必要な知識や経験、判断力等を有する女性がいない」というのが約5割で最も多い。また、男女別定年制及び結婚・妊娠・出産退職制については、制度上は解消している。
また、国家公務員の採用に係る男女平等の実現に関しては、人事院規則の改正により女子の国家公務員採用試験に係る受験資格制限を撤廃してきたところであり、現在、我が国の国家公務員採用試験(一般職)の受験、採用その他について、女子に対する制限、差別はない(国家公務員の管理職等における女性の割合については、別表4参照)。
- (b)男女雇用機会均等法の遵守措置
募集・採用、配置・昇進など女子の雇用管理の問題については、各都道府県の婦人少年室において、男女雇用機会均等法のより一層の遵守とその趣旨に沿った雇用管理の実現に向けて、啓発や相談、制度改善指導、個別紛争の解決のための援助業務を行っている。具体的には、婦人少年室には、女子労働者、事業主等から年間2万件にのぼる相談が寄せられており、男女雇用機会均等法上問題がある企業に対しては厳正な指導を行っている。また、一方では、定期的に企業の女子の雇用管理に関する事情聴取を行い、問題を把握した場合は厳しく是正を求めるなど積極的な指導にも努めている。さらに、男女雇用機会均等法の趣旨に沿った雇用管理の改善を促進するため、企業における自主的取組を促進している。
- (c)育児・介護
家族的責任を有する男女労働者にとって職業生活と家庭生活との両立が可能となるような支援策を推進することが必要であり、特に、我が国においては、少子・高齢化、核家族化が進む中で、育児と家族の介護の問題が、労働者が仕事を継続するための重要な課題となっている。このため、1991年に育児休業法が成立し、1歳未満の子を有する労働者に育児休業の権利が認められた。1993年に実施された調査(労働省「平成5年度女子雇用管理基本調査」:全国の8,000事業所対象)によると、育児休業制度が導入されている事業所において、1992年4月1日から1993年3月31日までの間に出産した女子労働者に占める育児休業取得者の割合は48.1%(配偶者が出産した男子労働者に占める育児休業取得者の割合は0.02%)である。1995年の育児休業法の改正により、介護休業制度が法制化されるとともに、育児や家族の介護を行う男女労働者のために国等の行う支援措置も盛り込まれた。我が国では、これら両休業制度の定着を図る他、育児休業・介護休業を取得しやすく、かつ職場復帰しやすい環境の整備、育児・介護を行う労働者が働きつづけやすい環境の整備等、労働者の職業生活と家庭生活との両立を支援するための施策を総合的、体系的に推進しているところである。また、1995年6月9日には、「家族的責任を有する男女労働者の機会及び待遇の均等に関する条約(ILO第156号条約)」を批准したところである。
国際協力
- (a)WIDイニシアティブ
1995年の第4回世界女性会議において、我が国は、女性のエンパワーメント、女性の人権の尊重、男女間、政府とNGO、及び国境を越えたパートーナーシップの促進の3点を強調する演説を行い、同時に、女性のエンパワーメントのための我が国の国際貢献として「途上国の女性支援(WID)イニシアティブ」を発表し、特に、女性の「教育」、「健康」、「経済・社会活動への参加」の3つの分野を中心に、今後とも開発援助の拡充に努力していくことを表明した。
このイニシアティブは、我が国が開発援助の実施にあたり、就学、就業、出産、経済・社会活動といった女性の一生のすべての段階を通じて、女性のエンパワーメントなどに配慮するものである。
- (b)女性に対する暴力撤廃におけるUNIFEMへの貢献
女性に対する暴力の問題は、第4回世界女性会議においても、現代社会における深刻な問題として取り上げられたように、現代社会における深刻な問題とされている。我が国は、国際社会が一致協力して取り組むべきこの問題に積極的に貢献していきたいとの考えの下、また、第4回世界女性会議で採択された行動綱領のフォローアップの一環として、女性に対する暴力に関する基金をUNIFEM内に設置するための決議を1995年の第50回総会に提出した。この決議は、コンセンサスにて採択されたところ、我が国は、この基金に応分の資金拠出を行う考えである。
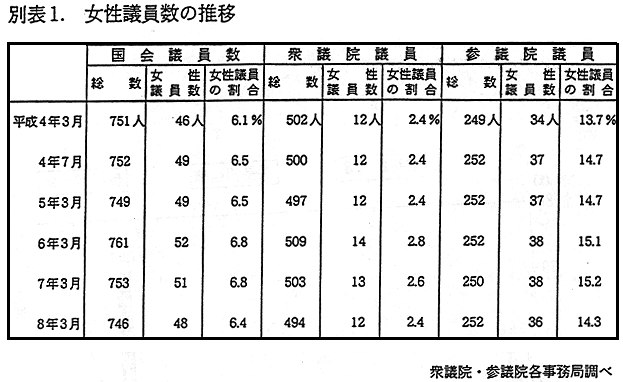
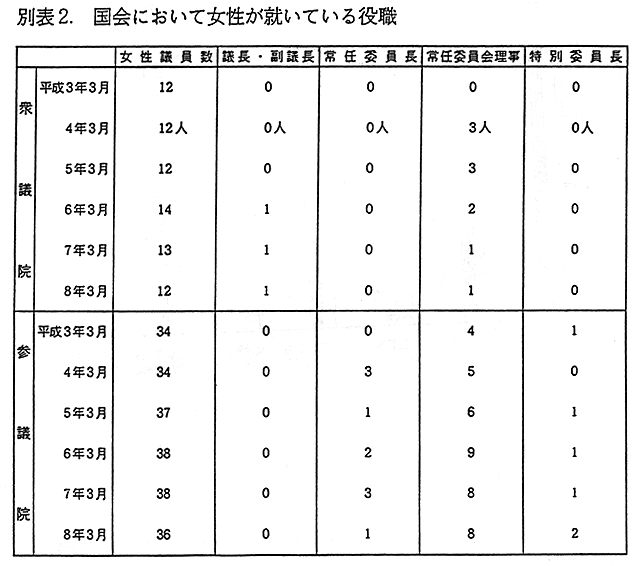
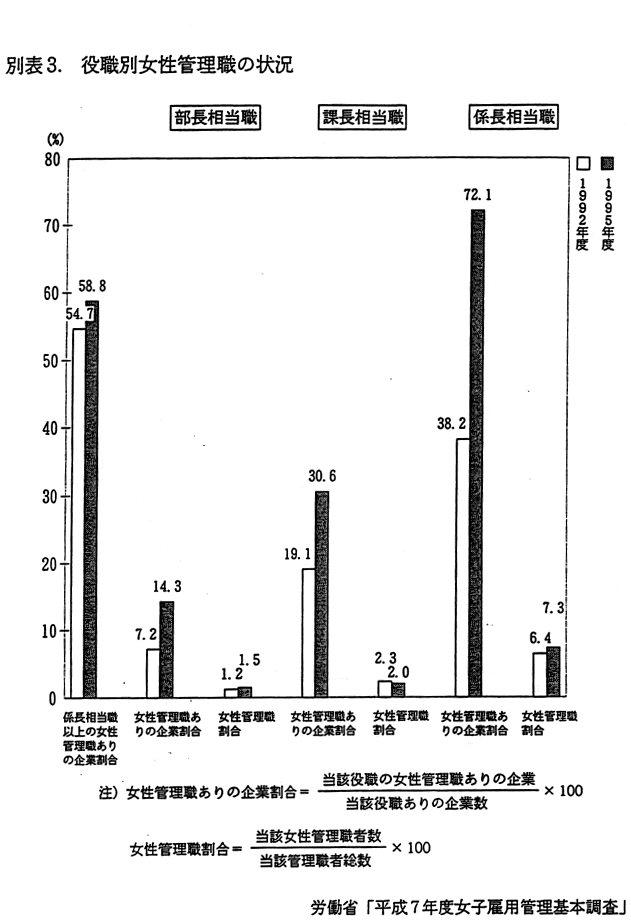
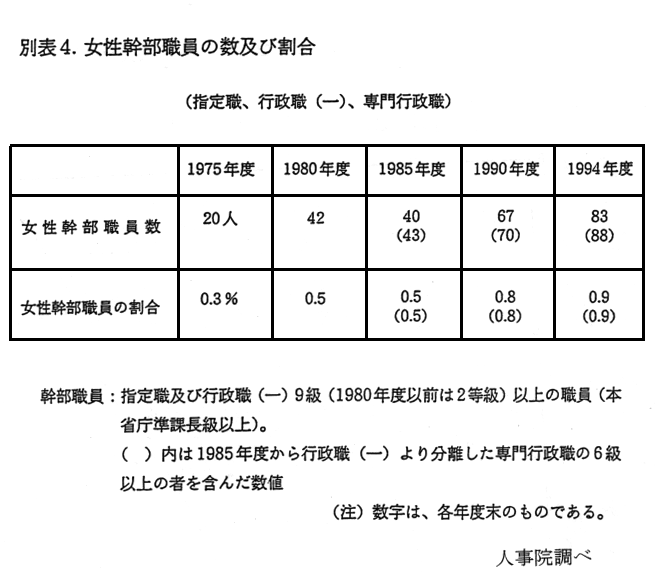
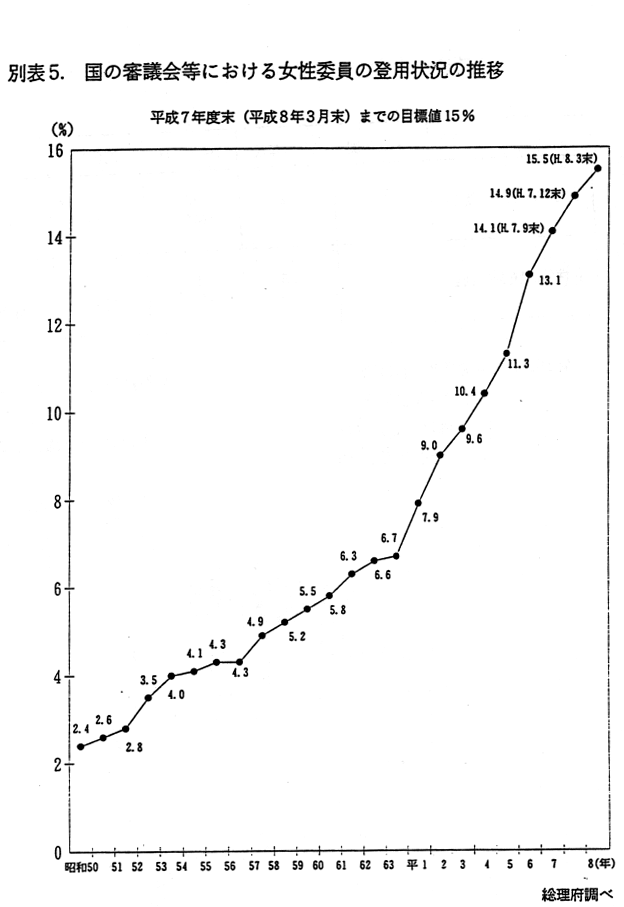
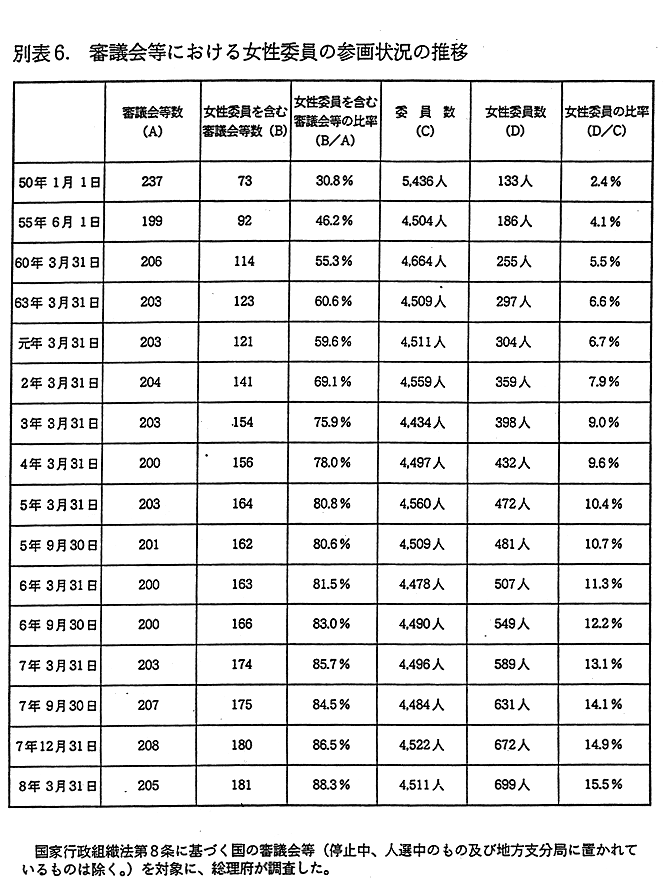
| BACK / FORWARD / 目次 |
![]()
|
| ||||||||||