|
| ||||||||||||||||
| トップページ > 外交政策 > 人権・人道 |
|
| ||||||||||||||||
| トップページ > 外交政策 > 人権・人道 |
- 6 民間女性団体(NGO)等の活動
(1)国際婦人年日本大会の決議を実現するための連絡会- 1975年の国際婦人年以降、女性の団体の活動は多様な分野にわたって活発に行われており、さらに、1995年の第4回世界女性会議を契機に全国各地に数多く誕生した女性の様々な団体、グループが草の根的な活動を展開している。
全国的な規模を持つ女性の団体としては、国際婦人年を契機に41団体が初めて連絡協議会組織を結成し、1975年11月、「国際婦人年日本大会」を開催して、我が国における行動計画の策定などに関する決議を行った。その後、これらの団体は「国際婦人年日本大会の決議を実現するための連絡会」(以下、「国際婦人年連絡会」という。)を組織し、女性の地位向上を目指して積極的な活動を展開している。国際婦人年連絡会は、1998年4月現在、51団体により構成されている。
国際婦人年連絡会は、北京会議の後、1995年11月に、「21世紀に向けて-NGO日本女性大会」を開催し、6分野から成る民間行動目標を採択した。1996年4月 には、「七婦人団体議会活動連絡委員会」との共催により、女性参政権行使50周年記念集会を開催し、一層の女性の政治参画の促進を訴えた。
また、1997年10月には連絡会代表から、内閣官房長官(男女共同参画担当大 臣)に対し、あらゆる分野への女性の参画の確保、総合的な女性施策を推進するための内閣総理大臣直属の組織と機能強化及び男女共同参画推進の実現を促進するための基本的な法律の制度についての要望を提出した。
- (2) その他のNGOの動き
- 上述のNGOのほか、女子差別撤廃条約の研究・普及活動を行っている国際婦人の地位協会など、各地で活動を展開している多数の女性団体やグループが存在している。また、北京会議参加を機に新たな団体、北京JACが結成されるなど、日本のNGOをはじめグラスルーツの人々の間には、女性の地位の向上について更に一層の関心が深まっており、近年では都道府県・市町村のレベルにおいて、女性問題に携わる官民の連絡会議形式の組織が作られるなどの動きも出てきているほか、女性問題に関するネットワーク型組織が新たな活動形態として誕生しつつある。また、北京宣言及び行動綱領に基づく政府や地方公共団体の男女共同参画社会づくりのための諸施策や活動に対し様々な意見・要望も出されている。
- 7 男女共同参画推進本部機構
- 男女共同参画社会の実現に向けて、広範多岐にわたる関連施策の総合的な推進に当たる男女共同参画推進本部、内閣総理大臣及び関係各大臣の諮問機関である男女共同参画審議会を中心に国の取組が進められており、これらの組織に加えて、国民各界各層との連携を図る男女共同参画推進連携会議が男女共同参画社会づくりを全国民的な運動として展開している。本部、審議会及び連携会議の活動が有機的に行われるよう、内閣官房、総理府(男女共同参画室)その他の関係行政機関が相互に緊密な連携を保ちつつ、事務的なサポートを行っている。(男女共同参画推進本部機構図は次の通りである。)
第3回報告審議以後の機構の変遷等については、第2部各論の 2 第3条参照。
男女共同参画社会形成の促進に関する推進体制図 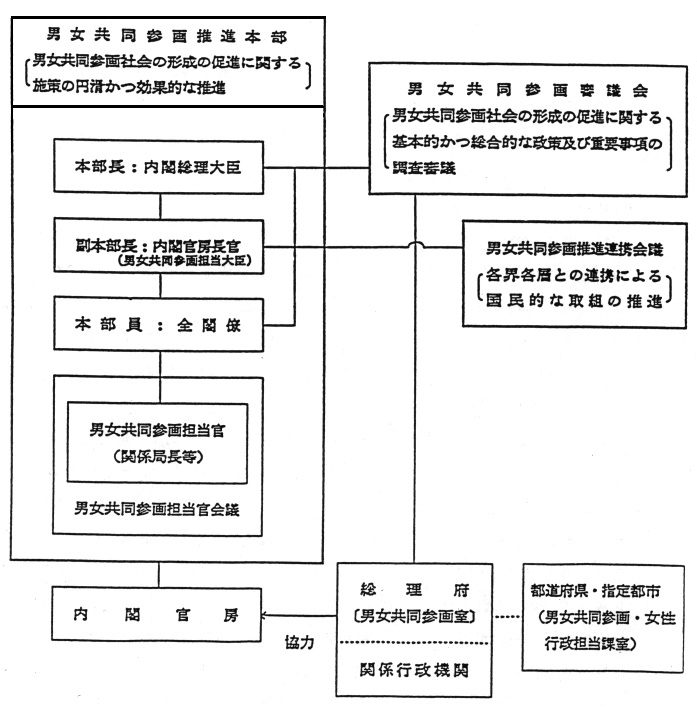
- 8 国内行動計画
- 1996年7月、男女共同参画審議会(男女共同参画審議会令(1994年6月24日政令第190号)に基づき設置)は、広く国民各層の意見を求めつつ、第4回世界女性会議の成果を踏まえ、内閣総理大臣に対して「男女共同参画ビジョン」を答申し、男女共同参画社会実現のため、我が国の経済・社会の変化を踏まえつつ、おおむね2010年までを念頭に、目指すべき方向とそれに至る道筋を提示した。
そこで、前回(第3回)報告において報告した「西暦2000年に向けての新国内行動計画」(1987年策定)の改定に当たっては、このビジョンにおいて示された方針を踏まえつつ、新国内行動計画第1次改定(1991年)の成果や課題を継承しつつも、これを抜本的に改正した新たな国内行動計画を策定することとし、1996年12月に、西暦2000年(平成12年)度までに推進すべき計画として「男女共同参画2000年プラン-男女共同参画社会の形成の促進に関する平成12年(西暦2000年)度までの国内行動計画-」と題する国内行動計画を決定し、北京行動綱領(パラグラフ297)の要請にも応えた。
プランの策定に当たっては、団体や個人から寄せられた約1,100件の意見・要望を参考にするなど、国民各界各層の声の取り入れを図った。またその構成は(1)男女共同参画を推進する社会システムの構築、(2)職場・家庭・地域における男女共同参画の実現、(3)女性の人権が推進・擁護される社会の形成、(4)地球社会の「平等・開発・平和」への貢献、という4つの基本目標と、11の重点目標から成っている。なお、今回、新たな課題として、「男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し」、「女性に対するあらゆる暴力の根絶」、「メディアにおける女性の人権の尊重」、「生涯を通じた女性の健康支援」が重点目標として掲げられた。政府は、現在、このプランに従い、男女共同参画社会づくりのための諸施策の推進に努めているところである。
- 9 地方公共団体等の活動例
- 地方公共団体においても男女共同参画に関する行政が積極的に推進されており、全47都道府県・12指定都市に男女共同参画施策の企画・調整のための部・課(室)が置かれ、男女共同参画施策推進のための行動計画が策定されている(1998年4月現在)。また、市区町村(指定都市を除く。)における行動計画策定率は、3243市区町村中382(11.8%)(1997年4月現在)となっている。
| BACK / FORWARD / 目次 |
![]()
|
| ||||||||||