|
| ||||||||||||||||
| トップページ > 外交政策 > 人権・人道 |
|
| ||||||||||||||||
| トップページ > 外交政策 > 人権・人道 |
D.適当な情報の利用(第17条) 85.児童福祉法、放送法、学校図書館法及び図書館法等があり、児童が国の内外の多様な情報源からの情報及び資料を利用することができるよう、これらの法令に基づく措置により、具体的には次のようなことが実施されている。
(a)図書館の設置
86.図書、記録その他の資料を利用し得る公共の図書館が、1993年度現在、全国に2,138館あり、政府は、地方公共団体に対する図書館の施設、設備に要する経費等につき一部の補助を行っている。また、学校には、学校図書館が設けられている。(b)児童文化財の推薦
87.中央児童福祉審議会及び都道府県児童福祉審議会が設置されており、これら審議会は、児童及び精神薄弱者の福祉を図るため、児童文化財の推薦を行うことができるとされている。中央児童福祉審議会では、1951年から専門家、学識経験者から成る文化財部会を設け、児童が楽しく利用し、情操を高め、諸能力を発達させる優良児童文化財の推薦を行っている。1995年における推薦件数は、出版物89点、音響・映像等49点、舞台芸術29点であった。なお、これまでに推薦された児童文化財の中から幼児、小学生を対象とした優れた作品を選び、それぞれ全国の児童館を巡回し、上演・上映する事業を実施している。(c)映画
88.文部省では、児童向けの優れた映画等の制作を促進し、その利用普及を図るため、制作者からの申請に基づき、生涯学習審議会教育映画等審査部会における審査を経て、教育上価値が高い作品を「文部省選定」として、更にその中で特に価値の高いと考えられるものを「文部省特別選定」として決定し、それらの作品の概要を広報し、その利用普及に努めている。1995年は、「文部省選定」作品として264本、「文部省特別選定」作品として3本が選定となった。また、社会教育及び学校教育に役立つ教材映画のうち、文部省特別選定となった作品等を買い上げ、各都道府県及び政令指定都市教育委員会に配布している。(d)放送番組
89.放送法では、教育番組の編集及び放送に当たっては、その放送の対象となるものが明確であるようにすること、内容がその者に有益適切であり、組織的、継続的であるようにすること、その放送の計画及び内容をあらかじめ公衆が知ることができるようすることのほか、当該番組が学校向けのものであるときは、その内容が教育課程の基準に準拠するようにしなければならないことと規定している。90.政府でも、民間放送局による教育番組の充実向上と放送を通じた家庭教育の充実、青少年の健全育成に資するため、(財)民間放送教育協会にテレビ家庭教育番組の企画、制作、放送及び調査研究の事業を委託している。
国際協力
91.我が国の放送法は、日本放送協会による国際放送等の放送番組の編集及び放送又は外国放送事業者等に提供する放送番組の編集に当たって我が国の文化等を紹介して我が国に対する正しい認識を培い及び普及することを規定している。
政府では、1991年4月より、日本の教育番組等を開発途上国向けに翻訳する事業を支援するため、年間約2億円を「(財)放送番組国際交流センター」(外務省と郵政省の共管法人)を通じて補助している。1996年3月末までの実績としては、日本語から英語等へ吹き替えた番組が478本、提供された番組は19ヶ国、368本となっている。92.また、アジア・太平洋地域の子供たちに廉価で良質の本を提供するために、各国の児童書出版の専門家と協力して、児童図書の共同出版等を実施しているユネスコ・アジア文化センターに対し、助成を行っている。
93.更に、国際文化協力の一環として、文化無償協力により、教育・文化放送番組の供与を行っている。文化無償協力における教育文化放送分野(教育・文化番組、ソフト)での1995年度の協力実績(予算ベース)は、2件(61.1百万円)であった。
有害な情報からの保護
94.児童を取り巻く社会環境は、発達途上にある青少年の人格形成に強い影響を及ぼしている。特に、性的感情を著しく刺激し、又は粗暴性、残虐性を助長するおそれがあるといった児童の福祉に有害であると認められる情報、書籍等は、しばしば非行の誘因ともなっており、児童の健全育成の観点から憂慮すべき問題となっている。このような認識に基づき、有害な情報等からの保護については、次のような施策を実施している。
95.児童福祉法が中央児童福祉審議会及び都道府県児童福祉審議会による出版物を販売する者等に対する勧告(児童福祉法第8条第7項)を定めているほか、放送法では、放送事業者は、国内放送番組の編集に当たって公安及び善良な風俗を害しないことのほか、自ら番組基準を定め、これに従って放送番組を編集すること、放送番組の適正を図るために放送番組審議機関を設置することを規定している。
96.また、都道府県では、青少年に有害な図書、ビデオ、映画、広告物等を規制するために、それぞれの地域の実情に基づき、青少年保護育成条例を制定しており、1994年度においては、条例による有害指定件数は、71,828件にも上った(資料5参照)。政府としては、これらの条例の適正な運用、整備等による規制措置の徹底を推進している。
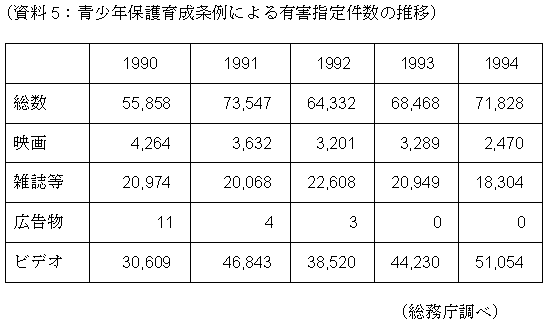
97.更に、政府は、社会環境の変化に応じて、関係業界に対し、有害な情報の提供の自粛・自制の要請等を行い、関係業界の支援を得て、児童の有害な情報からの保護を推進している。例えば、映画については、映画関係業界の独立機関である映倫管理委員会により、成人映画を指定し、これにつき18歳未満の者の入場を事実上制限する映画倫理規程の管理、適用が行われている。
98.また、近年、メディアの多様化が著しく、社会に与える影響も増大し、児童の心身への影響が憂慮されていることにより、次のような措置がとられている。
(i)コンピュータソフトウェアについては、コンピュータソフトウェア倫理機構が、18歳未満の青少年への販売を禁止すべきソフトにシールを貼付し、明確に区別するなどし、また、1994年7月より、15歳未満の者への販売を禁止するR指定制度も導入した。
(ii)インターネットについては、1996年2月、パソコン通信サービスを提供する事業者を会員とする電子ネットワーク協議会が、電子ネットワークを活用する上での倫理的観点からガイドラインである「電子ネットワーク運営における倫理綱領」及び「パソコン通信を利用する方へのルール&マナー集」を作成した。また、警察では、パソコン通信を利用してわいせつ情報を提供する事犯について、1996年1月、インターネットを利用したわいせつ図画公然陳列事件を検挙する等、この種事犯の取締りを強化している。
(iii)更に、政府では、1996年5月より衣服を脱いだ人の姿態の映像を主たる内容とするCD-ROM等の販売等を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規制対象である風俗関連営業の要件に加えた。
99.なお、有害な情報等からの児童の保護の促進に当たっては、住民の活発な地域活動も重要であり、政府では、地域の団体、住民等による地域活動の促進も図っている。
| BACK / FORWARD / 目次 |
![]()
|
| ||||||||||