2.文化外交
(1)文化事業
諸外国における対日理解を促進し、良好な対外関係を維持・強化するため、外務省では、在外公館や国際交流基金を通じて、日本文化紹介事業を積極的に実施している。以前から取り上げている伝統文化・芸術に加え、近年は世界的に人気の高いアニメ、漫画などのいわゆるポップカルチャーも文化外交の主要なツールとして活用している。
その一環として、7月に、パリ(フランス)で開催される世界最大級の日本ポップカルチャーイベントであるJAPAN EXPO 2009の機会に、外務省、経済産業省、観光庁の三省庁及び国際交流基金・パリ日本文化会館、映像産業振興機構(VIPO)、国際観光振興機構が連携して関連事業を実施し、16万人に及ぶ欧州内外からの参加者に向けて日本文化を発信した。
また、在外公館及び国際交流基金が実施する文化事業等で、ファッションを通じた日本文化紹介を行うことを目的とし、新たにポップカルチャー発信使(通称「カワイイ大使」)として、ファッション分野で顕著な活動を行っている若手リーダー3名に協力を依頼した。3名は、タイ、フランス、イタリア、ロシア、ブラジルを始め多くの国を訪問し、各地で大きな反響を得た。
2007年に創設した「国際漫画賞」は第3回を迎え、55の国・地域から303作品の応募があった。12月には受賞者を日本に招き、授賞式が行われた。今回から海外における日本の漫画への理解促進及び普及に貢献した人物・団体を顕彰する「特別賞」が新設された。
周年事業は、外交上の節目となる年に大規模かつ総合的な記念事業(要人往来、各種会議、広報文化事業等)を実施し重点的な交流を行うことにより、一層効果的な対日理解を目指すもので、政府関係機関や民間団体と連携して行っている。「日本ドナウ交流年2009」においては、国際交流基金主催事業として「能楽公演」、「邦楽公演」等を、「日メコン交流年2009」においては、大型文化事業として「邦楽デュエット公演」等をそれぞれ実施した。
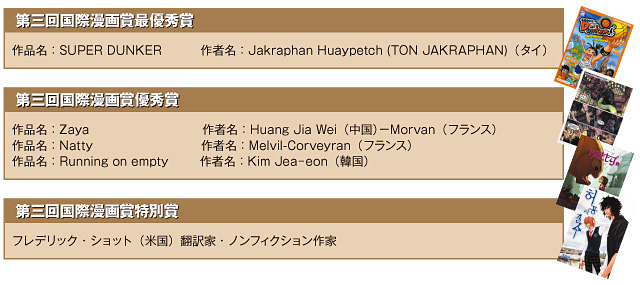
(2)人物、教育分野での交流
人物交流は、諸外国との相互理解を増進し、関係を強化する上での重要な外交施策である。外務省は、対日理解や友好関係の増進、人脈構築を主眼とした人物交流を促進することによって、日本の外交上の立場を有利にするとともに日本のプレゼンスを高める努力を行っている。
例えば、「21世紀パートナーシップ促進招へい」によって、将来各界で指導的立場に就くことが有力視される人々を世界各国から毎年400名以上招待することにより、日本に対する正しい理解の推進や人脈構築に努めている。また、スポーツ交流では、大規模国際スポーツ大会の日本への招致活動支援や、各種国際スポーツ大会の後援、柔道・空手・剣道等の日本の伝統スポーツ分野における交流を通じた対日理解促進・親日家育成も図っている。

イ JETプログラム(注1)
2009年には、米国、英国を始めとする36か国から4,436人の外国青年を招致し(7月1日現在)、日本全国の学校等における外国語活動や各自治体における国際交流活動に携わらせており、1987年からの参加者は累計5万人以上となった。本プログラム経験者は、各国・地域において日本との相互理解を促進することを目的とした同窓会組織「JETAA」を自発的に発足させており、外務省はJETAAの活動を支援している。

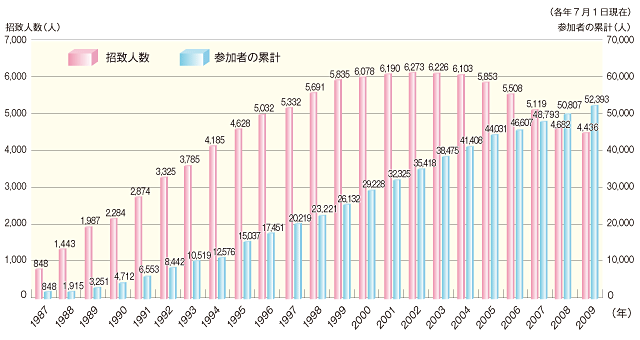
ロ 留学生交流
日本の高等教育機関で学ぶ外国人留学生の在籍者数は、2009年5月現在13万2,720人で過去最高となり、日本語教育機関で学ぶ学生数は、2008年7月現在3万4,937人と着実な増加傾向にある。外務省は在外公館を通じて、日本への留学機会を積極的に広報するとともに、各国の優秀な学生を国費留学生として受け入れるための広報・募集・選考等の窓口業務を担い、留学生が日本での学業を終えて帰国した後も、母国において知日家・親日家として活躍できるよう、各国にある「帰国留学生会」に対する支援(注2)を行っている。


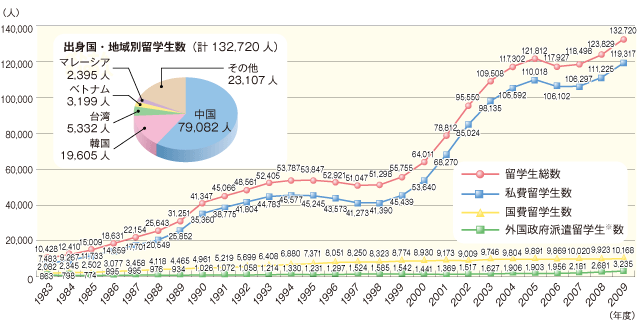
(3)知的分野の交流
イ 日本研究
諸外国の日本に対する理解を深め、それぞれの国との良好な関係を維持、発展させるために、海外における日本の政治、経済、社会、文化等に関する研究を支援している。
2009年度は、国際交流基金を通じ、中国の北京日本学研究センターなど各国の日本研究の中核となる機関への客員教授派遣、日本関係図書拡充、会議開催助成等による複合的支援(33か国67機関)や、海外の日本研究者に対する日本での研究・調査活動の機会の提供(44か国153名)などを行った。また、10月に初めての「世界日本研究者フォーラム2009」を開催したり、世界各地の日本研究学会の会合を支援したりするなど、日本研究者の間のネットワーク形成にも努めている。
ロ 知的交流
世界や地域に共通する課題解決に向けた取組を推進し、世界の発展と安定に向けた日本の知的貢献を促進するため、日本は、多国間の共同作業・交流を重視した知的交流事業を企画、実施、支援している。具体的には、中国、東南アジア、中東・北アフリカから知識人を地域別にグループで招へいしたり、5月には国際交流基金とドイツ政府の文化機関であるゲーテ・インスティトゥートの共催でシンポジウム「平和のための文化イニシャティブの役割」を開催するなど、知的交流の深化に努めている。
また、2007年11月の日米首脳会談の際に日本側が発表した、知的交流、草の根交流及び日本語教育の三本柱からなる「日米交流強化のためのイニシャティブ」を受け、米国シンクタンクとの関係強化、日本研究の拠点となる米国の大学等への支援に重点を置いた日米の知的交流を行っている。
ハ 国際連合大学(UNU)との協力
日本政府は、日本に本部を置くUNUとの間でホスト国として協力を進めてきた。特に、2007年9月に就任したオスターヴァルダー学長による「日本に根ざした国際連合大学」、「開かれた国際連合大学」を目指した取組を支援している。UNUは、世界各国の大学と提携して、新たに大学院プログラムを開始するために準備を行っており、12月には、そのために必要なUNU憲章の修正決議が国連総会において採択された。
(4)日本語普及
海外における日本語普及は、日本との交流の担い手を育てるものであり、日本理解を深め、諸外国との友好関係の基盤をつくるものとして重要である。海外では133の国・地域において、298万人余りが日本語を学習しており(2006年国際交流基金調べ)、学習者数は30年間で20倍以上に増加している。近年では学習目的も多様化し、従来の就職・留学のような実利志向の強い目的のみならず、異文化理解やアニメ、漫画などポップカルチャーへの関心を動機とする学習者が増加している。日本は国際交流基金を通じて、日本語教育専門家の海外派遣、海外の日本語教師及び外交官等の訪日研修、日本語教材の開発・購入助成等を行い、日本語普及に努めている。また、2008年までは全世界50の国・地域、159都市で日本語能力試験を実施(2008年は約56万人が受験)してきたが、2009年は、例年の12月試験に加え、日本国内、中国、韓国、台湾において1、2級のみの7月試験も実施した。2010年は、内容を一層充実させるため、今まで1~4級までであったレベルを5段階に区分しなおすとともに、さらなる受験機会の拡充を図る予定であるほか、NHK教育テレビや海外のテレビ局を通じて放映している若者向けの映像教材「エリンが挑戦!にほんごできます。」の放映枠を一層拡充していく方針である。
さらに、国・地域ごとのニーズに応じた日本語普及事業の展開と関係機関の連携強化のため、国際交流基金の海外事務所及び日本語教育専門家が派遣されている諸大学を中心に、今後1年の間に「JFにほんごネットワーク(通称:さくらネットワーク)」を世界100か所以上に展開していく予定である。
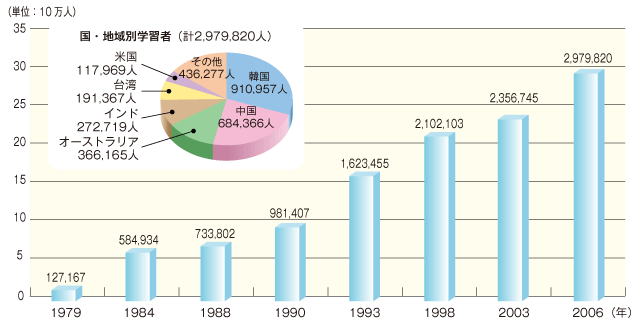
(5)文化無償
開発途上国における文化・高等教育振興の取組を支援し、日本とこれら諸国との相互理解や友好親善を深めるため、ODAの一つである文化無償資金協力を実施している。2009年は全世界で一般文化無償資金協力を15件(総額15億2,000万円)、草の根文化無償資金協力を44件(総額約3億円)実施した。例えば2009年11月に完成したラオス武道館は翌12月の東南アジア・スポーツ大会武道会場として活用され、同大会でのラオス柔道選手の活躍もあいまって大変感謝されている。

(6)国連教育科学文化機関(UNESCO(ユネスコ))を通じた協力
日本は、1951年、戦後いち早くユネスコに加盟して以来、教育、科学、文化、コミュニケーションなどの各分野における国際的知的協力や開発途上国に対する開発支援等のユネスコの様々な取組に積極的に参加している。特に、文化面では、世界の有形・無形の文化遺産の保存修復、振興及び人材育成の分野における支援を協力の柱として、積極的に取り組んでいる。
優れた文化遺産は、次の世代に受け継がれるべき人類共通の遺産であると同時に、その遺産を有する国の国民にとっては誇りであり、アイデンティティの根源に深くかかわるものである。日本は、高い技術と豊富な経験を生かし、海外の文化遺産の保存修復や人材育成に協力するとともに、文化遺産保護のための国際的枠組みにも積極的に参画している。その一環として、日本は、ユネスコに有形・無形それぞれの文化遺産保護を目的とした日本信託基金を設置している。文化遺産保存日本信託基金では、カンボジアのアンコール遺跡やアフガニスタンのバーミヤン遺跡保存修復事業を、日本の専門家が中心となり、将来はその国の人々が自分たちの手で遺跡を守っていけるよう、現地の人々と力を合わせ、人材育成を行いながら実施している。無形文化遺産保護日本信託基金では、開発途上国における音楽・舞踊等の伝統芸能や伝統工芸等を次世代に継承するための事業や、無形文化遺産条約締結に向けた国内制度整備を支援している。
さらに、日本は、ユネスコに人的資源開発信託基金を設置し、ユネスコが主導機関としての役割を務める「万人のための教育(EFA)」の推進など教育分野を中心とした開発途上国の人材育成への取組を支援している。また、日本において取組を強化している「持続可能な開発のための教育(ESD)」については、3月末から4月初めにかけて開催されたESD世界会議(於:ボン(ドイツ))において、国連・持続可能な開発のための教育の10年(DESD、2005~2014年)の締めくくり会合を日本で開催する旨表明し、ESDの更なる推進を目指している。
イ 世界遺産条約
世界遺産条約は、文化遺産や自然遺産を人類全体の遺産として国際的に保護することを目的として、1972年のユネスコ総会で採択され、1975年に発効した。日本は1992年にこの条約を締結している。
世界遺産は、建造物や遺跡などの「文化遺産」、自然地域などの「自然遺産」及び文化と自然の両方の要素を持つ「複合遺産」に分類され、日本からは、文化遺産11件、自然遺産3件の計14件が世界遺産に記載されている。なお、6月、セビリアで行われた世界遺産委員会において、日本を含む6か国が共同推薦した「ル・コルビュジエの建築と都市計画」が「情報照会」決議(追加情報の提出を求めた上で次回以降の審議に回すもの)を受けたことを踏まえ、再推薦に向けた準備を進めている。
世界遺産条約は、発効から30年以上が経過し、締約国と世界遺産の数は飛躍的に増加している。世界遺産委員会を中心に、条約運用の制度や世界遺産の在り方と価値の定義を見直すための議論が行われており、日本はこれら議論にも積極的に参画している。
ロ 無形文化遺産条約
無形文化遺産条約は、2003年のユネスコ総会で採択され、2006年4月に発効した。この条約により、伝統芸能や伝統工芸等の無形文化遺産についても国際的保護の体制が整えられることとなった。国内における無形の文化財の保護において豊富な経験を持つ日本は、この条約の作成に当たってもけん引役となり、条約発効後は、第2回政府間委員会を2007年に日本において開催し、議長国として運用指針の主要部分を取りまとめるなど、積極的な貢献を行っている。2008年6月には、この運用指針が締約国会議において採択され、本格的運用が始まった。2009年10月、アブダビにおいて開催された第4回政府間委員会においては、条約に基づく「人類の無形文化遺産の代表的な一覧表」への初回記載が行われ、日本からは「雅楽(ががく)」、「小千谷縮(おぢやちぢみ)・越後上布(えちごじょうふ)」、「京都祗園祭の山鉾(やまほこ)行事」など13件が記載された。

京都市東山区祇園の八坂神社の祭礼に合わせて行われる疫病除けを祈願する行事。一千年の歴史をもつとも言われ、町衆によって豪華絢爛な29基の山鉾の巡行が行われる。日本の夏祭りを代表する行事。

島根県西部の石見地方に伝承される、手漉きの半紙を製作する技術。江戸時代に大阪で重用され、石州半紙の名が広まった。原料は地元産の石州楮(こうぞ)で、独特の原料処理方法により、極めて強靭な紙を漉く。

日本に古くから伝わる「東遊(あずまあそび)」などの音楽と舞、6世紀以降にもたらされた外来の音楽と舞が日本独自に整理・発展した管絃と舞楽、平安時代につくられた「催馬楽(さいばら)」「朗詠(ろうえい)」などの声楽曲の総称。長く宮中を中心に伝承されてきた。

岩手県碑貫郡大迫町(ひえぬきぐんおおはさままち)に伝承される神楽で、もと早池峰山を霊峰として仰いだ山伏修験によって演じられた。早池峰神社の8月1日の祭礼などに演じられ、能楽大成以前の姿を暗示するもの。
(注1)語学指導等を行う外国青年招致事業(The Japan Exchange and Teaching Program)は、日本の小中学校・高校における外国語教育の充実や、地域の国際交流の発展を図ることを目的として、日本の地方自治体を始め、外務省、総務省、文部科学省及び(財)自治体国際化協会(CLAIR)が協力して実施している。1987年に開始。詳細はhttp://www.mofa.go.jp/j_info/visit/jet/(外務省)又はhttp://jetprogramme.org/((財)自治体国際化協会)を参照。
(注2)名簿・会報の作成、懇談会開催などの帰国留学生相互のネットワーク形成を支援し、留学生会が実施する日本文化紹介事業を支援している。