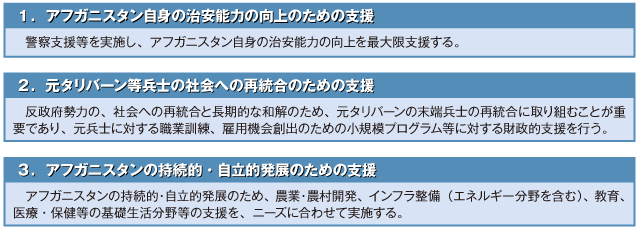2.アフガニスタン
(1)政治・治安情勢
アフガニスタンでは、2001年のタリバーン政権崩壊以降、近代的な国家構築のための復興努力が続けられている。2009年8月には2回目となる大統領選挙及び県議会選挙が実施され、11月にカルザイ大統領が再選された。
治安は不安定の度合いを強めており、特に、パキスタンと国境を接する南部・南東部・東部の治安は懸念すべき状況にある。9月の国連事務総長報告では、反政府勢力が比較的安定していた地域の不安定化を招き、市民の犠牲を顧みない、より洗練され、かつ複合的な攻撃を増加させており、7月までの治安事件発生件数は898件(前年同時期比約32%増)で、簡易爆弾(IED)の使用は前年比で60%増加している旨などが報告されている。アフガニスタン政府は、国際社会の支援を受けて、国軍や警察の拡大や強化に取り組んでいる。また、NATOが指揮を執るISAFの派遣人数が、2009年の1年間で1万人以上増加するなど、治安面での国際社会による支援も強化されている。

(2)経済・社会状況
アフガニスタンの復興においては、これまでに500万人の避難民が帰還したほか、2007年には16.2%の経済成長率を記録した。教育分野では、就学人数が2001年の100万人以下から2007年には570万人に増加し、医療分野では、はしかの予防接種率が2000年の35%から2007年の70%に改善した。
その一方で、アフガニスタンでは内戦が過去数十年にわたって続いたことから、今後の復興・開発に不可欠な基礎的インフラは未整備の部分が多く、地方への支援拡大も課題となっている。特に麻薬問題の解決は最重要課題の一つである。アフガニスタンのアヘン生産量は世界の生産量の94%を占めているとされているが、ケシ栽培が前年比で22%減少し、アヘンの売買価格も過去最低の水準となったことから、2009年は前年に比べて約10%の減少が見込まれている。
(3)日本の復興支援策
アフガニスタンの安定と復興は、国際社会全体が対処している最重要課題の一つである。12月1日に行われた、米国の対アフガニスタン・パキスタン新戦略の発表に続き、NATO加盟国を始めとした25か国が増派を公約するなど、国際社会全体として支援を強化してきている。
日本は、アフガニスタンをテロの温床に逆戻りさせないとの決意の下、2002年1月にアフガニスタン復興支援国際会議(東京会議)を開催し、アフガニスタンの和平・復興の努力に対する国際社会の支援を取りまとめるなど、これまでアフガニスタン支援について国際社会で主導的な役割を果たしてきている。10月には岡田外務大臣がカブールを訪問し、カルザイ大統領やスパンタ外相らと今後の支援のあり方について意見交換し、視察を行った。
日本はこれまで、政治プロセス、治安改善、復興のすべてにわたりアフガニスタンに対する支援を行ってきており、2001年10月から2009年12月までに日本が実施・決定した支援実績は約18億米ドルに達している。また、アフガニスタン全土で活動するNATOの地方復興チーム(PRT:軍人及び文民復興支援関係者から構成される軍民混成の組織)と連携した形でも支援を行っており、2009年5月以降、ゴール県のチャグチャランPRTに日本の文民を派遣するなど、地方への支援も強化している。
さらに11月、日本は新たなアフガニスタン・パキスタン支援策を発表した。アフガニスタンに関しては、早急に必要とされる約800億円の支援を行うとともに、今後のアフガニスタンの情勢に応じて、2009年から概(おおむ)ね5年間で、最大約50億米ドル程度までの規模の支援を行うことを決定した。そこでは[1]アフガニスタン自身の治安能力の向上、[2]元タリバーン末端兵士の社会への再統合、[3]アフガニスタンの持続的・自立的発展のための支援の3つを柱としている。