
第63回国連総会出席時の麻生総理大臣(左)と潘基文国連事務総長(右)(9月25日、米国・ニューヨーク 写真提供:内閣広報室)
7. |
国連 |
今日の国際社会は、気候変動、テロ、大量破壊兵器の拡散、貧困、感染症等、個々の国家・地域のみでは対応困難な多くの課題に直面しており、国連が果たす役割は以前にも増して重要となっている。日本は、外交政策の主要な柱の一つである国連を中心とした国際協調を推進するため、安保理改革を始めとする国連改革の早期実現を目指すとともに、国際社会において日本の国益を増進するために国連機関を含む国際機関に対し人的・財政的貢献を行っている。
日本は2008年10月、多数の加盟国の支持を得て国連安全保障理事会(安保理)非常任理事国に当選した。これは、加盟国中最多の10回目の任期となる。日本は2009年から2年間、安保理理事国として安保理における議論に積極的に参加するとともに、常任理事国を目指す国としてもふさわしい役割を果たすことを通じ、安保理改革及び日本の常任理事国入りの早期実現に向けた機運をより一層高めていく考えである。
日本が国連・国際機関を通じた外交を力強く推進していくためには、国連の役割や日本の取組に関する国民の理解が不可欠であり、広報活動にも積極的に取り組んでいく考えである。
 第63回国連総会出席時の麻生総理大臣(左)と潘基文国連事務総長(右)(9月25日、米国・ニューヨーク 写真提供:内閣広報室) |
(1) |
日本と国連の関係深化 |
2008年は日本がG8北海道洞爺湖サミットの議長国を務め、また第4回アフリカ開発会議(TICAD IV)を横浜で開催するなど、国際社会において日本のリーダーシップが求められた年であった。そのような中、食料価格や原油価格の高騰、世界的な金融危機といった一国では有効に対処し得ない問題が顕在化し、国連・国際機関を通じた多数国間外交の必要性が改めて認識された。5月にはミギロ国連副事務総長がTICAD IVのため来日し、開発や食料問題を中心に関係者との意見交換を行った。6月には潘基文(パンギムン)国連事務総長夫妻が公賓として事務総長就任後初めて来日した。潘基文事務総長は、京都大学で行われた気候変動に関するタウン・ミーティングで講演したほか、福田総理大臣や町村孝官房長官、高村外務大臣とそれぞれ会談し、環境・気候変動、開発・アフリカ、食料価格高騰問題等、国際社会の直面する様々な課題について意見交換を行い、日本と国連が緊密に協力していくことを確認した。特に、潘基文事務総長は、国際社会の平和と発展のために包括的な貢献を行っていくとの日本の姿勢を高く評価するとともに、安保理改革を含む国連改革についても意見交換を行った。来日時に自ら体験した日本のクールビズ(軽装)に着想を得て、国連においても類似の取組(「クールUN」)を導入するなど、日本と国連の協働を象徴する訪日となった。さらに、潘基文事務総長夫妻は7月に行われたG8北海道洞爺湖サミットに出席するために再び来日し、国連の立場から開発・アフリカや気候変動に関する議論に貢献した。
9月に開会した第63回国連総会における一般討論演説の際には、就任直後の麻生総理大臣及び中曽根外務大臣がニューヨークを訪問した。麻生総理大臣は国際社会に対して、経済的繁栄と民主主義を通じて平和と幸福を実現するという自らの信念を訴えるとともに、技術力や発想力をいかした日本ならではの外交について、力強くメッセージを発信した。また、食料危機・気候変動に関する国連事務総長主催夕食会に出席したほか、潘基文事務総長、ラッド・オーストラリア首相、タラバーニー・イラク大統領との会談を行った。中曽根外務大臣はデスコト第63回国連総会議長と会談し、日本が気候変動、開発、国連改革、人権を始めとする国際的な諸課題について緊密に協力していく考えを伝えるとともに、安保理改革に関する政府間交渉を早期に開始する必要性があるという点で一致した。
(2) |
安全保障理事会 |
国連安全保障理事会(安保理)による国際の平和と安全の維持のための活動は、特に冷戦の終結以降、[1]国連平和維持活動(PKO)の設立、[2]多国籍軍の承認、[3]テロ対策、不拡散に関する措置の促進、[4]制裁措置の決定等多岐にわたっている。安保理決議に基づくPKOや多国籍軍の活動は、停戦監視等を中心とした活動(ゴラン高原等)から、民主的統治、復興、警察支援等の平和構築を含む活動(東ティモール、アフガニスタン等)までその任務は多様さを増している。また、大量破壊兵器の拡散、テロ等の新たな脅威に有効に対処するため、下部機関を設置し、各国による関連安保理決議の実施を支援している。このように、国際社会における平和と安全の確保のため、安保理が果たす役割は拡大している。
日本は、2008年10月に行われた安保理非常任理事国選挙において、加盟国最多となる10回目の当選を果たし、2009年1月から2年間の任期で安保理非常任理事国を務めている。

安保理議場風景(C)UN Photo/Mark Garten |
(3) |
安保理改革 |
安保理の構成は、その役割の拡大にもかかわらず、国連発足後60年以上の間、基本的には変化していない。このような状況の中、国際社会では、安保理の「代表性改善」と「実効性向上」の二つの側面から、その構成を早期に改革すべきとの認識が共有されている。
安保理改革は、各国の利害・思惑(わく)の対立が絡み、調整が困難な課題であるが、改革実現に向けた機運は継続しており、2009年2月からは安保理改革に関する政府間交渉が開始されることとなった。
日本は、常任・非常任双方の拡大を通じた安保理改革の早期実現と日本の常任理事国入りを国連外交の最も重要な課題の一つと位置付け、[1]安保理理事国の構成を今日の国際社会をより正確に反映し、国際社会を代表するにふさわしいものに改めること、[2]また国際の平和と安全の維持に主要な役割を果たす意思と能力のある国が常任理事国となり、常に安保理の意思決定に参加することが必要との立場を主張している。
日本が常任理事国となることにより、主要な国際問題に関する意思決定過程に深く、また、恒常的にかかわることが可能となり、日本の国益をより一層効果的に確保できる。日本はこれまでも平和の定着や国づくり、人間の安全保障、軍縮や不拡散等の様々な分野において国際社会への貢献を行ってきており、また、財政面における国連への貢献も世界第2位と極めて大きい。常任理事国となることにより、日本は、これらの貢献にふさわしい地位及び発言力を得ることが可能となる。
イ |
安保理改革の早期実現に向けた各国への働き掛け |
日本は、2008年も引き続き、様々な国際会議や二国間会談の機会をとらえ、各国の首脳・外相等に対し、安保理改革の早期実現の必要性を訴え、各国の理解と支持を広げる努力を行った。5月に横浜で開催された第4回アフリカ開発会議(TICAD IV)の際に発出された「横浜宣言」では、早期の安保理改革の重要性及び各国が安保理改革の実現に向けて努力すべきであることが強調された。また、5月の日中首脳会談、6月の日英首脳会談、9月の日米外相会談、10月の日仏首脳会談を始め、様々な二国間首脳・外相会談において、安保理改革の必要性につき認識が共有され、改革の早期実現に向け、各国と協力を継続していくことが確認された。
ロ |
第62回国連総会会期(~2008年9月)における動き |
国連においては、ケリム第62回国連総会議長が、作業部会(OEWG(Open-Ended Working Group)(1993年の国連総会決議により設立))の議論を主導し、2008年6月には、各国の立場を取りまとめた報告書を発表した。同議長は、同年7月以降、政府間交渉に向けた加盟国の異なる立場の調整を本格化し、イタリア、パキスタン、韓国、メキシコ等の改革消極派グループが難色を示し続けたものの、第62回国連総会最終日(9月15日)まで及んだ調整の末、最終的には2009年2月28日までに政府間交渉を開始するとの勧告を含むOEWG年次報告書が総会本会議で無投票採択された。
安保理改革に関する議論の場が、コンセンサス(全員一致)が必要なOEWGから国連総会の場に移され、具体的な成果を求める段階に入ったという点で、改革実現に向けた大きな前進だと考えられる。
ハ |
第63回国連総会会期(2008年9月~)における動き |
9月23日から29日まで国連総会において190か国の首脳・外相等が一般討論演説を行い、多くの国が安保理改革に言及した。日本からは麻生総理大臣が、常任・非常任双方の議席拡大を通じた改革の早期実現の必要性を強く国際社会に訴えた。各国の発言の中には、安保理改革に関する政府間交渉の開始の決定を歓迎し、早期の交渉開始を望む声も多く見られた。
2008年10月以降も、デスコト第63回国連総会議長は政府間交渉の進め方などについて、加盟国間の議論を主導している。11月には安保理改革に関する総会審議が行われ、日本を始め、発言した多数の国が常任・非常任議席の双方拡大の必要性を明言し、遅滞なき政府間交渉の開始を支持した。
日本としては、2009年2月に開始された政府間交渉に積極的に参加するとともに、様々な機会をとらえて主要国を始め各国と意見交換を行いつつ、安保理改革の早期実現及び常任理事国入りを目指す考えである。
(4) |
国連行財政 |
イ |
国連予算 |
国連の活動を支える予算は、分担金(通常予算、PKO予算、旧ユーゴスラビア及びルワンダ国際刑事裁判所予算、国連本部庁舎修築計画予算)と各国が政策的に拠出する任意拠出金から構成されている。
国連通常予算(注1)については、為替要因及びイラク、アフガニスタン政治ミッション等の経費増により、2008/2009年の2年間で48.7億米ドルと過去最大規模になっている。また、安保理が派遣を決定するPKO(単年予算)は、ダルフール、コンゴ民主共和国等への新規派遣・増派により、2008/2009年度(7月~翌年6月)は同じく過去最大規模の約70.8億米ドル、年間ベースで通常予算の約3倍となった。
日本は、厳しい財政事情の中、16.624%(2009年国連通常予算分担金は約4.1億米ドル、2008年国連PKO予算分担金は約12.6億米ドル)と加盟国中2番目の財政貢献を行っており、国連が行財政の観点からもより一層効率的かつ効果的に運営されるよう働き掛けを行っている。
ロ |
マネジメント改革及び事務局改編 |
2007年に就任した潘基文事務総長は、国連が国際社会の諸課題により適切に対応できるよう積極的な改革努力を続けている。その結果、2007年のフィールド支援局の新設に続き、2008年には政務局及び開発部局の強化が国連総会で承認された。また、2008年には国連本部職員とPKOの文民職員との処遇差を解消するための人事制度改革案が採択されるとともに、強制力を伴う判決を包摂した訴願制度が創設された。
こうした改革努力の結果として、国連の財政規模が拡大することに関しては、加盟国に対して国連事務局が説明責任を果たしていく必要がある。また、増大する傾向にある国連の業務の整理や優先度付けが引き続き大きな課題となっている。
国連予算(分担金)の推移(ネット額)
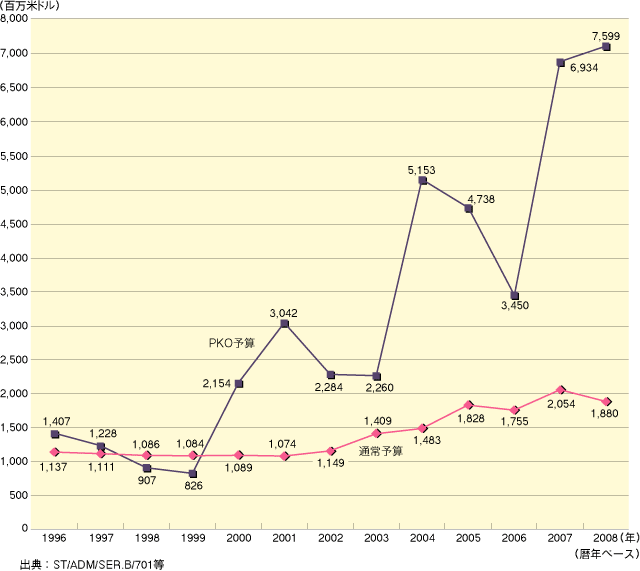
国連関連機関に対する主要国の任意拠出金と分担金の比較(2006年)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※シェアは世界全体に占める割合。 出典:国連資料A/63/185, ST/ADM/SER.B/701等 |
| (注1) | 国連の会計年度は偶数年1月から翌奇数年12月までの2年間。2008/2009年の予算額は、2008年12月に改定された金額。 |