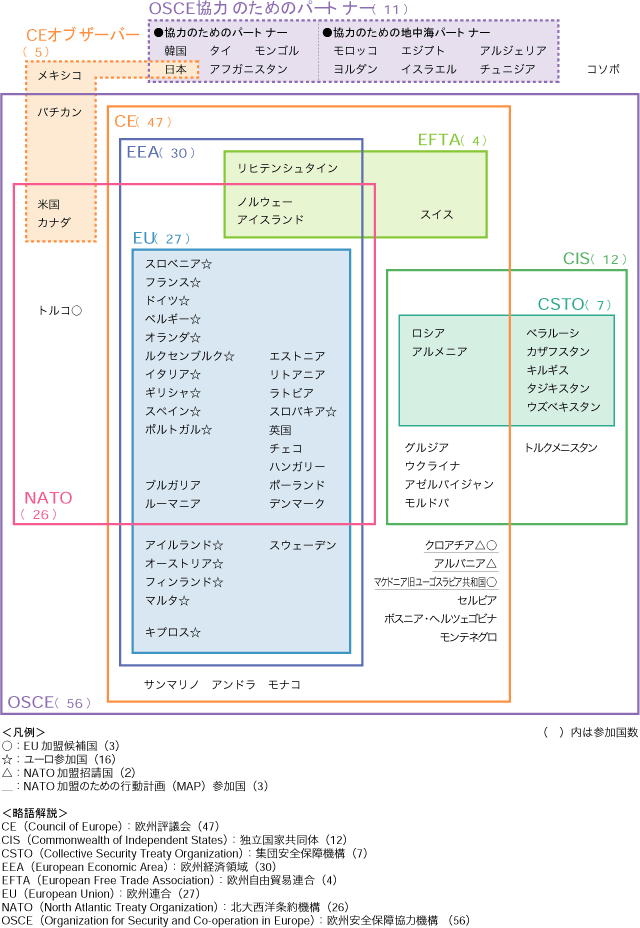2. |
欧州地域機関との協力 |
(1) |
北大西洋条約機構(NATO)との協力 |
NATO(加盟26か国(2009年2月末現在))は冷戦後の安全保障環境の変容の中で、国際的な平和と安定のための取組を強化し、コソボにおける国際安全保障部隊(KFOR)、アフガニスタンにおける国際治安支援部隊(ISAF)等、域外での展開を拡大している。10月から12月には、国連事務総長からの要請を受け、ソマリア沖の海賊対策として、WFP契約船舶の護衛等を実施した。また、4月のブカレスト首脳会合でクロアチアとアルバニアへの新規加盟招請を決定するなど、将来のウクライナとグルジアの加盟を含め、NATOの拡大についての議論が活発に行われた。グルジア紛争に対しては、9月にNATO・グルジア委員会を立ち上げ、グルジアの改革を支援していく姿勢を明らかにした。
日本との関係では、2007年12月の福田総理大臣とデ・ホープ・スケッフェルNATO事務総長の共同記者発表で、日本とNATOが基本的価値とグローバルな安全保障上の課題の解決に向けた責任を共有していることを再確認したことを受け、こうした取組におけるパートナーとして、日本とNATOの協力が進んでいる。
4月にNATO首脳会合の一環として開催されたアフガニスタン会合には、佐々江賢一郎外務審議官が出席し、日本のアフガニスタン復興支援へのコミットメント強化、その中でのNATOとの更なる連携等について発言を行った。
アフガニスタンでは、2007年にNATOの地方復興チーム(PRT)と連携しつつ、日本が草の根・人間の安全保障無償資金協力を通じてNGO等を支援する枠組みが構築され、九つのPRTと連携した43事業(2009年2月末現在)が実施されている。この円滑な実施のため、カブールでは、在アフガニスタン日本大使館の連絡調整員がNATO文民代表部と緊密に連携している。
また、3月には、NATO平和のためのパートナーシップ(PfP)信託基金を通じ、アフガニスタンの武器弾薬管理能力強化プロジェクトに対する協力を実施した。日本は、引き続き「テロとの闘い」等の共通目標に向けて、NATOとの協力を強化していく考えである。
(2) |
欧州安全保障協力機構(OSCE)・欧州評議会(CE)との協力 |
OSCEは、北米、欧州、中央アジアの56か国が加盟する世界最大の地域安全保障機構である。米露欧が集うフォーラムとして、特に12月にヘルシンキで行われた第16回OSCE外相理事会は、グルジア紛争とともに、ロシアが提案した新しい欧州安全保障条約構想を議論する場として、各国の注目を集めた。安全保障問題がグローバル化する中、日本はパートナーとして、OSCEとの対話と協力を促進している。同外相理事会では、伊藤![]() 太郎外務副大臣が参加し、北朝鮮の拉致(らち)問題・核問題など日本の安全保障に関する立場についてOSCEの理解と支持を訴えた。さらに伊藤外務副大臣は多くの外相等と会談を行い、ド・ブリシャンボー事務総長との間では、2009年に日本で開催するOSCEとの共催会議の成功に向け、連携を強化することで一致した。
太郎外務副大臣が参加し、北朝鮮の拉致(らち)問題・核問題など日本の安全保障に関する立場についてOSCEの理解と支持を訴えた。さらに伊藤外務副大臣は多くの外相等と会談を行い、ド・ブリシャンボー事務総長との間では、2009年に日本で開催するOSCEとの共催会議の成功に向け、連携を強化することで一致した。
CEは、民主主義、人権、法の支配等の分野における国際社会の規準づくりに重要な役割を果たす、加盟国47か国の欧州の地域国際機関であり、東欧や中央アジア・コーカサス諸国等で民主化支援事業等を実施している。日本は、アジアで唯一のオブザーバー国として、2008年中も様々な会合に積極的に参加した。さらにアゼルバイジャンの民主化に携わる青年指導層の養成を目的とするアゼルバイジャン・バクー政治研究スクールの活動を支援した。
欧州の主要枠組み