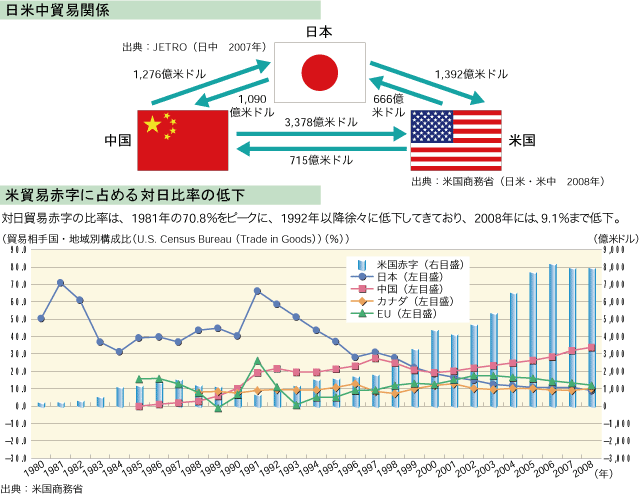日米首脳会談に臨む麻生総理大臣(左)とオバマ米国大統領(右)(2009年2月24日、米国・ワシントン 写真提供:内閣広報室)
1. |
米国 |
(1) |
日米同盟関係 |
イ |
日米首脳間の取組 |
日米両国間では、首脳レベルを始め、あらゆるレベルで相互の信頼関係の強化と緊密な政策協調が行われている。7月のG8北海道洞爺湖サミットの際に福田総理大臣とブッシュ大統領との間で行われた日米首脳会談においては、ブッシュ大統領が就任した2001年以来、日米同盟が安全保障及び経済を含む幅広い分野において深化してきたことを確認するとともに、日本のみならず、アジア太平洋地域の平和と繁栄の礎である日米関係を一層強化し、北朝鮮問題、「テロとの闘い」、気候変動、アフリカ開発といった課題に協力して対処していくことで一致した。また、日米交流の強化に関し、福田総理大臣から、2007年11月に訪米した際、ブッシュ大統領との間で日米交流の強化につき一致したことに触れ、両首脳は、日米間の交流の更なる強化に共に取り組んでいくことにつき一致した。
9月に就任した麻生総理大臣は、就任直後に行った所信表明演説及び国連総会における一般討論演説において、日米同盟は日本外交の基軸であり、その強化は日本外交の第一原則であると述べた。11月には、APEC首脳会議(於:ペルー)の際に日米首脳会談が行われ、両首脳間で、日米同盟は日米両国にとってもアジア太平洋地域にとっても平和と繁栄の礎であり、8年間に及ぶブッシュ政権下で日米同盟が深化した旨を確認し、北朝鮮、世界経済、イラク、アフガニスタンといった幅広い分野での協力を通じて、日米同盟を一層強化していくことで一致した。
ロ |
日米二国間の課題への対処 |
日米両国は幅広い分野において緊密に協調・協力している。日米二国間の課題としては、在日米軍再編、弾道ミサイル防衛(BMD)(第3章第1節1.「日米安全保障体制」を参照)、米国産牛肉輸入問題等が挙げられる。
ハ |
国際社会が直面する課題への共同の取組 |
| (イ) | 戦略対話 |
日米両国は、地域・国際社会が直面する諸課題について、中長期的観点からの情勢認識や共通戦略のすり合わせの場として、戦略対話を行っている。6月には東京で日米戦略対話高級事務レベル会合を開催し、北朝鮮を含むアジア情勢、中東情勢及びG8プロセスにおける日米協力について議論を行うとともに、本協議を継続していく重要性を再確認した。
またその機会に、アジア太平洋地域における平和と安定の促進という共通の戦略的利益を有する日米豪3か国による日米豪戦略対話高級事務レベル協議を開催し、3か国の連携と協力の拡大に努めた。
| (ロ) | 北朝鮮 |
北朝鮮問題については、2007年10月の六者会合成果文書において、第二段階の措置として、北朝鮮が、すべての核計画の「完全かつ正確な申告」を実施すること等が明記されたが、北朝鮮が2008年6月26日に核計画の申告を提出したことを受けて、朝鮮半島の非核化に向けて、早急に実効的な検証方法に合意し検証を開始できるよう、日米で緊密に連携を行った。
7月の日米首脳会談で両首脳は、しっかりと検証を行い、最終目的である「すべての核兵器及び既存の核計画」の放棄につなげていくことが必要であるとの点で一致した。また、11月の日米首脳会談においては、ブッシュ大統領から、核の検証問題はしっかり取り組まなければならない旨述べたのに対し、麻生総理大臣から、日米間で緊密に連携をとって、しっかりとした検証体制をつくっていきたい旨述べ、核問題の解決に向け、引き続き日米、日米韓で連携していくことで一致した。
拉致(らち)問題については、米国からは首脳レベルを含め一貫して日本政府に対する支持が示されている。
| (ハ) | テロ対策 |
日米は、国際社会の重要課題であるテロ対策に関し、緊密に連携している。2007年11月1日に中断したインド洋における日本の補給支援活動は、2008年1月11日の補給支援特別措置法成立により、2月に再開した。こうした補給支援活動は、米国を含む国際社会から高く評価されており、日本は12月14日に同法を1年間延長した。アフガニスタンの復興支援については、2009年のアフガニスタン大統領選挙等に向けて、日米で積極的に協力している。このほか、日米両国は、出入国管理・交通保安体制の強化、国際法的枠組みの強化、テロ資金対策等のテロ対策に関する協力を引き続き行っている。
| (ニ) | イラク |
イラクについては、政治プロセスが着実に進み、治安状況も改善傾向にある。こうした状況等を踏まえ、航空自衛隊による輸送支援は、その活動目的を達成したと判断し、12月に任務を終了した。今後は、円借款事業や技術協力、経済・ビジネス関係強化を通じたイラク支援を引き続き行っていくこととなる。
| (ホ) | グローバルな課題 |
アフリカ開発については、TICAD IVの成果を踏まえて7月の日米首脳会談で議論された結果、日米両国が、アフリカにおける保健(保健システム強化、ポリオ根絶、マラリア対策、顧みられない熱帯病対策)及び食料安全保障(食料増産と交易・交通インフラの整備やアフリカの中小企業の支援)上の課題に関して協力していくことで一致した。
気候変動については、G8北海道洞爺湖サミットの直前に行われた日米首脳会談において、両首脳は、この問題が人類が直面する最も深刻な脅威の一つであるとの認識を共有し、G8サミット及びその際に行われた主要経済国首脳会合(MEM)に向けて協力することで一致し、G8北海道洞爺湖サミットでの成果に貢献した。なお、オバマ大統領は、国内の排出量取引への積極的姿勢、自国の温室効果ガス排出量削減の中期及び長期目標の発表等、気候変動政策で指導力を発揮する立場を表明している。
ニ |
新政権への対応 |
11月に行われた大統領選挙において、民主党のオバマ候補が共和党のマケイン候補に勝利し、2009年1月20日、米国で8年ぶりに民主党政権が発足した。日本は、両陣営に対して選挙期間中から種々の働き掛けを行い、新政権発足後も引き続き良好な日米関係が維持されるよう努めてきた。オバマ大統領は選挙期間中から日米同盟の重要性について理解と支持を明確にしており、選挙直後の11月7日に麻生総理大臣と電話会談(注1)を行うとともに、新政権発足後の2009年1月29日にも麻生総理大臣と電話会談を行い、両首脳は、共に手を携えて、[1]金融・世界経済情勢への対処、[2]「テロとの闘い」や中東情勢、[3]気候変動・エネルギー、アフリカ開発等のグローバルな課題への対処、[4]拉致問題を含む北朝鮮問題を始めアジア太平洋地域の平和と繁栄の確保について日米で緊密に連携するとともに、日米同盟を一層強化していくことで一致した。
また、外相レベルでも、オバマ政権発足直後の2009年1月23日に中曽根外務大臣とクリントン国務長官の間で電話会談が行われ、クリントン国務長官から、日米同盟は米国のアジア政策の礎(cornerstone)であり、国際社会が直面する諸課題に共に対処していきたい旨の発言があった。
2009年2月16日から18日にかけてクリントン国務長官が就任後最初の外遊先として日本を訪問し、日米外相会談を行った。会談では、クリントン国務長官から、日米同盟は米国の外交政策の礎であると述べ、中曽根外務大臣と在日米軍再編の着実な実施を通じた日米同盟の一層の強化で一致するとともに、北朝鮮及び中国等のアジア太平洋地域情勢、アフガニスタン、気候変動・エネルギー、金融・世界経済、アフリカ開発等のグローバルな諸課題に関して幅広く意見交換を行った。
さらに同月24日には麻生総理大臣がオバマ大統領の招待を受けて、ホワイトハウスを訪問する最初の外国首脳として、首脳会談を行った。会談では、[1]日米同盟を一層強化することで一致するとともに、[2]この同盟を基軸として、アジア太平洋地域の平和と繁栄の確保、さらには、[3]金融・国際経済、アフガニスタン・パキスタン、気候変動・エネルギーなどのグローバルな課題に、共に手を携え取り組んでいくことを確認した。
(2) |
日米経済関係 |
近年の日米経済関係は、かつての摩擦に象徴される関係から、建設的な対話を通じた協調の関係へと変ぼうを遂げてきた。さらに、世界経済の持続可能な発展のために不可欠なグローバルな課題への対処や、9月の大手米国投資銀行リーマン・ブラザーズ経営破綻を契機とする金融危機への対応など、経済分野における日米協力は大きく広がった。
7月6日のG8北海道洞爺湖サミットに際して行われた日米首脳会談では、気候変動、アフリカ開発、アジア太平洋における防災・防疫等の分野で日米協力を一層促進することで一致するとともに、「アフリカにおける保健および食料安全保障上の課題に関する日米協力」を発表し、具体的な案件について協力を約束した。また、原油価格高騰の世界経済に与える影響を踏まえ、短期・中長期の政策につき、G8サミットで議論を行うことが重要との認識で一致した。
 日米首脳会談に臨む福田総理大臣(右)とブッシュ米国大統領(左)(7月6日、北海道洞爺湖 写真提供:内閣広報室)
 日米首脳会談に臨む麻生総理大臣(左)とオバマ米国大統領(右)(2009年2月24日、米国・ワシントン 写真提供:内閣広報室) |
11月の金融・世界経済に関する首脳会合やAPEC首脳会議においては、世界的な金融・経済問題への対応における日米連携を一層深め、11月22日のAPECに際して行われた日米首脳会談では、現下の経済情勢の下での保護主義台頭の防止、WTOドーハ・ラウンド妥結に向けた努力を行うことで一致した。また、同日行われた日米韓首脳会談では、11月に開催された金融・世界経済に関する首脳会合の成果を歓迎し、日米韓で連携しながらフォローアップしていくことを確認した。
さらに、11月の米国大統領選挙直後(同月7日)、麻生総理大臣とオバマ次期大統領の電話会談においては、金融不安・世界経済の問題、気候変動問題等の国際社会が直面する諸課題について日米が緊密に連携することで一致した。
「成長のための日米経済パートナーシップ」(注2)の枠組みの下では、日米両国が双方向の対話を原則として「規制改革及び競争政策イニシアティブ」に取り組んでいる。2008年も各作業部会(注3)や次官級の上級会合を経て、領事や電気通信分野において日本からの要望事項につき一定の進展が得られ、7月のG8北海道洞爺湖サミットに際して行われた日米首脳会談の際に、第7回報告書を両首脳に提出した。また、10月には、8年目の対話に関する日米それぞれの要望書を交換した。
二国間の個別案件として、米国産牛肉輸入問題については、2007年5月の国際獣疫事務局(OIE)総会において、米国の牛海綿状脳症(BSE)のステータスが「管理されたリスク国」と認定されたことを踏まえ、米国政府は、現在の対日輸出条件の緩和を要求しているが、日本政府は、食の安全を大前提に、科学的知見に基づいて対応することが重要であり、政府が一体となって適切に対応していくこととしている。
2001年9月の米国同時多発テロを受けて、米国はセキュリティ対策を強化している。その一方でセキュリティ対策が円滑なモノの流れを阻害することなく、「安全かつ円滑な貿易」を行うために日米間で協力していくこととしている。具体的な取組の一つとして、7月、日米両政府はメガポート・イニシアティブ(注4)のパイロット・プロジェクトを横浜港南本牧ふ頭において、2008年度中に実施することを発表した。
(3) |
米国情勢 |
イ |
政治(大統領選挙、議会選挙) |
2008年の大統領選挙は、80年ぶりに現職の正副大統領がいずれも出馬しない選挙となったこともあり、2006年末ごろから2007年前半にかけて候補者が相次いで出馬の意向を表明するなど、例年より早く選挙をにらんだ動きが活発化した。同時に、各党の候補者絞り込みのプロセスである予備選挙についても、各州が他州よりも先に実施することで選挙戦の流れに対する影響力を高めるべく、自州の予備選挙日を前倒ししたことから、予備選挙日程が全般的に前倒しされた。その結果、最初の予備選挙となったアイオワ州の党員集会は2008年1月3日と、これまでで最も早い時期の予備選挙開始となった。
1月4日から6月上旬までに各州で順次実施された各党の予備選挙では、共和党は、ジョン・マケイン上院議員が徐々に他候補とのリードを広げ、3月上旬には共和党大統領候補指名をほぼ確実にした。一方、民主党では、バラック・オバマ上院議員とヒラリー・クリントン上院議員が一進一退の激戦を繰り広げ、一連の予備選挙が終了した6月上旬の段階でクリントン候補が選挙戦撤退を表明し、オバマ候補の民主党大統領候補指名が確実となった。
各党の大統領・副大統領候補を正式に指名する全国党大会は、民主党については8月25日~28日にコロラド州デンバーで、共和党は9月1日~4日にミネソタ州セントポール/ミネアポリスで、それぞれ開催された。各大統領候補は、それぞれの党大会の直前に自らの副大統領候補を発表した。オバマ候補はジョセフ・バイデン上院議員を、マケイン候補はサラ・ペイリン・アラスカ州知事を、それぞれ副大統領候補に指名し、両正副大統領候補は党大会で正式に候補指名を獲得した。
その後、11月の本選挙までの間、両党候補による討論会(大統領候補3回、副大統領候補1回)を始め、激しい選挙戦が展開された。「変革」を訴えるオバマ候補が、選挙資金集めや若者などの新規有権者の発掘等で終始有利な選挙戦を展開した。さらに9月以降に深刻化した経済・金融危機により、選挙に向けた国民の関心は経済問題に一層傾斜し、外交・安全保障問題に強いとされたマケイン候補は、支持率でオバマ候補との差を狭めるに至らなかった。
11月4日の大統領選挙では、オバマ候補が28州及びワシントンDCで勝利し、22州を制したマケイン候補に大統領選挙人数で365対173の大差をつけて勝利した。2009年1月20日、オバマ大統領が就任し、米国史上初のアフリカ系大統領が誕生した。
大統領選挙と同時に実施された連邦議会選挙においても、民主党は上下両院で議席数を積み増し、多数党の座をより確かなものとした。
オバマ政権は、経済・金融危機への対応、イラク、アフガニスタン、中東和平といった喫緊の重要課題に直ちに対処する必要に直面している。オバマ大統領は、選挙直後から、経験と専門性を重視した閣僚・政府高官人事を相次いで発表しており、就任直後からこれらの課題に取り組む姿勢を見せている。
ロ |
経済 |
米国経済は、2003年第2四半期以降、堅調な個人消費、民間設備投資の持続等により、2006年第1四半期までほぼ一貫して年率3%以上の成長を記録してきた。しかし、2007年夏ごろからいわゆるサブプライムローン(低所得層向け住宅ローン(注5))問題が顕在化した。原油等のエネルギー価格の上昇等による個人消費の陰りや、インフレ対応としてのそれまでの金利の引上げ等もあり住宅市場が冷え込み、住宅価格の下落が継続した。こうした状況を受け、サブプライムローンの貸倒率は高まり、8月にはサブプライムローン関連金融商品が大量に格下げとなり、多くの金融機関に含み損が生じた。深刻化が進む金融不安は、証券化やデリバティブを用いた高度な金融商品のグローバル化を背景に、2008年9月のリーマン・ブラザーズの経営破綻を受け、世界的な金融危機へと発展した。10月に緊急経済安定化法が成立し、また、大手保険会社AIGを実質公的管理下に置くなど、米国政府による金融機関支援が進められている。金融機関の機能低下や、資産価値の下落による逆資産効果は、米国消費を大きく減退させ、2008年の第4四半期にはGDPの実質成長率が-6.2%(2009年2月27日時点)となるなど、2008年後半には実体経済への影響が深刻化した。近時では米国大手自動車メーカーの経営危機により政府が支援を実施するなど、予断を許さない状況が続いている。
金融面では、フェデラルファンド(FF)レートの目標値は、原油を中心としたエネルギー価格の高止まりによるインフレ圧力への警戒から2006年8月以降1年近く5.25%に据え置かれていたが、サブプライムローン問題の発生と、2008年9月のリーマン・ブラザーズの経営破綻による金融市場の逼迫(ひっぱく)を背景に、継続的な金利の引下げが実施された。2008年12月にはFFレートの目標値を0%~0.25%にし、実質ゼロ金利政策となった。2008年10月には、総額7,000億米ドルの公的資金による米国金融機関支援を目的とした緊急経済安定化法が成立した。大手銀行や地方銀行等を中心に公的資金による大規模な資本注入策がとられている。
また、2009年2月に、ガイトナー財務長官は金融機関の不良債権を買いとる最大1兆米ドル規模の官民投資ファンドを設立する意向を表明する等、金融機関支援が進められている。米国消費の低迷は実体経済に大きな影響を及ぼしている。2008年の米国自動車販売台数は1,324万台となり、2007年の1,614万台から大きく減少し、米国自動車メーカーの経営危機が深刻化している。GMやクライスラーに対しては政府による支援(計174億米ドル)が決まり、両社には今後大幅なリストラを含む経営再建が求められている。
こうした困難な経済状況下で、大手企業によるリストラや企業マインドの低下等により、2008年2月には4.8%だった失業率は2009年1月までに7.6%まで上昇するなど、米国労働市場は悪化の一途(いっと)をたどっている。オバマ大統領は、追加的な経済政策として2009年2月17日に7,870億米ドル規模の米国再生・再投資法を成立させ、これにより350万人の雇用の維持・創出が見込まれるとしているが、米国経済は依然として予断を許さない状況が続いている。
日米貿易関係:「摩擦」から「協調」へ
| 「摩擦」から「協調」へ 日米経済関係は、米国の貿易赤字に占める対日比率の低下、投資関係の強化、相互依存関係の深化、WTOによる紛争解決メカニズムの整備等により、かつての摩擦に象徴される関係から建設的な対話を通じた協調の関係へと変ぼう。 |
| 日米貿易 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||