(3)改革の取組
(イ)新ODA中期政策の策定
日本のODA政策は、その理念や原則を記したODA大綱を最上位として、その下に3年から5年の期間を念頭に置いた援助の指針であるODA中期政策、さらに国ごとの援助の指針となる国別援助計画、また分野ごとの援助の実施指針となる分野別政策(分野別イニシアティブ)によって枠組みが定められている。
2003年にODA大綱が改定されたことを踏まえ、各界との意見交換、パブリック・コメント、公聴会を通して広く国民の意見を聴取しつつ、2005年2月に新ODA中期政策を策定した。その内容としては、ODA大綱の基本方針の一つである「人間の安全保障」の視点、重点課題である貧困削減、持続的成長、地球的規模の問題への取組、平和の構築、そして効率的・効果的な援助の実施に向けた方策の各項目をとりあげ、これらの課題に対する日本の考え方やアプローチ、具体的取組について、大綱にのっとってODAを一層戦略的に実施するための方途を示している。また、援助の効率的・効果的な実施に向けた方策として現地機能の強化を打ち出し、具体的には現地ODAタスクフォース (注9) が援助政策の決定過程・実施において主導的役割を果たしていくことを明記した。
(ロ)ODAの更なる改革を目指して
厳しい財政状況を背景にODA予算が減少する中、ODAに対する国民の信頼を回復すべく、外務省は、ODA総合戦略会議の立ち上げ等によるODAの一層の戦略
化・重点化、実施体制の強化、国民参加、情報開示を進めてきた。6月に経済財政諮問会議から「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2005」が出され、ODA事業量の戦略的拡充 (注10) とともに改めてODAの改革が求められたことを契機に、外務省はこれまで以上にODAの点検と改善を進めていくことにした。そこで、ODA総合戦略会議の下に作業部会を設置し、外務省の自主的な取組として報告書「ODAの点検と改善~より質の高いODAを目指して~」をとりまとめ、公表した。本報告書は、(1)戦略的なODA実施のための援助政策の企画、(2)コスト縮減等を通じた事業の効率化、(3)チェック体制の拡充、の3点に焦点を絞り、PDCAサイクルを確立する (注11) ことで、より質の高い成果重視のODAの実施を目指している。具体的改善措置について試行的なものも含めすべて2005年度中に導入することが決定しており(図表「ODAの10の新たな改善措置」参照) (注12) 、今後も恒常的に「点検と改善」に取り組んでいく。また、2006年2月に出された「海外経済協力に関する検討会」の報告書や自民党の報告書「海外経済協力のありかた」では、海外経済協力に関する内閣としての司令塔的な機能を強化するために総理、官房長官、外務大臣、財務大臣、経済産業大臣を常設のメンバーとする「海外経済協力会議(仮称)」を設置するとともに、円借款、無償資金協力、技術協力の実施機能を基本的にJICAに一元化することが提言された。こうした流れを受け、ODAに関する政府全体を通ずる調整の中核の役割を引き続き果たすことになる外務省は、「国際協力企画立案本部」 (注13) 設置や経済協力局と国際社会協力部の多国間開発関連部分の統合・再編などの措置をとる考えである。外務省としては、引き続き国民及び国際社会の期待にこたえる質の高いODAの実施に努めていく。
▼日本のODAの政策的枠組
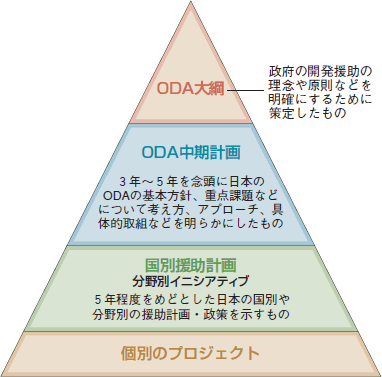
▼ODAの10の新たな改善措置
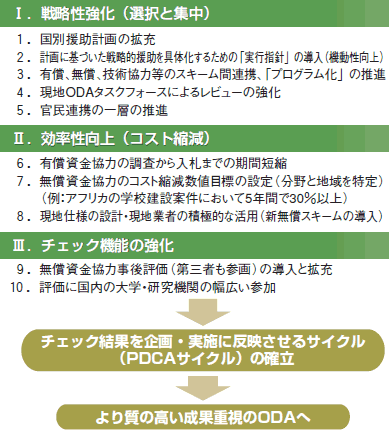
|
