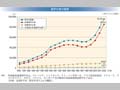第3章 > 第6節 > 1 国際文化交流の推進
【総論】
文化交流は、日本に対する国際的な理解と評価を高めることにより、各国との関係の安定的な発展に寄与するものであり、日本の外交政策の重要な柱である。特に、近年は、情報通信技術(IT)が発展し、メディアや非政府組織(NGO)、それに市民ひとりひとりといった、政府ではない組織や個人の活動が自ら情報発信を行うなど活動が活発になっていることもあり、政府として、日本及び日本外交に対する理解を得るための努力を行うことは、これまで以上に重要になっている。また、米国同時多発テロ以降、異なる文明間における相互理解を深めるため対話を行っていくことの重要性も改めて認識されている。このような基本的な認識の下、日本は、各国の対日理解を深めるため、日本文化、伝統の紹介を通じて日本の魅力と正しい姿を伝えたり、日本語の普及等に積極的に取り組んでいる。また、日本は、有識者・文化人から青少年・市民まで多様なレベルでの人的な交流を推進することによって各国との相互理解を深め、さらに、文化財保存を始めとする国際社会に対する文化的な協力等も重視するなど国際文化交流の推進に力を入れている。
【ワールドカップ・サッカー大会、日韓国民交流年、日中国交正常化30周年記念事業等】
日本は、国際社会における相互理解を深めるため、国際交流基金等を通じて、各国との間で文化交流事業を行っているほか、民間団体が行う文化交流事業を支援している。特に、特別の機会を迎えるいくつかの国との間で文化交流事業を重点的に行う「周年事業」を積極的に行っている。
2002年は日韓国民交流年として、日韓両国によるワールドカップ・サッカー大会の共催を契機に、両国国民の交流を一段と深めるための事業を積極的に行ってきた。具体的には、音楽、演劇等の共同制作から江戸時代の外交親善使節(朝鮮通信使)を再現する市民交流まで、多様な文化交流事業を実施するとともに、草の根交流事業を支援した。また、中国との間では、国交正常化30周年を記念して、日中合作オペラの公演やポップコンサート等種々の文化交流事業を実施した。
2003年は、「日本ASEAN交流年2003」として、東南アジア諸国連合(ASEAN)諸国との間で文化を含む様々な分野での交流事業を通じ、共同体(コミュニティ)意識の強化を図っていく考えである。また、年間を通じて「ロシアにおける日本文化フェスティバル2003」を開催する予定であり、首都モスクワ、建都300周年を迎えるサンクトペテルブルグを始めロシア各地で日本文化を紹介する事業を実施することになっている。さらに、米国との間では2003年から2004年にかけてを日米交流150周年記念の年と位置づけており、両国において関連の交流事業を一層促進させる考えである。
ワールドカップ・サッカー大会への取組

(コラム:ワールドカップ・サッカー大会を通じた国際交流)
【青少年交流・教育】
国際社会の明日を担う若い世代の交流は、将来、日本と各国との間で相互理解を基盤とした友好・協力関係を発展させるにあたって極めて重要であり、日本は、青少年交流や教育の分野における取組を積極的に推進している。
〈JETプログラム(注)〉
2000年に、語学指導等を行う外国青年招致事業(JETプログラム)に関する民間有識者による基本問題検討会が設置され、同プログラムの設立15周年を迎えた2001年には、報告書がまとめられた。現在、同報告書の提言も踏まえ、関係機関と連携しつつ、プログラムを更に充実・発展させ、青少年交流・教育の分野における取組を強化することに努めている。
JET参加者招致人数の推移と参加者の累計

〈留学生交流〉
日本は、日本で学んだという経験を通じて、日本の良き理解者をより多く育成するため、世界中で160を超える元日本留学生会に対する支援や、ホームページの日本留学総合ガイド等を通じた日本留学に関する情報提供等の留学生交流支援を強化している。
〈海外における日本研究・日本語教育〉
海外において、日本の政治、経済、文化、社会について、より深い理解を得るためには、海外での日本研究の促進や日本語の普及を図ることが不可欠である。そのために日本は、日本研究機関の助成、日本語教育専門家の派遣・海外日本語教師の研修、教材寄贈・日本語能力試験等を実施している。
留学生数の推移
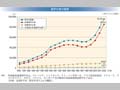
海外の日本語教育の推移

(コラム:JET青年として… 必要とされるありがたさ)
【文化協力】
日本は、開発途上国や国際機関による文化的活動に対して種々の協力を行っている。
開発途上国に対しては、日本は、経済や社会の開発に加えて、文化面での発展も含めた開発途上国の国造りを支援していくため、文化・教育活動のための機材を無償で供与する「文化無償協力」など、積極的な支援を行っている。2000年度からは、NGOに対する支援等、小規模できめ細かな協力を行う草の根文化無償、及び、人類共通の財産である文化遺産を保護するため、その周辺環境を整備するための文化遺産無償を導入し、開発途上国に対する文化協力を一層充実させている。
また日本は、従来から、国連教育科学文化機関(UNESCO)に設置した信託基金を通じ、世界の有形(文化遺跡等)、無形(舞踊・音楽等の伝統芸能、陶芸・漆芸・染色等の伝統工芸等)の文化遺産の保存に積極的に協力している。有形文化遺産に対する協力の代表的な例としては、カンボジア和平・復興の過程で開始されたアンコール遺跡保存・修復事業がある。また、アフガニスタン復興支援の一環として、UNESCOによるバーミヤン遺跡保存事業への支援を開始するため、日・UNESCO合同の調査ミッションを2002年10月現地に派遣した。
無形文化遺産の保存に関しては、文化の多様性が社会・経済の活力の源であるとの認識の下、たぐいまれな価値をもつ無形遺産の継承と発展を図るため、2001年5月、UNESCOは、日本の能楽を含む世界19件の無形遺産を世界無形遺産傑作宣言として発表した。日本は、今後ともUNESCOと協力しつつ、無形文化遺産保護の先進国としての知識・経験をいかし、無形遺産の保存・振興の取組を積極的に支援していく考えである。
なお、2002年、日本は、文化財の不法な国際取引を規制するための国際協力の一環として、「文化財不法輸出入等禁止条約」を締結した(同年12月9日に日本について発効)。

 次頁
次頁