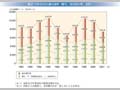第3章 > 第4節 政府開発援助(ODA)
【総論:転機を迎える日本の政府開発援助(ODA)】
2002年、日本のODAは転機を迎えた。2001年9月の米国同時多発テロの発生を受け、国際社会は一致してテロとの闘いに取り組んできた。この中で、特に、アフガニスタンの和平・復興の推進において、平和国家としての日本が果たす役割に対して国際社会の期待が集まり、日本は2002年1月に、東京でアフガニスタン復興支援国際会議を米国、欧州連合(EU)及びサウジアラビアと共に開催し、45億米ドルの支援を集めた。5月には、川口外務大臣がアフガニスタンを訪問したが、その際、アフガニスタンに対し、訪問に先立ち発表した「平和の定着」構想を説明し、その具体的な支援策として「平和のための登録(Register for Peace)」(注)を提唱した。こうした取組は、日本のODAが、紛争中や紛争直後における支援に対して、より積極的にかかわっていく転換点となった。
2002年には、国際社会による国際テロ対策の強化等も背景として、世界の各地において、紛争の解決に向けた動きが見られるようになった。こうした流れの中、特にアジアにおいて、日本は「平和の定着」に向けて積極的に取り組み各国の高い評価を受けた。スリランカにおける紛争解決に向けた動きに対しては、日本は、明石元国連事務次長をスリランカの平和構築及び復旧・復興に関する政府代表に任命し、和平プロセスに積極的に関与しており、2003年1月には、川口外務大臣も現地を訪問した。日本は、この中で、和平交渉の一つを日本で開催し、復興支援会議を日本が主催する意図を有していることを表明した。また、1998年のスハルト政権崩壊以降、独立アチェ運動(GAM)による分離独立運動が活発化し、政府との間で武力衝突が頻発してきたインドネシアのアチェについても、主要国代表を含む関係者を12月に東京に招聘〔しょうへい〕し、和平に向けて重要な会議を開催した。また、紛争により多大な影響を被り開発が遅れているフィリピン・ミンダナオ地域における貧困の削減と平和の定着に貢献するため、日本は2002年12月のアロヨ大統領訪日の際に、「平和と安定のためのミンダナオ支援パッケージ」を発表した。
平和の定着への取組により、ODAへの国民参加が一層促進された。特に、アフガニスタンでは、日本政府の支援の下、日本のNGOが、難民支援やその他の人道支援等の分野で、欧米のNGOと肩を並べて活躍している。医師や教師等の日本人専門家が現地に派遣され、国造りに直接携わっている。また、日本の官民の援助関係者が多数アフガニスタンに入って活躍している。日本政府も、従来慎重であった治安分野(警察)の支援や、武装解除・動員解除・社会復帰(DDR)(注)の分野の支援も積極的に進めている。
一方で、2002年には、開発に関する国際社会の潮流と日本の国内情勢との間に大きな乖離〔かいり〕が見られた。近年、G8サミットを始めとする主要国際会議の議題の多くは開発問題となっているが、米国同時多発テロ以降、その傾向は更に強まっている。2002年3月にメキシコのモンテレーで開催された開発資金国際会議では、冷戦終結以来、いわゆる「援助疲れ」に陥っていた欧米諸国が、一転、大幅な援助増額を打ち出した。そのような中で、日本の国内では、厳しい経済・財政状況を反映して、2002年度のODA予算は対前年度比10.3%減となり、ODAは5年間で2割以上削減されることになった。このような状況に対し、来日する多くの外国政府の閣僚や国際機関の長は、日本のODAが今後とも実質的役割を果たすよう期待を表明した。
ODAが置かれたこのような状況を打開するため、2002年には、効率性、透明性、そして戦略性を旗印に大胆なODA改革が推進された。6月には、「ODA総合戦略会議」が立ち上げられ、7月には「ODA改革・15の具体策について」を発表し、監査や評価が抜本的に強化された。また、ODAタウンミーティングやODAメールマガジンが創設された。11月には、国際協力事業団(JICA)を独立行政法人に移行させるための法案が成立した。12月には、1978年以来25年間続いてきた債務救済無償が廃止され、日本が後発開発途上国などに対して有する対象債権は放棄されることが発表され、また、改革の集大成として、2003年中ごろをめどに、ODA大綱を見直す方針が発表された(ODA改革の詳細については、第4章第1節に記述)。
最近10年のODA額の推移(贈与、政府貸付等、合計)
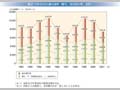
外務省とNGOとのパートナーシップ

(コラム:緊急人道支援、相次ぐプラン変更 ~アフガニスタン、南部アフリカのケースから~)
【2002年の重点地域・分野】
川口外務大臣は、日本のODAの戦略性を高めるため、アジア地域、人間の安全保障、そして平和の定着を重点とすることを提唱している。
〈アジア地域〉
アジア地域は、日本のODAの最重点地域である。2001年には二国間援助の半分以上に当たる42.2億米ドル(約56.6%)がアジア地域に供与された。
東南アジアにはアジア地域向けODAの6割が供与されている。2002年には、東南アジア諸国との連携が一段と深まった。1月、小泉総理大臣は東南アジア諸国連合(ASEAN)諸国を訪問し、日・ASEAN包括的経済連携構想を提唱した。その一環として日本は、8月には、ASEAN諸国及び日中韓の13か国による東アジア開発イニシアティブ(IDEA)閣僚会合を東京で開催した。IDEAは、東アジアの開発に関する協力の場であると同時に、東アジアが自らの開発モデルを世界に発信する初めての試みでもある。同会合において、参加国の共通認識が閣僚共同声明の形で表明された(注)。
中国に対するODAについては、日本の厳しい経済・財政事情や中国の国力の増大を背景とした日本国内の厳しい批判等を踏まえ、そのあり方について見直しを行い、2001年10月、対中国経済協力計画を策定した。同計画に基づき、2001年度対中国円借款について、重点分野との整合性などを総合的に検討した結果、規模は前年度比約25%の減額となり、また、その半分以上(約54%)が環境分野を対象とした案件となった。
南西アジアについては、1998年の核実験以来、インド及びパキスタンに対して行ってきた経済措置を2001年10月に停止した。2002年には、テロとの闘いに取り組むパキスタンを支援するため、同国に対する3億ドルの無償資金協力の供与を約束(コミット)し、順次実施している。インドについては、2003年1月の川口外務大臣訪問に際し、約1,100億円の円借款案件を供与する方針を伝えた。インドは、再び日本のODAの上位受取国となる見込みである。また、スリランカでは和平交渉の進展に資するよう同国北部に向けた支援を行っている。
最近10年のODA地域配分の推移

〈人間の安全保障〉
教育や感染症といった基礎生活分野の支援は、個人のもつ豊かな可能性を実現するために、人間の生存・生活・尊厳に対する脅威から各個人を守ろうという人間の安全保障に直接かかわっている。
●地雷
対人地雷は、人道的な観点のみならず、紛争後の復興と開発の観点からも重大な問題である。日本は、1997年、対人地雷禁止条約署名に際し、地雷除去及び犠牲者支援に関し、2002年までの5年間をめどに100億円程度の支援を行うことを表明した。日本は、これまでにカンボジアやボスニア・ヘルツェゴビナ、アフガニスタン、アンゴラ等において支援を行い、2002年10月末までにその目標を達成した。2001年度には58億円のODAを地雷分野の支援に供与した。
また、草の根無償資金協力案件において、これまで日本からの地雷除去機等の機材調達は、武器輸出三原則との関係で認めてこなかったが、論点を整理し、2002年8月にはこれを可能とする決定を行った。
●教育
世界には依然として1億1,500万人の未就学児童及び8億6,000万人の成人非識字者がおり、それらの約3分の2が女性である。2000年4月の世界教育フォーラムを契機に、「万人のための教育(EFA:Education for All)」の推進が国際的な流れとなり、ミレニアム開発目標(MDGs)(注)においても基礎教育の普及が主要な目標とされている。日本も2001年にODAの7.3%に当たる8.7億米ドルを教育分野の案件に供与している。
2002年6月、日本は、G8カナナスキス・サミットに際し、低所得国に対する教育分野のODAを向こう5年間で2,500億円以上供与することなどを内容とする「成長のための基礎教育イニシアティブ」を発表した。
●感染症対策
毎年300万人が死亡し、国境を越えて広がりを見せるHIV/AIDS等の感染症は、単なる個人の健康上の問題にとどまらず、国際社会にとって政治・経済・社会上の脅威となっている。このような認識の下、2001年に、日本は保健・医療分野(人口計画、リプロダクティブ・ヘルスを含む)に対して、ODAの2.6%に当たる3.1億米ドルを拠出している。
2000年のG8九州・沖縄サミットの際、沖縄感染症対策イニシアティブとして感染症対策支援や公衆衛生の増進等に5年間で30億米ドルをめどとする協力を行うことを打ち出し、2001年度までの2年間に18億米ドルを拠出している。このうち、日本は、2001年のG8ジェノバ・サミットで設立された世界エイズ・結核・マラリア対策基金(GFATM)に対し、2億米ドルの拠出を表明し、2002年までに8,000万米ドルを拠出している。
〈平和の定着に向けた取組(アフガニスタン支援)〉
紛争後の地域においては、食糧援助、住居修復等、地域住民の当面の生活環境を整える緊急の人道・復旧支援を行うと同時に、その後の「国造り」を支援するため、経済・社会開発のみならず、国家としての統治能力の育成をも含めた複合的な支援を行う必要がある。日本は、2002年1月の復興支援国際会議を皮切りとするアフガニスタン支援を一つの契機として、人道・復旧から「国造り」まで切れ目のない援助を実施するため、ODAを積極的に活用している。
川口外務大臣は、2002年5月のアフガニスタン訪問に際して、同国の和平プロセス、国内の治安、復興・人道支援の三つの要素からなる「平和の定着」を支援していく方針を表明し、以降、日本はこの構想に基づいてアフガニスタン支援を実施している。
ボン合意に基づく和平プロセスを支援するため、日本は、2002年6月に開催された緊急ロヤジルガの開催を支援するとともに、会議の模様をテレビでアフガニスタン国民に伝えるための技術支援及び機材提供を行った。さらに、財政基盤のないカルザイ政権を支援するため、新たな試みとして、従来実施してこなかった行政経費支援(注1)や公用車の供与を行った。
国内の治安については、軍閥や兵士の武装解除・動員解除・社会復帰(DDR)が重要な課題となっており、日本は、川口外務大臣が提唱した「平和のための登録(Register for Peace)」構想を踏まえ、国連アフガニスタン支援団(UNAMA)と共に、除隊兵士の社会復帰支援プログラムを策定するなど、参加するドナーのとりまとめ役として活動している。日本は、2003年2月のカルザイ大統領訪日の際に本プログラムへの支援を表明した。また、地域住民の安全を確保し、開発を円滑に進めるため、地雷除去等の対人地雷対策活動を支援しているほか、麻薬対策への支援や文民警察再建のための支援も検討している。
復興・人道支援については、国連開発計画(UNDP)が実施する雇用創出プロジェクト(REAP)を支援するとともに、同プロジェクトと連携して国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)等が実施する難民・避難民の再定住化、さらには地域総合開発をする「緒方イニシアティブ」(注2)を推進している。また、日米首脳間で合意した首都カブールと南部の主要都市カンダハルを結ぶ幹線道路建設のほか、農業復興、教育、保健・医療等の分野においても積極的に支援を行っている。

 次頁
次頁