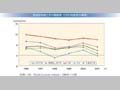第2章 > 第1節 > 2 中国とその近隣諸国・地域
【総論】
2002年は日中国交正常化30周年にあたり、両国において「日本年」「中国年」を記念する一連の行事や交流活動が行われ、両国国民間の相互理解と相互信頼が深まった。また、2001年末の中国の世界貿易機関(WTO)加盟を経て、日中間の経済関係も、拡大と深化を続けており、2002年の貿易総額は1,000億米ドルの大台を突破し、史上最高額を更新した。
日中間の相互依存関係は深化の方向にあり、中国との間で安定した友好協力関係を築いていくことは、日本の安全と繁栄の確保にとって極めて重要である。国際社会の中で大きな影響力を有している日中両国は、単に二国間の利益を図るのみならず、アジア太平洋地域、ひいては国際社会の平和・安定と繁栄を実現するため、互いに協力していくことが求められている。
こうした点を踏まえ、日本は、日中関係を最も重要な二国間関係の一つとして重視しており、「平和と発展のための友好協力パートナーシップ」(注)の下、様々な分野における協力を一層推進していくこととしている。例えば、両国の首脳・外相レベル等の会談でも、二国間の問題に加えて、朝鮮半島情勢等の地域情勢、環境問題等の地球規模の問題について積極的に意見交換を行っている。
今後とも、日本は、日中両国関係の基礎を一層堅固なものとしていくとともに、国際社会における協力関係を一層強化していくことによって、国際社会の平和・安定と繁栄の実現に向けて貢献していく考えである。
【日中関係】
〈総論〉
日中国交正常化30周年にあたる2002年、両国間で幅広いレベルの交流が活発に行われた。様々な国際会議の機会をとらえて、首脳・外相会談が行われたほか、9月には川口外務大臣が中国を訪問し、江沢民〔こうたくみん〕国家主席、銭其 〔せんきしん〕副総理、唐家
〔せんきしん〕副総理、唐家 〔とうかせん〕外交部長等と有意義な会談を行った。こうした会談等を通じ、両国間に存在する個々の問題につき、解決の糸口が見出されてきたほか、両国間の問題に加え地域・国際情勢の問題について積極的な意見交換が行われた。
〔とうかせん〕外交部長等と有意義な会談を行った。こうした会談等を通じ、両国間に存在する個々の問題につき、解決の糸口が見出されてきたほか、両国間の問題に加え地域・国際情勢の問題について積極的な意見交換が行われた。
一方で、2002年4月及び2003年1月の小泉総理大臣の靖国神社参拝に対しては中国より抗議があり、2002年10月の第10回アジア太平洋経済協力(APEC)首脳会合の際に行われた日中首脳会談でも江沢民主席より不満が表明されている。
〈「日本年」「中国年」の実施〉
2002年は、日中両国において「日本年」「中国年」を記念する一連の行事や交流活動が実施された。「日本年」「中国年」開幕レセプションが東京において盛大に開催され、小泉総理大臣や李鵬〔りほう〕全人代常務委員長等が出席した。その後、中国から5,000人の訪日、日本から1万3,000人の訪中が実現、日中合作オペラ「蝶々夫人」、日本の著名ミュージシャンによるコンサート等、数多くの交流事業・記念事業が行われた。1万3,000人の日本人の訪中の際の交流式典では、江沢民国家主席が演説し、日中友好関係の強化及びアジア地域の繁栄のための日中間協力の重要性が強調された。
〈日中経済関係〉
2002年の日本と中国の経済関係は、中国の順調な経済発展及び2001年12月の中国のWTO加盟等を背景に大きな進展が見られた。2002年の貿易総額は、好調な対中輸出の増加(対前年比32.3%増)を背景に、対前年比15.0%増加し、12兆7,043億円(約1,016億米ドル)を記録した。中国は米国を抜き、最大の対日輸出国となり(輸出入総計では第2位の貿易相手国)、日本は中国にとって第1位の貿易相手国である。対中投資は、2002年度上半期、契約ベースで1,132億円(約9億米ドル)と、対前年度同期比で23.2%の伸びを示した。(注1)
一方、中国の急速な経済発展及び日中経済関係の緊密化に伴い、一部摩擦も生じている。この点につき、小泉総理大臣は4月のボアオ・アジアフォーラム(注2)において講演し、中国の経済発展は、日本にとって「脅威」ではなく、「挑戦」、「好機」であり、日中経済関係は、「対立」ではなく、「相互補完関係」にあるとの考えを表明した。また、同フォーラムの機会に行われた小泉総理大臣と朱鎔基〔しゅようき〕総理との会談では、両国間の経済問題の早期発見及び紛争の未然防止を図るとともに、両国経済の相互補完関係を一層強化していくことを目的として、日中経済パートナーシップ協議の設立につき合意した。これを受け、第1回会合(次官級)が、10月15日に北京で開催され、模造品被害等の知的財産権問題、対中投資に関連したビジネス上のトラブル、中国による鉄鋼セーフガード措置発動、中国産農産物の残留農薬問題などの懸案につき率直な意見交換が行われた。
〈北朝鮮工作船の引揚げ〉
2001年12月に発生した九州南西海域不審船事案(注3)については、同船の沈没地点が、事実上、日本が中国の排他的経済水域として扱っている海域であったことから、その引揚げにつき中国との間で調整をしつつ、適切に対処する必要があった。4月のボアオ・アジアフォーラムの機会に行われた小泉総理大臣と朱鎔基総理との会談で、本件について、両国間の冷静な話合いを通じて解決していくことで一致した。その後、中国との間で継続的な協議を実施した結果、6月18日、日中両国は同船の引揚げに関する口上書を交換し、翌19日にタイにおいて開催された日中外相会談で本件の決着につき確認した。同船の引揚げ作業は、6月25日から9月14日にかけて成功裏に実施され、工作船事案の真相解明に向けて大きなステップとなった。
〈在瀋陽日本総領事館事件〉
5月8日、北朝鮮人5名が在瀋陽日本総領事館への入館を試み、中国の武装警察官に拘束・連行されるという事件が発生した。日本は、中国の武装警察官が日本の同意なく同総領事館に立ち入ったことは公館の不可侵に反するものであるとして、強く抗議を行うとともに、入館を試みた5名の人道上の要請が満たされることが最優先であるとの申入れを累次にわたって行った。その結果、中国に拘束されていた5名の出国が認められ、5月23日、同5名はフィリピンのマニラ経由で韓国へ出国した。
6月及び7月に、それぞれタイ及びブルネイで行われた川口外務大臣と唐家 外交部長との会談において、川口外務大臣より、本件に関する日本の立場に変化がないことを改めて指摘の上、日中両国は、再発防止のため、両国外交当局間の協議を行っていくことで一致した。これを受け、日中間の領事協力の枠組みに関する第1回協議が8月末に北京で、第2回協議が2003年1月に東京でそれぞれ行われ、類似事件の再発防止を含む日中間の領事分野の協力について建設的な話合いを行った。
外交部長との会談において、川口外務大臣より、本件に関する日本の立場に変化がないことを改めて指摘の上、日中両国は、再発防止のため、両国外交当局間の協議を行っていくことで一致した。これを受け、日中間の領事協力の枠組みに関する第1回協議が8月末に北京で、第2回協議が2003年1月に東京でそれぞれ行われ、類似事件の再発防止を含む日中間の領事分野の協力について建設的な話合いを行った。
日本の対中政府開発援助(ODA)実績

〈対中経済協力〉
日本は、1979年以来、中国に対して政府開発援助(ODA)を実施し、中国の改革・開放政策を支援してきたが、中国の経済発展に伴って中国自身の援助需要が変化したほか、環境問題など日本にも直接の影響が及ぶ事項が増加してきた。また、日本の厳しい経済・財政事情、中国の軍事費増大や中国の第三国援助などを背景とする日本国内の厳しい見方も踏まえ、2001年10月、日本は対中国経済協力計画を策定し、新たな対中援助方針を打ち出した。この計画に基づき、2001年度対中国円借款について、重点分野との整合性等を総合的に検討した結果、案件の半分以上が環境分野を対象としたものとなり、また、規模は対前年度比約25%の減額となった。今後とも、対中国経済協力計画で掲げられている環境分野への対応、内陸部の民生向上・社会開発、相互理解の増進等の重点分野への支援を一層重視するとともに、国民の支持と理解を得つつ、対中ODAを実施していく方針である。
【中国情勢】
〈内政〉
現在の中国は、経済建設を最優先課題として取り組んでいることもあり、比較的安定した政権運営が行われている。そのような中、2002年の中国内政は、11月に行われた中国共産党第16回全国代表大会(党大会)(注)を軸に展開した。
3月に行われた第9期全国人民代表大会(全人代)(注1)第5回会議において、朱鎔基総理は、「本年は非常に重要な1年」と指摘し、 内需拡大策(国債発行や農民を含む低所得者層の所得増加を図る施策)による経済成長、
内需拡大策(国債発行や農民を含む低所得者層の所得増加を図る施策)による経済成長、 WTO加盟に伴う産業構造調整、
WTO加盟に伴う産業構造調整、 反腐敗闘争の継続、
反腐敗闘争の継続、 「三つの代表」思想(注2)の徹底した実践等を図ることを表明したが、それは中国が直面している問題に対する当面の取組姿勢を示すものであった。
「三つの代表」思想(注2)の徹底した実践等を図ることを表明したが、それは中国が直面している問題に対する当面の取組姿勢を示すものであった。
第16回党大会は、11月8日から14日にかけて開催され、中央委員の選出や党規約の改正等が行われた。同大会では、江沢民総書記が開幕日に行った政治報告を、江沢民総書記時代の「13年間の偉大な実践の総括」として高く評価するとともに、経済建設と安定・団結を最重点・最優先とした国家運営を引き続き推進するとの基本方針に変更がないことを明らかにした。
また、同大会では、党規約修正案(注3)が採択された。修正党規約においては、中国共産党の指導指針として、江沢民総書記が提唱した「『三つの代表』という重要思想」が新たに盛り込まれた。また、中国共産党を「労働者階級の前衛」であるとともに、「中国人民と中華民族の前衛」として位置づけ、入党資格として新たに「その他の社会階層の先進的分子」を加えて私営企業主など現在の中国経済の発展を担っている社会層の共産党入党を正式に容認することになった。これは、これまで「労働者階級の前衛党」であった中国共産党が「国民政党」へ本質的に転換していく道を開いたものと言える。
続く11月15日に行われた第16期中央委員会第1回全体会議(一中全会)(注1)では、胡錦濤〔こきんとう〕氏が江沢民氏に替わり党総書記に選出されたほか、新たな中央政治局常務委員(注2)として胡錦濤、呉邦国〔ごほうこく〕(副総理)、温家宝〔おんかほう〕(副総理)、賈慶林〔かけいりん〕(前北京市党委書記)、曾慶紅〔そうけいこう〕(前党中央組織部長)、黄菊〔こうぎく〕(前上海市党委書記)、呉官正〔ごかんせい〕(山東省党委書記)、李長春〔りちょうしゅん〕(広東省党委書記)、羅幹〔らかん〕(国務委員)の9名が選出され、新体制が発足し、2003年3月の第10期全国人民代表大会第1回会議では、胡錦濤総書記が国家主席に就任し、新体制が始動することになった。なお、江沢民氏については、党中央軍事委員会主席への留任が決定されており、「三つの代表」思想とあわせ、同人の政治的影響力が依然温存される形となっている。
中国共産党旧指導部・新指導部比較一覧表

〈経済〉
中国経済は、改革開放政策に転じて以来、これまで24年間に年平均の実質国内総生産(GDP)成長率が約9.6%の高成長を達成し、GDP規模(2001年名目)も世界第6位(米国、日本、ドイツ、フランス、英国に次ぐ)になるなど急成長を遂げた。
2002年3月の第9期全国人民代表大会第5回会議において、年7%程度の経済成長を目指す方針が示されたが、最終的に目標を上回る8.0%の経済成長を達成した。
11月に開催された党大会では、2020年のGDPを2000年の4倍増にするとの新たな経済成長の目標が提示された。このためには、今後20年にわたり、年平均7%程度の経済成長を維持することが必要となる。また、党大会において、私営企業主等が中国共産党へ入党する道も正式に開かれ、中国経済の牽引役としての地位を向上させつつある。
このように順調な経済成長を続ける一方で、国民1人当たりGDPは911米ドルに過ぎず、国際社会の中でも低いレベルにとどまっている。都市と農村、沿岸部と中西部、都市内部の経済格差、産業構造(特に、農業、国有企業、金融の各分野)の転換、就業圧力の高まり、環境保全と経済成長の両立等、中国は依然として多くの深刻な課題に直面している。
高成長を続ける中国経済(GDP成長率の推移)
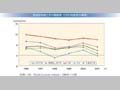
〈対外関係〉
中国は、最優先課題である持続的な経済発展を可能とするため、良好な国際環境を求めており、米国、ロシア等の大国との関係発展、近隣諸国との協力強化及び国際的な枠組みへの積極的参画等の全方位外交を展開している。
米中関係は、2月のブッシュ大統領訪中に続き、10月下旬には江沢民国家主席が訪米するなど、基本的に良好に推移した。米中両国は首脳外交を軸に引き続き建設的協力関係の促進を図っている。10月25日に行われた米中首脳会談では、イラク問題、北朝鮮問題が優先議題とされ、また、同会談を機に、ミサイル技術等の拡散、人権、軍事交流等の米中間の懸案事項について、米中対話の実施等の進展が見られた。
中露関係では、2001年に締結された中露善隣友好協力条約(注1)の下に協力関係を発展させている。12月には、プーチン大統領が訪中し、中国の新たな指導部とも意思疎通を図るとともに、今後の中露関係の発展の方向を示す共同声明を発出した。
近隣諸国との関係では、韓国との間で国交10周年を記念する活動を行ったほか、2月には江沢民主席がベトナムを訪問した。また、11月の中国・東南アジア諸国連合(ASEAN)首脳会議の際には「包括的経済協力のための中国・ASEAN枠組み協定」(注2)に署名するなど、近隣諸国との間で良好な関係を維持している。さらに、中国がメンバーとなっているASEAN地域フォーラム(ARF)、アジア太平洋経済協力(APEC)、ASEAN+3、上海協力機構(SCO)(注3)等の地域協力の枠組みにも積極的に参画している点が注目される。
【香港】
2002年に返還5周年を迎えた香港では、一国二制度(注4)が基本的に順調に機能している。董建華〔とうけんか〕香港特別行政区(SAR)長官は、2月に、第2期行政長官に無投票で再選を果たした。4月には、立法会にて政府高官任命制(注5)を発表、6月に同制度の政府高官人事が発表され、7月1日より実施された。
香港経済は、アジア通貨・金融危機に伴う景気後退から脱却したものの、2001年の米国経済の減速等の影響を受けマイナス成長が続いた。その後、わずかながら回復が見られたが、不動産市況の回復、デフレ基調及び高失業率の改善等が依然として課題として残されている。
日本と香港の要人往来については、2002年8月、松浪外務大臣政務官が香港を訪問し、梁錦松(アントニー・リョン)財務庁長官と会談したほか、11月には曾蔭権(ドナルド・ツァン)政務庁長官が訪日し、福田官房長官、川口外務大臣等を表敬した。
【台湾】
台湾では、2000年5月に民進党・陳水扁〔ちんすいへん〕「政権」が誕生し、50年以上「政権」の座にあった国民党が下野した。民進党「政権」は当初、少数与党として苦しい政局運営を強いられたが、2001年12月の「立法院」選挙において、民進党が国民党を抑え第一党となり、李登輝〔りとうき〕前「総統」が支持する台湾団結連盟と組んで、現在、与野党はほぼ拮抗状態にある。
台湾経済は、2001年には、情報通信技術(IT)関連産業の不況や米国の景気減速等の影響を受けて、年間成長率はマイナス2.18%であったが、景気は底を打ったと見られており、2002年の経済成長率は3.54%に回復した。なお、台湾は独立関税地域として、2002年1月1日にWTOに正式加盟した。
両岸関係については、2002年8月に、陳水扁「総統」が「中国と台湾は別々の国(一辺一国)」と発言し、これに対して中国が強く反発するなど、「一つの中国」をめぐる中台双方の立場の隔たりが依然として大きく、2002年も両岸対話は再開されなかった。一方で、両岸間の経済交流はますます増大しており、その中で、直接の通商、通信、通航を行う「三通」の検討が進められている。なお、2003年1月には春節(旧正月)期間中に、大陸に進出している台湾ビジネスマンの台湾帰省の便宜を図るため、台湾の航空会社による「春節チャーター便」(香港、マカオ経由)が中国当局から許可され、台湾の旅客機が中国内の空港に初めて乗り入れることになった。
日本と台湾の関係については、1972年の日中共同声明に従って、非政府間の実務関係として、民間及び地域的な往来を維持している。日本にとって台湾は緊密な経済関係を有する重要な地域であり、台湾は日本の貿易相手先として、総額で米国、中国、韓国に次ぐ第4位となっている。
両岸関係については、日本は、当事者間の直接の話合いを通じて平和的に解決されることを強く希望しており、そのために、両岸対話が早期に再開されることを期待していると累次表明している。
【モンゴル】
2002年は、モンゴルとの外交関係樹立30周年にあたり、皇族として初めてとなる秋篠宮同妃両殿下のモンゴル訪問、トゥムルオチル国家大会議議長及びエルデネチョローン外相の訪日といった要人往来、文化交流が盛んに行われた。
日本は、モンゴルにおける民主化と市場経済化の成功は北東アジア地域の平和と安定に寄与するとの認識の下、モンゴルの改革努力を一貫して支援しており、今後とも、両国間の総合的パートナーシップを一層強化していく考えである。
内政面では、安定した政局を背景に、史上初めて、土地の私有化法案が成立し、経済面でも3.7%(速報値)のプラス成長を維持している。現政権は、2002年を外国投資誘致年として、投資セミナーの開催や外国投資法改正を行い、外資導入を図った。
外交活動については、バガバンディ大統領の欧州訪問、エンフバヤル首相の米国、中国、東南アジア訪問やカシヤノフ露首相、白南淳〔ペクナムスン〕北朝鮮外相のモンゴル訪問等が行われた。

 次頁
次頁 〔せんきしん〕副総理、唐家
〔せんきしん〕副総理、唐家 〔とうかせん〕外交部長等と有意義な会談を行った。こうした会談等を通じ、両国間に存在する個々の問題につき、解決の糸口が見出されてきたほか、両国間の問題に加え地域・国際情勢の問題について積極的な意見交換が行われた。
〔とうかせん〕外交部長等と有意義な会談を行った。こうした会談等を通じ、両国間に存在する個々の問題につき、解決の糸口が見出されてきたほか、両国間の問題に加え地域・国際情勢の問題について積極的な意見交換が行われた。 外交部長との会談において、川口外務大臣より、本件に関する日本の立場に変化がないことを改めて指摘の上、日中両国は、再発防止のため、両国外交当局間の協議を行っていくことで一致した。これを受け、日中間の領事協力の枠組みに関する第1回協議が8月末に北京で、第2回協議が2003年1月に東京でそれぞれ行われ、類似事件の再発防止を含む日中間の領事分野の協力について建設的な話合いを行った。
外交部長との会談において、川口外務大臣より、本件に関する日本の立場に変化がないことを改めて指摘の上、日中両国は、再発防止のため、両国外交当局間の協議を行っていくことで一致した。これを受け、日中間の領事協力の枠組みに関する第1回協議が8月末に北京で、第2回協議が2003年1月に東京でそれぞれ行われ、類似事件の再発防止を含む日中間の領事分野の協力について建設的な話合いを行った。
 内需拡大策(国債発行や農民を含む低所得者層の所得増加を図る施策)による経済成長、
内需拡大策(国債発行や農民を含む低所得者層の所得増加を図る施策)による経済成長、 WTO加盟に伴う産業構造調整、
WTO加盟に伴う産業構造調整、 反腐敗闘争の継続、
反腐敗闘争の継続、 「三つの代表」思想(注2)の徹底した実践等を図ることを表明したが、それは中国が直面している問題に対する当面の取組姿勢を示すものであった。
「三つの代表」思想(注2)の徹底した実践等を図ることを表明したが、それは中国が直面している問題に対する当面の取組姿勢を示すものであった。