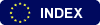| (1) |
二輪車・商用車の車両形式認証制度(WVTA)の創設
現在、WVTAは乗用車及び二輪車について適用されているが、商用車については、いまだ本制度の適用がなされていない。2001年8月の欧州委員会回答によれば、商用車への本制度の適用については、2001年中に理事会及び欧州議会へ提案する旨述べられているが、早急に実施細目を定めて制度の運用を開始するよう引き続き要望するとともに、適用開始までのスケジュールの明示を求める。
|
| (2) |
車両型式認証制度(WVTA)におけるECE規則13Hの採用
ECにおいて、ECE規則13Hが採用されたことを評価する。しかし、今後、本規則がWVTAにおいて使用可能となるためには、自動車の型式認定に係るEU指令(指令1970/156/EECのANNEXⅣ)に同規則を追加する作業が必要である。2001年8月の欧州委員会回答によれば、同規則の採用手続き終了後、直ちに同指令に同規則を追加する旨述べられているが、未だ同指令の改正は行われていないと聞いている。ついては、同指令改正の早期実施及び改正スケジュールの明示を要望する。
|
| (3) |
歩行者保護法規
歩行者保護基準についてはEUが独自に作業を進めているが、国際研究調和プロジェクト(IHRA)の枠組みの中で、日本、米国などとも歩調を合わせたうえで調和基準を策定するよう要望する。
|
| (4) |
ELV(End of Life Vehicles:廃自動車)指令
2001年8月の欧州委員会回答によれば、前回、我が方が要望していた使用禁止物質に関する現行の適用除外リストの拡充に関しては、明年開催予定の廃棄物規制に関する規制委員会で優先的に検討する旨述べられているが、現行の適用除外リストは、代替不可能と考えられる物質が網羅されておらず、不十分であると思われるため、引き続き適用除外リストの拡充を要望する。
また、先般、JAMA(日本自動車工業会)及びACEA(欧州自動車工業会)が、適用除外リストへの追加希望物質を明記した意見書を共同作成し、欧州委員会に提出した旨聞いているが、今後、適用除外リストの拡充を検討するにあたっては、この意見書の内容を十分尊重するよう要望する。
|
| (5) |
運転視界に関する国際調和基準策定に向けた日EU間の協力★
現在、我が国においては、自動車の運転者からの視界に関する安全基準の策定を検討中であるが、EUにおいても、同様の検討がなされていると聞いている。
我が国は、同安全基準について、自動車の安全性の向上及びと自動車基準の国際調和促進の一環として、グローバル協定(the1998 Global Agreement)に基づく、世界的技術規則(Global Technical Regulations)を策定していくことが望ましいと考えている。ついては、今後、本件に関し、日EU共同で世界的技術規則の策定を行うことの可能性について早期に意見交換を開始し、より一層の基準調和を図ることにつき、EUの協力を要請する。 |