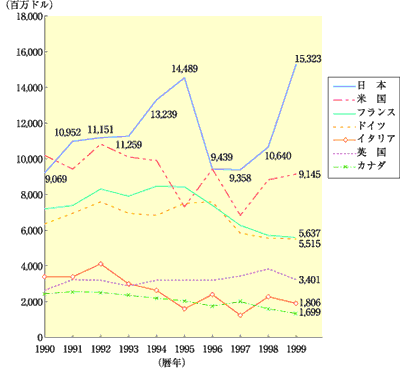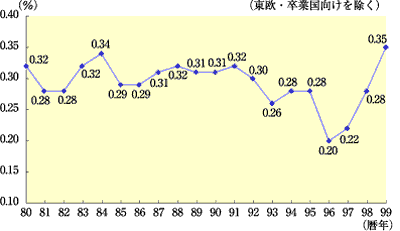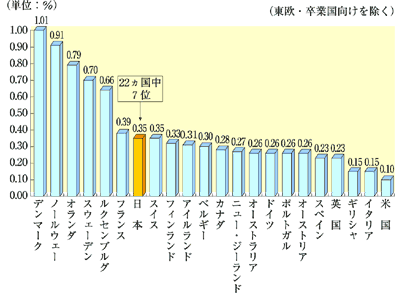20世紀後半は、史上例を見ないほど開発が進みその成果が達成された時代である。例えば、人間の生命・生活に係わる指標を見た場合、途上国における平均余命は1970年の55歳から98年には65歳に上昇したほか、同期間の幼児死亡率は新生児1,000人中107人から59人へ低下し、成人識字率も53%から70%へ向上している(注1)。特に、東アジアにおいては、その大半の国でこの20年の間に貧困の割合が半分以下に低減したと見られる(注2)。因みに、アジア・太平洋地域全体では、91年から98年の間の国内総生産(GDP)成長率は平均8.5%を示している(注3)。
そうした成果にもかかわらず、途上国を中心とする人口の急速な増加に伴い、貧困人口は減少せず、現在でも世界の総人口約60億人のうち12億人が1日1ドル以下、また、30億人近くが1日2ドル以下の生活をしている。サブ・サハラ・アフリカ(サハラ以南のアフリカ。以下、アフリカ)においては、同じ期間に貧困層が7,400万人増加し、98年における同地域の貧困人口は2億9,100万人と見られている(注4)。また、急速に貧困削減が進んだとは言え、中国においても、未だにおよそ2億2,500万人が1日1ドル以下で生活していると推計されている(注5)。
加えて、近年、グローバル化の進展は新たな開発課題を浮き彫りにしている。97年のアジア通貨・経済危機は、目覚ましい経済成長を遂げた東アジア諸国が、グローバル化の下での世界経済への適応、貧困層を含めた衡平な成長の実現、統治(ガヴァナンス)のあり方(注6)といった側面で未だに脆弱性を抱えていることを示す結果となった。アジア通貨・経済危機により、東アジアにおける近年の貧困人口の急速な削減傾向にも歯止めがかかった。また、貧困、紛争、感染症、統治(ガヴァナンス)の欠如が悪循環となり、グローバル化の利益を享受できないでいる途上国、なかんずくアフリカ諸国の状況は看過できない。更に、地球温暖化などの地球環境問題、組織犯罪、麻薬等の地球規模問題は、途上国、先進国双方に等しく悪影響を及ぼすものであり、国際社会が一致して取り組む必要がある。
相互依存関係が深まる今日、世界全体の繁栄は途上国の繁栄と不可分の関係にあることから、途上国の持続可能な開発を達成するために、先進国、途上国、NGO等を含む国際社会全体が連携・協力してこれに取り組む必要性は大きい。このような観点から、2000年7月に開催された九州・沖縄サミットにおいても、途上国の開発が主要なテーマの一つとして取り上げられた。日本は、G8の議長国として、また主要援助国としての立場から、感染症や情報格差(デジタル・ディバイド)、教育、債務問題など開発を巡る様々な問題を積極的にサミットの重要課題として取り上げるなど指導力を発揮して、国際的に高い評価を得た(第3部「主要援助国としての日本の課題別取り組み」参照)。