第1章 変わりつつある国際環境の下でのODAの役割

ベトナムで建設中のサイゴン東西ハイウェイのトンネルを眼下に望むホーチミン市街(写真:永武ひかる/JICA)
第1節 グローバル経済の中の途上国とODA
日本が開発途上国に対する技術協力を開始してから、2014年10月で60周年を迎えます。これまでに日本は169か国、20地域に対する二国間支援に加え、世界銀行やアジア開発銀行(ADB)などの国際開発金融機関、国連開発計画(UNDP)、国連教育科学文化機関(UNESCO(ユネスコ))、国連児童基金(UNICEF(ユニセフ))、世界保健機関(WHO)、世界食糧計画(WFP)、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)などの国連機関に対する拠出を通じた支援を行ってきています。日本の行ってきたこうした支援は世界から、途上国から、どのように受け止められているのでしょうか。英国の公共放送BBCは毎年「世界に良い影響/悪い影響を与えている国」を調べる世界世論調査を行っていますが、日本は毎年「世界に良い影響を与えている国」の上位を占めています。最近では2008年と2012年に第1位になりました。こうした日本に対する高評価の背景には、日本がこれまで行ってきたODAなどの国際協力が大きく貢献しています。また、日本が多くのODAを供与してきているASEAN(アセアン)主要6か国における2008年の対日世論調査では、92%の人たちが日本のODAが自分たちの国の開発に役立っていると評価し、93%の人が日本を信頼のできる友好国と考えています。2011年の東日本大震災の後に世界中から送られてきた応援メッセージの中にも、自分たちが被災したときに日本に助けてもらったこと、自国の開発を支えてくれた日本への感謝の念に触れるものが数多くありました。こうしたことは、この60年間日本が行ってきた支援が日本への信頼の強化に大きな役割を果たしてきた証(あか)しといえます。
その一方で、現在および将来の日本のODAのあり方を考える際には、日本を取り巻く国際環境が近年大きく変化してきていることに留意しなければなりません。一つには、政治安全保障上の環境の変化が挙げられます。世界各地で民主的な体制を求める民衆の声が高まる中で、日本は、自由、民主主義、法の支配といった普遍的価値に基づく国際秩序の形成に向け、一層の戦略的な外交を展開していくことが求められています。ODAはそのための最も重要な手段の一つです。ODAを通じて普遍的価値や戦略的利益を共有する国、民主化・国民和解を進めている国への支援を強めていくことで、そうした好ましい動きを促進、助長することができます。
経済開発面での国際環境の変化も著しいものがあります。2000年代初頭までは、民間資金の流入が期待できず、自国の開発のほとんどをODAに依存しなければならない国々がアフリカ諸国を中心に多くありました。しかし、その後の世界の政治、経済状況の変化により、このような事情は一変しました。内戦やクーデターが減少し、政治・治安情勢が改善するとともに、経済のグローバル化が進展する中で、資源価格や一次産品価格の高騰等を背景に、多くの途上国が新たな投資先・市場として注目を浴び、これらの国々にはODAを上回る規模の民間資金が集まるようになりました。グラフ「先進国から途上国への資金フロー(名目値)」に示すとおり、2012年にはODAの約2.5倍の民間資金が途上国に流入しています。ODAに加えて民間資金が新たな原動力となって、これら途上国は世界経済を牽引(けんいん)する目覚ましい経済成長を遂げています。これまで貧困に苦しんできたアフリカでも、年5%を超える成長を達成する国々が次々と登場しました。こうした状況を背景に、2013年6月に横浜で開催された第5回アフリカ開発会議(TICAD(ティカッド) V)においては、貿易・投資を通じた民間資金主導による成長を国家目標に掲げ、日本企業に自国への投資の増大を求めるアフリカ諸国首脳の声が相次ぎました。
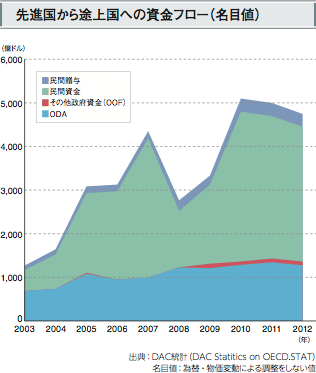
また、中国、インド、ブラジル等のいわゆる新興国が目覚ましい経済成長を遂げ、世界における存在感を増しています。これらの国々では、貿易・投資を通じた経済成長により、国内の貧困が大幅に減少し、ミレニアム開発目標(MDGs)の達成に大きく貢献しました。こうした国々は開発のための資金を供与する立場となり、近年その供与額を飛躍的に増大させています。
そうした状況の一方で、世界の多様化、多極化がますます進行していることにも目を向ける必要があります。MDGsの多くを達成する途上国がある一方で、目標達成に十分な進展が見られない国々も未だ数多くあります。これらは、地域紛争や内戦等の事情により開発が立ち後れ、引き続きODAに依存せざるを得ない国々です。また、ミャンマーをはじめとして、民主的な国づくりに努力する国もあります。民主化を推し進め、開かれた経済の下で成長を志向するこうした国々では、ODAによる開発協力の大きなニーズが存在するだけでなく、投資環境も急速に改善しており、今後の民間投資の増大を通じた飛躍的な経済成長が期待されています。その一方で、順調な経済成長を遂げている国の中でも、国内格差の拡大により依然として深刻な貧困問題が存在しています。これらの国々が抱える困難にも支援の手を差し伸べることが必要です。

エチオピア・ソド コトソフェラケベレの子どもたち(写真:今村健志朗/JICA)
グローバル化の進展は、また、世界経済の一体化と相互依存を加速させています。この点もこれからのODAの役割を考える上でたいへん重要な要素です。世界各地のあらゆるリスクが世界経済全体に大きな影響を与える時代となっています。このことは、リーマンショックや欧州債務危機といった先進国発のリスクに限りません。投資マネーが途上国にも広く波及している現在、地域紛争やテロの脅威といった地政学的リスク、国家信用にかかわるソブリンリスクといった途上国発のリスクも世界経済全体に直ちに波及します。日本および世界全体にとって、世界におけるどんな局所的なリスクも、もはや「対岸の火事」とはいえない状況になっているといっても過言ではありません。
このように変化する国際環境の中で、日本のODAに求められる役割も質的に変化しています。
第一に、開発途上国において持続可能な成長を達成する上で、民間資金の役割が重視されるのに伴い、近年、民間資金を呼び込むための触媒的役割や環境整備のためのODAの役割に期待が高まっています。途上国への直接投資の増加は、途上国への技術・ノウハウの移転、さらに途上国での雇用増加や所得増大につながります。日本としては、途上国の現地企業の活力を引き出すことを通じて、途上国の持続的な経済成長を後押ししたいと考えています。具体的には、途上国のビジネス環境整備につながるインフラ整備、途上国の産業人材の育成、BOPビジネス(注1)支援等の官民連携などの取組を一層強化していく考えです。このような成長の側面を重視したODAのあり方は、日本が従来から推し進めてきた途上国への開発協力の理念と軌を一にするものです。
第二に、世界の多様化・多極化に伴い、ODAに求められる役割も多様化しています。民間資金の流入が期待できない国々に対しては、貧困削減により強い焦点を当てて、人づくりのための技術協力など、人間の安全保障の理念に基づいた開発協力を展開していくことが、引き続き重要です。こうした国々が抱える課題の多くは、地域紛争や、感染症、気候変動といった地球規模問題など、日本を含む世界全体が影響を被りかねないものでもあります。こうした分野へ日本が積極的に取り組むことは、国際社会における日本への信頼と存在感の強化にもつながります。また、民主的な国づくりに努力する国々をODAで支援することは、自由や民主主義といった普遍的価値に沿った国際秩序形成を促し、自由で豊かな国際社会の実現に大いに貢献することが期待されます。
第三に、世界経済の一体性と相互依存が高まる中、途上国の問題はもはや途上国だけのものではなくなっています。実際に、途上国発の要因により先進国経済が恩恵を受けたり、逆に負の影響を被ったりする場面が増えています。先進国経済が伸び悩む中で、途上国の経済成長が今後の世界経済全体の成長の行方を左右する時代に突入しているといわれます。途上国の均衡のとれた持続可能で強靱(きょうじん)な世界経済の成長を実現していくことは、日本を含む世界全体の安定的な発展と繁栄を確保する上で必須の条件となっています。こうした中で改めて明らかになってきたのは、ODAを通じた途上国支援は、途上国のためだけではなく、先進国も含めた国際社会全体にとっても利益になるということです。途上国支援のニーズは、経済インフラ支援といった世界経済への短期的効果が期待できるものから貧困削減や平和構築など、長期的な取組が必要な分野まで様々ですが、そうした途上国のニーズに対応することで、世界の経済成長や平和と安定といった形で、その効果が国際社会全体にも還元されるのです。ODAは、10年先、20年先を見据え、途上国が自立、発展していくため、そしてその発展が世界全体にとっての成長の糧となるように行う、大切な「未来への投資」であるということができます。
こうしたODAに対する考え方は、日本にとって、ある意味でなじみ深いものですが、大きな環境の変化を受けて、他の援助国においても、ODAについて同様の認識が広がってきています。米国の国際開発庁長官も務めたアトウッド前OECD開発援助委員会議長は2012年の寄稿文の中で「開発援助は未来への投資である」として、ODAの増大を国際社会に訴え、「OECD諸国が成長を求めるならば、途上国を包含したグローバルな視野を持たなければならない」と主張しました。
また、これまで、どちらかといえば、開発援助について自国の利益と国際益を峻別(しゅんべつ)し、開発は後者のためにあるべきとの立場にあった英国でも、キャメロン政権下になって歴代の国際開発大臣が「開発援助予算は、開発途上国と英国のための未来への投資である」として、ODA予算増大の必要性を強く訴えています。途上国のみにとどまらない、国際社会全体のさらなる発展に向けた未来への投資としてODAを捉えることが広く共有されるようになってきたといえるでしょう。日本としては、このような視点に立ち、途上国の発展とともに先進国も含めた国際社会全体の成長と繁栄にも役立つODAを実施していきたいと考えています。
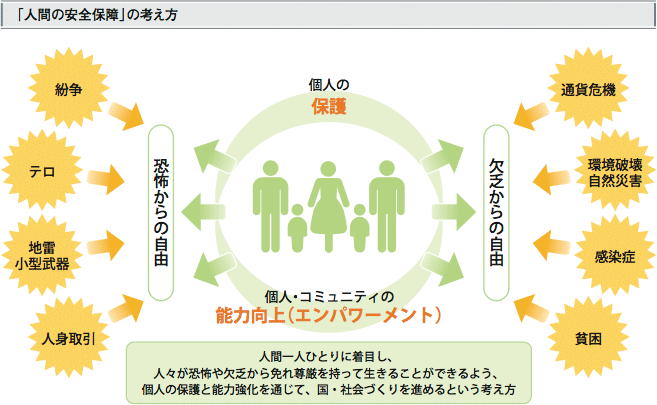
注1 : BOPビジネスについては、こちらを参照