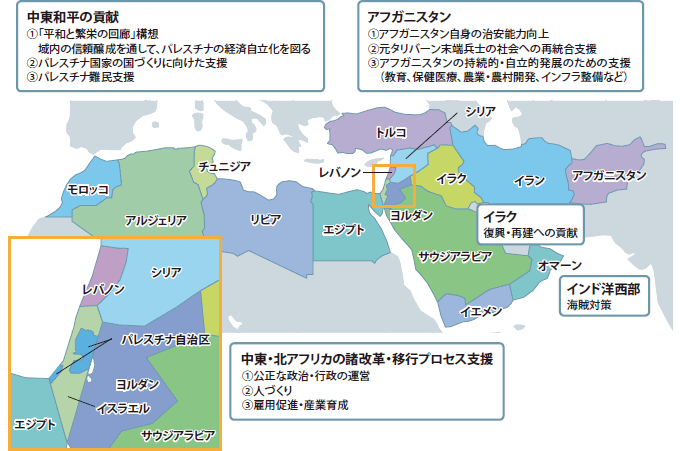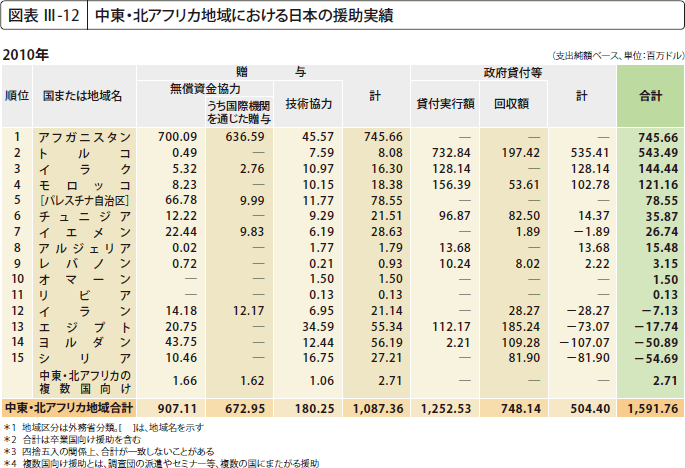5. 中東・北アフリカ地域
中東地域は、世界の石油埋蔵量の約6割、天然ガス埋蔵量の約4割を占めるだけでなく、アジアと欧州を結ぶ海の交通の大動脈ともいえる地域です。この中東地域の安定は世界経済にとって重要です。日本も石油資源の約9割を中東地域に依存している上、日本と欧州とを結ぶ貿易の中心となる航路は中東地域を経由しており、日本の経済とエネルギーの安全保障という意味からもきわめて重要な地域となっています。

訪問先のヨルダンで、無償資金協力「南部地域給水改善計画」の署名式にハッサン計画・国際協力大臣と臨む徳永久志外務大臣政務官
< 日本の取組 >
中東地域には、パレスチナ問題に加え、アフガニスタンやイラク等、生活・社会基盤の荒廃や治安の問題を抱える国や地域が存在します。そうした理由でその国や地域の経済社会が疲弊するだけでなく、中東全体、さらには国際社会全体の平和と安全にも悪い影響を及ぼしかねない状況にあります。これらの国・地域においては、持続的な平和と安定の実現、国づくりや国家の再建のために国際社会が一致団結して支援していくことがとても重要です。以上のような中東地域の位置付けからも日本として積極的に支援を行う大きな意義があります。
また、2010年12月以降、チュニジアを発端として中東・北アフリカ域内の各国・地域で市民による大規模デモが頻繁に起こり、特にチュニジアとエジプトにおいては、そのデモによって旧政権が倒れ、民主的な政治プロセスへの道が開かれるなど、この地域はまさに歴史的な変革期に入っています。一方で、これらの中東・北アフリカ諸国における様々な改革や体制移行の動きはまだ始まったばかりです。今後「政治体制の民主化」だけでなく、高い失業率、食料価格の上昇、貧富の差の拡大など、多くの経済的、社会的な課題を克服する必要があるため、域内各国はこれからたいへん重要な時期を迎えることになるといえます。この地域の平和と安定を保つ上でも、このような諸改革や体制の移行を安定的に実現させることが肝心であり、そのためにも国際社会による一層の支援が必要となっています。2011年5月に開催されたG8ドーヴィル・サミット(フランス)においても、出席した各国首脳は、この地域で起こっている変革の動きを「アラブの春」と呼んだ上で、歴史的な変革を歓迎し、G8としてその努力を支援していくことを互いに確認しました。
中東地域には、所得水準が高い産油国もあれば、所得の低い後発開発途上国、あるいは紛争後の復興期にある国まで、その経済状況は様々です。日本としては、アフガニスタンやイラクにおける平和と安定の実現、中東和平の実現は、国際社会全体の平和と安全にかかわる問題であり、また、ODA大綱の基本方針である「人間の安全保障」ならびに「平和の構築」の実現という点からも意義が大きいと考え、国際社会と連携しつつ、積極的に支援しています。また、産油国においては、順調な経済発展を続けながら、産業の多角化を推進することで、石油に依存する経済から脱して、安定した経済基盤が構築できるように協力します。また、石油等の天然資源がない低中所得諸国に対しては、貧困の削減に取り組むとともに、持続的な経済成長のための支援を引き続き実施していきます。特にG8ドーヴィル・サミットにおいては、日本も、この地域で起こっている変革の動きに対して国際社会と連携して対応し、アジアの成長と安定に貢献してきた経験等を活かし政府や民間企業が連携して、以下のような取組によって、この地域の安定的な体制移行および国内諸改革に向けた各国の自助努力を積極的に支援していくことを表明しました。
すなわち日本としては、<1>公正な政治・行政の運営、<2>人づくり、<3>雇用促進・産業育成を中心に支援していくとともに、<4>経済関係の強化と、<5>相互理解の促進にも取り組んでいくこことしています。こうした観点から、2011年9月の国連総会においては、野田総理大臣より、この地域の雇用状況の改善や人材育成に貢献するため、インフラ整備や産業育成に役立つ事業に対して、今後新たに総額10億ドルの円借款を実施することを含む日本の支援策を表明しました。
さらに、貴重な水資源の管理は地域の安定に影響を与える中東地域の各国共通の重要課題です。日本は、国ごとに支援の分野や対象の重点を適切に配慮し、中東地域の経済的・社会的安定と中東和平達成に向けた環境づくりのための支援を積極的に行っています。重視していく点は、次のとおりです。
(1)平和の構築支援(イラク、アフガニスタン、パレスチナ)
(2)中東和平プロセス支援のための協力(対パレスチナ支援、周辺アラブ諸国支援など)
(3)公正な政治・行政運営のための支援(エジプト、チュニジアに対する選挙支援、格差是正と安定化支援(農村開発、貧困削減、水資源、防災、テロ・治安対策等)を含む)
(4)人づくりや雇用促進・産業育成に役立つ経済社会インフラ整備支援
(アフガニスタン、イラクおよびパレスチナについてはこちら以降を参照)
●トルコ
「ボスポラス海峡横断地下鉄整備計画」
有償資金協力(1999年9月~実施中)
アジアとヨーロッパの境に位置するイスタンブール市は、トルコの商業・貿易活動の中心として栄える東西文明の十字路の大都市です。ボスポラス海峡を境に、市のビジネス地区は主に欧州側、居住地区はアジア側に分かれていますが、ボスポラス海峡に架かる2つの橋は通勤時に慢性的な渋滞を引き起こしています。著しい交通渋滞を緩和するため、ボスポラス海峡を渡る鉄道に大きな期待が寄せられていました。そこで日本は、円借款により海峡を横断する地下鉄(総延長13.6km、そのうち海峡部分は約1.4km)の建設を支援しています。これにより100万人の通勤が可能となります。トルコは日本と同じ地震国ですが、マグニチュード7.5程度の地震にも耐えられる強度設計の海底トンネルが設置され、地震国・日本の耐震技術が活用されています。地下鉄にトルコ国鉄が乗り入れることになり、将来的にはアジアとヨーロッパをつなぐ鉄道の主要幹線として大きな役割を果たすことでしょう。

ボスポラス海峡を横断する海底トンネル(最深部は海面下約60m)と地上(アジア側)から掘り進んだトンネルの接合を祝う工事関係者たち(写真提供:JICA)
●エジプト
「大エジプト博物館保存修復センタープロジェクト」
有償技術支援―附帯プロジェクト(2008年6月~実施中)
エジプトにおける観光は、経済振興に果たす役割が大きく、中でも文化遺産は重要な観光資源となっています。このプロジェクトは、今後建設が予定されている「大エジプト博物館」(2006年5月に、日本の円借款による支援を決定)に展示される予定である10万点の文化財の保存修復や管理を行う人材の育成を目的としています。2008年から、同博物館に併設される保存修復センターのスタッフを対象に、紙・染織品や金属の修復、文化財の梱包・移送方法等に関する多くの研修を実施しています。
パピルス(古代エジプトで使用された植物の繊維で作られた紙状のもの。その上に文字や絵が描かれた)などの貴重な文化財を適切に保存するためには、国際水準の修復技術を習得し、展示環境を整える必要があります。エジプト人技術者は基礎的な技術力は有するものの、最新の技術や管理方法についての知識・経験はまだ不足しており、また、今後を担う若手技術者の育成も課題となっています。これらに対し、高い技術力を有する日本の専門家が実践的な指導を行っています。

ツタンカーメンの遺物確認作業を行う(写真提供:JICA)
中東・北アフリカ地域における日本の国際協力の方針