3. 地球規模課題への取組
(1)環境・気候変動問題
環境問題についての国際的な議論は1970年代に始まりました。1992年の国連環境開発会議(UNCED、(注27)地球サミット)、2002年の「持続可能な開発に関する世界首脳会議(WSSD)」(注28)での議論を経て、国際的にその重要性がより一層認識されました。2008年7月のG8北海道洞爺湖サミットにおいては、環境・気候変動が主要テーマの一つとして取り上げられ、建設的な議論が行われました。環境問題は、未来の人類の繁栄のためにも、国際社会全体として取り組んでいく必要があります。
< 日本の取組 >
●環境汚染対策
日本は環境汚染対策に関する多くの経験や技術を蓄積しており、それらを開発途上国の公害問題を解決するために活用しています。特に、急速な経済成長をとげつつあるアジア諸国を中心に、都市部での公害対策や生活環境改善(大気汚染対策、水質汚濁防止、廃棄物処理など)への支援を進めています。
●気候変動問題
気候変動問題は、国境を越えて人間の安全保障(図版参照)を脅かします。人類にとって差し迫った課題であり、先進国のみならず、開発途上国も含めた国際社会の一致団結した取組の強化が求められています。
2010年10月には、前原外務大臣がアバル・パプアニューギニア外務貿易移民相と共同議長を務め、名古屋で「森林保全と気候変動に関する閣僚級会合」を主催しました。この会合で、気候変動の重要な柱の一つである開発途上国における森林保全(REDD+)*(注29)の取組を加速するための方向性を打ち出しました。また、同年12月にカンクン(メキシコ)で開催された国連気候変動枠組条約第16回締約国会議(COP16)(注30)では、日本は議長国メキシコをはじめとする各国と緊密に連携し、米国・中国等の温室効果ガスの主要排出国を含む包括的な国際枠組みの構築につながる「カンクン合意」が採択されました。カンクン合意では、気候変動分野の途上国支援のための基金である「緑の気候基金」の設立と、この基金の制度設計を行うための移行委員会の設立が決定されました。日本はこの移行委員会の第2回会合を2011年7月に東京で開催するなど、この基金の制度設計プロセス(過程)に積極的に参加し、COP17での基本設計の合意に大きく貢献しました。さらに、温室効果ガスの排出削減に取り組む途上国や、気候変動の影響に対して脆弱な途上国に対し、2012年末までに官民合わせて150億ドル規模の援助の実施を表明しました。そのうち2011年10月末時点で125億ドル以上の支援を実施しています。
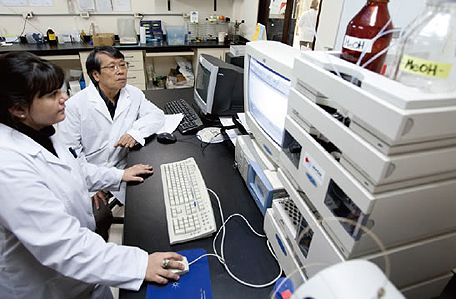
アルゼンチン「産業公害防止(産業排水及び廃棄物による汚染軽減のための技術力強化)」により機材を供与した国立水研究所で水質検査の技術指導をするシニアボランティア(写真提供:久野真一/JICA)
このほか、2011年5月にセネガルの首都ダカールで行われたTICAD閣僚級フォローアップ会合において、アフリカ諸国との間でアフリカ低炭素成長に関する戦略の策定を提案し、アフリカにおける低炭素社会の構築*のための取組を進めています。さらに、世界経済の成長センターであり、中国、インドなどの大量の排出国が集中する東アジア地域に対しては、低炭素技術の普及を促し、経済成長と温暖化対策の両立を図るための「東アジア低炭素成長パートナーシップ構想」を提唱しています。
2011年末に南アフリカ・ダーバンで開催されたCOP17では、日本は交渉に対して建設的な提案を行い、積極的に議論に貢献しました。その結果、将来の枠組みへの道筋、京都議定書第二約束期間の設定に向けた合意、緑の気候基金の設立、およびカンクン合意の実施のための一連の決定、という4つの大きな成果がまとめられました。「緑の気候基金」については、その基本設計が合意され、設立に向けて前進しました。

ブータン「ブータンヒマラヤにおける氷河湖決壊洪水に関する研究プロジェクト」氷河湖での探査中(写真提供:小森次郎)

パラオ「サンゴ礁モニタリング能力向上プロジェクト」地方の環境保全担当者を対象に生態学的モニタリングの訓練を実施(写真提供:PICRC)
●生物多様性
2010年10月に、愛知県名古屋市において生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)およびカルタヘナ議定書第5回締約国会議(COP-MOP5)*(注31)が開催されました。この会議で、生物多様性条約を効果的に実施するための2011年以降の世界目標である「愛知目標(戦略計画2011-2020)」*、遺伝資源へのアクセスと利益配分(ABS)(注32)について各締約国が具体的に実施すべき措置を規定した「名古屋議定書」*、そして遺伝子組換え生物により生態系に損害が生じた場合の責任の範囲や対応措置を規定した「名古屋・クアラルンプール補足議定書」*が採択されました。また、「愛知目標」の達成を目指す開発途上国の取組を支援するため「いのちの共生イニシアティブ」として、2010年から3年間で生物多様性の保全に役立つ分野に対し総額20億ドルの支援を発表しました。なお、日本は、名古屋議定書の早期発効と効果的な実施を支援するために地球環境ファシリティ(GEF)(注33)への名古屋議定書実施基金(NPIF)(注34)の設立を主導し、2011年に10億円を拠出しています。
今後、これらの目標に向かって着実に取り組んでいくことにより、生物多様性を保全し、持続可能な利用を確保していくことがきわめて重要です。

国連総会における生物多様性ハイレベル会合でCOP10の主催国として演説する前原誠司外務大臣
生物多様性

用語解説
*REDD(レッド)
REDDは開発途上国における森林減少・劣化に由来する温室効果ガスの排出削減に関し、過去の推移などをもとに将来の排出量の参照レベルを設定し、資金などインセンティブを付与することにより、参照レベルからの削減を達成しようとする考え方。森林保全、持続可能な森林経営、森林炭素蓄積の増加に係る取組を含む場合には、「REDD+(プラス)」と呼ばれる。
*低炭素社会の構築
環境技術など、日本のすぐれた技術を活用し、高効率な発電所、持続可能な森林経営、省エネ・再生可能エネルギーの促進・制度整備、廃棄物管理の支援を通じて、二酸化炭素の排出量の少ない社会を構築すること。
*愛知目標(戦略計画2011-2020)
「ポスト2010年目標」とも呼ばれている。中長期目標として「2050年までに人と自然の共生の実現」を、短期目標として2020年までに生物多様性の損失を止めるための行動を実施することを掲げ、「少なくとも陸域17%、海域10%を保護地域に設定して保存される」など20の個別目標を採択。
*名古屋議定書
ABS(遺伝資源へのアクセスとその利用から得られる利益の配分)に関する議定書。遺伝資源(医薬品や食品の開発につながる動植物や微生物)の利用から生じる利益を、資源提供者へ公平に分配することを、先進国を中心とする資源利用者に求める。
*カルタヘナ議定書
2003年に発効。国境を越えた遺伝子組み換え生物が自然界に放出されて、生物多様性の保全および持続可能な利用に悪影響を及ぼすのを防止するため、安全な移送、取扱い、利用について、十分な保護を確保するための措置を規定。
*名古屋・クアラルンプール補足議定書
遺伝子組換え生物の輸出入により、生物多様性の保全などへ悪影響が生じた場合、「責任と救済」(誰が責任を負うのかを特定し、この責任事業者に対して損害の防止策や原状回復などの対応措置を求めること)を規定。
●ブラジル
「アマゾン森林保全・違法伐採防止のためのALOS衛星画像の利用プロジェクト」
技術協力プロジェクト(2009年6月~実施中)
ブラジルのアマゾン地域では、違法伐採による森林減少が深刻な問題となっています。しかしながら、広大な熱帯林の違法伐採を地上パトロールで取り締まることは容易ではありません。この問題を解決しようと、日本はブラジルにて人工衛星を用いた違法伐採の発見に取り組んできました。衛星画像の利用で大きな課題となるのが、地表が雲で覆われる雨季への対策です。このプロジェクトは、日本の人工衛星に搭載されている雲を透過できるレーダーを用いて、地表が雲に覆われた雨季であっても違法伐採を発見できるよう、技術支援を進めています。
*ALOS : Advanced Land Observing Satellite 陸域観測技術衛星

森林伐採地の検出を行う日本人専門家とブラジル側担当者(写真提供:JICA)
●南アフリカ
「気候変動予測とアフリカ南部における応用」
技術協力プロジェクト(2010年4月~実施中)
アフリカ南部は、自然環境に大きく依存した農牧畜業の従事者が多い一方、自然災害に対する社会基盤の整備が十分ではありません。そのため、気候変動が引き起こす異常気象の影響を受けやすい傾向にあります。そこで、日本と南アフリカ共和国の研究所は、アフリカ南部における気候変動による影響の軽減を目的に、気候変動予測の共同研究を進めています。本プロジェクトでは、アフリカ南部の気候に影響する大気と海洋の双方のモデルを使って地域気候変動を予測するという手法を用いており、エルニーニョ現象などの気候変動現象予測に成功しています。今後は、気候変動予測の精度を一層高め、その成果をインターネットや携帯電話等により地域住民に広く発信していく予定です。

西ケープ大学で講義を行う日本人研究者(写真提供:JICA)
注27 : 国連環境開発会議 UNCED:United Nations Conference on Environment and Development
注28 : 持続可能な開発に関する世界首脳会議 WSSD:World Summit on Sustainable Development
注29 : 途上国における森林減少・劣化に由来する温室効果ガスの排出の削減等 REDD:Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, in Developing Countries
注30 : 条約の締約国会議 COP:Conference of Parties
注31 : 議定書の締約国会議 MOP:Meeting of the Parties
注32 : 遺伝資源へのアクセスと利益配分 ABS:Access and Benefit-Sharing
注33 : 地球環境ファシリティ GEF:Global Environment Facility
注34 : 名古屋議定書実施基金 NPIF:Nagoya Protocol Implementation Fund