第2章 衡平な開発の実現に向けて

ネパールの小学校で算数のモデル授業を行う青年海外協力隊員。子ども主体の授業のあり方を現地教師に指導する(写真提供:佐藤浩治/JICA)
第1節 人間の安全保障と衡平性という視点
人、物、資本、情報などの移動が容易に国境を越え、地球規模で盛んになる中で、国内紛争の国際化、テロ、感染症の広まり、人の移動の増大に伴う人身取引や難民問題、経済危機、貧困問題の拡大、気候変動・環境問題、災害など、人々を脅かす脅威もまた多様化、深刻化しています。このような地球規模の課題に対応するためには、人間の安全保障(図版参照)、衡平(こうへい)性、相互扶助、持続可能性といった考え方がますます重要となっています。
特に、恐怖にさらされている人間一人ひとりに着目し、人々が恐怖や欠乏から免れ、尊厳を持って生きることができるような社会を目指す「人間の安全保障」の考え方、また、支援の手から取り残される人々をなくす「衡平性」という考え方は、今後日本として支援を行う上で、鍵となる考え方であるといえます。
人間の安全保障 ~理念の普及と実践~

アフガニスタン・カブールの国内避難民キャンプ。泥の家は避難民が自ら作った(写真提供:谷本美加/JICA)
日本は、人間の安全保障の考え方を1990年代から自らが中心になって主張するとともに、先駆者として積極的に実践してきました。グローバル化が進んだ現在の国際社会においても国民を保護するに当たり国家が重要な役割を担うことには変わりはありません。しかし、地球規模の課題に効果的に対処するためには、国家がその国境と国民を守るという伝統的な「国家の安全保障」のみでは、紛争などによって政府が機能しなくなった場合、国民を守りきれないケースが出てくるのも事実です。そこで、国家の安全保障を補完し、強化するものとして提唱されたのが、人間一人ひとりに焦点を当てる考え方、すなわち人間の安全保障の考え方です。
人間の安全保障を進めていくためには、まずは国内外において政府・国際機関、それに市民社会に至る関係者の間で、人間の安全保障の重要性が理解されることが重要です。このため日本は、たとえば国連の場における議論を主導するのみならず、国際的フォーラムや学会、NGOとも協力をしています。また、2011年1月には、ダボス会議(スイスのダボスで開催される世界経済フォーラム)において人間の安全保障に関するセッションが開催されました。
さらに、日本の主導で1999年に設立された国連人間の安全保障基金を通じて、日本は人間の安全保障の考えに合致した具体的なプロジェクトを支援してきており、これまで、累積額402億円(約3億6,000万ドル)を拠出し、121の国・地域で206件のプロジェクトが実施されています。このほか、日本独自で、草の根・人間の安全保障無償資金協力において、2010年度のみで122か国1地域、1,176件の案件を実施しています。
国連人間の安全保障基金を通じた支援の一例として、コンゴ民主共和国における「イツリ地方における統合されたコミュニティ強化と平和構築支援」が挙げられます。この事業では、農業・漁業・畜産という多様な分野において、技術指導、地方行政施設の補修、医療関係者への訓練の実施、住民に対する保健・衛生教育の実施など、人々やコミュニティの能力強化につながる活動を、国連開発計画(UNDP)(注5)、国連食糧農業機関(FAO)(注6)、国連児童基金(UNICEF(ユニセフ))(注7)、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)(注8)の4つの国際機関が連携して行いました。さらに、これらの支援を補完するような形で日本が二国間支援を行うことにより、コミュニティに対する包括的・多面的・重層的な支援を可能にしています。
人間の安全保障がとる3つのアプローチ、すなわち、<1>人々およびその所属するコミュニティを脅威から「保護」するだけでなく、脅威に対処するために自ら選択・行動できるよう「能力強化」を重視する人間中心のアプローチ、<2>包括的・分野横断的なアプローチ、<3>国、地方政府、国際機関、NGO、市民社会など様々な活動主体間の連携と調整を重視する全員参加型アプローチは、今後の援助に不可欠な概念であると同時に、もう一つの重要な鍵である「衡平性」を確保する上でも重要な観点となります。
注5 : 国連開発計画 UNDP:United Nations Development Programme
注6 : 国連食糧農業機関 FAO:Food and Agriculture Organization
注7 : 国連児童基金ユニセフ UNICEF:United Nations Children's Fund
注8 : 国連難民高等弁務官事務所 UNHCR:United Nations High Commissioner for Refugees
衡平性の確保に向けて
現在、国際社会は、共通の目標であるミレニアム開発目標(MDGs)達成のため努力を続けているところです。しかし、その成果を測る指標は、国家の平均値を用いることがほとんどのため、富裕層と貧困層、都市部と農村部、男女、民族等の国内に存在する格差が覆い隠され、本当に支援を必要とする弱い立場の人々に必ずしも支援が届かないという問題があります。こういった事態を避けるためにも、開発途上国内における貧富の差や社会的弱者の状況に配慮した、衡平性の概念が一層必要となります。
日本は、2010年、ガーナのUNICEFが実施する複数指標クラスター調査(MICS)*(注9)を支援しました。この調査は、衡平性の観点から、ガーナ全土にわたって、保健、教育、児童保護、HIV/エイズの分野で統計を取るのもので、UNICEFのみならず、国や他ドナーによる政策決定、事業の企画立案等に活用されています。日本は、2010年9月の国連首脳会合において、国際保健政策を発表しました。国際社会と共に何人の命を救うことができたのか、数値による成果目標の設定と質の高いモニタリング・評価を通じて具体的な成果を報告していくアプローチであり、MICSはこの政策とも方向性を同じくするものです。
人間一人ひとりに着目した人間の安全保障の実現を目指す支援は、弱者に手の届く衡平性を確保した支援であると同時に、衡平性を確保した支援は、そのコミュニティの人間の安全保障を実現するために不可欠ともいえ、これらの考え方は相互に密接にかかわっています。
2015年に迫ったMDGsの達成期限に向けて、その取組を最大限に高めるため、日本は2011年6月にMDGsフォローアップ会合を東京で開催し、MDGs達成に向けた人間の安全保障および衡平性の視点の重要性について議論を深めました。日本としては、引き続き人間の安全保障と衡平性という考え方の重要性を国際社会にアピールするとともに、これらの考えに基づいた支援を着実に実施していきます。
用語解説
*複数指標クラスター調査(MICS)
MDGs、国連エイズ特別総会において設定された目標のような、国際的重要性を有する諸目標の達成度を調査するために、通常3年に一度、全国規模で行う世帯調査。教育、保健、子どもの保護、HIV/エイズの分野について行う。
「人間の安全保障」の考え方
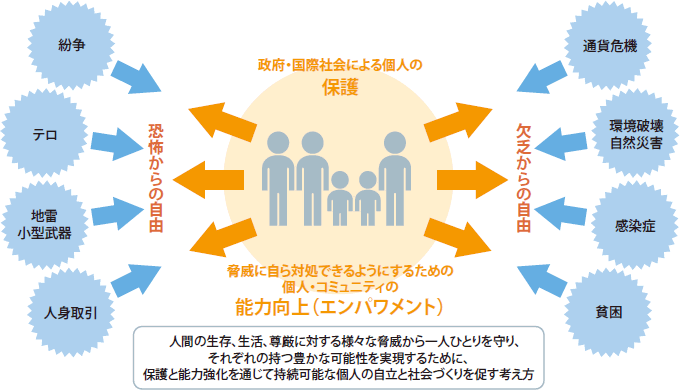
注9 : 複数指標クラスター調査 MICS:Multiple Indicator Cluster Survey