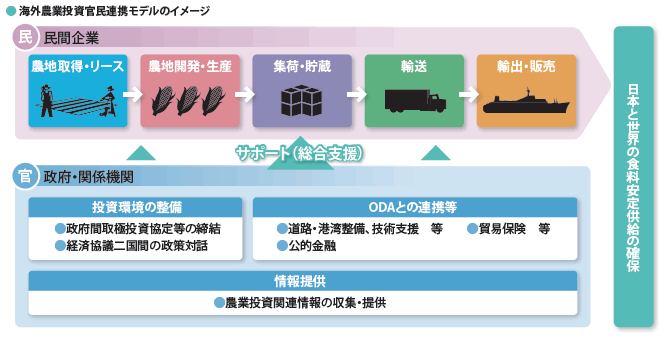囲み 4 食料安全保障と日本の取組~官民連携モデルで海外農業投資を促進へ~
2008年、食料需給のひっ迫や投機資金の流入などにより、食料価格は史上最高値を記録しました。食料輸出国の一部は、自国の食料確保のために輸出規制を行い、これがさらなる価格上昇を招きました。このため、多くの開発途上国において飢餓が拡大するとともに、食料が手に入らなくなるかもしれないという不安が高まり、暴動が発生する国もありました。現在、食料価格はピーク時に比べて落ち着きを取り戻したものの依然高水準で推移しており、開発途上国では食料危機はいまだ去っておらず、世界の栄養不足人口は10億人を超える見込みです。
こうした事態への根本的な解決策として、農業投資の促進によって食料生産を拡大することが重要となっています。世界全体の農業生産力を強化することは、食料の約6割を輸入に依存する日本への食料の安定供給の確保にもつながります。一方、近年、食料輸入国の企業や欧米の投資家による開発途上国の農地への大規模投資が活発化しており、これを「新植民地主義」あるいは「農地争奪」と批判する声もあります。
農業投資、特に国際的な投資は、投資側と投資受入れ側の双方が利益を得る形で行われなければなりません。日本は、2009年7月のG8ラクイラ・サミットの機会に、責任ある形での国際農業投資を促進するための国際的枠組みの形成や行動原則の策定を提案しました。この具体化のため、日本は同年9月、ニューヨークでの国連総会の際に、「責任ある国際農業投資の促進に関する高級実務者会合」を世界銀行、国連と共催するなど、国際社会においてイニシアティブをとっています。
また、日本は同年8月、「食料安全保障のための海外投資促進に関する指針」を策定し、日本自身の行動原則として、被投資国における農業の持続可能性や透明性の確保、法令の遵守、農業者や地域住民への適正な配慮、環境への適切な配慮、および食料事情への配慮、を発表しました。指針では、これらの原則に基づきつつ、道路・港湾整備などの生産・流通インフラ整備へのODAの活用や技術移転、貿易保険などを総合的に活用することで、日本から海外への農業投資促進を図ることが示されています。
農業分野は干ばつや水害など天候リスクに加え、輸出国によって時に輸出規制が実施されるなど非常に投資リスクが高く、さらに開発途上国では農産物の輸送に必要なインフラが整備されていないため、輸送コストが高くなるなど、民間資金を効果的に呼び込める環境ではないのが実情です。日本は、公的支援ツールを活用した官民連携モデルにより、責任ある国際農業投資の促進を図っています*1。
*1 : 日本は、世界で主要な農業分野のODA供与国(OECD-DAC諸国の支援総額の約2割)として、世界全体の食料増産と農業生産性向上に積極的に取り組んでいる(農業分野における日本の取組に関しては、第II部第2章第2節を参照してください)。