2006年度、日本は研修員3万1,161人受入、専門家5,675人派遣、調査団5,869人派遣、協力隊4,407人派遣、その他ボランティアを1,405人派遣しました。
「国づくりは人づくりから始まる」といわれますが、人づくりへの支援は日本の援助の重要な柱の一つです。人づくりへの支援は、開発途上国の発展に直接寄与する人材育成のみならず、「人」と「人」との交流を通じた相互理解の促進や、開発途上国の将来を担う青少年を含む各界指導者との人間関係の構築を通じて、二国間関係の増進にも大きな役割を果たします。また、日本の基本理念である開発途上国の自助努力(オーナーシップ)を強化する上でも極めて重要な要素です。
開発を担う人材の育成のためには、基礎教育のみならず、高等教育、技術教育、職業訓練、行政等実務の研修など様々な分野での支援を進めることが必要です。
日本の人材育成への支援は、留学生受入、高等教育機関の能力・機能向上、行政実務者の能力向上支援、職業能力開発・向上支援、労働安全衛生、産業競争力向上への支援などの技術協力を中心に進められています。また、人材育成に際しては、より低コストで質の高い支援が実施できるよう情報通信技術(IT)を積極的に活用しています(注14)。
2007年1月にフィリピンで行われた第2回東アジア首脳会議において、安倍晋三総理大臣(当時)から、東アジア地域を中心に、5年間、毎年6,000人程度の青少年を日本に招く350億円規模の交流計画を発表しました(「21世紀東アジア青少年大交流計画(注15)」)。これは、アジア地域の一体感の醸成および青少年交流を通じたアジアにおける良好な対日感情の形成を促進することを目的としており、これまでの交流計画をはるかに上回る規模となっています。2007年5月には、第一陣として中国から高校生代表団200人が来日し、日本各地においてホームステイなどを経験しました。
留学生受入については、日本は、渡日前から帰国後まで体系的な留学生受入のための諸施策の充実に努めてきました。国費留学生制度の充実、私費留学生などへの援助、留学生相互交流の推進、留学生に対する教育・研究指導の充実など、各種の留学生施策を推進してきました。留学生在籍者数は、2003年5月には10万人を超え、2006年5月現在、11万7,927人となっています。引き続き、留学生の受入・派遣の両面での一層の交流推進を図るとともに、併せて留学生の質を確保し、向上させる施策に積極的に取り組んでいきます。
また、開発途上国の若手行政官等を対象とする人材育成には、無償資金協力で「人材育成支援無償」を実施しています。円借款では、これまで、いわゆる「留学生借款」などを通じて、インドネシアやマレーシアを中心に、開発途上国の人材育成のための留学生派遣等の事業に資金供与を行っています。
図表II-12 日本に滞在する留学生数の推移(2006年5月現在)
● 高等教育分野
高等教育分野での支援としては、開発途上国の大学などの高等教育施設の整備、運営管理向上支援、教育・研究能力向上、産業界や地域との連携強化、一国を超えた地域内の高等教育機関のネットワーク化などを実施しています。例えば、国際協力機構(JICA (注16))は、ケニアのジョモケニヤッタ農工大学構内に社会・経済開発と貧困削減に資する人材育成分野の機関として「アフリカ人づくり拠点(AICAD (注17))」を設立しました。ここではケニア、タンザニア、ウガンダ3か国の15大学とのネットワークを活用した「研究開発」、「研修普及」、「情報発信」の3機能を中心に、研究・開発した技術を地域住民へ普及することを目指した活動を行っています。
東南アジア諸国連合(ASEAN (注18))地域に対する技術協力「ASEAN工学系高等教育ネットワーク(SEED-Net)プロジェクト」では、ASEANのメンバー大学・日本の国内支援大学(10大学)の間の「大学間ネットワーク」型アプローチをとり、ASEAN各国の工学系トップ19大学(「メンバー大学」)の教育・研究能力の向上を支援しています。SEED-Netは、2003年から5年間で、学位取得による400名以上の教員の能力強化、ASEANのメンバー大学での大学院国際プログラムの新設・強化による人材育成体制の構築、ASEANと日本の大学間の実質的な交流・連携関係の構築とこれを活用した地域課題への取組など、大きな成果を上げ、内外から高い評価を受けています。
このほか、大学の社会貢献を促進するため産業界・地域社会との連係機能を強化するプロジェクトをガジャマダ大学(インドネシア)やホーチミン工科大学(ベトナム)で実施しているほか、社会・経済発展の基盤技術となりつつある情報通信技術(IT)に関する人材育成機能を強化するため、ラオス国立大学やスラバヤ工科大学(インドネシア)でIT学部の能力強化を行うプロジェクトを実施しています。
● 技術教育・職業訓練分野
技術教育・職業訓練分野における支援としては、職業訓練の質の向上や労働市場ニーズに適した訓練の実施を目的とした協力を行っており、2006年度はスリランカ、エクアドル、トルコ、セネガル、パラグアイなどで技術協力プロジェクトを実施しました。具体的には、スリランカに対して情報通信、メカトロニクス、金属加工などの専門家を派遣、エクアドルに対しては、電気・電子分野、機械・金属分野の専門家を派遣し、現地での技術移転や、日本での研修員受入を行ったりしました。また、アフガニスタン、エリトリア、スーダンなどの紛争後の国々における除隊兵士を対象とし、円滑に地域社会に復帰し職に就けるよう、基礎的な技術訓練についても協力しています。
● 産業人材分野
人材育成を通じた協力の一分野として、人材育成を通じて貿易・投資環境を整備する支援を行っています。同分野では、中小企業の産業振興や鉱物資源開発に関する協力を実施しており、近年は産業基盤制度整備や生産性向上などの管理技術、さらに工業化に伴う環境・エネルギー関連の協力にまで及んでいます。このほかにも、貿易投資関連では、日本貿易振興機構(JETRO (注19))や海外技術者研修協会(AOTS (注20))などを通じた、各分野の専門家派遣や研修員受入、セミナーの開催などを実施したり、知的財産権保護や基準・認証、物流効率化、環境・省エネルギー、産業人材育成などの制度整備、「アジア標準」の構築に向けた支援も行っています。
● 労働安全衛生分野
労働安全衛生分野では、労働安全衛生政策や建設業における労働安全管理、職業病防止等に関する研修をアジア、中南米、アフリカ等幅広い地域の行政官を対象に実施し、監督行政や作業環境および労働者の健康管理の改善に向けた人材育成を行いました。アジアを中心とした支援については、財団法人国際労働財団および財団法人日本経団連国際協力センター(NICC)を通じた、研修の実施、招へい等も行っています。また、2006年度にはASEAN事務局と協力して、ASEAN地域合同の政労使三者構成セミナーや能力向上ワークショップ、国別セミナーを実施しました。その他に、ボスニア・ヘルツェゴビナやアルメニア等の欧州地域を含む国々の労使関係行政に従事する中堅幹部職員を対象に、労使関係政策の向上に向けた研修を実施しました。
● 市場経済化支援等
市場経済へ移行する国々を対象に、市場経済化への改革努力に対する支援策の一環として、現地の中小企業経営者や起業家の人材育成を主な目的とした「日本人材開発センター(日本センター)」を東南アジア、中央アジア等に設置し、日本の知見や経験を活用しています。これまでにラオス、カザフスタン、キルギス、ウズベキスタン、ベトナム(ハノイおよびホーチミン)、モンゴル、カンボジア、ウクライナにおいて日本センターが開所されています。現在、東南アジアの「人材開発センター」では、ASEAN加盟国間格差の解消を目的として、ASEAN後発加盟国(カンボジア、ラオス、ベトナム)における人材育成分野の基盤整備の支援およびASEAN後発加盟国とそれ以外のASEAN諸国との間の人材育成に係る技術協力の促進を行う「日・ASEAN人材養成協力事業」を実施しています。
その他、アジア、中東およびアフリカ地域の文化財保護に関する国際協力の充実を図ることを目的に文化遺産の保護に資する研修等、ネットワーク拡充も行っています。
開発途上国船員の養成
優秀な船員を養成するためには、実際に乗船して適切な実務訓練を行うことが不可欠です。しかし、開発途上国では施設が不足するなど、船舶職員として乗船するためのライセンス取得に必要となる、適切な事前乗船訓練の機会が少ないのが現状です。
日本は1990年から、フィリピン、インドネシア、ベトナムおよびバングラデシュ等の優秀な船員志望者を日本に招き、研修を行っています。2007年3月現在で1,094名が研修を終了しており、半数以上が引き続き日本船社に雇用されるなど、人材育成に寄与するとともに、雇用の機会創出にもなっています。
 |
(写真提供:国土交通省)
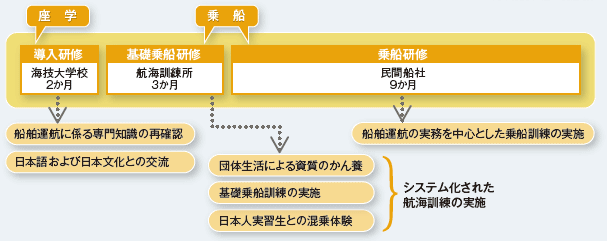 |
