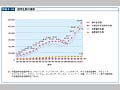本編 > 第II部 > 第2章 > 第3節 > 2.持続的成長 > (3)人づくり
(3)人づくり
「国づくりは人づくりからはじまる」と言われますが、人づくりへの支援は日本の援助の重要な柱の1つです。人づくりの支援は、持続的成長の基礎となる国づくりに直接貢献する人材を育むのみならず、「人」と「人」との交流を通じた相互理解の促進や、途上国の将来を担う青少年を含む各界指導者との人間関係の構築を通じて二国間関係の増進にも大きな役割を果たします。
日本の人材育成への支援は、留学生受入、行政実務者の能力向上支援、職業能力開発・向上支援、労働安全衛生、産業競争力向上への支援などの技術協力を中心に進められています。また、人材育成に際しては、より低コストで質の高い支援が実施できるよう、例えば、マレーシアにおいて、マルチメディア大学をハブサイトとし、地方の5つの教育機関をリモートサイトとしたマルチメディア・ネットワーク教育体制確立を目指した「マレーシア・マルチメディア・ネットワーク教育プロジェクト」を実施するなどITを積極的に活用しています。
図表II-18 留学生数の推移
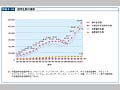
日本は、「留学生受入10万人計画」(注1)に基づき、国費留学生受入の計画的整備、私費留学生等への援助、留学生相互交流の推進、留学生に対する教育・研究指導の充実など、各種の留学生施策を推進してきました。2003年5月には留学生受入総数が約10万9,500人となり、この計画の目標は達成されました。今後は2003年12月の中央教育審議会の答申を踏まえて、留学生の受入・派遣の両面での一層の交流推進を図るとともに、留学生の質の確保・向上を目指した施策に積極的に取り組んで行く方針です。なお、文部科学省では、2004年度の留学生関連予算として534億5,800万円を計上しており、そのうちODA予算は431億2,000万円となっています。
留学生受入などの人材育成にはその他の資金協力の活用も図られています。具体的には、無償資金協力では「留学生支援無償」(注2)、円借款では「留学生借款」(注3)等を通じて途上国の人材育成・留学生派遣事業に資金供与を行っています。
また、日本は、途上国の自助努力支援を基本理念としつつ、途上国における職業能力開発分野での支援についても、関連施設の設置・設営に対する協力や、専門家派遣、研修員受入等を通じて行っています。2003年度は、JICAを通じパラグアイ、ウガンダ、チュニジア、エクアドル等において職業能力開発政策・職業訓練に関する技術協力プロジェクトを実施するとともに、研修員受入、専門家派遣などによる支援を行っています。
労働安全衛生分野でも同様にマレーシアにおいて技術協力プロジェクトを実施するとともに、研修員受入、専門家派遣を行っています。
人材育成を通じた産業競争力向上への支援としては、中小企業の産業振興や鉱物資源開発に関する協力を実施しており、近年は産業基盤制度整備や生産性向上などの管理技術、さらに工業化に伴う環境・エネルギー関連の協力にまで及んでいます。2003年度は、2000年から2002年の2年間行われた「中核的人材育成機関(COE:Centers of Excellence)包括プログラム」のフォローアップ事業として、ASEAN各国により登録されたCOEに対し、AOTSによる研修実施への支援や各国のグッドプラクティスを共有するためのワークショップを開催しました。
さらに、アジア諸国の市場経済化への改革努力に対する支援策の一環として、経済実務に携わる人づくりを主な目的とした「人材開発センター(日本センター)」(注4)を各国に設立しています。2004年3月現在、ラオス、カザフスタン、キルギス、ウズベキスタン、ベトナム、モンゴルにおいて日本センターを開所しています。また、労働分野における支援として、アジア地域の途上国における労使関係の安定化を目的とした「日・ASEAN労使間交流促進事業」、企業における人事・労務管理能力の向上を目的とした「アジア開発途上国人事・労務管理者育成事業」、労働者の技能を適正に評価するための制度づくりを支援することを目的とした「技能評価システム移転促進事業」等を実施しています。
columnII-5 ウズベキスタン日本センター

 次頁
次頁