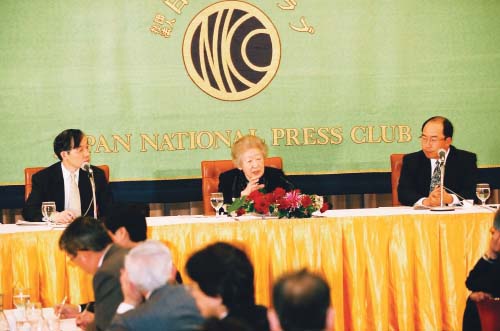本編 > 第II部 > 第2章 > 第1節 変化しつつある日本のODA
第2章では、新しいODA大綱の構成に従い、2003年度のODA実績(注)を報告します。また、新しい大綱が、その実施状況をODA白書において明らかにするとしたことを踏まえ、以下の各節においては、ODA大綱の実施状況についても、2003年度のODA実績を報告する中で説明します。
第1節 変化しつつある日本のODA
本節では、ODA大綱の実施状況について特徴的ないくつかの点について説明します。具体的には、国別アプローチの強化、中期政策の評価と見直し、国際協力機構(JICA:Japan International Cooperation Agency)の環境社会配慮ガイドライン改定、無償資金協力審査ガイドラインの作成、外務省機構改革、JICAの組織再編について説明します。
■国別アプローチの強化
日本のODA政策は、開発援助の理念や原則等を明確化した基本文書であるODA大綱を最上位の政策として、その下に、より短い期間を念頭においた援助のあり方に関する指針である政府開発援助に関する中期政策(以下「ODA中期政策」)、さらに各国ごとの日本の援助計画として、具体的な案件選定の指針となる国別援助計画、という3つの文書によって、枠組みが定められています。
2003年8月に改定された新しいODA大綱では、政府全体として一体性と一貫性をもってODAを効率的・効果的に実施するため、主要な被援助国について、日本の援助政策を踏まえ、当該国の真に必要な援助需要を反映する国別援助計画を策定することが明記されています。
国別援助計画は、2000年以降、2004年6月までに16か国に対して策定されています(注)。特に、対ベトナム国別援助計画の改定と対スリランカ国別援助計画の新規策定については、ODA総合戦略会議での議論を経た上で、新しいODA大綱の下、2004年4月の対外経済協力関係閣僚会議において正式に決定されました。また、2004年7月現在、モンゴル、インドネシア、インド、パキスタンの4か国について新規策定作業が進められており、更に、今後1~2年をめどに、ラオス、ウズベキスタン、カザフスタン、エチオピアについての新規策定作業と、バングラデシュ、ガーナ、タイ、エジプト、フィリピンについての改定作業を行うことが予定されています。
国別援助計画は、現地ODAタスクフォースの積極的関与の下で、有識者から構成される各国別の計画策定タスクフォースを中心とする検討、関係府省との協議、非政府組織(NGO:Non Governmental Organization)、経済界、援助実施機関との意見交換、被援助国における政府、経済界、NGO等からの意見聴取等、援助に係る多様な関係者の意見を踏まえて策定されます。また、国別援助計画の策定に際しては、可能な限り事前に国別評価を行い、その結果と提言を国別援助計画策定の参考としています。
国別援助計画策定において重要な役割を果たす現地ODAタスクフォースは、日本貿易振興機構(JETRO:Japan External Trade Organization)や国際交流基金等の政府関係機関にも必要に応じて参加を求め、経済協力に携わる大使館員のほか、JICA及び国際協力銀行(JBIC:Japan Bank for International Cooperation)の現地事務所の所員を主要な構成メンバーとして活動しています。主な活動としては、[1]被援助国の開発を巡る動向の把握・分析、[2]被援助国政府との現地ベースの政策協議の実施、[3]国別援助計画の策定・見直しのプロセスへの関与、[4]現地援助コミュニティとの連携が挙げられます。現地ODAタスクフォースは2004年7月までに64か国で立ち上げられており、日本のODAの戦略性・透明性・効率性の向上に向け活動しています。(現地ODAタスクフォースについてはII部2章6節1-(5)、および2003年版ODA白書66頁も参照して下さい。)
columnII-1 ガーナにおける現地ODAタスクフォースの活動
図表II-10 現地ODAタスクフォースの立ち上がっている国

世界64か国にある現地ODAタスクフォースの活動は、被援助国の状況などにより、様々ですが、積極的に活動している現地ODAタスクフォースの一つにバングラデシュがあります。
バングラデシュでは、各種セクターに作業部会を設置して、セクターの知見を共有し組織的に蓄積するとともに、セクターごとの援助のプログラムを作成しています。また、バングラデシュの状況を把握するための勉強会を月に1度開催し、援助の実施にあたって最大の課題となる主要セクターにおける被援助国のニーズの把握を行っている他、半年に1度、バングラデシュの財務省、関係省庁と日本大使館、JICA、JBICとの定期協議を行い、援助方針の共有や個別案件に関する協調を行っています。
バングラデシュは、ODA総合戦略会議において他の8か国とともに、今後1~2年間を目途に国別援助計画を策定・改定する国の一つに選ばれました。積極的に活動しているバングラデシュの現地ODAタスクフォースの役割は、今後ますます重要になってくると思われます。
■中期政策の評価と見直し
日本のODA政策の枠組みを構成する文書の一つである、ODA中期政策は、1999年に策定されました。2003年度、外務省ではODA大綱の改定などを踏まえ、これまでの取組を検証し、中期政策の見直し作業の参考とするため、有識者によるODA中期政策評価検討会を開催し、現行の中期政策に対する評価を行いました。
検討会では、[1]ODA中期政策が上位政策である1992年のODA大綱(旧ODA大綱)や国際的な開発ニーズに合致しているか、[2]ODA中期政策は分野別及び国別の援助政策に確実に反映されているか、[3]ODA中期政策を適切に実施し、検証するための取組が行われているか、という観点から評価が行われました。その結果、1992年の旧ODA大綱や国際的な開発ニーズとは概ね合致しており、分野別及び国別の援助政策にも反映されている、全体として連携や検証システムが維持されているとの評価を得ました。また、これらの結果や最近の援助動向を踏まえた幅広い観点から、以下のような提言がなされました。
ODA中期政策全体に及ぶ提言としては、[1]新しいODA大綱が、中期政策の内容を取り込む形で改定され、より具体的な内容を持つようになったため、次期中期政策の位置づけと役割を再定義する必要がある、[2]結果重視のアプローチを強調し、評価の結果を政策改善のために活用する、[3]投下資源の分散を防ぐためにも、「選択と集中」が可能となるような仕組みを盛り込むべきである、[4]次期ODA中期政策においては、ミレニアム開発目標(MDGs:Millennium Development Goals)への取組に言及し、他国・機関との目標を同じくする、といった提言がなされました。
また、重点課題については、今後のイニシアティブは、基本的に次期中期政策の具体化に沿うものとすべきであり、重点課題の内容について、経済インフラ支援、平和構築、ジェンダー、災害等に配慮すること、さらに地域別援助に関しては、地域レベルの政治経済交流の活発化に伴い、「リージョナル・アプローチ」が重要である旨の提言を得ました。
援助手法、実施・運用上の留意点については、NGOとの連携、他の援助国・機関との協調、国内機関間の連携について提言が得られ、次期中期政策については、情報公開の強化、開発人材の育成、現地機能の強化が強調されました。
現在、政府としては、こうした評価の結果も踏まえつつ、2003年の新しいODA大綱の策定を受け、新たな中期政策を策定すべく検討作業を進めています。
■JICAの環境社会配慮ガイドライン改定
新しいODA大綱は、ODAの実施が途上国の環境や社会に与える影響などに十分注意を払い、公平性を確保することを定めています。JICAでは、既に、1988年の第1次分野別援助研究会(環境)の提言に基づき、1990年から環境配慮ガイドラインを導入していましたが、その後の10年間の経験、JICAの事業に対する環境社会配慮の基本方針の作成、ガイドラインの対象範囲の拡大及び遵守を確保する体制の整備等の必要性、ODA大綱の改定に代表される環境社会配慮を強化する日本の方針、情報公開等の動きなどを踏まえ、2004年3月、環境社会配慮ガイドラインを改定しました。

環境社会配慮ガイドラインに関する会議の様子 (写真提供:国際協力機構(JICA))
環境社会配慮ガイドラインの改定にあたっては、国内各方面の様々な意見を反映するよう努めました。2002年12月より、改定委員会を設置し、2003年9月までに合計19回の委員会を開催しました。委員会は政府関係者の他、大学関係者、NGO、民間団体の有識者から構成され、幅広い層からの意見を取り入れるよう配慮しました。また、合計5回のパブリック・コンサルテーションの他、ガイドライン案をホームページに公開し、広く意見を募りました。
このような作成過程を経て、2004年4月1日より新しい環境社会配慮ガイドラインが施行されることとなりました。新しいガイドラインは、被援助国政府の開発目的に資するプロジェクトが環境や地域社会に与える影響を回避または最小化し、受け入れることができないような深刻な影響をもたらすことがないよう、適切な環境社会配慮の確保を支援し、途上国の持続可能な開発に寄与することをJICAによる環境社会配慮の基本方針としています。また、そうした基本方針に照らし、要請された案件の採択等に関する日本政府の意思決定が適切になされるよう、新しいガイドラインは、JICAが行う協力事業の方針に関してJICAが外務省に対し提言を行うことが規定されています。
この改定されたJICAの環境社会配慮ガイドラインと、2003年10月より全面的に施行されているJBICの環境社会配慮確認のための国際協力銀行ガイドラインにより、日本のODA実施にあたっては、より一層の環境社会配慮がなされることとなりました。
■無償資金協力審査ガイドラインの作成
無償資金協力審査ガイドラインは、外務省が、無償資金協力を行うにあたり、案件の発掘・形成段階から、案件の実施、さらには実施後の監理の各過程において、環境社会配慮を含む適正な事業の実施のために行うべき審査の視点、及びその手順を示すことを目的とするものです。
環境社会配慮ガイドラインについては、上述の通り、JICAの環境社会配慮ガイドラインが改定され2004年4月より施行されていますが、外務省はこうした動きを踏まえ、また、ODA大綱の実施という観点から、JICA環境社会配慮ガイドラインの具体的な準用方法を含む無償資金協力審査ガイドラインを作成することとしました。
作成にあたっては2004年4月、政府原案を外務省のホームページに公開し、広く意見を募集しました。ガイドラインの内容はこれらの意見を踏まえたものにしています。
無償資金協力審査ガイドラインについては、2004年8月から当分の間試行的に適用し、その後、試行期間中に得られた関係者や一般の方々等の意見を踏まえ、所要の改定を行って、本格的に適用することとしています。
■外務省の機構改革
新しいODA大綱では、これまでのODA改革の成果を踏まえ、援助政策の立案及び実施体制について、一貫性のある援助政策の立案、関係府省間の連携、政府と実施機関の連携、途上国との政策協議の強化、政策の決定過程・実施における現地機能の強化、国際社会における協調と連携などにつき明確に示しました。これにより、政府全体としての一体性と一貫性のあるODAの実施を確保するとともに、現地や内外の援助関係者との連携や国民参加の拡大等により幅広い支持が得られるような効果的なODAを実施していく考えです。
そのような考えにも沿った形で、日本のODA政策の要となる経済協力局では、2003年3月に発表された外務省機構改革最終報告で「被援助国の現状に応じ、「国別援助計画」を核として政府全体の政府開発援助(ODA)政策を立案し、これを戦略的・効果的に実施するため、スキーム別の課編成から地域別重視の体制に移行する」とされたことを踏まえ、2004年8月に、国別開発協力第二課を新たに設置し、国別2課体制としました。これまで国別開発協力課が所掌していた事務のうちアジア及び大洋州地域に関することを国別開発協力課第一課が所掌し、アフリカ、中南米、中東及び欧州地域(中央アジア・コーカサス地域を含む)に関することを国別開発協力第二課が所掌するようになりました。これにより、ODA政策の立案・実施における国別アプローチの強化を通じ、政策の立案面においては途上国の開発政策及び援助需要の総合的かつ的確な把握による戦略的な国別援助政策の立案が、実施面においてはセクター別の援助プログラムを通じた各種援助形態の連携の強化が期待されています。
なお、国別2課体制となったことに伴い、調査計画課と国際機構課の課の所掌事務を基本的に引き継ぐ課として開発計画課を設置しました。これまで分野別の援助計画の策定等を所掌していた調査計画課とDAC、国連開発計画(UNDP:United Nations Development Programme)、世界銀行等の国際機関との関係などを担当していた国際機構課の事務を整理・統合することにより、国際的な援助潮流を踏まえた総合的な援助政策や水・衛生、環境、感染症等分野別の援助政策の立案とその対外発信の強化を図ることとしています。
図表II-11 開発計画課及び国別開発協力第一課・第二課の概念図

また、グローバル化の下で、紛争、難民問題、感染症、突然の経済危機、地球環境問題など、人間の生存、生活、尊厳に対する脅威の質が変容している中、局部を越えた連携が不可欠となっているという問題意識に対応し、「地球規模問題戦略本部」を発足させました。
「地球規模問題戦略本部」は、局部の横断的取組が必要な地球規模問題に係る基本戦略策定・調整、人間の安全保障を実現するための諸施策実行のための各局・部間の連携強化や、国際機関に関わる予算支出、邦人職員増強、選挙に関する戦略的体制の強化、地域局と関係の深い多国間外交案件等に関する調整や方針提言等を行うことを、基本的な目的としています。
図表II-12 地球規模問題戦略本部の概念図

■JICAの組織再編
外務省の機構改革と並び、ODAの実施機関の一つであるJICAにおいても、組織が再編されました。JICAは2003年10月に独立行政法人化し(詳細は2003年版ODA白書64頁を参照して下さい。)、元国連難民高等弁務官の緒方貞子氏を理事長に迎え、独立行政法人国際協力機構となりました。これを機に緒方理事長のイニシアティブの下、2004年3月に「JICA改革プラン」(JICAの新たな方向性)を発表し、その一環としてODA実施体制を強化する目的で本部組織を再編しました。また、「現場主義」を掲げ、途上国の様々な開発問題により的確かつ迅速に対応できるよう、在外事務所の体制を強化しています。
具体的には国別・地域別アプローチを強化し、各国・各地域のニーズにきめ細かく応えるため、従来の地域4部を地域5部体制に改編し(「アフリカ部」「中東・欧州部」を新設)、MDGsなどの開発課題へのアプローチを強化するため、スキーム・セクター別体制から課題別の実施体制に移行し、技術協力プロジェクトを担当する5部と開発調査を担当する3部を、課題別5部に改編し、課題への対応力を強化しました。これにより課題部内に分野・課題ごとの知見やノウハウを蓄積し、今後、在外への技術支援を強化していきます。
在外事務所の体制としては6か国に地域支援事務所を設置し、個別の在外事務所によるプロジェクト形成支援や地域戦略策定への支援、地域横断的な課題への取組などを推進します。また、本部と在外の人員比率を1:1にすることを目標に、約30事務所の人員を集中的に強化し、これらの在外事務所における事業実施の責任と権限を拡大していきます。
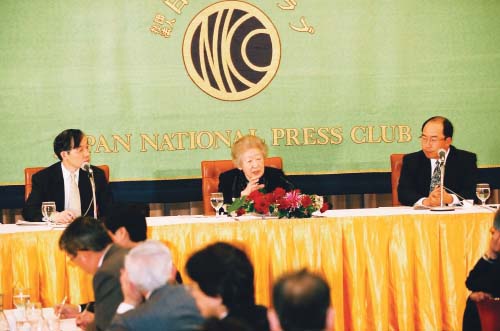
JICAの組織再編に関する緒方理事長の記者会見 (写真提供:国際協力機構(JICA))

 次頁
次頁