1.欧州情勢
(1)欧州連合(EU)
EUは、27の加盟国、人口約4億9,000万人、GDP約18兆4,000億米ドル規模の世界最大の共通市場を擁し、経済・通貨統合のみならず、共通外交・安全保障政策(CFSP)等の幅広い分野で統合を進めている。
拡大したEUは、気候変動・エネルギー問題等の新たな課題に、より効果的に対応するため、2007年12月に新基本条約(リスボン条約)に合意した。同条約は、2008年6月のアイルランドでの国民投票で批准が否決されたが、同国の中立政策等に対し法的な保証を与えるという欧州理事会の決定後、2009年10月に2回目の国民投票で批准が可決された。11月には全27加盟国の批准が終了し、12月に同条約は発効した。
欧州理事会(EUの首脳会議)の常任議長(同条約の発効に伴って新設)にはファン=ロンパイ前ベルギー首相が、EUの外相に相当する外務・安全保障政策上級代表にはアシュトン前貿易担当欧州委員が、それぞれ任命された。また、2010年2月にはリスボン条約体制下で新しい欧州委員会(第2次バローゾ委員会)が発足した。リスボン条約の発効により、今後EUが「一つの声」で発言する方向性が強まっていくと見られる。EU拡大については、2009年に、アルバニア、アイスランド、セルビアがEUへの加盟申請を行った。
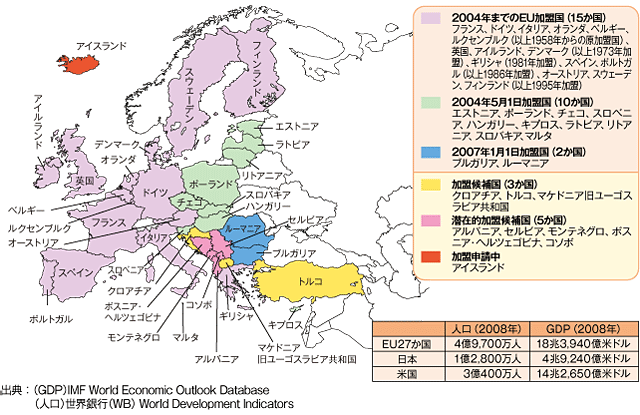
経済面では、世界経済・金融危機により、戦後最も深刻な景気後退を経験したが、2009年終盤には金融市場の緊張は緩和してきており、在庫調整の進展や自動車買い換え支援策等の政策効果もあり、最悪期は脱したとみられる。中・東欧、バルト諸国では多くの国で景気が急速に悪化し、IMFによる金融支援を受ける国もあった。2009年の実質GDP成長率はEU(27か国)で4.1%のマイナス、ユーロ圏で4.0%のマイナスとなった。労働市場は厳しい情勢が続いており、失業率は2009年にはEUで8.9%、ユーロ圏で9.4%となった。財政赤字の対GDP比は、経済対策や税収の大幅な落ち込みなどにより悪化が続き、EUで6.9%、ユーロ圏で6.4%となる見通しである。また、欧州に進出している日本企業も、自動車産業を中心に影響を受け、雇用調整や一時的な操業停止等の対応を行った。
経済の先行きは、基調としては緩やかな持ち直しに向かうと見込まれるが、信用収縮の深刻化、雇用情勢の悪化、政策効果のはく落とその反動による下押し圧力等が予想以上に大きなものとなれば、景気は低迷を続けることとなりかねない。また、ギリシャ等一部の国では財政問題が深刻化しており、欧州経済安定のためにも早期の財政再建が望まれる。
外交面では、2008年8月のグルジアにおける軍事衝突を受けて、同年10月から展開されているグルジアEU監視ミッション(EUMM)が、2009年6月に国連や欧州安全保障協力機構(OSCE)の同地域におけるミッションが終了した後も活動を継続し、警察官など200名以上の文民が停戦合意の履行の監視に当たっている。また、ソマリア沖での海賊対策として、2008年12月から1年の予定で開始されたEU海軍作戦(EU NAVFOR)を1年間延長し、引き続き国連世界食糧計画(WFP)の契約船舶などの護衛に当たっている。EUはこのように、軍事、文民の両面において欧州安全保障・防衛政策(ESDP)ミッションを各地に派遣し、国際社会の平和と安定のための取組を積極的にリードしている。
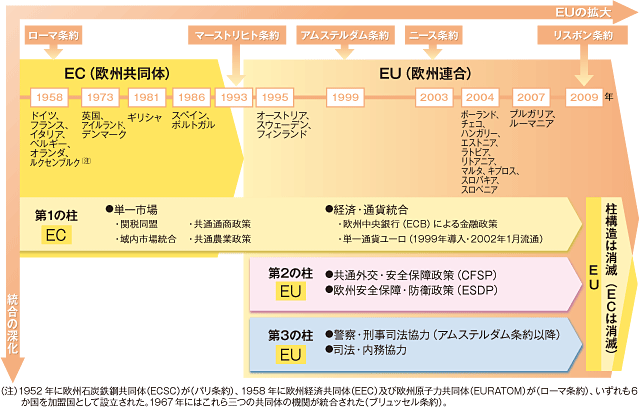
日本との関係では、5月にプラハで第18回日・EU定期首脳協議が開催され、麻生総理大臣とクラウス・チェコ(2009年前半のEU議長国)大統領及びバローゾ欧州委員会委員長が出席した。同協議では、日本とEUが、気候変動や世界経済・金融危機問題等、国際社会が直面する課題に対し共同でリーダーシップを発揮していく方針を確認したほか、「日・EU協力のための行動計画」が2011年に終了するのを受け、次の新文書の策定に向け検討を開始することで合意した。さらに、9月のニューヨークにおける国連総会の機会に、岡田外務大臣出席の下、日・EUトロイカ外相協議が開催され、気候変動問題における日本とEUとの連携を確認したほか、北朝鮮、イラン、アフガニスタンなどの地域情勢について有意義な意見交換を行った。また、鳩山総理大臣は、11月にファン=ロンパイ欧州理事会議長が選出された直後に電話会談を行い、日・EU関係の重要性について確認した。

(2)英国
ブラウン労働党政権は、世界経済・金融危機への迅速な対応と強力な指導力で一時的に支持率を回復したが、上院議員による汚職疑惑や議員追加手当不正請求といったスキャンダルが政治不信を招き、6月の統一地方選挙、欧州議会選挙で惨敗した。2010年6月までに実施される次期総選挙を控え、最大野党である保守党が支持率でリードする状況が続いており、各党とも選挙に向けた動きが活発化している。外交面では、米国との同盟関係を引き続き重視し、新興経済国との関係強化にも積極的である。分野別外交では、気候変動、核不拡散といった地球規模の課題に積極的に取り組んでいる。アフガニスタンへは引き続き支援を表明しているが、英国兵士の犠牲者数増大に世論は厳しい見方をしている。
日英間では核不拡散、国連改革といった国際的課題や、アフガニスタン、北朝鮮等の地域的課題について緊密な協力を進めている。1月のダボス会議(於:スイス)、4月のG20ロンドン・サミットの機会に麻生総理大臣とブラウン首相との間で首脳会談を実施し、世界経済回復に向け両国が協力して対処していくことで一致した。鳩山政権発足直後の9月の国連総会の際にも首脳会談を実施し、新政権の下で日英関係を更に強化していくことを確認した。外相間では、6月に開催されたG8トリエステ外相会合(於:イタリア)の際に会談したほか、9月の国連総会の際にも岡田外務大臣とミリバンド外相が会談した。経済面でも、英国高速鉄道整備に日本企業が参画するなど関係が深まっている。また、11月には、2008年9月に開始した日英外交関係開設150周年事業の閉幕式典がロンドンの大英博物館において実施され、彬子女王殿下の御臨席の下、日英関係の新たな幕開けを感じさせる盛大な催しとなった。

(3)フランス
2007年5月に就任したサルコジ大統領は、11月に任期半ばを迎えた。内政面では、国民の支持率は下落傾向にあるものの、同大統領は安定した政権基盤を背景に、重要な内政問題については自ら陣頭指揮をとる形で、経済の競争力強化、世界経済・金融危機への対応策、環境関連法案の策定、行財政改革等の政策を矢継ぎ早に実施した。
外交面では、サルコジ大統領は、中国、インド、ブラジルといった新興大国との関係を重視しながら、国際社会におけるフランスの立場・利益の強化を目指す実利主義的な外交を推進した。9月のG20ピッツバーグ・サミット(於:米国)では、金融市場の透明性、ガバナンス、責任といった国際金融におけるルールの重要性を強調し、銀行家のボーナス制限問題を提起した。また、12月のCOP15では、コペンハーゲン合意の取りまとめのために、自ら主要国首脳とともに尽力した。
日本との関係では、2008年の日仏外交関係開設150周年を記念する多数の交流事業実施の効果もあり、文化面での関係が一層緊密化した。経済面では、自動車などの分野で企業間の提携が推進されるとともに、フランスの地域産業政策が2009年から第2フェーズに入ったことにより、日仏の地域間産業協力の推進も今後期待される。政治対話に関しては、中曽根外務大臣とクシュネール外務・欧州問題相との間で4月及び7月に電話会談等を実施したほか、様々なレベル・分野で緊密な意見交換が頻繁に行われている。
(4)ドイツ
ドイツにおいては、2005年以降、キリスト教民主同盟/社会同盟(CDU/CSU)と社会民主党(SPD)とによる大連立が政権を担当してきたが、9月に4年ぶりに行われた連邦議会選挙において、連立与党であるCDU/CSUとSPDが苦戦し、自由民主党(FDP)、同盟90/緑の党、左派党といった野党各党が躍進する中、第1党の座を維持したCDU/CSUがFDPとあわせて議席の過半数を制し、10月、メルケルCDU党首を首相とする中道右派の連立政権が成立、ヴェスターヴェレFDP党首が外相兼副首相に就任した。また、5月には連邦大統領選挙が行われ、現職のケーラー・ドイツ大統領がCDU/CSU、FDP、自由選挙民同盟の支持を得て再選された(任期5年)。
2009年は、1989年11月9日にベルリンの壁が崩壊してから20周年に当たり、首都ベルリンを始め、各地で記念行事が行われた。
日本とドイツは、共に普遍的価値を共有するグローバルなパートナーとして、国際社会の諸課題の解決に向けて引き続き緊密に連携している。5月には、麻生総理大臣がドイツを訪問し、メルケル首相との間で日独首脳会談を行い、世界経済・金融危機、気候変動問題等、国際社会の重要課題における一層の連携を確認した。麻生総理大臣は、ケーラー・ドイツ大統領を表敬し、フンボルト大学(ベルリン)で欧州政策スピーチを実施した。
(5)イタリア
2008年5月に発足した第4次ベルルスコーニ政権は安定した議会運営を行い、4月に発生したラクイラ地震に対し迅速な復興支援を実施したことや、同地でG8サミットを開催したことも評価され、高い支持率を維持している。また、ベルルスコーニ首相は、3月に創設された自由国民党(PDL)の党首に選出され、与党内における地位を強固にした。しかし、10月に国家要職者に対する刑事訴訟の中断を定める法律に違憲判決が下ったことから、ベルルスコーニ首相に対する刑事裁判が再開される可能性もあり、司法改革をめぐる今後の動きに注目が集まっている。
麻生総理大臣は、ベルルスコーニ首相と、4月のG20ロンドン・サミット及び7月のG8ラクイラ・サミットの際に会談し、同月にラクイラ地震に対する復興支援を表明した。G8関連会合がイタリアで開催されたことから、中曽根外務大臣を始め多数の閣僚・要人も同国を訪問した。9月には、ナポリターノ大統領が日本を訪問し、鳩山総理大臣と会談を行い、イタリア文化を日本に紹介する行事に参加するなど、二国間の友好関係が一層促進された。
(6)G8各国を除く欧州地域の情勢、日本との関係
日本とオランダは、2008年の外交関係開設150周年に続き、2009年には通商400周年を迎え、両国において2年にわたって多数の行事が開催された。8月には日蘭協会名誉総裁の秋篠宮同妃両殿下が日蘭通商400周年記念式典への御臨席のためオランダを公式に御訪問になった。政治・経済面でも両国関係は緊密である。3月には中曽根外務大臣がアフガニスタンに関する国際会議出席のためオランダを訪問した。10月にはバルケネンデ首相がオランダ首相として9年ぶりに訪日して、鳩山総理大臣と会談するなど、両国の伝統的友好関係の一層の強化が図られた。
スペインやポルトガル、アイルランドでは、経済対策が2009年の最も重要な課題の一つとなった。ポルトガルでは、9月、任期満了に伴う総選挙が実施され、社会党(中道左派)が引き続き政権を担うこととなった。アイルランドからは、1月にカウエン首相が訪日し、麻生総理大臣と首脳会談を行った。
北欧地域では、デンマークで、4月にアナス・フォー・ラスムセン首相がNATO事務総長に転出するため辞任し、ラース・ルッケ・ラスムセン財務相が新首相に就任した。麻生総理大臣は、1月のダボス会議(於:スイス)の際にアナス・フォー・ラスムセン首相と会談し、鳩山総理大臣は、10月に国際オリンピック委員会(IOC)総会、12月にCOP15出席のためコペンハーゲンを訪れ、ラース・ルッケ・ラスムセン首相と気候変動問題への対応を中心に首脳会談を行った。ノルウェーでは9月に総選挙が行われ、ストルテンベルグ首相の続投が決まった。外交関係開設90周年を迎えたフィンランドとの間では、様々な記念行事が開催された。11月にはストゥブ外相が訪日して岡田外務大臣と会談し、平和構築分野における協力等に合意した。
アイスランド及びバルト諸国は、世界経済・金融危機により深刻な影響を受け、一部の国では政権交代も見られた。ラトビアでは2月にドンブロウスキス内閣が、アイスランドでは5月にシグルザルドッティル内閣が成立した。リトアニアでは同月にグリボウスカイテ氏が初の女性大統領に就任した。日本との関係では、1月には日本の在ラトビア大使館が開設され、また、ゴドマニス・ラトビア首相が訪日し、麻生総理大臣と世界経済・金融危機への対応について意見交換した。5月には、ASEM外相会合(於:ハノイ(ベトナム))の機会に、中曽根外務大臣とウシャツカス・リトアニア外相との間で、アフガニスタンにおける協力を中心に会談が行われた。
ベルギーでは、11月にファン=ロンパイ首相が欧州理事会議長に転出し、レテルメ外相が首相に復帰した。ルクセンブルクでは、6月に選挙が実施され、ユンカー首相の続投が決まった。
日本とバチカンの関係においては、3月にドミニク・マンベルティ法王庁外務長官が外交関係開設以来外務長官として初めて日本を訪問し、中曽根外務大臣と会談したほか、7月には麻生総理大臣がバチカンを訪問し、法王ベネディクト16世に謁見し、ベルトーネ法王庁総理と会談を行った。
中・東欧地域においては、1月にウクライナ経由のガス供給が停止されたことにより、エネルギー安全保障面での脆(ぜい)弱性が浮き彫りとなった。また、世界経済・金融危機の影響を受けて、国際社会やEUからの支援を受けた国も見られた。
ハンガリーでは首相の交代、また、ブルガリア、モルドバ、ギリシャでは政権の交代が行われたものの、概(おおむ)ね安定的な政策運営が行われている。
キプロスでは、ギリシャ系及びトルコ系キプロスによる再統一に向けた交渉の機運が引き続き高く、国連仲介の下での両系代表間交渉が継続された(注1)。
日本との関係では、2009年は、オーストリア、ハンガリー、ルーマニア及びブルガリアとの交流が節目を迎え、「日本・ドナウ交流年2009」として活発な交流事業や様々な記念事業が行われた。1月には、パルヴァノフ・ブルガリア大統領及びシュピンデルエッガー・オーストリア外相、9月にはフィッシャー・オーストリア大統領、12月にはショーヨム・ハンガリー大統領がそれぞれ訪日し、また、日本からは5月に秋篠宮同妃両殿下が上記ドナウ交流年関係4か国を御訪問になり、友好関係及び相互理解が増進された。このほか、ポーランドとの間では国交樹立90周年を、ギリシャとの間では日・ギリシャ修好110周年を祝う交流事業が行われた。

スイスとの関係では、1月に麻生総理大臣がダボス会議に出席するためにスイスを訪問し、2月にはロイタード・スイス副大統領兼経済大臣が訪日して、欧州の国との間では初めてとなる経済連携協定である日・スイスEPAに署名し、9月には同協定が発効した(ロイタード・スイス副大統領兼経済大臣は、同協定発効記念のシンポジウム等のため10月にも日本を訪問)。

このほか、3月にはティモシェンコ・ウクライナ首相、11月にはライチャーク・スロバキア外相が訪日し、日本との協力関係を一層強化していくことが確認された。日本からは、5月に麻生総理大臣が、第18回日・EU定期首脳協議出席のためEU議長国であるチェコを訪問した際、トポラーネク・チェコ首相と首脳会談を行った。
西バルカンでは、ボスニア・ヘルツェゴビナなど一部の地域で民族問題の解決が課題となっているものの、平穏な情勢が維持されており、各国ともEU加盟に向けた改革に取り組むなど、全体として安定と発展に向けた進展を見せている。4月には、クロアチア及びアルバニアのNATO加盟が実現し、また、懸案となっていたスロベニアとクロアチアの国境問題についても進展が見られるなど、西バルカン諸国の欧州への統合に向けた進展が見られた。
コソボにおいては、11月に地方選挙が平和裏に実施された。日本は、2008年3月に国家として承認したコソボとの外交関係を2月に開設し、10月には初の対コソボ経済協力協議を実施した。
10月には、アルカライ・ボスニア・ヘルツェゴビナ外相及びイェレミッチ・セルビア外相がそれぞれ訪日し、協力関係の強化が確認された。
(7)ヴィシェグラード4か国(V4)、GUAMとの協力
日本は、ヴィシェグラード4か国(V4:チェコ、ハンガリー、ポーランド、スロバキアで構成される地域協力の枠組み。1991年に設立合意会合が開かれたハンガリー北部の地名に由来)との間で、外相レベルでの会合や双方の関心分野におけるセミナーの開催等を通じ、対話と協力を進めてきた。5月に第3回「V4+日本」外相会合(於:ハノイ(ベトナム))が行われ、国際的課題について緊密に連携していくことが確認されたほか、10月には、東京で環境・気候変動ワークショップが、また、ハンガリーで世界経済・金融危機問題に関するセミナーが開催されるなど積極的な協力が進められている。
GUAM(グルジア、ウクライナ、アゼルバイジャン、モルドバ)は、民主主義と市場経済による安定と繁栄を目指す旧ソ連欧州部とコーカサスの4か国で構成され、日本と基本的価値を共有するパートナーとして関係強化を進めている。2月の第4回「GUAM+日本」会合(於:東京)では、協力の方向性や国際情勢等について意見が交わされ、また、具体的な協力として、同月に貿易投資、11月に観光振興の実務家等をそれぞれ日本に招き、各分野における関係拡大を支援するためのワークショップを開催した。
(注1)キプロスは1960年に英国から独立。独立直後からギリシャ系住民とトルコ系住民の間で対立・衝突が激化し、1974年のトルコ軍侵攻以降現在に至るまで、北(トルコ系)と南(ギリシャ系)に分断されている。トルコ系は「北キプロス・トルコ共和国」(Turkish Republic of Northern Cyprus)として1983年に独立を宣言(トルコのみ承認)。