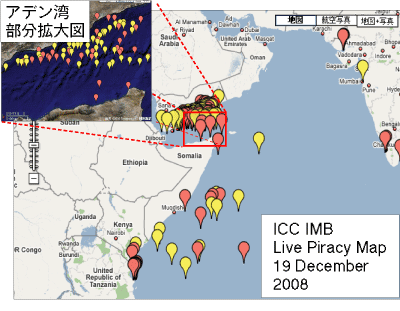本編 > 第3章 分野別に見た外交 > 第1節 国際社会の平和と安定に向けた取組 > 4.海上安全保障
【総論】
日本は、エネルギーや食料資源の輸入、また貿易の多くを海上輸送に依存する海洋国家であり、貿易立国である。船舶の航行の安全の確保やテロ・海賊対策といった海上の安全確保は、日本にとって国家の存立・繁栄に直結する課題であるのみならず、地域の経済発展を図る上でも極めて重要なものとなっている。
現在、マラッカ海峡やソマリア沖・アデン湾等、欧州や中東から東アジアを結ぶ、日本にとって極めて重要な海上交通路において、海賊行為が多発・急増しており、この事態を大変懸念している(図表「海賊等事案報告件数」を参照)。特に、ソマリア沖海域はいつ海賊の襲撃を受けるともしれない状況であり、(社)日本船主協会や全日本海員組合から、海上自衛隊艦船の派遣について強い要請を受けている。海賊対策は国際的な課題であると同時に、何よりも、政府の最も重要な責務の一つである日本国民の生命及び財産の保護の観点から、急を要する課題である。
海賊対策として、日本はこれまで、収集した安全情報を船会社に提供し、有志連合との安全確保に関する調整を実施するとともに、沿岸国の海上取締り能力の強化と人材育成などの協力を行ってきている。
【各論】
アジア地域においては、「アジア海賊対策地域協力協定(ReCAAP)」が日本の主導の下に作成され、2006年9月に発効(日本は2005年4月に締結)した。同協定に基づき、情報共有センターがシンガポールに設立され、アジア地域における海賊情報の共有体制や各国協力網の整備のための積極的な活動を展開しており、国際的にも高い評価を得ている。現在、海賊事件の多発に悩むアフリカ地域において、ReCAAPをモデルとした地域協力の枠組みづくりが進められている。
航行の安全に関して、2007年にシンガポールで開催された国際海事機関(IMO)による第3回「マラッカ・シンガポール海峡に関する国際会議」において、沿岸国・利用国・利用者間の新たな国際協力の枠組みである「協力メカニズム」の発足が決定された。日本は、民間からの基金拠出も含め、沿岸国の提案プロジェクトの幾つかに支援の意思を表明した。日本は、引き続き、これらの協力メカニズム及びプロジェクトに積極的に参画し、沿岸国との協力を進めていく考えである。
アフリカ地域、特にソマリア沖・アデン湾の海賊問題は、国際的な課題となっている。国連においては、関連する安保理決議が全会一致で採択されており、日本もそのほとんどについて共同提案国となってきている。また、欧米・アジアの国々も軍艦等を派遣しており、国際的な対応が行われている(コラムを参照)。
海賊等事案報告件数
| 区分/年 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
| 東アジア |
173 |
257 |
178 |
175 |
193 |
173 |
117 |
88 |
79 |
| 東アジアのうちマラッカ海峡 |
37 |
112 |
58 |
34 |
36 |
60 |
20 |
22 |
12 |
| インド洋 |
51 |
109 |
86 |
66 |
96 |
41 |
51 |
53 |
40 |
| アフリカ |
52 |
62 |
80 |
70 |
89 |
70 |
73 |
62 |
120 |
| 中南米 |
29 |
41 |
23 |
67 |
72 |
46 |
26 |
31 |
25 |
| その他 |
4 |
2 |
3 |
5 |
2 |
0 |
0 |
6 |
18 |
| 合計 |
309 |
471 |
370 |
383 |
452 |
330 |
267 |
240 |
282 |
| 日本関係船舶の被害件数 |
39 |
31 |
10 |
16 |
12 |
7 |
9 |
8 |
10 |
東アジアにおける日本関係船舶
の被害件数 |
28 |
22 |
4 |
12 |
11 |
7 |
9 |
6 |
6 |
|
|
| 出典:国際海事機関(IMO)「REPORTS ON ACTS OF PIRACY AND ARMED ROBBERY AGAINST SHIPS(2007年版)」等、国土交通省「2007年の日本関係船舶における海賊等事案の状況及び世界における海賊等事案の状況について」
|
CSV形式のファイルはこちら
ソマリア沖・アデン湾における海賊等事案の急増と日本及び各国・国際機関の取組
最近、ソマリア沖・アデン湾における海賊等事案が急増しています。特に2008年夏以降急増し、同年10月~12月には48件と約2日に1件の割合で発生、状況は更に悪化しています。国際海事局(IMB)レポートによれば、同年の同海域における海賊等事案は111件と、全世界の約4割に当たり、2007年の約2.5倍にも上ります。
国連海洋法条約には、公海上における海賊行為について、海賊船舶の船籍にかかわらず、すべての国に軍艦その他の政府公船による取締りが認められていますが、現在、日本には、公海上で海賊行為を取り締まる一般的な国内法令がありません。ソマリア沖・アデン湾には年間約2,000隻の日本関係船舶が通航しており、政府としては、日本国民の人命・財産の保護の観点から、できることから早急に措置を講じていく必要があると考えています。
各国・国際機関も同海域において積極的にこの問題に取り組んでいます。国連安保理は、安保理決議第1816号、第1838号、第1848号及び第1851号において、海賊行為等に対するソマリア沖海域で活動している軍艦等による警戒、当該海域への軍艦等の派遣等を要請しています。これまでに、米国、英国、フランス、ドイツ、デンマーク、カナダ、オランダ、スペイン、ロシア、ニュージーランド、インド、中国、マレーシア等の国が同海域に軍艦を派遣してきています(報道等公開情報による)。
また、国連安保理決議第1851号に従い、ソマリア沖海賊対策に関する国際協力メカニズムとしてコンタクト・グループが設置されたのに加えて、国際海事機関(IMO)主催でソマリア周辺海域諸国の域内協力のための会議がジブチで開催されるなど、国際的な協力の枠組みもできつつあります。日本は、こうした取組にも積極的に取り組んでいます。
テキスト形式のファイルはこちら
▲このページの上へ