世界の各地域・経済共同体等の貿易額(2007年)(単位:100万米ドル)
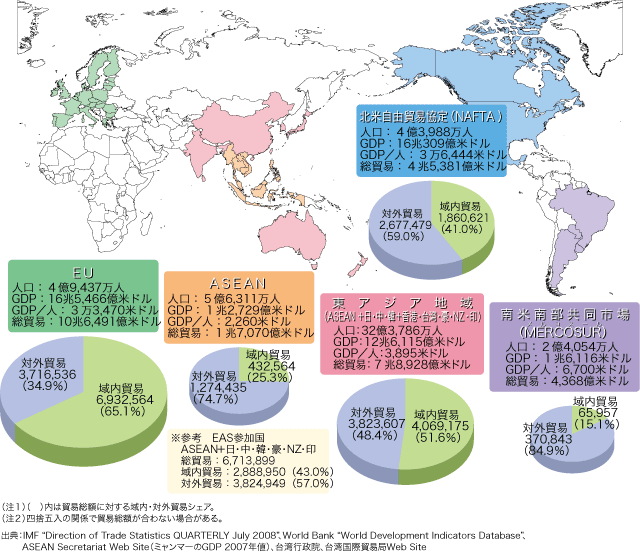
3. |
東南アジア |
(1) |
東南アジア諸国連合(ASEAN)情勢全般 |
ASEANは、2015年までのASEAN共同体形成を目指して、統合努力を加速化している。ASEANを中核として、ASEAN+3や東アジア首脳会議(EAS)、ASEAN地域フォーラム(ARF)といった複数の枠組みの下で地域協力が進められている。ASEANが、人権、民主主義、法の支配といった普遍的価値に立脚する形で統合を着実に進め、発展していくことは、この地域の将来の安定と繁栄にとって重要である。
12月15日、ASEAN共同体の基本文書であり、普遍的価値が行動原則として盛り込まれた「ASEAN憲章」が発効した。同憲章では、日本を含むASEANの対話国はASEAN担当大使を任命することができると規定しており、これまでに日本を含む各対話国がASEAN担当大使を任命している(日本は10月に鹿取克章(かとりよしのり)・前駐イスラエル大使を任命)。このようにASEAN統合に向けて、ASEANと日本等域外国との関係強化も進展している。
世界の各地域・経済共同体等の貿易額(2007年)(単位:100万米ドル)
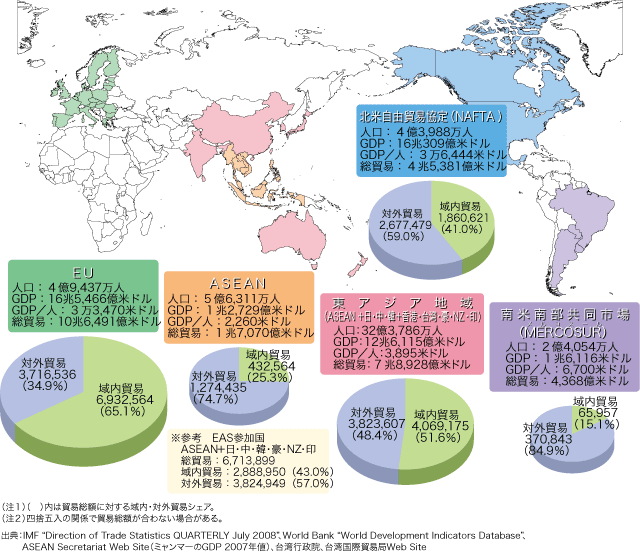
日本とASEAN(貿易・投資及び経済協力・旅行者数)

(2) |
日・ASEAN関係 |
日本とASEANの関係は、21世紀に入り、新たに「戦略的パートナーシップ」として位置付けられ、日本とASEANという二者間の関係推進にとどまらず、東アジア全体の地域協力の推進のためにも、その協力関係は一層拡大・進化してきている。
日本は、ASEANの2015年までの共同体実現を全面的に支持し、そのための協力を惜しまない旨表明している。
日本とASEANは、ASEANの統合を支援し、地域の課題に対処する目的で2006年に創設した日・ASEAN統合基金(JAIF)等を活用し、「戦略的パートナーシップ」にふさわしい協力を着実に推進している。2008年には、テロ対策対話や環境対話を開催し、協力を強化させた。ASEAN各国の鳥インフルエンザ対策として、計50万人分の抗ウィルス剤の各国への配備を完了した。また、2007年11月の日・ASEAN首脳会議で日本は、海上の安全確保や環境保全等のため、5年間で3億米ドル規模の資金協力と300人以上の人材育成をASEAN諸国に対し実施することを表明し、2008年はこれを着実に実施した。
12月1日には、日・ASEAN包括的経済連携(AJCEP)協定が日本とシンガポール、ベトナム、ラオス及びミャンマーとの間で発効し、今後、批准手続を終えたASEAN各国に順次効力が発生する。同協定は、日本とASEANの域内全体における生産ネットワークの強化に役立つものであり、また、ASEANとの戦略的関係の強化という意義も持つ。
さらに、2008年は3回にわたり、日・ASEAN賢人会議が開催され、次回日・ASEAN首脳会議において、日・ASEAN関係を一層強化するための具体的提言が行われる予定である。
メコン諸国(カンボジア、タイ、ベトナム、ミャンマー、ラオス)との協力では、1月に初の日・メコン外相会議を東京で開催し、5月に高村外務大臣が「メコンの成長はASEANの利益、ASEANの成長は日本の利益」と題したスピーチを行い、日本の対メコン地域協力の重要性を訴えた。7月、カンボジア、ラオス、ベトナム(CLV)との外相会談を行い、日・メコン及び日・CLV協力など、幅広い分野での協力について議論した。2009年1月から「日メコン交流年2009」が始まり、多くの分野で日・メコン間の交流事業が実施されている。
イ |
カンボジア |
7月に総選挙が行われ、与党・人民党が圧勝した。同選挙に、日本は木村仁外務副大臣を団長とする政府選挙監視団を派遣した。9月、フン・セン首相を首班とする人民党とフンシンペック党との連立政府が成立した。クメール・ルージュ裁判では、予算不足など紆余曲折(うよきょくせつ)を経つつも、2009年2月に最初の公判が開廷された。
2008年は日・カンボジア外交関係開設55周年に当たり、要人往来や幅広い分野での交流が活発化した。7月には日・カンボジア投資協定が発効した。また、2009年1月には中曽根外務大臣がカンボジアを訪問した。

フン・セン・カンボジア首相(左)への表敬を行う中曽根外務大臣(右)(2009年1月11日、カンボジア・プノンペン) |
ロ |
タイ |
2007年12月の総選挙を受け、2月に国民の力党を中心とするサマック連立政権が成立した。5月以降の反政府デモは8月に首相府占拠に至った。9月にサマック首相が憲法違反の判決を受けて失職し、ソムチャイ副首相兼教育相が政権を引き継いだ。しかし、反政府デモは継続し、11月、バンコクの二つの空港がデモ隊により占拠・閉鎖され、物流の停滞のみならず日本人を含む観光客の往来が滞り、政治・経済に深刻な影響が出た。12月、前年の選挙違反に関して憲法裁判所から国民の力党の解党判決が出され、ソムチャイ内閣は退陣した。これを受け、野党民主党のアピシット党首を首相とする政権が発足した。
外交面では、1月にスリン元外相がASEAN事務局長に就任し、タイは2008年7月から2009年12月までASEAN議長国を務める。12月にタイで開催予定であったASEAN関連首脳会議は反政府デモの影響で延期となった。また、カンボジアとの国境地域にあるプレアビヒア寺院の世界遺産登録に端を発し、国境問題をめぐってカンボジアとの間で9月に小規模な軍事衝突が発生した。
6月にノパドン外相が訪日し、2009年1月には中曽根外務大臣がタイを訪問し、カシット外相と会談した。また、2009年2月にはアピシット首相が訪日した。
ハ |
ベトナム |
日・ベトナムは外交関係開設35周年を迎え、幅広い分野において交流が活発化し、両国関係が「戦略的パートナーシップ」構築に向けて、より高い次元へと引き上げられた。両国において多くの記念事業が開催され、特に5月のベトナムでの「ハノイ・ホーチミン音楽祭」及び9月の東京での「ベトナムフェスティバル2008」では、両国要人を含む多くの国民が参加した。
3月に衆議院議長の招待によりチョン国会議長、外務省賓客としてニャン副首相兼教育訓練相が訪日した。ニャン副首相訪日の際、「ベトナム博士育成計画」に関する覚書が署名された。日本からは、7月に高村外務大臣が訪越し、日越協力委員会第2回会合において、両国の互恵的協力の拡大のための包括的政策対話が行われた。
日・ベトナム経済連携協定は、9月に大筋で合意に至り、12月にホアン商工相が訪日して中曽根外務大臣との間で署名を行った。
2009年2月には、皇太子殿下が、ハノイ、ホーチミン、フエ等を公式訪問された。
ニ |
ミャンマー |
5月、ミャンマー南部をサイクロン・ナルギスが直撃し、死者・行方不明者合わせて13万人以上に達する大規模な被害が発生した。日本は、迅速に緊急援助物資を供与したほか、5月中旬に木村外務副大臣、同月下旬に国際プレッジング会合出席のため宇野治外務大臣政務官がミャンマーを訪問した。さらに、同月下旬から国際緊急援助隊医療チームを派遣するなどの支援を実施し、7月にシンガポールにて行われた日・ミャンマー外相会談において、被災地支援のため、人道的見地から約3,300万米ドルの支援を実施する旨表明した。
民主化問題に関し、ミャンマー政府は5月10日(一部地域は24日)に国民投票を実施し、その後、92%以上の賛成にて新憲法が承認された旨発表した。2010年に新憲法に基づき総選挙を実施する予定である。その一方で、11月には2007年9月のデモにおいて中心的な役割を果たした政治活動家の多くに対し長期刑判決を下した。
日本は、あらゆる機会をとらえ、同国の民主化及び人権状況の改善に向けミャンマー側に対する働き掛けを行った。また、2007年のデモの際の日本人ジャーナリスト死亡事件に関する真相究明を引き続き求めた。
国際社会においては、ガンバリ国連事務総長特別顧問による周旋努力が引き続き行われており、同特別顧問は3月、8月及び2009年1月にミャンマーを訪問した。
ホ |
ラオス |
ラオスは、第6次社会経済開発5か年計画に基づき、市場経済化、改革開放路線を堅持している。農業、鉱業、水力発電等を中心に外国投資が伸び、年間8%の順調な経済成長を達成した。活発な要人往来が行われ、両国関係は貿易・投資、観光、環境、青少年交流等の多岐にわたって進展した。
トンルン副首相兼外相訪日時に高村外務大臣との間で日・ラオス投資協定が署名され、8月に発効した。12月に開催された日・ラオス官民合同対話第2回会合においては、ラオス政府が投資環境改善に向けた「行動計画」を発表した。5月のチュンマリー国家主席兼党書記長訪日時には、「環境・気候変動問題に関する共同発表」を発出し、クールアース・パートナーシップに基づく協力関係を構築した。また、2009年1月には中曽根外務大臣がラオスを訪問した。
ヘ |
インドネシア |
ユドヨノ政権は、民主化、汚職撲滅、テロ対策、金融危機の下での経済対策など種々の政策課題に取り組んでいる。2009年には総選挙及び大統領選挙を控え、国内の景気対策や弱者支援などと健全なマクロ経済運営の両立が現政権の課題となっている。経済面では、2008年上半期の実質経済成長率は1998年の経済危機以後、最高の6.4%と好調であったが、9月以降、国際金融・経済危機の影響を受けて株価と為替が急落し、貿易及び雇用などの実体経済へ影響が懸念されている。外交面では、ユドヨノ大統領のG8北海道洞爺湖サミット主要経済国首脳会合(MEM)出席(7月)、アジア地域において民主主義の促進を目指す「バリ民主主義フォーラム」閣僚会合の主催(12月)など国際社会での活躍が目を引いた。日本との関係では、2008年は外交関係開設50周年を記念し「日本インドネシア友好年」の諸行事が1年を通じて両国で実施され、その一環として秋篠宮同妃両殿下が1月にインドネシアを公式に訪問された。また、7月、日・インドネシア経済連携協定(EPA)が発効し、両国間の経済関係の拡大が期待される中、日本として初めての外国人看護師・介護福祉士候補者をインドネシアから受け入れた。

「日本インドネシア友好年」開会式のためインドネシアを訪問された秋篠宮同妃両殿下(左)とユドヨノ・インドネシア大統領夫妻(右)(1月19日、インドネシア・ジャカルタ) |
ト |
シンガポール |
リー・シェンロン政権は、極めて安定した政権運営を続けている。経済面では2008年は世界金融危機の影響が、特に金融業や外需依存率が高い製造業などで強く出始めた。その結果、2007年の高い成長率(7.7%)から一転、2008年の成長率は2%台の見込みで、2009年には1%~2%のマイナス成長に陥ると予測されている。外交面ではASEAN議長国として7月には関連外相会合を主催した。同国は、安全保障、経済面で米国の関与を重視し、ASEAN諸国等と善隣外交を進める伝統的スタンスに加えて、台頭著しい中国、インド、中東諸国等との関係強化にも積極的に取り組んでいる。
チ |
フィリピン |
アロヨ政権にとって、政権の安定性確保は引き続き課題となっている。2008年は通信事業における中国企業の不正入札疑惑への大統領の親族の関与が取りざたされ、政権支持率は低迷した。行財政改革の進展により2007年の実質経済成長率は7.3%を記録し、財政状況は改善傾向を示しているが、原油・食料価格の高騰と世界的な金融危機等を受けて、アロヨ政権は追加的財政支出を決定し、均衡財政達成を2008年から2010年に先送りした。2008年の成長率は4%台となる見込みである。モロ・イスラム解放戦線(MILF)との和平は、土地問題に関する合意が署名に至らなかったことを機に武力衝突が激化し、8月以降、和平プロセスが停滞している。
日本との関係では、12月に貿易・投資の自由化や看護師及び介護、福祉士の候補者の受入れ等を規定する経済連携協定(EPA)に加え、租税条約改正議定書が発効し、経済関係の更なる進展が期待される。
リ |
ブルネイ |
豊富な石油・天然ガス収入により国民所得水準が高く、社会福祉も充実し、内政は安定している。日・ブルネイ経済連携協定(EPA)発効(7月)、日・ブルネイ租税条約署名(2009年1月)等により、天然ガス開発、貿易等の経済面を中心に両国関係がより強化されることが期待されている。
ヌ |
マレーシア |
3月に行われた総選挙において与党連合が大きく議席を減らし、州議会選挙においても13州中5州で野党が政権を奪回した。こうした与党の勢力減退を背景に、10月、アブドゥラ首相は、2009年3月に延期された党総裁選に出馬せずに退任、ナジブ副首相に政権を移譲する旨表明した。
堅調だった国内経済は、世界金融危機を受け、株安、通貨安、輸出減の兆しがある。これを受けて、政府は70億リンギ(2,100億円相当)の景気対策を発表、2009年度の成長率見通しを5.4%から3.5%に下方修正した。
日本との関係では、5月の日・マレーシア首脳会談において、2001年から検討されているマレーシア日本国際工科大学設立構想について政府間の協議を加速化し、2009年7月の開校に向けて準備を行うことにつき一致した。ASEANの人材育成拠点として日本型の工学部教育を行う大学の設立を通じ、東方政策(注1)を基盤とした両国関係の更なる発展が期待される。
(3) |
東ティモール |
2月、ラモス・ホルタ大統領及びグスマン首相に対する襲撃事件が発生した。ラモス・ホルタ大統領は重傷を負い、非常事態宣言が発出される事態に及んだが、治安悪化に至らず、治安は維持されている。ラモス・ホルタ大統領も4月に職務復帰し、グスマン首相率いる連立政権は、野党と対立しつつも、治安対策、国内避難民の帰還、嘆願兵問題の解決、雇用対策、国家警察・国軍訓練、国家機関の能力向上等の諸問題に精力的に取り組んでいる。経済面では、石油基金(ティモール海で産出される石油・ガスからの税収を財源)に資産が積み上がり(2008年末現在、約42億米ドル)、石油・ガス開発及び同基金の効率的な運営が今後の経済の鍵(かぎ)を握る。2008年には、要人往来も活発に行われ、良好な二国間関係を継続している。日本は、引き続き、経済的・人的支援を通じ、同国の平和構築・国づくりを積極的に支援していく方針である。
| (注1) | 東方政策:1981年にマハティール首相が提唱したマレーシア人の人づくり政策。日本(と韓国)の発展の経験や労働倫理等を学ぶことを目的とし、留学生・研修員を日本等に派遣するプログラムを実施。 |