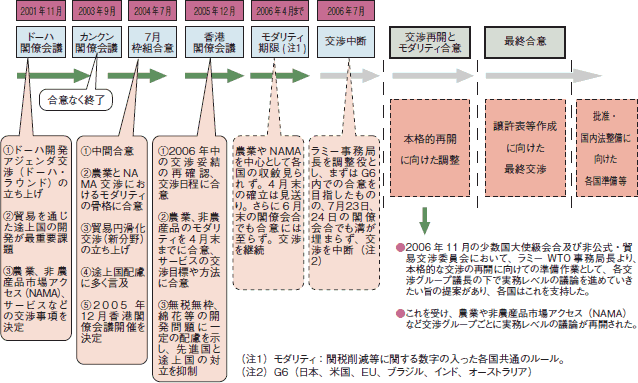各国は2006年年明け以降、累次にわたって閣僚会合を開催するなど集中的な交渉を行った。しかしながら、主に、農業の市場アクセス(関税引下げ)、農業の国内支持(農業補助金)、非農産品市場アクセス(NAMA)の3つの論点について、米国、EU、オーストラリア、日本、インド、ブラジルなど主要国間で意見が一致せず、4月末のモダリティ (注3) 合意という目標が未達成に終わったばかりか、上記3つの論点が相互に絡み合ういわゆる「三すくみ」 (注4) の膠着状態に陥った。
こうした状況を打開すべく、7月上旬にはラミーWTO事務局長が調整役として日本を含む主要国との対話を行ったほか、同月中旬のG8サンクトペテルブルク・サミットではG8首脳が、ドーハ・ラウンド妥結へ向けて柔軟性をもって協調し、1か月以内にモダリティ確立を目指すことを確認した。しかし、7月下旬の主要国閣僚会合でも各国の立場の乖離は埋まらず、遂にラウンド交渉は中断という事態を迎えた。
7月下旬の交渉中断以降は、各国とも交渉を早期再開させるべく静かな外交プロセスを展開してきた。こうした努力もあり、11月のAPEC首脳会議でドーハ・ラウンド交渉の早期再開を呼びかける独立文書が採択されるなど交渉を後押しする機運も再び高まりを見せ、同月から各国間で実務レベルでの議論が再開した。