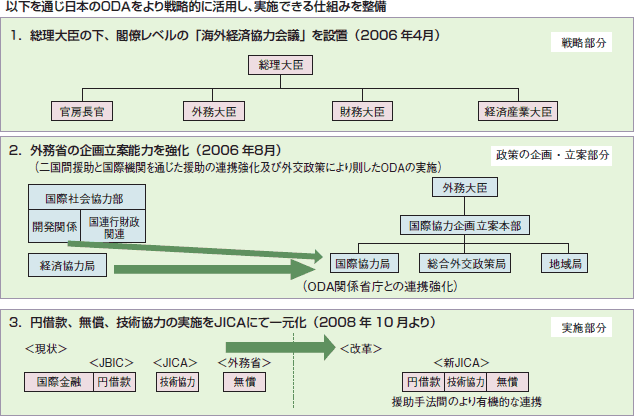(イ)日本の実績と国際公約の達成
2005年の日本のODA実績は、対前年比47.3%増の約131.5億ドル、対国民総所得(GNI)比も0.28%に上昇したが、これはイラクに対する債務救済及びインドネシア等への債務支払猶予という特殊要因によるものである。こうした特殊要因を差し引けば、ODA実績は約85.8億ドルで対前年比3.8%減となっている。
日本は、世界的な目標であるODAの対GNI比0.7%の目標達成の観点から、2005年に(1)3年間でアフリカ向けODAを倍増すること、(2)5年間で(2004年実績をベースとする額と比して)ODA事業量の100億ドル積み増しを目指すこと-を表明している。これらの国際公約が着実に実行できるよう、今後とも積極的にODAの実績を積み重ねていく考えである。
(ロ)重点地域への取組
2006年に設置された海外経済協力会議と国際協力企画立案本部は、同年中にそれぞれ5回開催された。海外経済協力会議ではアジア地域、中国、インド、イラク、資源・エネルギー、貿易・投資等が、国際協力企画立案本部ではアジア地域、イラク、アフリカ、中央アジア・コーカサス及びGUAM(グルジア、ウクライナ、アゼルバイジャン、モルドバ)、貿易・投資等、その時々の外交課題に即した議題につき議論がなされた。これらの議論で示された基本的な枠組みを踏まえつつ、ODAは以下のように実施された。
(i)アジア
日本と密接な関係にあり、日本の安全と繁栄に重要な意義を有するアジアは、ODA大綱においても重点地域とされている。日本は東アジア地域を中心に経済インフラ基盤整備を進めるとともに、民間投資や貿易の活性化を図るなど、ODAと投資・貿易を連携させた経済協力を進めることにより、アジア地域のめざましい発展に貢献してきた。2005年実績では二国間ODAのうち、アジア地域が占める割合は約38億4,100万ドルとなり、全体の36.6%と最も大きな割合を占めている(対前年比51.0%増)。
まず日本と政治・経済・文化などあらゆる面で緊密な相互依存関係にあり日本の平和と繁栄にとって重要な意義を有する東アジア地域に対しては、インドネシアをはじめ円借款の新規供与国先上位5か国のうち3か国が同地域で占める(2005年度実績) (注49) など、引き続きODAにより大きな支援を行うニーズがある。特にASEAN諸国に対しては、日本はASEAN域内の格差是正や一体性の強化の観点から協力を強化しており、2006年には日・ASEAN統合基金を新設し総額75億円を拠出した (注50) 。ASEAN後発加盟国を中心とするメコン地域に対する協力として、12月に、今後3年間メコン地域をODAの重点地域とし、メコン地域に対するODAを拡充すること、日・ASEAN包括的経済連携協力基金への新規拠出5,200万ドルを活用し、CLMV(カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム)に約4,000万ドルの支援を行うことなどを内容とする日本・メコン地域パートナーシップ・プログラムを発表した。また、カンボジア、ラオス、ベトナムにまたがる辺境地帯「開発の三角地帯」に対しては、教育や医療などの基礎生活分野を中心に協力を行っている。さらに、今後エネルギー需要の急増が見込まれる東アジア地域のエネルギー安全保障の向上を図りより一層の発展を図るため、省エネやバイオマスエネルギーの推進、石炭のクリーンな利用、エネルギー貧困の解消(3年間で20億ドルのODAの供与)を柱とするエネルギー協力イニシアティブを2007年1月の第2回東アジア首脳会議(EAS)にて表明した。
▼日本・メコン地域パートナーシップ・プログラム(2006年12月発表)
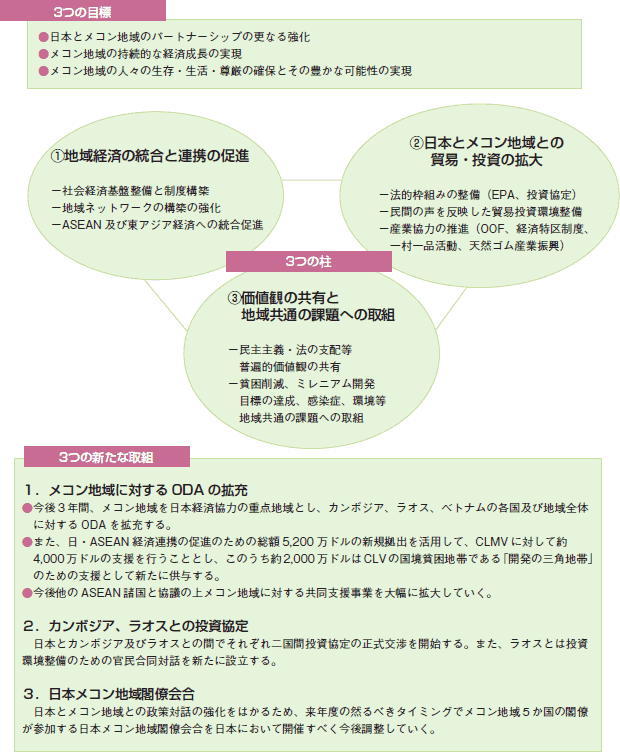
世界最大の民主主義国であり基本的価値を共有するインドは急速な経済成長を遂げる一方で、世界の貧困人口の3分の1を抱えている。日本は経済交流拡大のための取組から貧困問題への対策まで幅広くインドと協力を進めている。12月のシン首相訪日時には、インドがODAの重点国であることを確認し、インフラ整備からエネルギー、環境対策まで幅広い包括的な協力を行うことを日印両国間で確認した。
一方、中国に対するODAについては、中国経済の発展が進む中で、その大部分を占める円借款の必要性が以前より相対的に低下してきていることから、日中両国は2008年の北京オリンピック前までに円借款の新規供与を「円満終了」することにつき共通認識に達している。一方で、中国における環境問題や省エネ、感染症等、日中両国が協力すべき分野は多く残っている。日中両国は、2006年後半に安倍総理大臣訪中をはじめAPECやEAS開催にあわせ首脳会談、外相会談を行い、酸性雨・黄砂対策分野など省エネ・環境分野での協力を確認した。
(ii)中東
世界の主要なエネルギー供給地域であり、日本が原油輸入の9割以上を依存する中東地域の平和と安定の確保は、国際社会全体の平和と繁栄に直結する重要な課題である。そしてイラクやアフガニスタンの復興は、中東地域全体の安定化にとって極めて重要であり、日本は国際社会と連携しつつ、引き続き積極的に支援を行っていく方針である。
5月に正式な政府が発足したイラクにおける今後の復興プロセスにおいては、イラク政府のより主体的かつ自律的な取組を国際社会とともに支援している。日本の支援としては、2005年11月に合意した債務救済(約76億ドルの対象債務を3段階に分けて合計80%削減)に加えて、15億ドルの無償資金協力による当面の支援がすべて実施・決定されている。現在は、最大35億ドルの円借款による支援の段階へ移行しており、2007年1月には電力、運輸、灌漑分野の計4件につき、円借款供与のための書簡の交換がなされた。また資金協力とも連携を図りつつ、研修を通じた能力構築も継続していく。
アフガニスタンでは、日本は、政治プロセス・ガバナンス、治安の維持、復興の3つの柱を中心に支援を行っている (注51) 。政治プロセス・ガバナンスに対する支援については、暫定政権への行政経費支援や選挙監視支援などを行った。一方、治安の維持に対する支援については、DDR、非合法武装集団の解体(DIAG:Disbandment of Illegal Armed Group)、地雷対策、警察支援などを行っている。また復興に対する支援として、難民・避難民の再定住支援、農業・農村開発支援、教育支援、インフラ整備などの支援を行っている。さらに、2007年1月の安倍総理大臣のNATO訪問時に、アフガニスタンの安定に向けNATOの地方復興チーム(PRT)が実施する基礎生活分野での復興活動との協力を強化する旨表明した。
(iii)アフリカ
2000年の国連ミレニアム・サミット以降、深刻な貧困、紛争、飢餓、感染症、累積債務等の諸課題を抱えるアフリカに対する支援強化の機運は国際社会において極めて高い。日本も1993年以降、TICADプロセスを基軸として「平和の定着」、「経済成長を通じた貧困削減」、「人間中心の開発」を三本柱とする積極的な支援を行っている。2月には「TICAD平和の定着会議」において、元児童兵社会復帰や紛争後のコミュニティ支援など6,000万ドル規模の支援策を発表した。
今後も、これら支援策を着実に実施していくとともに、2008年のTICAD IVを念頭に、国際機関・他ドナーとの連携や南南協力、特にアジア・アフリカ協力の推進を通じて、アフリカの自律的発展に向けた協力を強化していく。