日本は、2006年も国連総会に核軍縮決議案 (注20) を提出し、同決議案は圧倒的支持を得て採択された。また、G8等の主要国との軍縮・不拡散に関する二国間協議も開催している。いまだに発効していない包括的核実験禁止条約(CTBT) (注21) の発効促進については、9月にニューヨークでオーストラリア等とともにCTBT外相フレンズ会合を主催し、伊藤外務大臣政務官が未批准国に対し早期の批准を呼びかけた。CTBTの国際監視制度 (注22) は、北朝鮮による核実験実施の際に改めてその有用性が認識され、日本としても引き続き整備に取り組んでいく。ジュネーブの軍縮会議(CD)においては、10年にわたり、多数国間の軍縮条約に関する実質的交渉が行われていなかったが、2006年の会期中に議長を務める6か国大使によるイニシアティブを受けて実質的な議論が行われ、米国がいわゆるカットオフ条約 (注23) に関する条約案を提出するなど、停滞打開の端緒となる動きが見られた。日本も、同条約案に関する作業文書を提出したほか議論に積極的に貢献した。また、河野衆議院議長や山中外務大臣政務官が軍縮会議に出席し、CD停滞打開と同条約の早期交渉を訴える演説を行った。
▼大量破壊兵器、ミサイル及び関連物資等の軍縮・不拡散体制の概要
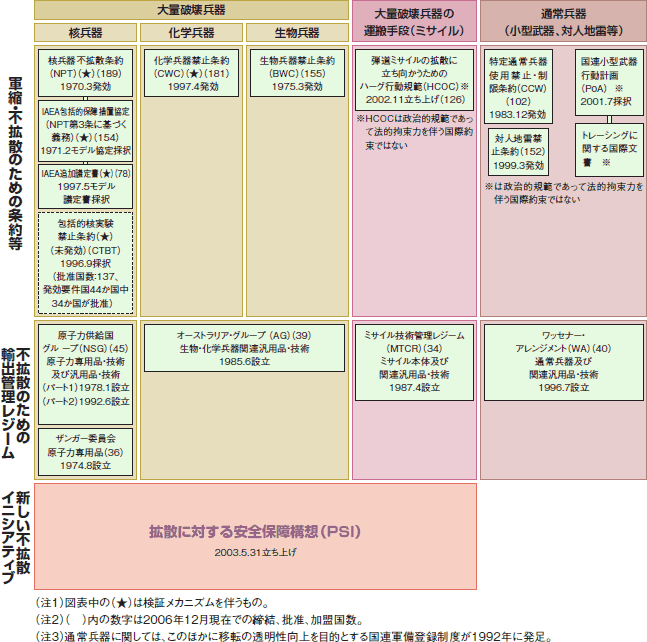
1998年に核実験を実施したインドとパキスタン (注24) は、依然としてNPT加入とCTBT署名に至っていない。日本は、1月の麻生外務大臣のインド訪問を受け、インドとの初の軍縮・不拡散協議を5月に開催し、また、パキスタンとも7月に協議を行うなど、両国に対し、引き続きNPTへの加入及びCTBTの署名・批准を働きかけてきている (注25) 。また、インドに対する民生用の原子力協力の実施を内容とする米印間の合意 (注26) については、インドの戦略的重要性、エネルギー需要の増大の手当ての必要性等も踏まえつつ、NPTを礎とする国際的な核軍縮・不拡散体制に与える影響等を注意深く検討する必要があり、そのような観点から日本は国際的な議論に参加している。イスラエルは中東においてNPTに加入していない唯一の国であり、CTBT等の大量破壊兵器の軍縮・不拡散のための条約も批准していない。日本は、機会をとらえ、イスラエル側に対し、大量破壊兵器の軍縮・不拡散体制への参加を強く求めてきている。
日本は軍縮・不拡散と日本海周辺の環境汚染防止の観点から、日露非核化協力委員会を通じてロシア極東地域に残された退役原子力潜水艦の解体支援 (注27) を実施している。また、現在ロシアによって進められている原子炉区画陸上保管施設建設 (注28) に対して協力を行っていく予定である。